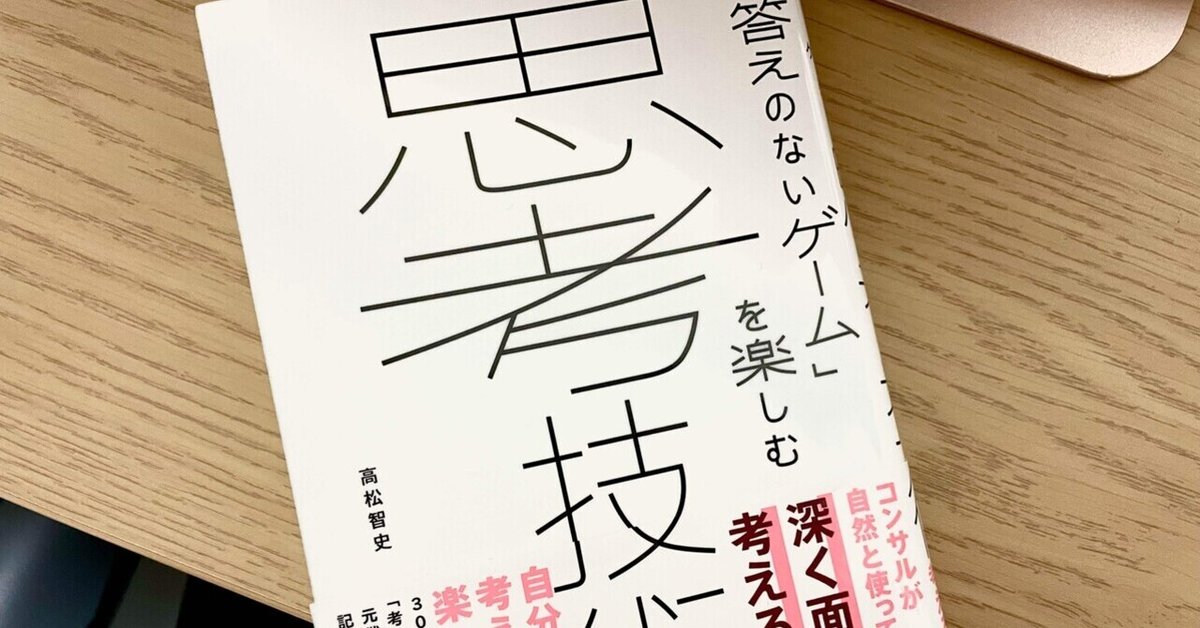
「『答えのないゲーム』を楽しむ 思考技術」を読んでの学び
本日は「『答えのないゲーム』を楽しむ 思考技術」を読んでの学びを残していきます。
自分で考えるための思考のポイントが学べる
本書を開くと、このメッセージが勇気づけてくれます。
「考える力」はスキルであり、技術。
だから、身につけることができるよ。
考える力は身につけることができる。
そして、身につけると「アタマの使い方が良くなる」と著者の高松さんはおっしゃっています。
そんな考える力をつけるために、「答えのないゲーム」をテーマに考え方のポイントが書かれている本です。
日常やビジネスシーンで役に立ちそうな考え方が詰まっており、読みながら自分で考える場面がたくさん出てきます。
何度も読み直しながら思考技術を身につけていきたいと思いました。
無意識に「答えのあるゲーム」をしてしまっているかも
私たちは自然と「答えのあるゲーム」の戦いをしてしまっています。
これは義務教育の中で答えのあるスタイルが身についてしまっているから。
きっと、このような場面も思い当たる方がいるのではないでしょうか。
上司に何かを確認する時「これで合ってますか?」と聞いてしまっていませんか?
これは「答えのあるゲーム」の戦い方で、上司に「答えのないゲーム」をさせ、自分は「答えのあるゲーム」をしてしまっています。
思い当たるかも…という方は今後は「答えのないゲーム」として捉えることができると成長スピードが上がります。
「答えのないゲーム」の戦い方とは、自分なりの考えを作るということ。
「答えのないゲーム」の戦い方とは
自分なりの最高のプロセス(答え)を出す
「絶対的」な答えがないのだから「相対的」に答えに近づくしかない
2つ以上の選択肢を作り、より良いものを選択する
「なぜそれを選ぶのか」自分で言語化する
人と意見は違うもの。だからこそ「議論」を怖がるな
本書ではもっと独特な言葉に例えられていますが笑
ポイントとしてはこのような感じ。そもそも相手に求めるのではなく、自分が最高だと思うプロセスを考える。そしていくつかの選択肢を並べた上で良いものを選び、自分で言語化する。
正解がないのだから議論することが前提である。
思考プロセスの「教科書」をもとに自分で考える
物事を考えるとき、問題解決をしなければならないときにこの「教科書」をもとにプロセスをチェックしていきます。
ステップ1:論点を立てる
ステップ2:ファクトから示唆を抽出する
ステップ3:仮説をつくる
ステップ4:仮説を検証する
「論点を立てる」時のポイントとしても書かれているのですが、ついやってしまいがちなのが、「とりあえず作業」になってしまうこと。
例えば「何かについて調べてほしい」という依頼があったときに「Google検索で調べる」「詳しい人に聞いてみる」などの行動を先にしてしまうのはNGで、何がわかったら良いのか?といった論点を立てることを先にしなければなりません。
特に印象に残ったこと
・答えを求めずに自分で考え抜く
・ファクトを元に「何が言えるっけ?」を癖づけする
・とりあえず始める前に論点を立てる
本書にはいくつか問題が出題されるのですが、自分で考える前につい答えのページをめくりたくなってしまうんですよね。
そんな私に対してこんな言葉が。
自分で解く努力をし、悩みに悩んでから、解説を読んでほしい
情報が溢れる今、調べ物はいくらでもできるし、他人の意見もたくさん見える世界です。
でも、自分で考え抜き、出した答えに自信を持って自分なりの考えを持つことが大事であると改めて感じました。
私の書いているnoteも自分なりのアウトプットを残していけるようにしていきたい。
