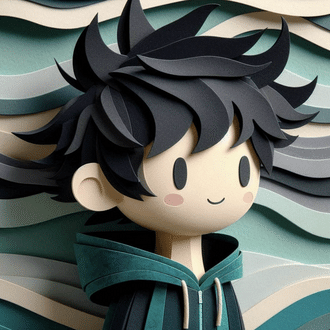リーダーという職業の難しさ
毎日日記を書いている。
それも日々の日記ではなく、仕事のことが中心。
何があったとかもそうだが、どの展開でどういう感情になったか、どんな判断をその時に下したかというようなことが中心。
別に毎日見返すわけではないが、たまに困難な状況になった時にパラパラめくってヒントを探すというような感じ。
どうせなら日記がてら書いているものを、どうせならリアルなものとして参考にしてもらえたらってことでnoteにも転載しようかと。
業務過多問題
部内のシフトどうするかメンバーと相談していたら、主任が僕のルーティン分を免除してくれようとしていた。これ、結構泣ける。いや「オマエは使えんからルーティンなしな」ってことなのかもしれないけど、客観的にみても多分それはない…はず。
まあ、現実はルーティンやらないといけないんだけど、確かにマネジメント業務がわりと圧迫していてどうしようかと思ってた。
でもルーティンもやりたいんや。我は臨床検査技師。書類仕事やその他社内政治的なことをするために、この職業を選んだわけじゃない。ましてや役職なんてただの看板みたいなもんだし。偉くもなんともない。
抱えているタスクがたくさんありそうなことを察して(ある程度開示しているが)、配慮してくれるのは心遣いとしては泣きそうなほど嬉しいけど、やっぱり現場であーだこーだ言いながら、みんなと切磋琢磨していきたいなと思う。
エースの扱い
こうしたことがあると、自分がいわゆる「しごでき」な人間とは言えないけど、部署をなんとかしようとしているのは、なんとなく伝わっているのかなとは思える。普段からメンバーには感謝しかないけど(たまにサボるやついるのはイラっとするが)、改めて感謝。
結果を出していけるのはメンバーのおかげ。
エース依存から脱却したのが大きかった。
これは持論だけど、エースひとりにチームの成果を任せるやり方は、短期的には結果が出やすいし、それこそ短期PJなどでは効果があるんだけど、長期目線となるとエース自身が勘違いしてくる。
自分は有能だ、このチームの中心だって。
しかし実はそれ、エースのせいではなくて。キャプテン(リーダー)がそこんところをしっかり締めていないからつけ上がってしまう。チームの中心になるものこそ、ベクトルを自分に向けないといけない。ベクトルが外に向いていると、いいことがない。それをわからせてあげる、言い続けるのはリーダーの仕事だと思っている。
ベクトルはいつも自分に向ける
チームがうまく回らない……というのはどうしたってあること。
どんなに優秀な指揮官でも、それは起きてしまう。やっぱりメンバー次第な部分があるというのが本音だし、取り巻く環境にも依存されてしまう。
それでも。
そういう現実があったとしても、リーダーだけは自分にベクトルを向ける。率先してそういう姿勢を示す。それがメンバーにも伝播して、いいチーム状態に戻っていくというのが理想。
いいときはメンバーのおかげ、悪いときは自分のせいでいい。そういう覚悟を持ってやらないと、いいチームなんて絶対にできない、メンバーも育ってくれない。
これは今季で退任されたが、川崎フロンターレを8年間率いた鬼木達監督から学んだこと。
オニさんはうまくいかない時も、絶対にメンバー批判なんてしないし、全部自分にベクトルを向けて仕事していたんだと思う。じゃないとあんなにメンバーが慕うはずがない。
それは野球で世界一に導いた栗山英樹さんにも言えることだと思う。会見でも書籍でも「全部オレのせい」と断言していた。それくらい選手には愛情持って接していたのがわかる。
優しくするとか、甘くするとかではなく。
いいリーダーとは?を考え続ける
オニさんの退任がついにきてしまった……と、わかっていたことではあるが、少し辛いものがある。あれだけ選手がいなくなれば結果を出すのだって難しいはず。ましてやただ選手がいなくなるんじゃなくて、大黒柱が抜けたり、日本代表級の選手が4〜5人も抜ければ。。。
それでも言い訳しなかったのはさすがとしか言いようがない。
同じ状況なら愚痴のひとつでも言いたくなるような環境。
こういうところでも「いいリーダー」との境目があるのだと感じる。
いろいろ考えさせられることがあったからというわけではないが、改めてチームのことを第一に考えて仕事していこうと思う。
いいなと思ったら応援しよう!