
ミャンマーを知りたくて ③難民キャンプへ
メーソートの街から車で難民キャンプへ向かいます。
建物も人の気配もなくなり、舗装はきれいにされているものの、両サイドは密林のような道路をひたすら走る。
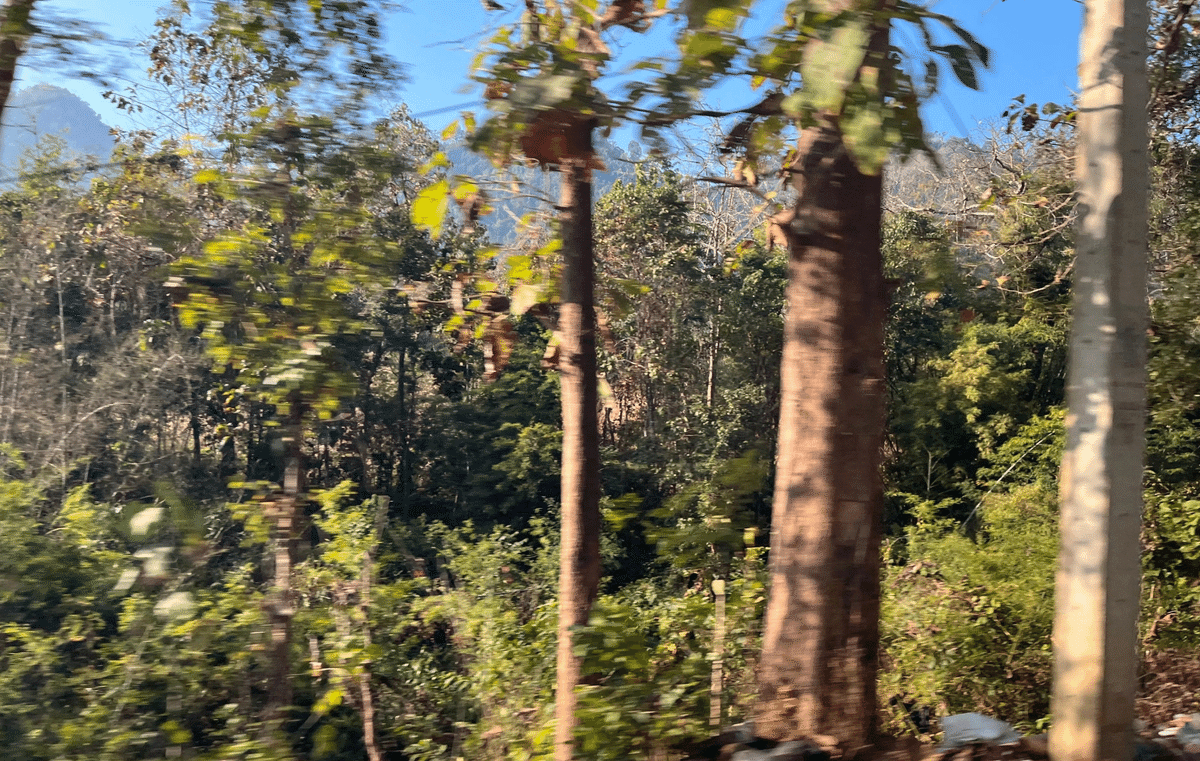
「ここはさ、旧日本軍が太平洋戦争中に進んだ道なんだよ」
当時、イギリスが支配していたミャンマー(ビルマ)に侵攻し、占領下に置いた日本軍。
インド・インパールにあったイギリス軍の拠点も攻略するためにビルマから行われたインパール作戦では、数万の日本兵が亡くなっています。
日本から遠く離れた、この過酷な道なき道を進んだ人たちを思うと、胸がぎゅっとなりました。それから何十年も経って、同じ日本人の私がこの道を進んでいることに、不思議な気持ちになります。
しばらくすると、車窓からの景色が急に変わりました。


道沿いに背の低い小屋がポツポツ出現し始めた。人影もある。
「もうこの向こうは難民キャンプだね。もうすぐ入り口だよ。」
国境沿いにはいくつかに分かれて難民キャンプがあり、
私が訪れたのはその中の一つ。
入る前にも検問所のようなところがあり、軍のチェックが入ります。
それも抜けていよいよキャンプの中へ。

まずは事務局に案内していただいて、今の状況についてレクチャーを受けました。

事務局ではキャンプ内の人数の把握や、支援団体全体の統括をしています。
キャンプ内ではたくさんのNGOがそれぞれの分野で支援活動を行い、日々の生活が成り立っています。
食べ物、学校、医療など、そしてシャンティさんは図書館事業での支援。
まずは、事務局からシャンティさんのスタッフに支援への感謝が伝えられ、お話を伺いました。
↓↓ ここからは事務局の方の話 ↓↓
ミャンマー国内では、いたるところで戦闘がある。
政府が空から爆撃して国民を殺害し、あらゆるものに損害を与えるようなことをしている。
軍の攻撃により自分の村や家を捨てて山の中で潜伏しているような人たちがたくさんいる。
場所によっては、ほとんどすべての建物、学校、教会、家が燃えてしまったところも。
特に女性や子供たちが生き残るのは困難。
キャンプには高校までの教育機関があるが、卒業後は何もすることがない。
仕事もない、基本的にはここから出ていくこともできない。
難民たちが絶望してドラッグやアルコールに溺れてしまったり、鬱のようになってしまったりする現状がある。
若い世代は、自分たちの未来を想像することができない。夢を見ることもできない。
働くスタッフの待遇についても問題がある。スタッフが受け取る給与は非常に少ない。良い人材を確保するのは簡単ではないし、このままでは教師たちがキャンプを去ってしまうかもしれない。
今、キャンプ内の学校は図書館と連携して子供たちの教育にあたっている。
学校にも本はあるが、基礎教育のための限られた教材しかないので、
シャンティが運営するような、絵本などたくさんの本がある図書館はとても大切。
折り紙など、勉強以外のことを教えてくれるのも子供たちにとって良い影響を与えてくれる。
私たちはここで人々を保護して、危機的状況にあるミャンマーの避難民に安全な場所があると伝えたいが、今、新しい難民の受け入れに関しては制限されている状態。私たちが支援すること自体、デリケートな問題。
ミャンマー国内には多くの天然資源があり、良い指導者がいればとても平和で豊かな国になるはずなのに、軍がすべてを支配しようとしているのを見ているだけのような状態になっている。
他の大国が圧力をかけてくれたら、何か変化があるかもしれない。
・・・というようなお話でした。
補足しますと、
難民キャンプ内では、基本的に経済活動=仕事ができません。
一度入って登録されると、勝手に外に出ることは許されません。
インターネットや電気などもほとんど使えません。
仕事しなくていいの最高じゃん、と思う人もいるんですけど、
旅行にいくことはもちろん、映画のサブスクもなく、漫画喫茶もなく、インターネットも使えず、美味しいものを食べにお店を探したりすることもできず、ただただ生きていくってどうでしょうか。
以前はアメリカやヨーロッパへの移住の道もあったのですが、今は海外の受け入れもほとんどストップしているため、それも難しい。
ミャンマーが誰にとっても安全な国になり、そこに帰れたら良いはずなのですが・・・。
事務局の方とはここでお別れ。
お礼に成田空港で購入したクッキーをお渡ししたら、はじける笑顔見せてくれました。
日本のお菓子、やはり強いかもしれない。
次はキャンプ内を歩いてお住まいにお邪魔します。

難民”キャンプ”という名前から、テントの集合だとイメージする方も多いのですが、(もちろんそういう場所もありますが)
数十年にわたって問題が続いているところでは、住宅や学校、医療施設も建設されています。
私が訪れたこちらのキャンプも、木や竹で作られた家が並び、印象としては ”村” でした。

歩きながら観察していると、ほとんどの軒先に水と砂が入ったビニール袋が下げられています。

「それは Fire extinguishant(=消火剤) だよ」
木造の家が密集しているし、水道がいたるところにあるわけではないので、もし火事が起きたら大変。燃え広がらないようにこれを投げるんだそうです。
舗装はされていないものの、人の歩きで固められているので歩くのはそこまで大変ではない。
しかし粘土質っぽい土なので、濡れているところがあると滑る、急にへこんでいるところもあってたまに足をくじきそうになる。
10分ほど歩いたところで一軒の家の前で止まる。
ここの住民にお話しを聞けるように手配してくださっていました。
さっそくお邪魔すると、
中は2階建て。床面積でいうと7~8畳あるかどうかという広さ。
2階には上がりませんでしたが、1階部分は身長約160cmの私がギリギリ立てるくらい。

竹と細い丸太を組んだカベは隙間が大きくて、ひっきりなしに虫が入ってくる、電気がないので日中でも暗く、風通しもあまりよくないようでじめっとしている。
この家に2家族住んでいるとのこと。
部屋の真ん中には大きな木のテーブルがあり、生活に必要なもの、大きな水筒?夏の運動部が使うようなドリンクサーバーのようなものや、コップ、ザルやタライなどが雑多に置かれている。
あと何用なのか聞けなかったけど、足元にケージに入ったウサギがいて、
インタビュー中に脱走して足をクンクンされたり走り回って邪魔されたりしてた。カワイイ。
入ってすぐのところにベッドがあって、そこに5人の大人が座っていた。
このままお話を聞く。
60代のMさんと、その40代と30代、20代の子供たち。
そしてMさんの同い年のいとこ。
Mさんはもともとミャンマーの政府関係で働いていたが、政府の考えに反対して国にいられなくなってしまった。
とにかく命が大事、安全なところへと、このキャンプへ来たが、あまりにも未来への展望がないことでかなり参っている様子。
もう15年以上ここにいるので、新しく来た人の相談役になったり、たまに支援してくれる人たちの活動を手伝ったりすることはあるが、それ以外はやることがない。
30代の息子さんに、今何が一番欲しいかと聞くと、
やはり仕事だそうです。ここにただ住んで時間が経過していくだけという状況がつらいと。
暮らす中で少し大変なところはあるけど
(たまに気温が下がると家は全く防寒できず、他の家から毛布を借りないと大変だそうです。私が行ったこの時も、寒そうにしている人が多かった。)
命の危険はないしありがたい。
しかしとにかくやることが欲しい。
仕事がしたい。
ミャンマーに戻ることは難しいから、できればここを出て他の国で仕事を見つけたい。
これに関して、60代のMさんは、息子たちは外国に行かせてやりたいけど自分は年齢的にも他の国で生きていくことは難しい、と溜息をついていました。
マズローの欲求5段階説ってどこかで聞いたことありますか?
人間の欲求を5段階のピラミッドで表していて、
低い階層が満たされるとその上の欲求を満たしたくなるそうなんですが、
命の危機をとにかく脱しようとキャンプにきて、
まず安全が保障されたことに安堵するのですが、
その後、生活は保障されていることに感謝しつつも、
ただ生きているだけ、何も目標を持てない、先の見通しが立たないことに愕然としてしまうようです。
最初はよくても、残りの人生あと何年、何十年、ずっとこのままかもと思ったら絶望してしまうよね・・・
逆に、今一番幸せを感じるときは?と聞いてみました。
すると、Mさんも、Mさんのいとこも
「神に祈っているとき」
と答えてくれました。
この家族は全員キリスト教徒。
聖書を読んで、神に祈って神とともにあると感じているとき、一番心が癒されて苦しみを忘れられるんだそうです。
「近いうちに大きな変化が起こる可能性だってある、軍事政権が権力を失って、何かが変わるかもしれない。困難な状況だけど、私は神を信じている。」
信仰って、こういうときに支えになるんだな・・・
Mさんのいとこは足が不自由なのですが、キャンプの中で障がい者グループを作って、相談を聞いたり、お互いに助け合ったり、励まし合ったりする活動をしているとのこと。
経済活動はできないけど、こういう生きがいを見出しているみたい。
この話のときは他の家族も少し明るい表情になっていました。
お邪魔させてもらってありがとうと握手をして別れました。
