日本の教育に過度な期待をする(評価管理する)のはやめにした方がいいのではないか
日本は少子高齢化社会に突入するのだと言われて久しい。1990年に合計特殊出生率が1.57であったことから、それを「1.57ショック」と呼称し一般的な認識を得るに至ったが、その実、1975年から現在に至るまで少子化減少の一途なのだ。
すでに50年近く前からわかっていたことで、30年前には一般化するに至った国家的な課題であったとしても、それを取り組んでくるには至らず、日本は以下の内閣府が出している『少子化対策白書』を見る限り人口はどこまでも減っていけるのだと逆説的な希望を抱くことができる。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2021/r03pdfhonpen/pdf/s1-1.pdf

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2021/r03pdfhonpen/pdf/s1-2.pdf
どうも、えんどう @ryosuke_endo です。これらを踏まえると、日本の高等教育を含めたあらゆる教育に「優秀な人材を輩出すること」と「高い研究成果を出すこと」などを求めることはあまりにも敷居が高すぎる話ではないのかと思いはじめたことをツラツラと書いていく。
▶︎ 優秀人材の絶対数が減少する事実は変わらない
▷ 中央集権的な国立大学は衰退するのでは
日本の国立大学で有名どころといえば東京大学や京都大学だろう。入れるものであれば入りたい。僕はそんなところにも手が届かない無能側の人間のため、今回の閑言は与太話として済ませてくれて構わない。
日本を代表する国立大学である東京大学と京都大学だが、まったく同じ条件(言語や金銭面、通学の距離などあらゆる条件が同じ)だと仮定した場合、ハーバード大学やMIT(Massachusetts Institute of Technology:マサチューセッツ工科大学)などの世界でも名高い名門大学とではどこに入学し、卒業したいと望むだろうか。
有無を言わさずにハーバードやMITだろう。
それらに入学し、卒業していく人間は世界中から集まってくる秀才たちであり、ビジネス界での強烈なコネクションとなることは間違いない。いくら同じ条件だとはいえ、現状の評価からいうと東京大学や京都大学はドメスティックな日本という国の中では高評価だろうが、一旦国の外へ出てみると大きく差を開けられている。
ここからいえるのは、世界的な意味での競争の只中に日本の有名大学が入らなければならないのか。入った上で勝ち残れるのかといえば、そもそも国の経済状況が芳しくないうえに、言語も日本語という唯一言語を利用するような、それこそガラパゴスな国の有名大学を出たところで何になるのか。
たとえば、同じ研究を行うにしても英語をはじめとした世界中で使われる言語環境で研究や学問を学び、そこで交友関係を深められた方が人生の選択肢が増えることは目に見えている。
そんな環境や状況の中で、これまでのようにノーベル賞を受賞するような研究者を輩出することが果たして現実的なのかといえば一定の割合で存在はしうるだろうが、これからは難しいと言わざるを得ない。
2012年にノーベル生理学・医学賞を共同受賞した山中伸弥氏。彼は現在iPS細胞研究所の所長だが、2022年3月での退所が決まった。しかし、よく考えてみると彼はマラソンを走っていたが、その傍らで研究費用を募金で募ってもいた。これをみて率直に「研究するための費用を募金で募らなければならないほどに研究費用の捻出に苦労していたのか」と思わざるを得ない。
そもそも彼が趣味でマラソンを走る分にはまったく構わないが、大々的に研究所の名前と個人名を出しつつ参加して募金を募らなければならないというのはどう考えても予算が足りないことを補填する広報活動だとみるしかない。そして、これが日本の大学研究における実情なのだろうと考えると非常に物悲しい思いを抱くが「最後は研究に注力したい」という言葉があまりにも痛々しく聞こえてしまうのは僕だけではないだろう。
▷ 微調整を含めてどんぐりの背比べ
ノーベル賞を受賞しているのにも関わらず、日本の研究所に残ってまで懸命に研究活動を繰り返してきた人材が研究を行う環境を満足に整えられないとなると、突き抜けることはできないのだと思わざるを得ない。
次に、いや既に起こっていることだろうが、携帯電話業界からガラケーの発端となった『微調整の嵐』が隆盛を誇るだろう。
NTTドコモが生み出した「i-mode」は世界に先駆けて携帯電話でインターネット通信を可能にした技術であることはご存知の方も多いだろう。さらにネット決済もできるようにしたり、動画も視聴できるような機能を備える優秀なソフトウェアだったが、iPhoneのような超絶クールなハードが生まれなかったため世界で覇権を握るまでには至らなかった。
結果、日本の中で起こったことは各種メーカーがカメラの性能を競ったり、ワンセグと呼ばれる携帯電話でTVを視聴できる機能の性能を競うなど、いま振り返ってみてもどんぐりの背比べをしはじめていた。
人口が減少していくことが確定しており、日本人をいかにして確保していくのかといった獲得競争に明け暮れることになる大学にも同様のことが起こるのは明白だ。
現に、専門学校に入学したとしても編入学等の制度を利用して学士が取れるような時代である。そこから言えるのは単一の学部学科として生き残ることは難しくなることが目に見えていることから、大学や専門学校などでは広範な魅力を訴えることが主流になるだろう。
つまり「この大学に入ればあれもこれもそれも叶えられる」といったデパート状態となることを意味するが、それは生徒募集のために行われるものであり、本質的な意味での大学が果たすべき「学問を極めること」や「深く高尚な研究をするため」ではない。(生徒集めができなければ大学を維持できないとする意見を否定するものではない)
こうなってくると結局は資本があり、大きな規模を有している大学が生き残ることになるだろうし、小規模大学であれば先鋭特化することで生き残りを果たそうとするため結果的に差別化していくだろうが、小規模であるが故に資金の問題へ常にぶつかり深い研究をするには至らず、結果的に優秀な教員職員が規模の大きな大学に流れるのだろう。
しかし、世界の大学競争において日本の大学が優位になるわけではない。つまり、井の中の蛙であり茹でガエルのままなのだ。これほど苦しいものはないが、そうなることがわかっているのであれば日本の大学に競争を求めるのはやめにして「今よりも悪くならないよう」にしてもらえればそれでいいのではないかとすら思える。
つまり、再び日本の人口が増えてくる段階では使用言語も多様化していることを期待するばかりだが、そこからはじめて世界で活躍できる人材、つまりはエリート教育を行うことに国庫からの資金を全力で投入することで世界における日本人の存在感を示すことだ。
▷ 地方大学の可能性
これらを鑑みると現状の人口の多い箇所に存在する大学よりも地方の大学の方が可能性があるのではないか。
直近で言えば地方回帰の流れが少しずつみられる。地方発での創業が決して冷遇されない現状は地方の中で優秀な人材を都会ではなく地方大学でプールし埋もれさえることなく活用することにより、若者が地方に残る理由を作れるようになった。
これによって地方の国立大学をはじめとした各種高等教育機関の存在意義を改めて定義することが可能となる。
大学を卒業すると同時に地方で起業するなどする土壌と、その経済をぶん回せるほどの経済性が地方で育まれること、要は経済を回せるだけの産業が生まれることが根付くことによって一定の地方には可能性があるだろう。
すべての地方都市にその可能性があるのかと言えば、それはない。
限界集落のような地方都市は人口が減少するのと同時に消滅させなければならないだろう。崖の上に残っている一軒家を残すために少ない税金を投入するのかと言えばすべきではないからだ。
地方都市でも集約が起こり始めるのと同時に、拠点となる大学が明白になるだろう。結果、その大学の近辺やほどない距離にある企業とが手を取り合いながら人材プールを上手に行なっていくことで立ち位置を明白にしていく。
つまり大学は就職予備校ではなく研究機関としての地位も得ながら、勃興するベンチャー企業の人材輩出も手がけ、その人材を受け入れる企業が多く生まれる土壌や経済を行政や政治がうまくカバーしていく。そういう意味では地方都市にある大学に可能性があるだろうと期待しているが、そうなるのかどうかは正直なところわからない。
なぜ、僕がこのような意見を書いたのかと言えば、地方都市で未来を生きなければならない子供と生活しているからだ。
そして、彼らが希望を抱けないような地方都市になってほしくないと願うからであり、そうなってしまった都市には未来なんてないだろうことが明白だからである。
期待はしたいが過度な期待は果たされなかった時に痛々しいほどの悲しみを生み出すため、ほどほどにしながら自身ができることは何かを模索するおじさんでいようと思う。
ではでは。
えんどう
▶︎ おまけ
▷ 参考となる紹介したいnote
以下のnoteに限らず、高等教育に関する意見が書かれたステキなnoteはたくさんあるのだが、これらは実際に読んだうえで紹介したいと思ったのでリンクを貼っている。(他にもステキなものはたくさんある)
▷ 著者のTwitterアカウント紹介
僕の主な生息SNSはTwitterで、日々、意識ひくい系の投稿を繰り返している。気になる人はぜひ以下から覗いてみて欲しい。何ならフォローしてくれると毎日書いているnoteの更新情報をお届けする。
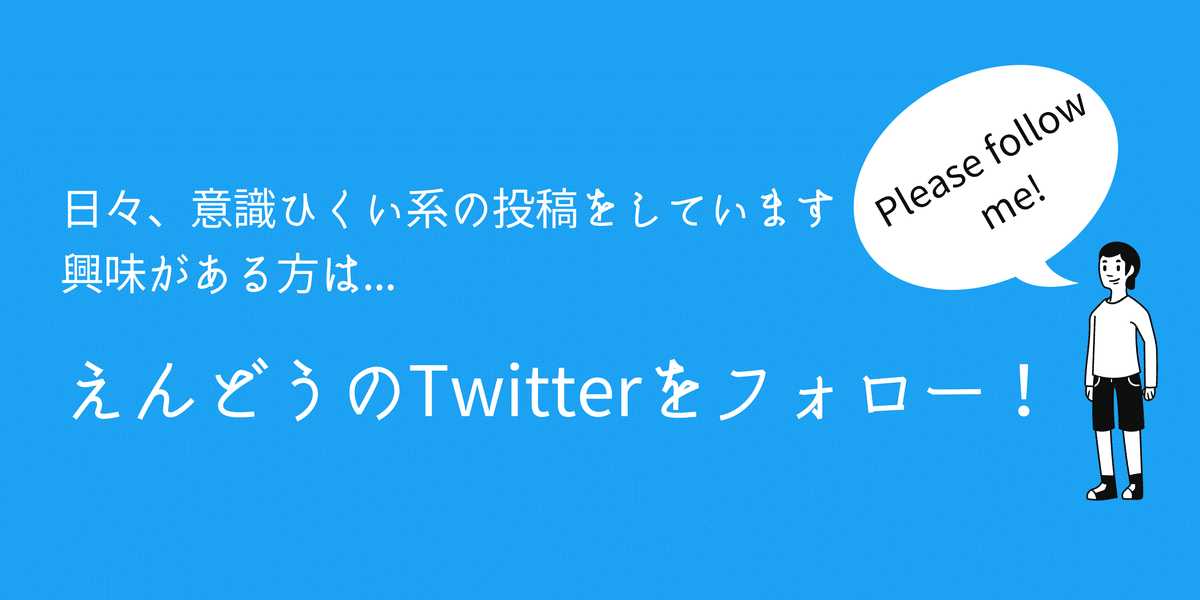
▷ 書籍紹介
デジタル庁の初代長官になることをかなり期待していた伊藤穰一氏。本人の実力や経験とは関係のない「知人が悪いから」という理由で長官の話は無くなってしまったが、その知見はぜひとも書籍から感じてもらいたい。ので紹介。
いいなと思ったら応援しよう!

