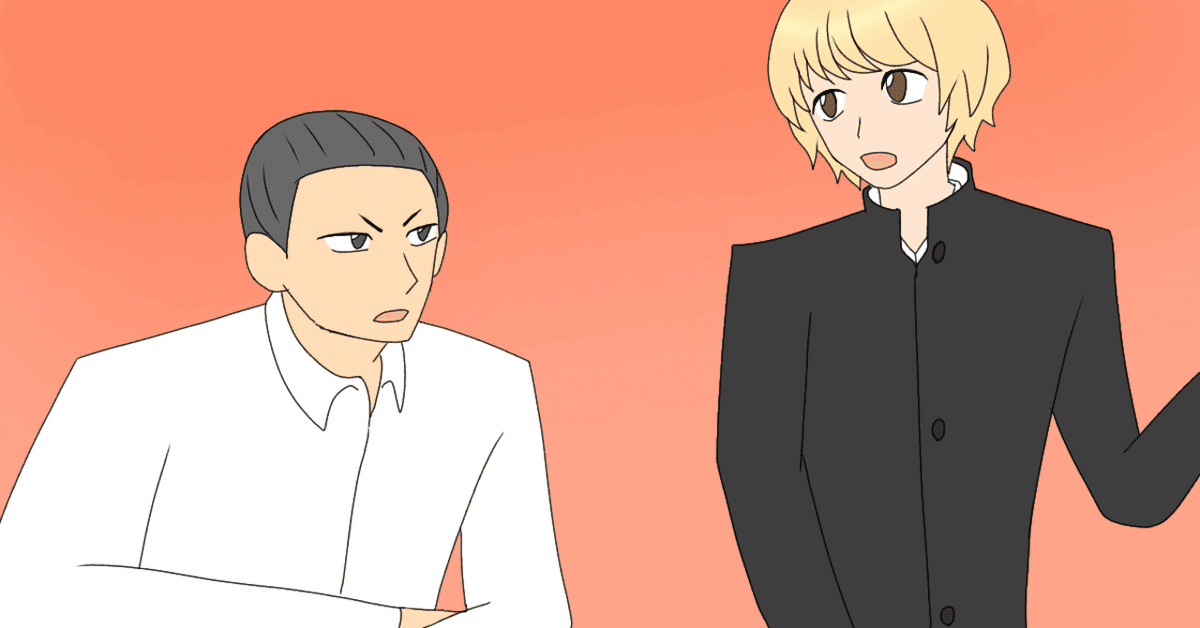
文芸部の放課後 やさしさの概念分析、あるいは創作論
文芸部の部室にいるのは、道明寺と僕の二人だけだった。
道明寺はいつものように原稿用紙に向き合い、僕はノートパソコンを広げている。僕たちは何かが僕らのそばを通り過ぎる一瞬を決して逃さないように沈黙している。詩であれ小説であれ、書くのは常に一人だ。
静かなときが流れる。誰もが何も語らず、何かを待っている。まるで祈っているかのように。僕はこの時間が好きだった。
詩になり得るイメージをつかもうともがきながらもそんなことを漠然と考えていた僕の耳に、不意に救急車のサイレンの音が響く。もしかしたら消防車かもしれない。僕にはよくわからない。ただ、サイレンの音は僕の記憶のものよりもずっと強く、長く響いていた。道明寺を見ると彼も窓の方を見ている。静寂は破られていた。
「執筆は順調……とはいかないようだね。さっきから手が止まってる」
「ああ。どうも考えがまとまらなくてな」
道明寺は答えると、軽く伸びをした。休憩の合図だ。
「どんな小説を書いてるの?」
「やさしさをテーマにした小説を書こうと思って。だが、なかなかに難しい」
「なるほど……でも、道明寺ってテーマから入る人だったっけ?」
ある程度創作活動をしてきた人間は大抵自らの創作ルールを持っている。もちろん僕が道明寺のそれの全貌を把握しているなんてことはあり得ないけれど、少なくともテーマを先に考えることに対して道明寺は批判的であるように感じていた。
「テーマを明確に語ることができるのならば、それを小説という形式で表現する必要はない、というのが俺の考えだ」
「ほう」
「だが、そもそも俺はテーマを考えてから小説を書くということを今まで一度もしたことがなかったんだ。試したことのないアプローチを批判するのもどうかと思ってな。今回やってみることにした」
「なるほど。やさしさ、ねぇ……」
「如月はどう思う? やさしさとは何か」
やさしさとは何か。改めて問われると難しい。
もちろんありきたりな具体例を挙げることは可能だ。けれどそれはやさしさの具体例であって「やさしさ」そのものではない。それに、少なくとも今僕が思いつく具体例はどれも、本当の意味でやさしさを表しているかと考えるとはなはだ疑問であった。
「例えば僕がある女の子に親切なことをしたとする。何でもいいんだけれど、その子が体調不良で学校を休んでいたときの授業のノートを見せてあげる、とかさ。それは『やさしい行動』ではあると思うのだけれど、仮にその子がクラス一の美少女で、僕はその子の気を引きたいという理由もあってノートを見せてあげたのだとしたら、そのやさしさは、なんというか、純粋なものではないような気がする」
「俺もそう感じるな」
「つまり、ある行動が『やさしい』ということを心から納得するためには、その行動が純粋に利他的なものでなければならない」
「なるほど」
問題はここからだ。純粋に利他的な行動とは何か。そもそもそんなものが存在するのかどうか。
「さっき簡単に調べただけなのだが」
道明寺が言った。
「生物学においては、一見純粋に利他的行動に見えるものも実は自分に何らかのメリットがあるからこそ行われる、と考えられているらしい。自然選択説を維持するにはそう考える他ないのだそうだ。だが、そうだとすると……」
「純粋な意味で利他的な行動など、どこにもないことになるね」
「ああ」
「よってやさしさもどこにもないと」
「そうなるな」
道明寺は押し黙ると、しばらくの間、空中にある何かをじっと眺めていた。
「だがそれは直感に反する。
やさしさは、確かに存在する」
「その直感は幻想かもしれない」
「直感を信じられなかったら、小説など書けない」
「そりゃそうだ」
僕は考えてみた。少し振り返ってみたいと思う。
「僕たちはやさしさとは何か考えるにあたって、まずとっかかりとして『やさしい行動』について考えてみることにした。そしてその行動がやさしい行動であるには、純粋な利他的行動であることが必要だと仮説を立てた。
純粋な利他的行動とは何か。これも難しい問いだけれど、とりあえずは自分の利益にはならないが、他者の利益にはなる行動、とでも考えればよいと思う。
しかしここで問題が発生する。現代の科学の成果によると、自分の利益にならない、かつ、他者の利益になるような行動は存在しない。純粋に利他的に見える行動も、よくよく調べてみると自分の利益にもなっている。少なくともそのように考えられている。
したがって純粋に利他的な行動は存在しない。それゆえやさしい行動も存在しない。それはやさしさが存在しないことを示唆している」
最後は若干の飛躍があるように感じる。もちろん最後だけではない。突っ込みどころはいろいろとあるだろう。
「とりあえずやさしい行動であるためには純粋に利他的な行動である必要がある、っていうところと、純粋に利他的な行動の定義が怪しい気がする。個人的には科学を信じ切っているところもあまり好きじゃないけれど」
「生物学についてはちょっと調べただけだから、俺の解釈が間違っているのかもしれない。まぁ今回はそこは大目に見てくれ。
如月の言い分もわかるが、俺はその二点は問題ないと思う。
つまり、自分の利益にはならないが、他者の利益になる行動が実際に存在する、すなわちその意味での純粋に利他的な行動は存在するし、その中には真の意味でやさしいと言える行動もある、と俺は感じているんだ。その二点を曲げてしまうことはできない」
「なるほど。じゃあその路線で考えてみよう。でも、そうすると現代科学に真っ向から対立することにな……」
対立することになる、のだろうか。
ならない方法もあるような気がしてきた。
「純粋に利他的な行動は自然選択により淘汰される。したがってそのような行動は起こりえない……。いや、別に起こっても良いんじゃないかな? 人間は完璧じゃない。常に完璧に正しい行動ができるわけでは決してない。自分の利益には一ミリもならない、むしろ害にすらなるかもしれない、人を思いやった行動を、人間は取り得る。
言ってしまえばそれはエラーだ」
「なるほど」
再びの沈黙。水曜日の放課後だというのに、今日の学校は嫌に静かだ。
「やさしさの正体はヒューマンエラー……まったく、皮肉が効いている。しかし、ではなぜ俺たちはその『やさしさ』に触れて、心を動かされるんだ? まさか珍しいから、なんてわけじゃないだろう?」
「それもあると思うよ。希少な現象に僕たちは心を奪われがちだ」
価値があることは希少であるが、逆は真ではない。けれど人間は過ちを犯す。それは歴史が証明してきたはずだ。けれど……。
「けれど、それだけじゃない。むしろ希少であることは些細な問題に過ぎない。むしろ重要なのは」
僕はそこで言葉を切った。つまりどういうことなのだろう。それは。
「やさしさによって人は死に接近する。だからやさしさを美しいと感じる」
間違いを犯せば死ぬこともある。一回の過ちで死んでしまうこともあるし、積み重なった間違いが死に導くこともある。そういうことだ。
「なるほど」
と道明寺は言った。
人は死を恐れている。
一方で、どうしようもなく魅せられている。
「まったく僕たちは矛盾した存在だよ。不死すら願うほどに死を恐れていながらも、死に対して憧れにも似た気持ちを抱いている」
「そうとも言い切れないんじゃないか?」
「本気で言っているのかい?」
道明寺は肩をすくめた。
「芸術が、哲学が、数学が、存在しているんだ。僕としてはそれをもって証明としたいところだけれどね」
「……その証明を認めよう」
「やれやれ」
それから僕たちは構内の中庭に設置されている自販機に缶コーヒーを買いに行った。日はすっかり暮れてしまい、外の空気は僕が考えていたよりもずっと冷たい。僕はブラックコーヒーを買い、道明寺は嫌に甘いものを選択した。もちろんホットの方だ。コーヒー缶が冷えた僕の手を温める。もう校舎にはほとんど人がいないようだった。僕たちは自販機の前でコーヒーを飲んだ。会話の続きが始まる。
「やさしさは間違いであり、やさしさは死である。適当な分析の割にはなかなか詩的な結論にたどり着けと思うよ」
「試してみるものだな」
「だね」
「……しかし」
と道明寺は言った。僕は彼が「しかし」という接続詞を述べることを予期していた。なぜなら僕は、まだ彼の考えを聞いていないからだ。
「俺はその結論を理解はできても納得はできない」
「なるほど」
「やさしさは正しい。やさしさは間違ってなどいない」
道明寺は缶コーヒーの最後の一口を飲み干すと、缶をゴミ箱に捨てた。そして再び口を開く。
「するとどうなるか。簡単だ。やさしさは存在する。だが、この世界には存在しない。確かにある。だが、俺たちがそこにたどり着くことはない」
「ずいぶんプラトニックな答えだね」
と僕は言う。
「それが君の出した答えなのか?」
道明寺は目を閉じる。そして答えた。
「答えではない。例えて言えば、これは一つの物語の結末に過ぎない。如月だって、そうだろう?」
「まあね」
と僕は答えた。
そこで僕たちは沈黙する。どうやら対話は終わったようだ。
「今日はなかなか面白かったよ。けれど、素朴な疑問なのだけれど、やさしさをテーマにした小説を書くのに、『やさしさ』の概念分析なんてする必要はあったのかい? 実際にやってみてどうだった?」
「どうだろう……今日初めてやったことだから何とも言えないといえば言えないのだが、『やさしさ』についての分析が足りないのか、あるいは、俺にこのやり方があっていないのか……」
「まだはっきりしていないようだね」
「いや、一つだけ揺るぎない事実が存在する」
「ほう。それは?」
「それは……概念を分析したところで、さっぱり何も思い浮かばなかったということだ。物語も、登場人物も、世界も」
「……」
「もう少しこの方法を続けようとは思っているが、俺の直感としては、どうもこの方法、テーマを考えてから小説を書くという方法は俺には向いていないらしい。だがこの方法を試してみたことにはいろいろな価値があると思う。少なくとも俺が思考できる世界は広がった」
「それはよかった」
「無駄ではなかった、ということだ」
「……無駄ではなかったと言えば、僕は昔から『価値』について、漠然とした疑問を持ち続けているんだ」
「というと?」
「正確に言うと、もっと細かい問題なんだけれど。
簡単に言うとね、幸せな人生と、価値のある人生、どちらが優れているか、ということについて」
「ほう」
「考えてみないか?」
「第二ラウンド、というわけか」
「そうなるのかな」
「勘弁してくれ」
「嫌だと言ったら?」
「……やれやれ」
僕たちは駅に向かって並んで歩いている。
完全とは言えない満月が僕らを照らし、冬のはじまりの風が吹いた。
