いまこそ、広告はブランディングに回帰すると言うけれど
どうも、広告屋のエルモ(@elmo_marketing)です。
今日は、最近マーケティング業界でよく聞く「いまこそ広告はブランディングに回帰する」について。機能や価格競争では勝者がひとりだけなので、ブランディングで顧客に選ばれる理由を作ろうって話ですね。
この記事を書こうと思ったきっかけは、NIKEのブランドムービー。
動かしつづける。自分を。未来を。#YouCantStopUshttps://t.co/EEkOkOOeLt pic.twitter.com/aPnZcPAO05
— Nike Japan (@nikejapan) November 28, 2020
ご存じの通り、この120秒の映像CMはバズりにバズり、日本国内向けのプロモーションにもかかわらず、米国(CNN)や欧州(BBS)のニュースで取り上げられるまでになりました。
ただし今日の話は、NIKEプロモーションムービーの内容ではなく、
このブランドムービーを、他の企業が発信したらどうなっていたのか?
を視点に考えてみたいと思います。
ブランディングの存在意義
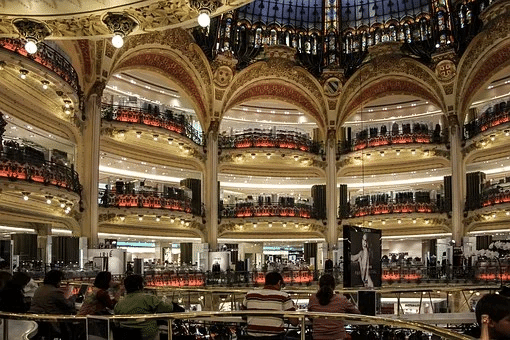
消費者視点にたつと、いまほど多くのブランドに囲まれている時代はありません。
あなたが気付いていないだけで、1日に数百、多いときには数千のブランドを無意識のうちに見かけています。
ぼくら消費者は、日々大量に接するブランド群の中から、「ある商品を選ぶ」という意思決定作業を毎日の消費活動でしているんですね。
ただ、”選ぶ”にも労力がかかります。人はできるだけ労力をかけずに、手間をかけずに良いモノを選びたい生き物。失敗もなるべく避けたいです。
なので、自分が知っていて、かつ印象の良い(イメージの湧く)ブランドを購入します。
わざわざ手間暇かけて新しいブランドを探すよりも、自分が知っているブランドのほうが楽。さらにいうと、なんとなく知っているだけではなく、そのブランドが提供する商品イメージがハッキリ分かるものなら安心して買える。
かくしてマーケティングにおいて、こういう不等号の関係性が成り立ちます。
【未認知】全く知らない
<<【認知】知っている
<<【ブランディング】知っているしイメージもある
つまり、ブランディングというのは、膨大な他ブランド群から抜け出すため(顧客に選ばれる確率を上げるため)に、自社商品とイメージを結びつけるものなんです。
なので、基本的にブランディングは全企業が取り組むべきものだと思っています。ただし、実際にブランディングを推進するのは難しいのもまた事実です。
ブランドムービー、どれくらい見られているのか問題
ブランディングのために、素晴らしいロゴやコピーを制作した。でも、作っただけでおしまい。ブランディング施策前後でとくに変化が起きなかった、なんて話は枚挙にいとまがありません。
ちなみに、ブランドムービーもそのひとつ。
やっと冒頭の話に戻ります。
あのNIKEのCM。
自社の企業スタンスを表し、社会に問題提起を起こしたあのムービーは、NIKEだからこそ、多くの人目に触れ、拡散されたのではないでしょうか?

ちなみに、NIKEのtwitterフォロワーは35万人。この自社リーチがあるからこそ、初回から多くの人に見てもらえたという事実があります。
これがフォロワー500人のスモール企業だったらどうだったのだろうと。
さらにいうと、NIKEのブランドムービーの尺は2分あります。
ここもひとつミソだと思います。
NIKEのCMが炎上したと言われていますが、実際にはソーシャルメディアにコンテンツを投稿しただけ。テレビCMやYouTubeなどの広告は使っていません。(たぶん)
最近強く思うのが、消費者に「広告枠×映像」でメッセージを伝える難易度が上がってきている点です。
テレビCMであれば、尺は15秒か30秒。これでは、時間の制約があり、伝えたいことをハッキリ伝えることができません。表現の自由度が高くないので、みな似通ったCMになってしまうんですね。
一方のYoutubeの広告枠であれば、好きなだけ長いムービーを広告で出すことができます。ただし、Youtubeにはスキップ機能があります。つまり、120秒のような長尺ムービーを最後まで見てもらえる保証はどこにもありません。
ということで、広告を使ってブランドムービーを流すには、せっかく作ったブランドムービー(多くのものは2分~10分)から、良い箇所を15秒30秒CMに圧縮して世に出すか、最後まで見られるか分からないリスクをとってYoutubeに出す必要があります。
あたりまえですが、どちらも広告。お金がかかる行為です。ずーっと大量の露出を続けることはできません。
という背景がありまして、せっかく作ったブランドムービーが見られない問題が発生しているのが現実です。
「ブランドムービー」で検索すると、世に出されたもののあまり見られていないであろう各企業の映像がたくさんでてきます.......
それは知名度のある有名な企業であろうと例外ではありません。
ソーシャルでユーザーと常時接続しているブランドが強い
結局それかと言われそうですが、ソーシャルや自社メディアで日頃からユーザーと繋がっているブランドはそれだけで強いという結論に行き着きます。
クリエイティブディレクターの水野学さんは、「ブランドとは”らしさ”であり、ブランディングとは”見え方のコントロール”である」と言います。
この”らしさ”を演出するのが、日々のコミュニケーション。顧客との”線の繋がり”です。
たとえば、NIKEらしいという言葉は、過去のイメージが顧客の頭の中にあって生まれるもの。たった1回の点のコミュニケーションから「〇〇らしい」という言葉は絶対に生まれません。
つまり、らしさを作り出す方法とは、一発逆転を狙って「ウチはこんなブランドなんだ!」と伝えるのではなく、日頃の蓄積の先にブランドアクションを起こすことなんです。
要は、日頃から発信を続けて、「このブランドってこうだよね」というイメージを蓄積している企業が強いんですね。
さらに言うと、ソーシャルで発信しているブランドは、フォロワーも自然と多くなります。NIKEのように35万人までいかなくとも、数千人、数万人のフォロワーがいるだけで、拡散の土台が生まれます。
長尺化するブランドムービーを多くの人に届けるには、ソーシャルでブランドが好きな人に拡散してもらうのが一番だよねって話です。
【さいごに】ソーシャル時代のブランディング
今日は、珍しくブランディングについて書いてみました。
実は、ブランディングって大きく3つのレイヤーに向かって行われます。
①インナー(そのブランドで働く人たち)に向けて
②ブランドのファン(日頃から接してくれている人たち)に向けて
③これからブランドに接して欲しい未認知・無関心層に向けて
よく聞くのが、「このブランディングはインナー向けだから、マーケットで反応がなくても問題ない」という、ある種言い訳にも聞こえるコトバです。
しかし、これはソーシャルが存在しなかった平成中期までの言い分だと思います。
ネット、ソーシャルの登場で透明性が上がり、ウラもオモテもなくなった今では、真に良いインナーブランディングはアウターブランディングにも繋がります。
そのときに肝となるのが、繰り返しになりますが、②ブランドファンとどれだけ繋がっているか?です。
理想の話になっちゃいますが、
①インナー(自社コンテンツを発信)
⇒②ファン(ファンが拡散する)
⇒③見認知層(普段自社に関心を持たない人にも届く)
ソーシャルパワーをうまく使えば、
「インナー⇄ファン⇄ライト層」まで一貫してコミュニケーションを取れる可能性を秘めているのだと感じます。
ということで、ソーシャル時代にうまくブランディングムービーを流通させるには、日頃からの発信が肝だよねという身も蓋もないnoteでした。
一発逆転を狙いがちですが、コツコツ発信するほうがよっぽど大事。
らしさを生み出すのは、少しの質と接触頻度の向上がカギですよ。
それでは。
twitterでも情報発信をしているので、よかったらフォロ―してください。
マーケティングとキャリアの攻略法というメディアも運営しています。
こちら、人気記事です。
【2021年厳選!】Webマーケティング転職に強い転職エージェント&転職サイトオススメ11選!
いいなと思ったら応援しよう!

