
【期間限定無料】こんな終わりかたをした理由は?──フリオ・コルタサル「続いている公園」(5)
コルタサルの「続いている公園」についての記事、最終回です。
前々回に書いたように、「続いている公園」の結末で狙われるターゲットは、
かなりの高確率で、
(a)その小説を読んでいる〈彼〉当人
だけど、
(b)〈彼〉が読んでいる小説のなかに出てくる、たまたま彼と同じような状況で本を読んでいる一登場人物
である可能性を100%排除することはできない
なわけです。
ということは、ですね。
どうしてこんな終わりかたをしているのか?
冒頭の、農場経営者である〈彼〉は、「続いている公園」の視点人物です。僕ら読者は、いわば彼の「手持ちカメラ」でもって、作中世界の現実を見ます。
その作中世界の現実のなかには、〈彼〉が読んでいる本も含まれます。
もし手持ちカメラの映像がとつぜん途切れてしまったら、カメラの動作に、ひいては撮影者の身に、なにか起こってしまったのではないか、と一般には考えます。
同じように、〈彼〉が読んでいる小説(犯罪小説?)の要約が続いてきたのに、ここぞというところでそれが途切れてしまったら、視点人物である〈彼〉の動作に異変が起こったために、要約がそれ以上報告されなくなったということが想像されるわけです。
つまり
(a)案が「ことが起こる直前で「続いている公園」という小説が終わる」
のにたいして、
(b)案だと、「作中作の内容中継を終わらせるような「こと」が起こったから、「続いている公園」がそこで終わってる」
わけです。
作中作の内容は農場経営者である〈彼〉の意識をとおして、僕らのもとに届いていました。
ですから、作中作の要約がここでいきなりぶつ切れとなり、その中断をもって「続いている公園」自体が終わってしまうことは、その「中継する意識」自体が消失してしまったことを示唆しているように見える。
つまり、作中作のこの殺人場面を読んでいるまさにそのときに、〈彼〉の身になにかが起こったのです。
これは「続いている公園」を含む『続いている公園』の5年前に刊行されたサミュエル・ベケットの小説『マロウンは死ぬ』(1951)が、語り手マロウンの話(マクマンという人物にかんする話)の途中で終わってるのになんとなく似てる。

あれもそのせいで(あとは題名のせいもあって)、「あ、マロウン死んだな」と思わせる。
まとめ
・(a)案だと、冒頭の〈彼〉と結末の〈小説を読んでいる男〉とは同一人物だが、このあとが書いてないから、冒頭の〈彼〉の安否は不明(=作中作の殺害計画の成否は不明なので)
・(b)案だと、冒頭の〈彼〉と結末の〈小説を読んでいる男〉とはべつの世界に住むふたりの人間だが、このあとが書いてないから、冒頭の〈彼〉が殺されたという可能性が案より高い
てことになってしまう。
(a)案だと「書いてないから安否は不明」となるのにたいして、(b)案だと「書いてないから〈彼〉は死んだにちがいない」となる感じがおもしろい。
しかもです。
(a)案だと、〈彼〉が小説のどの部分を読んでいるときに襲われたのかは必ずしも確定しない。
これにたいして、さっき書いたように(b)案だと、〈彼〉が小説の殺害場面(小説を読んでいる男が殺される)を読んでいるまさにその瞬間に殺されたっていうことが推測できる。
そこも、僕がつい(b)案に肩入れしたくなっちゃう理由なんです。
(詳しく書くとネタバレになるけど、(b)案はガルシア・マルケスの『百年の孤独』[1967]の結末、アウレリアーノ・バビロニアの死にざまにけっこう似てます)
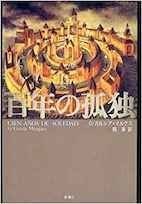
「続いている公園」はとても短いお話なのだけど、このように、
・物語階層
・視点
・解釈
・伏線
などのさまざまな話題を提供してくれます。
読むと、
「そうか、僕の(あるいは人間の)脳というのは、小説の文章(あるいは言語一般)を、こんなふうに情報処理しているのか」
ということに、いろいろ気づかせてくれるわけです。
あ、「伏線」と書いたけど。伏線の話はまだしてませんでしたね。
おまけ 伏線とフラグの違い。
読書会的な場所でこれを取り上げると、
「なんとなく自分も後ろを振り向きたくなった」
という感想があるんです。自分も背後から殺られるんじゃないかって思うわけですね。
その感じが気になるかたは、『続いている公園』の3年前に刊行されたフレドリック・ブラウンの『まっ白な嘘』(1953。中村保男訳、創元推理文庫《フレドリック・ブラウン短編集》第1巻)に収録されている「うしろを見るな」をお読みください。
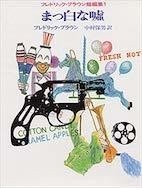
「続いている公園」の作中作の読書中の男に起こったこと(小説を読んでいるときに襲われる)が、それを読んでる作中現実の〈彼〉にも起こったのだったら、その小説「続いている公園」を読んでいるこの僕にだって、たしかに起こるかもしれない。
その感じを保証するのは、(a)案よりも(b)案なんじゃないかなあと思うわけです。
そう思って冒頭を読み直すと、こんなことが書いてある。
不意に人が入って来そうで落ち着かないので、ドアに背を向ける格好で愛用のひじ掛け椅子に腰をおろし、左手で緑のビロードを撫でながら残りの章を読みはじめた。〔強調は引用者〕
これが伏線だったかー、と感心しますね。
僕は「伏線」と「フラグ」とを区別して使います。
のちの展開を予想させるものはフラグ。
あとから思い出して(読み直して)「そういえば書いてあったな」と思わせるのが「伏線」。
だから同じ〈不意に人が入って来そうで落ち着かない〉にしても、初読時にここをなにげなく読み飛ばしてしまった僕にとっては伏線なんだけど、初読時に「これはきっとあとで、不意に人が入ってくるに違いない」と思って読んだ人(サスペンス小説を読み慣れてる人とかかなあ)にとってはフラグとして機能しているということになります。
次回の「文学理論ノート」予告
次回、今月中に更新できるかどうかわからないんですが、アゴタ・クリストフの『悪童日記』(1986。堀茂樹訳、ハヤカワepi文庫)を読んでおいてください。

例によって完全にネタバレするので、読んでてほしいです。
「続いている公園」についての文章を、最後まで読んでくださってありがとうございます。またおつきあいください。
(↓こちらへつづく)
この連載の目次はこちら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

