
【期間限定無料】ノートがそこにある理由──アゴタ・クリストフ『悪童日記』(堀茂樹訳、ハヤカワepi文庫)
またもカヴァーでネタバレ
やがて、久しぶりに再会した母は死に、戦争が終わり、祖母も息を引き取るが、国境には地雷原があり、越えることができない。
ある日父が会いにくる。
ふたりは国境を越えたがっている父を騙して、父に地雷を踏ませる。
ふたりのうちのかたほうがその死体を踏んで国境を安全に越え、もうひとりが家に戻るところで『悪童日記』は終わります。
またネタバレかよ! という話ですが、こないだのフリオ・コルタサル『遊戯の終わり』(1956。木村榮一訳、岩波文庫)所収「続いている公園」がカヴァーでネタバレしていたように、
この『悪童日記』も日本語訳が文庫化されたときの最初のカヴァー絵でネタバレしてます。
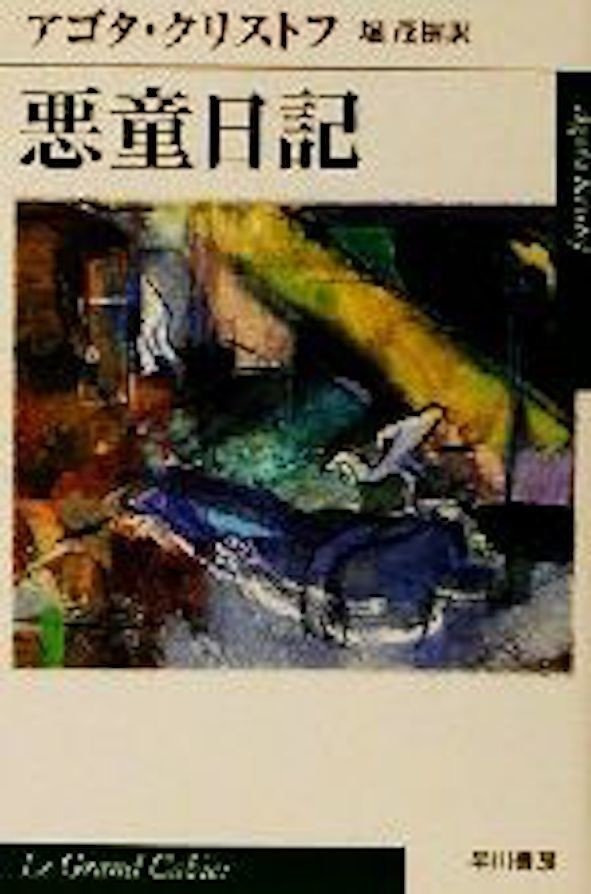
第2部以降のこと
このあと第2部『ふたりの証拠』(1988。堀茂樹訳、ハヤカワepi文庫)は、国内にとどまったルーカス(リュカ)・Tのその後を語ります。

淡々とした語りの背後に、彼の過去と例の〈大きなノート〉の存在を巡って、不穏な雰囲気が立ちこめているな、と思ったら、結末でいきなり壮大な前言撤回をやってのけます。
つづく完結篇『第三の嘘』(1991。堀茂樹訳、ハヤカワepi文庫)では冒頭から度重なる前言撤回の連打で、素朴な読者などは読了後、小説に書いてあることのいっさいが信じられなくなってしまうかもしれません。

この小説は第1部がいちおうの完結感をもって締めくくられていますし、第1部だけが映画化されていることもあり、そこで読みやめている読者も多いのです。
それではジェットコースターの最初の上り坂が終わったところで後ろ向きにゆっくり出発地点に戻ってきて降りてしまうようなものですね。3部作がメタフィクションとしての顔をはっきりと見せはじめるのは、第2部も終盤にかかってからのことです。
とはいうもののこの3部作は、第2・3部だけがメタフィクショナルなのではありません。そもそも第1部にすでに問題の種が周到に蒔かれています。
小説の言葉はどうやって読者のもとに届くのか?
それはなにかといえば結末の、双子の別れの場面です。
そう、国境を越すための手段が一つある。その手段とは、自分の前に誰かにそこを通らせることだ。
手に亜麻布の袋を提げ、真新しい足跡の上を、それから、おとうさんのぐったりした体の上を踏んで、ぼくらのうちの一人が、もうひとつの国へ去る。
残ったほうの一人は、おばあちゃんの家に戻る。〔273頁〕
この、なんの説明もないエンディングは、古今の長篇小説の結末のなかでも、もっとも衝撃的なもののひとつかもしれません。
このように、双子は小説の最終一文で、生まれてはじめて自分の意志で別れ別れとなってしまいました。
では、ノートはどうなったのでしょうか? ノートは国境を超えたのか、それとも国内に留まったのか?
ノートは国境を超えたのか、それとも国内に留まったのか?
そもそもこの〈大きなノート〉(先述のとおりこれは『悪童日記』の原題です)の文面は、いったいどうやって読者のもとに届いたのでしょうか?
布袋の準備をしているときには、ノートに言及されませんでした。
おばあちゃんの宝物を土の中から掘り出す。金貨や、銀貨や、たくさんの宝石だ。その大半を、亜麻布の袋に入れる。一人一個、手榴弾も身につける。〔269頁〕
つまりノートは国境へと持っていかれなかった、ということになります。
しかし最大の証拠は、最終の一文にあります。
ぼくらのうちの一人が、もうひとつの国へ去る。
残ったほうの一人は、おばあちゃんの家に戻る。〔273頁〕
もし、〈大きなノート〉の文章が、「ぼくらの学習」の章に申告されていたように、
作文の内容は真実でなければならない〔…〕。ぼくらが記述するのは、あるがままの事物、ぼくらが見たこと、ぼくらが聞いたこと、ぼくらが実行したこと、でなければならない。〔42頁〕
のだとしたら、最後の
残ったほうの一人は、おばあちゃんの家に戻る。〔273頁〕
も、〈ぼくらが見たこと、ぼくらが聞いたこと、ぼくらが実行したこと、でなければならない〉。
国境を超えたほうの兄弟は、相方がほんとうにそのあと〈おばあちゃんの家に戻〉ったのかどうか、見ていません。
ということはこの最終章は、国境の手前に〈残ったほうの一人〉、〈おばあちゃんの家に戻〉ったほうの兄弟によって書かれた、ということにならざるを得ません。
最終章の編集方針
そう考えてみますと、この〈大きなノート〉は国内にとどまったと思いたくなります。
事実、続篇『ふたりの証拠』を読みはじめると、いったんはその想像が補強されます。
しかしさらに3部作を読み進めていくならば、第2部の結末で起こる青天の霹靂ともいうべき壮大な前言撤回によって、ことはそれほど単純ではないということを思い知らされてしまうことになるのです。
が、前回書いたように、ここではいったん、『悪童日記』を独立したものとして読んでいくことにします。
もう一度『悪童日記』に戻りましょう。
筋の展開に目を奪われていると気づきませんが、〈大きなノート〉の執筆方針を思い出してください。どちらかいっぽうが書いたら、他方がそれをチェックするはずではなかったでしょうか?
もし想像されるとおり、作品の本文が作中に言及された〈大きなノート〉と同一だとするなら、この最後の章だけは、どちらかいっぽうが書いたままで他方のチェックを受けていない、ということになります。
小説の言葉は僕らのところにどうやって届くのか
小説っていうと、密室のなかで登場人物がやったこととか、登場人物の心のなかのこととかが、盗撮・盗聴されて読者のもとに直接届くかのような印象を持っている人が多いんですね。
だから、ついこの『悪童日記』も、現在形の文章の臨場感?とやらに騙されて、双子の行動を隠し撮りしたようなものと勘違いしてしまう。
僕はかつて、よく大学生のみなさんといっしょにこの小説を読む機会があったのですが、
「この〈大きなノート〉は国境を超えたと思いますか?」
と訊くと、そんなこと考えたこともなかった、っていう人がほとんどでした。
そもそも小説というのは言葉でできています。そして、その言葉というものには、それを書いたり喋ったりする発信者がいる。
小説はこの200年弱のあいだ、そのことを隠蔽するかのように発展してきて、僕ら読者はついつい小説の文面を、
「作中世界に無数に配置された盗撮装置・盗聴装置・読心装置(!)からのダイレクト発信」
のように捉えてしまいがちです。
でも小説がそういうものと見られるようになったのはせいぜいこの 1世紀あまりのことなんじゃないかなあと思います。
このマガジン「文学理論ノート」では、そこのところにしっかり気を配って小説を読んでいこうと思っています。
次回の「文学理論ノート」予告
次回、イタロ・カルヴィーノの《我々の祖先》3部作の最終篇『不在の騎士』(1959)を読みます。
最終篇といっても、独立して読めるものなので、他の2篇を読んでない人がこれから読み始めても不都合はありません。これもネタバレするので、読んでてほしいです。

僕はとりあえず、白水Uブックス《海外小説 永遠の本棚》版の米川良夫〔りょうふ〕訳に依拠して話を進めようと思います。
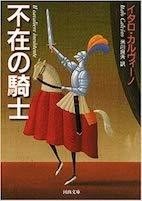
この小説の米川訳には他に河出文庫版、国書刊行会《文学の冒険》版があります。

また、松籟社《イタリア叢書》第8巻がこの小説の脇功訳です。

この小説のいちばん早い時期の訳は、學藝書林《全集・現代世界文学の発見》第12巻『おかしな世界』に収録された本川洋子訳です。

これはフランス語訳からの重訳らしく、人名もフランス化した人名をそのまま音訳してしまっている。積極的にはお勧めしませんが、ストーリーを読むうえでは支障ありません。
言語によって固有名が変わるというのがどういうことなのかについてはいずれ機会があれば書きたいなあと思っています。
最後まで読んでくださってありがとうございます。
ではまた、つぎの「文学理論ノート」で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

