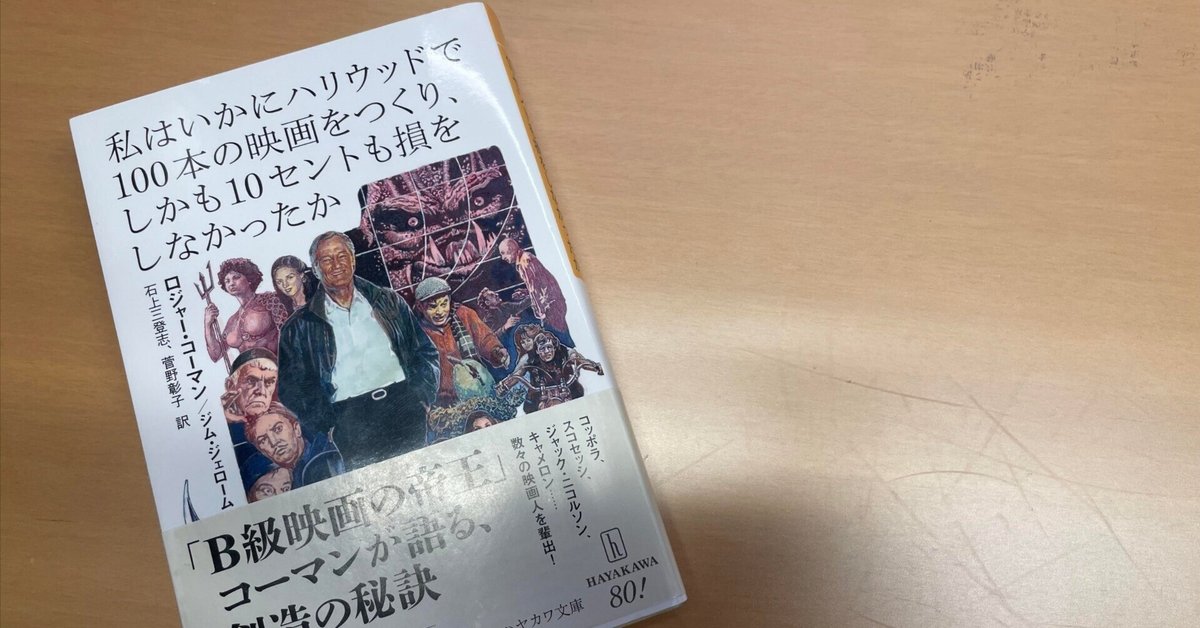
【読書感想文】「私はいかにハリウッドで100本の映画をつくり、しかも10セントも損をしなかったか」映画ファン最強のビジネス本
1.ロジャー・コーマン伝説の自伝はビジネス書だった
みなさんは、ビジネス書は好きだろうか?
自分はあまり好きではない。抽象的であたりまえのことしか書かれていないことが多いからだ。そして、実践するには難しく、一時的に分かった気になる「読むエナジードリンク」だと思っている。最近は、群論の勉強をしており具象/抽象の関係性を掴んできたので、アレルギーは減ってきたものの、やはりビジネス書を読むなら具象で殴ってきてほしいものがある。抽象は哲学書で嗜むからと。そんな中、素晴らしいビジネス書に出会った。
それがロジャー・コーマン「私はいかにハリウッドで100本の映画をつくり、しかも10セントも損をしなかったか」である。『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』や『X線の眼を持つ男』などといったジャンル映画を数多く手がけ、フランシス・フォード・コッポラ、マーティン・スコセッシをはじめとする巨匠を輩出したアメリカ映画界のドンことロジャー・コーマンの伝説的自伝である。名前は知っていたものの、今まで手にする機会がなかったのだが、先日、文庫版が発売されたので購入して読んだ。映画監督の自伝はエピソードの宝庫なので面白いのだが、本書はウィリアム・キャッスル「STEP RIGHT UP!...I'm Gonna Scare the Pants Off America」に匹敵する創意工夫に満ち溢れた映画戦略が書かれていた。
確かに昨今のコンプライアンスから考えると、やりがい搾取を匂わせる証言があったり、買い付けた『日本沈没』のフィルムを勝手に編集、日本パートをできるだけカット、そして『大津波』というタイトルで売り出しヒットさせたりと問題はある。それでも、パワフルに限られたリソースの中でやりたいことを実践していくロジャー・コーマンの生き様には元気づけられた。
2.ロジャー・コーマンはエンジニアだった
まず、驚かされたのはロジャー・コーマンは元々理系だったということだ。若い頃は映画監督になろうとは全く考えていなかったようで父親と同じエンジニアの道を進んでいた。大恐慌の中育っていたので、周囲では賃金カット、リストラ/レイオフの話が蔓延していたが父には仕事があった。幼少期からできるだけ文化に触れるよう教育されており、新聞配達のアルバイトをしようものなら「おとなになったらいやでも働くことになるんだよ」と辞めさせるような家庭であった。そんな父は43歳という若さでFIREし平和な暮らしをしていた。今の日本基準で考えると、最強の文化資本に恵まれた環境だったことがうかがえる。
ロジャー・コーマンは将来を考える際に、エンジニアとして専門知識をつけようとする一方、文章を読むのも書くのも好きだったため、文芸関係の仕事に就く選択肢も念頭に入れていた。実際に高校新聞によく寄稿していたと語っている。大学時代に、エンジニアにはならないと決めるものの、第二次世界大戦中だったため、ある程度自由が認められている海軍士官プログラムに志願した。戦後、彼はスタンフォード大学へ復学する。その中で、大学の批評誌を始めとするメディア制作に携わり、映画業界への関心が大きくなった。ただ、映画業界の組合員でなかったため仕事はなく、無職に苦しむ。仕方なくエンジニアの仕事に就くが3日で退職した。彼はこの時、上司へ次のように語った。
たいへんな間違いをしました。仕事をやめなければなりません。きょうです
ラッキーなことに1948年後半、友人の父親からの紹介でフォックスに潜り込めたのだ。
3.読者を惹きこむ短くパワフルな文章
ロジャー・コーマンの文章は、元エンジニアということもあってか一文が非常に短い。そして、最初に結論や問いかけから始まり、事実と数字ベースで語っていく。また、文芸に魅せられた人でもあるため、各章の最初の数文に力強さがある。ここでいくつか例を出してみよう。
一九五〇年代のエクスプロイテーション・マーケット用低予算映画づくりの魅力は、それらの映画がさまざまな分野にわたる楽しいテーマを持っていたことにあった。とくに十二本の映画を製作、監督した一九五六年と一九五七年の二年間、わたしはまったく退屈することがなかった。エクスプロイテーション映画づくりの基本は、若い人たちをドライブ・イン・シアターや劇場にひきよせる、内容がおもしろくて視覚的にも楽しいストーリーをスクリーンに展開し、その過程で深刻になりすぎないことだった。
『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』は、カルトの名作として、わたしの監督作品のなかではもっとも長い生命力を持つ作品だった。しかし実は、もっとも短期間で、もっとも安あがりに撮影された作品だった。
わたしは製作した映画と利益のほとんどは百パーセントを所有していて、会社を売りに出したいと思ったことは一度もなかった。しかし、どのような会社でも価格が適正であれば、売却の対象になるというのも一方の真実だ。一九八二年の春、拒絶できない条件を提示され、わたしはニュー・ワールドを売却した。
ここに並べた3つの章の冒頭は、いずれも数百字でこの章のコンセプトを魅力的に伝えている。4章では低予算ジャンル映画を大量生産していた頃の話が中心となっている。観客だけでなくロジャー・コーマンも映画の世界を楽しんでいたことが明確に伝わりかつ、映画作りの軸として「視覚/内容のバランス」が強調されている。
6章、16章では最初の文章に対して、正反対の文章をぶつけることで、その因果関係への好奇心を煽るものとなっている。最初に概要を書き、そこから詳細に入っていく文章の書き方はエンジニアとして働くわたしにとって勉強になる。無駄のない洗練された文章に感動した。
4.チャンスを掴むためにとにかく動く
ロジャー・コーマンの生き様はアメリカン・ドリームを象徴するものがある。それは、「自分のやりたいを実現するためにひたすら動き続ける」ことにある。チャンスを掴むためならオーバーワーク、無報酬も厭わないやり方は好き嫌いがわかれるところであり、怠惰に生きている私には真似できないものがあるが読んでいるとアドレナリンが出てくるのは間違いない。
フォックスでメッセンジャーの仕事をしていた頃、いかにしてプロデューサーに気に入られ昇進するかを考えていた。彼によれば監督よりもプロデューサーが王様の時代だったとのこと。彼は、スタジオ・マネージャーのところへ行き、無報酬でいいから土曜日に働かせてほしいと懇願した。これにはプロデューサーとの接点を持つだけではなく、撮影現場から技術を吸収する目的があった。また、週末には脚本部へ足を運び、脚本の研究をしていた。この努力が実り、ストーリー・アナリストとして脚本部への転職に成功した。給料も週給32.5ドルから65ドルと倍になったのだ。ストーリー・アナリストとして回ってくる脚本の大半は出来の悪い代物で頭を悩ませることとなるのだが、脚本の手直しをしたり、手柄を挙げても重役に手柄を奪われる出来事と対峙した。ここでの経験は後のロジャー・コーマンを肉付けしたように思える。
彼は国外から買い付けた作品をアメリカの観客にもわかるよう英語のセリフを入れるだけでなく、別撮りしたものを挿入して公開する戦術を取った。ソ連のSF映画を編集して『太陽のかなたの戦い』として公開するプロジェクトにはあのフランシス・フォード・コッポラがメインで関わっていた。
ロジャー・コーマンは、男女問わず有能な仲間を従え、膨大な映画を製作していくも決してトップとしての手綱は握りコントロールしていく点もストーリー・アナリスト時代の苦労によるものがあるだろう。
この姿勢はギリシャで思わぬ副産物を生み出す。史劇『アトラス』の撮影でギリシャへ渡ったロジャー・コーマン。しかし、3週間の短い撮影期間中にストライキが発生する。膨れ上がる予算、ただでさえスケジュールが押していて「ストライキなんかしている場合ではない」と考えた彼は、ギリシャのスタッフに酒を奢ることにし腹を割って話すこととなった。その中で問題の本質が浮かび上がってくる。ギリシャのプロデューサーたちが合法的な労働組合を認めず抑圧していたことに問題があった。問題を解決するためなら手段を選ばないロジャー・コーマン。なんと彼はギリシャ初の労働組合を作り、賃上げも約束したのだ。彼にとって、撮影が難航し製作が中止になるより、さっさと問題を解決する。そのための経費は渋らない選択肢を取ったのだ。ただ、皮肉にも本作は批評家からの評判も興行収入も芳しくなく、ロジャー・コーマン数少ない失敗作のひとつとなった。
5.大衆向けと社会派、芸術的との折り合いのつけかた
クリエイターは誰しも自分の中の美学と大衆との間にあるギャップに苦悩する。わたし自身、ブログや動画を毎日のように制作しているのだが、渾身の一本程あまり読まれていないし見られてもいない。サクッと作ったような作品や専門外のアニメの話の方が多くの目に触れている。
ロジャー・コーマンも、社会や政治に対する関心はあり、通俗な映画を大量生産する一方で、社会派映画を作ろうと目論んでいた時期があった。実際にアメリカ南部の黒人差別問題を扱った『侵入者』を制作する。ヴェネツィア国際映画祭で上映され、ロスアラモス国際平和映画祭で市川崑『野火』に次ぐ2番目の賞を受け取ったのだが、アメリカ公開に難航し興行的に失敗となった。
その約20年後に公開された『ミシシッピ・バーニング』が公開後2か月で5千万ドル以上のヒットを放ったことを横目にロジャー・コーマンは辛辣にこう語っている。
この映画がつくられたのが、あの事件の二十年後であるため、人々はあまり脅威を感じなかったのだ。映画を見ても「あれはわたしではない」といえるからだ。しかしわたしの映画は同時代の問題をあつかっており、観客は「自分が攻撃されている」と考えた。
それでも、ロジャー・コーマンはエクスプロイテーションの中に政治的側面を入れた社会派映画を作りたい欲望は衰えていなかった。『ワイルド・エンジェル』や『白昼の幻想』で高度技術社会やLSDでドロップアウトした若者の精神を反映させた映画を制作したのだ。『白昼の幻想』では実際にロジャー・コーマンがLSDを使って人体事件を行い、そこで得た知見を反映させている。無論、完全に再現してしまうとLSDの使用を褒めたたえる映画となってしまうため、時折恐怖描写を挿入することで批判を回避しているとのこと。
また、彼は配給業にも手を出すようになり、今までのエクスプロイテーション映画とは違った世界をみようとニュー・ワールド・ピクチャーズを立ち上げた。最初の配給作品として選ばれたのはイングマール・ベルイマン『叫びとささやき』。それをこともあろうことかドライブ・イン・シアターで上映した。また、プレミアを行った際には、会社の若い女性従業員にロングドレスを着せ、試写から出てきた女性客に黄色のバラを渡した。その結果、アメリカで大ヒットすることに成功し新境地を見出した。
ロジャー・コーマンは大衆向けのエクスプロイテーション映画を手掛けつつ、そこに社会派要素を挿入したり、大衆に歩み寄る側面を持ちつつ芸術系に手を伸ばすといった戦略を取っている。
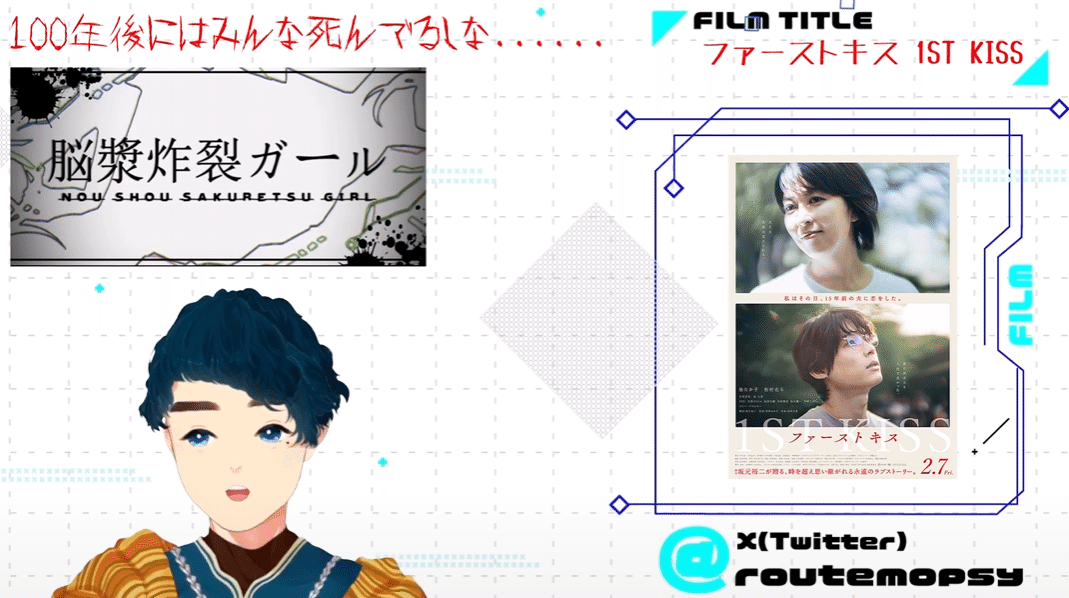

これは自分の創作活動にも繋がるところであり、VTuber活動としては男性アイドル出演作やアニメ映画のレビューに再生回数はお任せし、その横でゴリゴリのアート映画や日本未公開映画を紹介するアプローチを取っている。また、大衆向け映画でも他の人では出せないようなトピック、たとえば『ファーストキス 1ST KISS』のレビュー動画では、タルコフスキー『惑星ソラリス』との関係性を読み解くような内容を語り堅実にチャンネル登録者数と総再生時間を増やしている。
このように、「私はいかにハリウッドで100本の映画をつくり、しかも10セントも損をしなかったか」を読むとロジャー・コーマンの具体的な実践例から、ビジネス成功や人生が豊かになる秘訣を学ぶことができる。これは永久保存版として何度も読み直したい一冊であった。
いいなと思ったら応援しよう!

