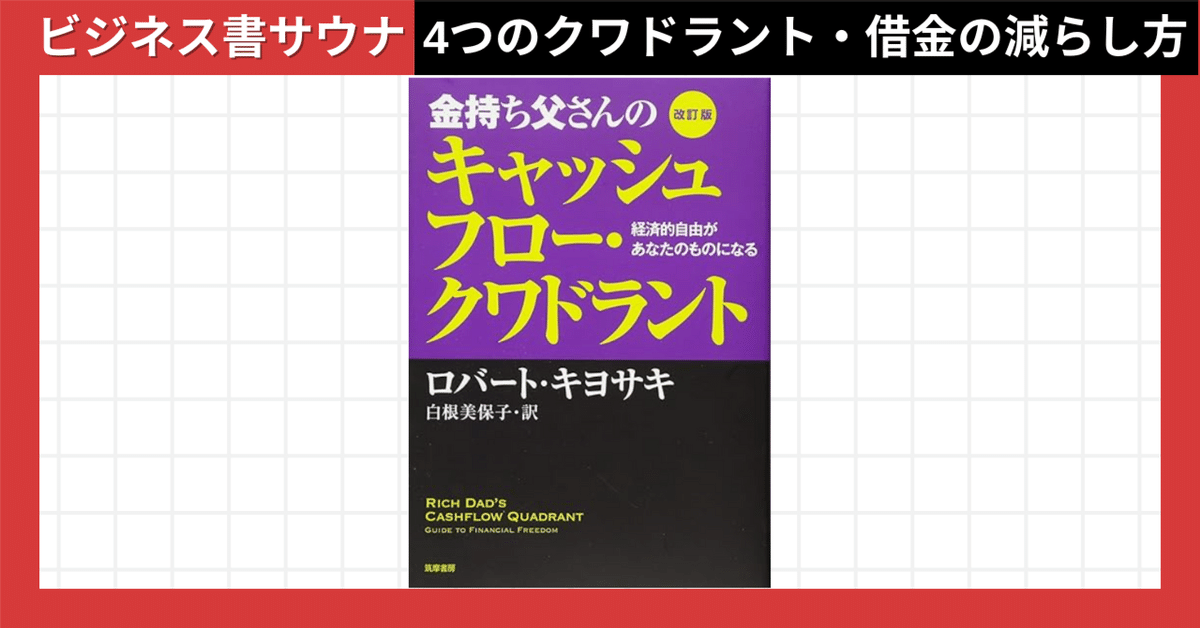
『金持ち父さんのキャッシュフロークワドラント改訂版』|ラットレースの抜け方は地道な一歩から【ビジネス書サウナ】
こんにちは、普段はゲームやエンタメの感想を書いている者です。
ビジネス書や金融本を通した解説というか読んだ感想を書いていく記事です。
頑張って稼ぐぞ系のゴリゴリのビジネス書とちょっとゆっくりしようやのダウナー系のビジネス書を交互に紹介していきます。
この落差で冷静になる感じがサウナっぽいなということで「ビジネス書サウナ」と命名してシリーズ化します。
選書は私の独断と偏見でやっていきますので、気楽にみてください。
第一弾は金融ビジネス書の元祖?『金持ち父さんのキャッシュフロークワドラント改訂版』です。
まずは金の稼ぎ方の4パターンと借金の減らし方を学んでいきましょう。
著:ロバート・キヨサキ
訳:白根美保子
出版社:筑摩書房
発売日:2013/11/8
前作の紹介はこちらから↓
あらすじ
「金持ち父さん」シリーズの第二弾
従業員・自営業者・ビジネスオーナー・投資家……
4つの生き方を決める価値観の違いを知って、人生の夢を実現しよう。
変化の時代のサバイバルツールとして世界中で読まれ続けるベスト&ロングセラー、待望の改訂版。
キャッシュフロークワドラントとは?
キャッシュフロークワドラントは、収入源を4つに分類する概念。
「従業員(E)」
「自営業者(S)」
「ビジネスオーナー(B)」
「投資家(I)」
4つの象限があり、それぞれ異なる収入の仕組みや働き方を示しています。
この4つは資本主義の構造をわかりやすく表しているので好きです。
ゲームの属性というか、所属組織みたいで面白いですよね。
それぞれのクワドラントには得意不得意や好む言葉使いがあります。

一方右側は学校では教えてくれないので我流でジョブチェンジしなければなりません。
あなたはどのクワドラント???
「従業員(E)(Employee)」
「従業員(E)」は、雇用されて働き、給料という形で安定した収入を得る人を指します。
時間や労働力を提供する代わりに、雇用主からの固定報酬を受け取りますが、収入は労働時間に依存します。
よく、「仕事は成果を出さなければならない」という論調がありますが、お金のもらい方としては基本原則として固定報酬制です。
この人たちは後述のBの作り上げたビジネスシステムのために働き続けます。
要は会社で働く人たちです。
日本では、よっぽどのことが無い限り、簡単には解雇されません。
私はこのクワドラントでしか働いたことないです、はい。
このクワドラントの人は安定や福利厚生を好み、リスクを恐れる割に金融知識があまりないと言われています。
学校や家庭で教えてもらえないので当然です。
社内政治やパワハラにはじまる各種ハラスメント、人間関係や過剰な労働の割に賃金が安いので精神的に参ってしまう危険性があります。
昇進や転職を通して賃金を上げていきます。
正社員やアルバイトは雇用形態に問わずここに分類されます。
学校では従業員を育てる教育をしていきます。
多くの国民は「従業員(E)」である親や教師に育てられます。
実は、金融商品を取り扱う銀行マン、FP、生命保険会社の営業マンもこのクワドラントに属しています。
彼らは金融システムのプロではありますが、収入源は月給が基本となっています。
「自営業者(S)(Self-Employed)」
「自営業者(S)」は、自らの専門知識やスキルを使って独立して働く人を指します。
収入は自分の労働に直接依存し、時間や労力に限界があるため、収入もそれに左右されます。
成果報酬型でお金をもらうので、労働時間が長いからといって給与が高くなるわけではありません。
つまり、仕事が早ければ時間単価が上がっていきます。
すべての責任を自分で負う特徴があります。
この人たちは、自分自身がビジネスシステムの一部になって自分で仕事をして自分で税金の対策をしていきます。もちろん外注もしますが基本は個人の実力でお金を稼いでいきます。
このクワドラントの人は独立心が強く何者にも縛られず生きることを好むと言われています。
取引先が気に食わなかったら別の会社と契約することもできる・・・?
高校大学、専門学校で学んだ専門知識を活かして士業や専門的な職人気質の仕事に就く人が多いです。
「自分の力で稼ぐ」ことが好きです。
逆に、同業他社が増えるのを嫌うので教育が苦手とされています。
自分の単価を上げることに集中しますが、固執する危険性もあります。
フルコミットの保険の営業マンはこのクワドラントに属しています。
「事業家(B)(Business Owner)」
「事業家(B)」は、ビジネスを所有し、他者が働く仕組みを作ることで収入を得る人を指します。
自身が直接働くのではなく、システムや従業員を使って収益を上げるため、労働に縛られずに収入を得られるのが特徴です。
その代わり、時給で働くわけでは無いので四六時中仕事をしている経営者もいれば、全然働かない経営者もいます。
この人たちはビジネスシステムを作り上げ、EやSのクワドラントの人を働かせて管理します。
このクワドラントの人は自分にはできないことは専門性の高い仲間に任せて、自分は資金繰りや管理をするといったマネジメント・リーダーシップ能力に長けていると言われています。
仕事が辛くて働きたくない人へみたいなYouTubeのサムネを開いたら大体事業家になろうと言いますね。
自分は労働せずにぬくぬくして良さげですがデメリットもあります。
投資家(株主)には勝てません。
自分の会社に出資している株主様の言うことは守らなければならない点では実質雇われの身です。
また、労働者を奴隷のように働かせて「ブラック企業」と認定される危険性もあります。
「事業家(B)」になる方法は学校では教えてもらえません。
自分で勉強するか、「事業家(B)」に弟子入りして教わるしかありません。
このクワドラントは「職場は学校と違うんだよ!」「先生みたいになんでも教えてもらえると思うなよ」と従業員に怒りがちです。
「投資家(I)(Investor)」
「投資家(I)」は、資産を他者のビジネスや金融商品に投資して収益を得る人を指します。
労働力ではなく、資本を活用して収入を生むため、投資の成果によって収入が増える可能性があります。
資産が成長することで、労働に依存しない収益が得られるのが特徴です。
このクワドラントはBの作り上げたシステムや会社にお金を投資して、売り上げの一部を利益や配当としてお金をもらいます。
金融の知識に詳しく良いビジネスシステムを見極める先見の明に特化したクワドラントです。
複利の力で資産を増やしていくため、経済的自由を果たすには必須です。
投資家といえばウォーレン・バフェット氏が有名でしょう。
金持ちのための最終地点なのでハッピーエンドかと思いきや、デメリットもあります。
暴落への精神的負荷や世界の情勢、金融知識が必須になります。
お金の動くケタも一般的な値段と違いますから、失敗したら一文無し。
誰も助けてくれないので孤独との戦いになります。
こちらも学校では投資の方法は教わることはありませんから独学するか、親が投資家ではないと辿り着けません。
実は「学校で教えてくれない」という大人になってからの文句は「教育基本法」を読めば当然なんですよね。
学校の目的は、教育基本法にこのように書かれています。
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
逆説的に学校で投資家の勉強や金融教育に力を入れていないのは、社会人として必要が無いからなんですよね。
全員が投資家やビジネスオーナーになって労働をしなくなったら、誰がインフラを守るのでしょうか。
と考察しております。
この資本主義の構造をわかった人が勝手に金融の勉強をすれば良いんでしょうね。
どうしたら金持ちになれるのか
最近、ロケハンの一環で何冊かビジネス書を読んでいるのですが、「自分がどうなりたいかの軸を自分で決める」というのは、どの本にも共通する普遍的な教えのようです。
本書では、自分軸の本質を「BE,DO,HAVE」という三つの言葉で説明しています。
「金が欲しい」= HAVE(所有)
「お金持ちみたいな生活をしたい」= DO(行動)
といった具合に、お金を得るために働き、何かを所有しても、それだけでは疲れ果てるだけだと述べています。
むしろ、「自分がどうなりたいか(BE)」をまず定め、それに基づいて行動し(DO)、その結果としてお金を得る(HAVE)という順序こそが、金持ちへの第一歩だとしています。
結局のところ、自分との対話が大切だということです。
その際の自己との対話で生まれる言葉によって、自分の得意なクワドラントがわかるようになるそうです。
ラットレースの抜け方
『金持ち父さん貧乏父さん』の前作でも解説されていた、「ラットレース」から抜け出す方法について紹介されています。
全部で7ステップなのですが、MECE(漏れなく、重複なく)の観点で見ると少し微妙・・・。
ざっくり言い換えると、以下の通りです。
自分のために働く
キャッシュフローを管理する
週5時間、金融の勉強をする
どんな投資家になりたいかを考える
良き師匠に出会う
小さく始めて小さく失敗する
自分を信じる
ただし、7に関しては全てのステップに包括される内容ではないでしょうか?
結局のところ、この本が伝えたいのは以下のような堅実な行動です:
簿記や会計の知識を身につけて家計簿をつけること。
借金は5年以内に完済すること。
貯金をし、その余剰資金で投資をすること。
・・・意外にも、書かれている内容は非常に堅実で地道です。
ただ、この長い解説を飛ばしてしまうと、短期的な投資でかえって借金を膨らませるリスクが高くなる可能性があります。
短期で一気に稼ぎたいと思えば思うほど、マルチ商法のような手っ取り早い詐欺に引っかかる危険性もあります。
個人的私見「なんでマルチ商法のバイブルになっている?」
読んでみるとわかるのですが、この本、かなり分厚くて仰々しい装丁にもかかわらず、内容自体は地味で堅実なものです。いわゆる「派手に稼ぐ」「短期間で大成功する」というような夢物語を推奨しているわけではありません。
それどころか、簿記や会計の知識を身につけること、キャッシュフローを管理すること、地道に貯金をして投資をすることなど、むしろ一般的で手堅いアドバイスが多く見受けられます。
では、なぜこの本がマルチ商法のバイブルとして扱われているのでしょうか。考えられるのは、マルチ商法の連中が、ネットワークビジネスに関する章だけを抜き出し、都合よく解釈して解説しているのではないか、という可能性です。
確かに、本書の中でネットワークビジネスについて触れられている部分はあります。ただし、その記述はわずか4段落程度と非常に短いものです。
この部分を無理やり誇張し、自分たちのビジネスモデルに合致しているかのように見せかけているのではないでしょうか。
一方で、ロバート・キヨサキ氏が実際にネットワークビジネスを推奨しているという話も耳にします。
彼の推薦を根拠に、自分たちの活動を正当化し、信頼感を高めようとしているのかもしれません。
いずれにせよ、原著の内容を冷静に読めば、マルチ商法やネットワークビジネスを積極的に推奨しているとは到底思えません。
それなのに、なぜこうした本がマルチ商法の支持者たちに利用されるのか、不思議でなりません。本書のメインテーマである「資産形成」や「自己成長」を無視して、一部だけを切り取ること自体が、本来の意図を歪めているように感じます。
まとめ
今回ご紹介した『金持ち父さんのキャッシュフロークワドラント改訂版』は、金融の基本や資本主義の構造を理解するための堅実な一冊。
本書の中心となる「キャッシュフロークワドラント」という概念は、働き方や収入の種類を4つに分類し、それぞれの特徴や違いを明確にするものです。
地道に金融知識を身につけ、キャッシュフローを管理し、資産形成を目指すことが推奨されています。
稼ぐための基礎知識を学べますね。
一方で、この筆者はネットワークビジネス肯定派で長期投資などの地道なものは否定派です。
本書の本質を誤解し、都合よく利用されているケースが見受けられるのも事実です。
原著を読めば、むしろ堅実で地味な行動の積み重ねが重要であることが伝わってきます。
次回は、クールダウンにぴったりなダウナー系ビジネス書をご紹介する予定です。頑張るだけでなく、時には立ち止まることで見えるものもあるはず。お楽しみに!
ビジネスマンが絶望する日曜夕方に更新予定です⭐️
いいなと思ったら応援しよう!

