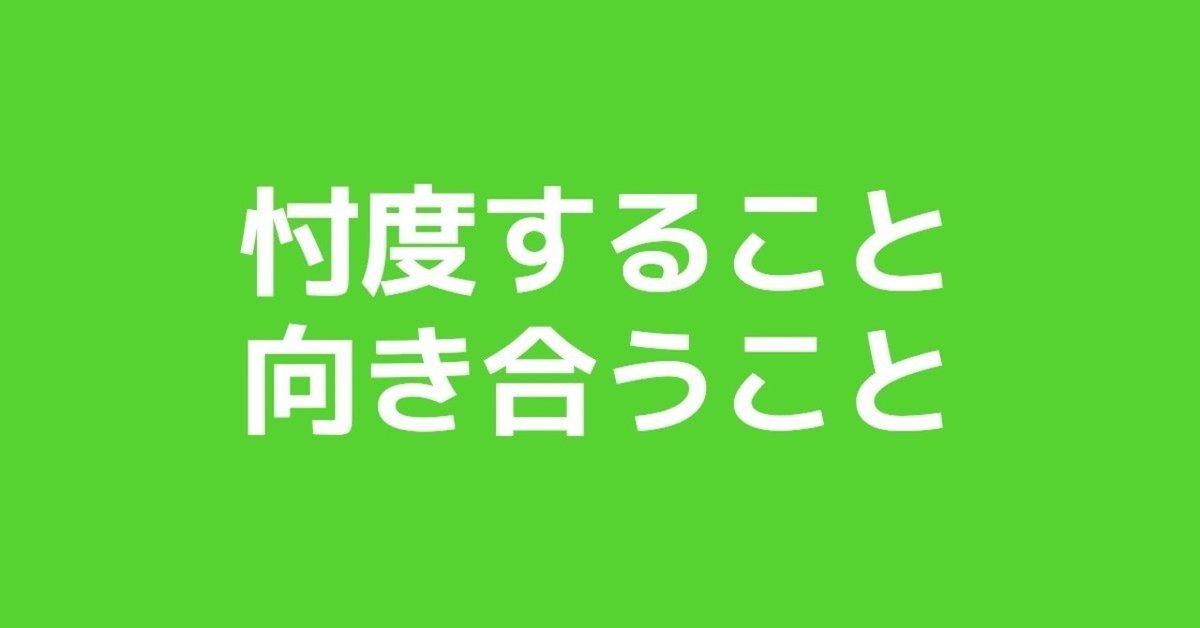
忖度すること、向き合うこと
2017年の流行語大賞にも選ばれたこの「忖度」。元来は「相手の気持ちを慮ること」「推し量って相手に配慮すること」というニュアンスの日本語であるとのこと。つまりは、語源を捉えた際に、特段悪い意味の言葉ではない。それが、森友学園問題の、籠池理事長がこの言葉を使った文脈と、それが日本人の「阿吽の呼吸」的文化との一致感があり、「ニュアンスとして悪い言葉」という風味で非常に流行したものと思う。
筆者が思うに、企業経営において、マネジメントや経営のレイヤーが上がる程に、この「忖度力」が重要になる。レイヤーが上がれば上がるほどに経営課題は抽象化するため、上位役職者からの指示にも抽象度が増す。それを文字通り「忖度」し、具体施策に落とし込み解決を図っていくのが会社における物事の動き方であるはずだ。
ところが近年の教育現場において「みんな違ってみんないい」を是とする「ゆとり教育」(筆者は、ゆとり教育の本質は「個性尊重」だと理解している)を受けた学生が、社会人として既に世に出ている彼らは「みんな違ってみんないい」を是とする中で、例えば同期や同僚の価値発揮(営業成績などが分かりやすいが)が低い場合にも、「彼には彼なりの事情がある」という「忖度」を働かせる傾向が強い。
と考えると、2020年の現在、
職場には「忖度」が溢れている。
さて、上位経営者の方針に対して、忖度が繰り返されるとどうなるか。
人間は易きに流れるもの。と考えると、ご想像の通り、いわゆる一般従業員レベルに近くなればなるほど、「薄まった方針」になっていく。
忖度の結果として方針が薄まることそのものは、特段、ゆとり世代より前の世代だったとしても大きく変わらない傾向にある。しかし問題なのは、「みんな違ってみんないい」の世代は、思っていることがあったとしても主張をしないのである。違うことに対して意見をすることは、「みんな違ってみんないい」を否定することになりかねないから。
過去は、「同調圧力」が組織全体にかかるような構造であった。反対意見は押しつぶされる。しかし同時に、圧力は「反発」を生む。つまり、反対意見が押しつぶされずに、より強い芽となり、木となり、最終的に花となることさえあった。つまり、現場発の上位陣の方針と異なる事業が、そのまま顧客の支持を得て主力事業化するということがある。
今は、「いいじゃんそれ」を、「みんな違ってみんないい」の根底思想から否定することなく(言ってしまえば「無関心」に近いものでもある)、そのまま流されてしまうようなことすらある。
それは失敗へのプロローグかもしれないのに。
どう考えても悪い方向に行きそうな取組みに対して、誰も必死で止めることをしない。
どう考えてもよくないことに対して、誰も必死で正そうとしない。
失敗を織り込み済みのテーマで戦うことそのものは、会社に余裕があり、長期的目線での人材育成を志向するならばそれでもよい。
だが、余裕がない場合、つまり短期的に成果を上げなくてはならない場合は、その忖度に溢れる職場において、
「これはよくない」「こうすべき」
を浸透させられるマネジメントも重要だと感じている。
(そのやり方として注目されているのが「心理的安全性の構築」だと筆者は理解している)
それは即ち「向き合う」ということだ。
いいものはいい。
悪いものは悪い。
シンプルにそれを認識し(させ)、改善に励むこと。
忖度が時に「無関心」「思考放棄」にならぬよう、組織全体に向き合うスタンスを波及させることも、マネジメントの一つの大きなテーマだと思う。
