
エンタメスタートアップで、ビジネスサイドのメンバーだけを集めて合宿をやってみた話
エンタメスタートアップ「ソラジマ」の組織開発責任者、サクライと申します。
弊社はwebtoonと呼ばれるマンガの制作/出版をメイン事業としたコンテンツカンパニーなのですが、創作活動と同じくらい「カルチャーの醸成」に力を入れています。
今回は、「ビジネスサイドのメンバーだけを集めて合宿をやる」という初の試みにトライしてきたので、自省を兼ねて備忘録的に残すことにしました。
なぜビジネスサイドのメンバー「だけ」で合宿をしたのか
ソラジマは今から3年ほど前に、webtoonと呼ばれる縦読みマンガ領域にチャレンジし始めました。
メンバーの並々ならぬ苦労の末少しずつ成果が出るようになり、マンガ編集者の採用に注力し始め、なんやかんやあって今に至ります。
現在の正社員メンバーのざっくりとした内訳は、マンガ編集者が40人弱、ビジネスサイドは20人弱、という形。
つまり、いよいよビジネスサイドのメンバーだけでも、小規模なスタートアップくらいになって来たんですよね。
(ビジネスサイドには業務委託で関わって頂いているメンバーも多くいるので、彼らを合計すると倍以上の人数に!)
一方、作品を生み出すキーパーソンはマンガ編集者ということもあり、今までは会社のリソースの多くを、マンガ編集者の育成や成長に投資して来ました。
とはいえ、マンガ編集者だけではソラジマは成り立ちません。
セールス、採用、テック、HR、、挙げたらキリがありませんが、彼らがいるおかげでソラジマがドライブしています。ビジネスサイドのメンバーが、縁の上まで支えてくれてる時代になりました。
そのため、マンガ編集者のみならず、ビジネスサイドのメンバーにもしっかり投資をしてあげたいし、その証左となるファクトを作り、示したい。これが今回のきっかけです。
ここで解決したい課題は2つ。
①ビジネスサイドにも、編集組織と同等に投資をしていくというスタンスを明示した上で、「実際にそうである」と言えるファクトを作りたい
②(教育投資が少なかった分、相対的にカルチャーの醸成度合いが低いので)編集組織に負けない、凌駕するような組織にしたい
この2点を実現するため、ビジネスサイドのメンバー「のみ」を集めた合宿を企画した、というワケです。
何をやったのか
設計編
「合宿やろうぜ!」と一口に言っても、目的なき合宿は参加者のエンゲージメントを極端に下げます。
言い換えると、「参加した結果何かが解決できた」と感じてもらえない合宿は、大抵の場合失敗します(自戒)
そこで、今回は合宿のテーマを「そこまでやっていいのかい???いいよ!!!!!」と設定し、合言葉にしました。

ログラインは、ざっくりいうと「会を通して一貫するテーマ」であり、ゴールイメージです
設定した理由として、前段で触れた以下が背景にあります。
②(教育投資が少なかった分、相対的にカルチャーの醸成度合いが低いので)編集組織に負けない、凌駕するような組織にしたい
ビジネスサイドには業務委託メンバーもそこそこいるので、ほぼ正社員のみで構成されているマンガ編集組織と比べると、カルチャー醸成のハードルが高いんですよね。
かつ、正社員だったとしても、前職での経験が色濃く残っていたり、ソラジマのカルチャーにチューニングするまでに時間がかかったり、うまくアンラーン出来ないことが往々にしてあります。
尚且つ、ソラジマのカルチャーは「Freedom&Responsibility」や「Why no Feedback」など、一般的な会社と比べて個人の自律性をとても強く求めます。




その為、特に新人メンバーにおいては、時として「エッッッッそこまでやっていいんすか....?」という迷いを生むことがあります。
社内ではよく「高速道路」という例えをするんですが、突然一般道から高速に入ってたらビビります。当たり前です。
例えスポーツカーのような加速が出る車だったとしても、いきなりアクセルベタ踏みするの怖いですよね。事故るかもだし。
とはいえ、ソラジマにおいては大抵の場合「そこまでやっていい」し「アクセルベタ踏みでいい」んですが、きっかけや腑に落ちる出来事がないと、行動レベルに落とし込むのは難しいよね、と。
ここ数年、ソラジマでカルチャーに責任を持ってきた今、カルチャー理解の本質は「あって良かった」と思えること、つまり効果性や存在意義を実感してもらうところから始まると確信しています。
なので、この合宿をきっかけに「アクセルをベタ踏み&ブレーキを破壊できるようになってほしい」ということで、このテーマにしました。
事前準備編
前段で設定したコンセプトをもとに、スケジュールを仮組みし、使える時間を洗い出しました。
ビジネスサイドのコアメンバーの多くが集まれるタイミングが1日しかなかった為、今回は1day実施です。
今回のテーマは先述した通り「そこまでやっていいのかい???いいよ!!!!!」なので、それが実現できるように以下3つのコンテンツを設計しました。
・最もアクセル全開になることが鍵になる「FR(自由と責任)」を後押しするコンテンツ
・FBカルチャーの根幹をその場で体験できるような儀式系コンテンツ
・ソラジマのカルチャーが「組織や経営のを爆速でアップデートしていくこと」を体感してもらえるようなコンテンツ

「腰を据えてちゃんと考える系のコンテンツは1~2hかつ2、3個が限界」という経験則があります
ソラジマが定常的に行なっている合宿は基本2daysですが、今回は1dayしか時間が取れなかったので、事前準備を工夫しました。
ハギマエ大相談会(FRカルチャーにまつわる相談会)
ソラジマの「FR」カルチャーはいわゆる「自由と責任」で、「あなたがソラジマにとってベストだと言えるなら、自由に意思決定して動いてOK」というものです。
とはいえ、一口に「自由」と言っても、最初はどこまでアクセルを踏んでいいかはわかりません。そんなもんです。
これを解決するために、初手のコンテンツは「ハギマエ大相談会」と銘打ち、メンバーから集めた「FRについての悩み」について、代表陣が双方向的にトークセッションする、という設計にしました。
まず、セッション内容の設計前にアンケートを行い、「どんな時に迷ったか」という事例を収集しました。まずはみんなの悩みを知ってから考えよう、ですね。

そして、このアンケート結果をもとに、代表が「FRはこう考えればいいよね」を語るインスト動画を制作しました。
参加メンバーの事前理解度を揃えたかったので、「これを見て来た上で当日の相談会にきてね!」という形で実施することにしました。



当日はセッション形式で、この疑問を挙げてくれたメンバーたちと議論しながら進めていったため、一定の課題解決ワークとして機能した感はあります。
終了後のアンケートで「代表の思考回路が理解できた」という意見も出ていたので、やって良かったなと思います。
代表・役員陣に対するガチFB会
このガチFB会は、ソラジマのフィードバックカルチャーの一つ「Why No Feedback?」を深く理解してもらうために設計しました。
通常はFeedback lunchという形で全員が全員に対してFBを持ってくるのですが、今回は「マネージャーや代表に対してもここまで言っていいんだ」という実感を生みたく、あえて一方向で行いました。上長に対して厳しいこと言うの、ハードル高いですからね。
▼実際のFeedback lunchの様子
つまり、このコンテンツはかなりカミソリなFBが出ることで「あ、ここまで伝えていいんだ」と思ってもらうことが一番の狙いです。
なので、事前に参加メンバーに対してアナウンスをかけつつ、「どんな事前準備をして来て欲しいか」という内容を動画でもメッセージングしました。
文面だけよりも、重要事項は顔を見せて話すと注視してもらえるのでオススメです。

ソラジマのフリー素材になりつつあります
尚且つ、この人はカミソリなFBを出すのが得意だ(櫻井調べ)と言うメンバーには、個人的に話して「キレッキレのやつ頼むで・・!」と言うコミュニケーションも取りました。ファーストペンギンがいないと心理的ハードルが高いコンテンツでもあるので、彼らにはいつも助けられています。
その結果、メンバーから経営陣に対してクリティカルなフィードバックがいくつか出ていたので、ここは前準備しておいて良かったなと思いました。

全員がカミソリフィードバックを出さずとも、数人が出してくれることで「あ、そこまで言っちゃっていいんだ」とブレーキを緩めることができるからですね。
厳しいフィードバックを臆せず出してくれたメンバーの皆さん、感謝しています。
ソラジマ捨てる会議!
3つ目のコンテンツは「ソラジマ捨てる会議!」と銘打ち、既存のあらゆるものを対象に、アップデートしようぜ!というものにしました。


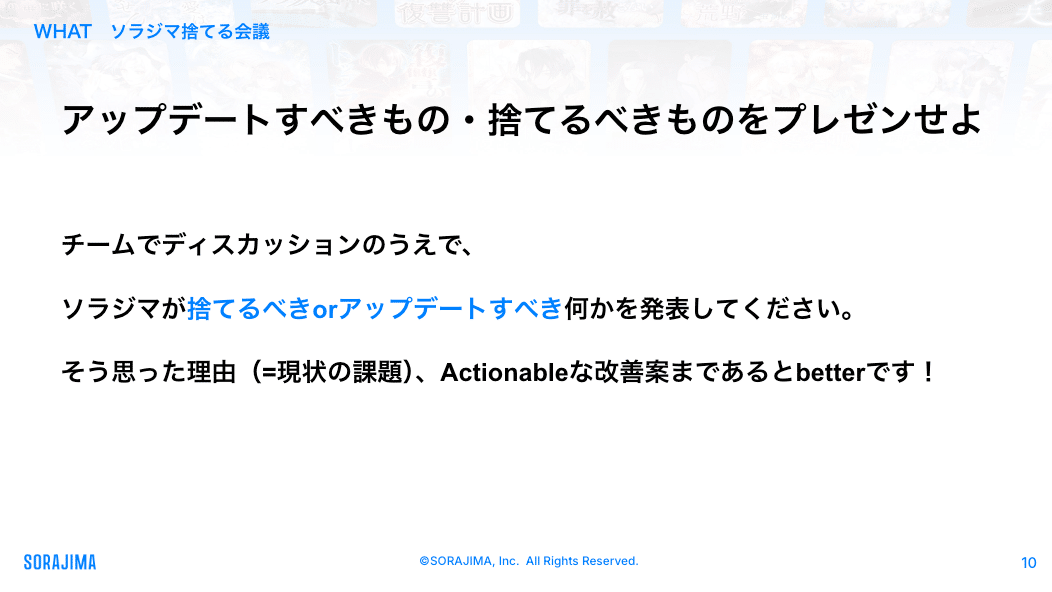
後述しますが、このコンテンツは絶妙に設計をミスった感があり反省しています。
この3つが終わったら懇親会。みんなで議論した後は美味い酒でも飲もうぜ、という魂胆です。
以上、この3つをビジネスサイドのみを集めた合宿で実施しました。
振り返り編
自分はほぼ全ての全社イベントで改善のためのアンケートをとっており、今回も同様に回答してもらいました。
その中で印象的だったものをいくつかピックして、振り返ってみます。

40〜120%で評価してもらっており、80%以下はカラーリングしている
ポジティブなFB(フィードバック)編
ポジティブなFBは、概ねFRについての「ハギマエ相談会」と「ガチFB会」に関するもの、合宿全体の運営に関するものが多かったですね。以下いくつか抜粋。
全体的に「カルチャーについて深く考えるきっかけになった」という意味で、本合宿の目的である「そこまでやっていいの??いいよ!!!!」というゴールは概ね達成できたと考えていいのかな、と感じます。
・FRについて代表や役員の見解を知れたのと、それについて全員が発言する場を作れていた。個人ワーク、1on1、グループワークの配分もちょうど良くて、仲を深めつつ議論も深めつつ、あっという間の時間だった。またやって欲しい!
・FRはここまでできる!の思い切りを理解できたし、経営のFRに対する考え方をハッキリと理解できたので!ありがとうございました!
・単純に良い機会だと感じた。こういうのもっと増えて欲しい。
・本音を引き出す会としてとてもよかった。こちらにFBいただく会もやりたい。
more!なFB編
とはいえ、「微妙じゃね?」という声も一定数いただけたのが反省が残るところ。これ系のFBを率直に出してくれるのは、運営側としては非常にありがたいです。
なお、主に3つ目のコンテンツ「ソラジマ捨てる会議」に対してのFBが多く、コンテンツとしては甘かったなと反省しています。
・捨てるという行為が新たなルール追加の案ばかりだったのは、我々が本当のFR(というかNO rule?)を理解してないからな気がした。その意味では未達かもしれない。
・もう少しフレームワークが無いと質の高い意見を出すのは難しい?
・チームによっては議論の趣旨がややずれている?部分もあったのかなとアウトプットを聞いて感じました。ある意味FRというものの解釈にズレが起こりやすいということの証左であると思うので、その学びにはなったと思う。日常の中でアクションを通じたFR&FBが推進されていくことが重要と感じました。
・チームで話しているときに、以前よりアンラーンすべきことがあまり浮かんでこなかった。考え方がかたまってきているのか、制度や環境が整ってきているからなのか、、
「捨てる会議」は、ビジネスサイドだけで行う初めてのアンラーン系コンテンツだったこともあり、明確なフレームを提示せず「成果達成を阻害するものをとにかくアンラーンしよう」という形で進めました。
その結果、「アンラーンすべきものがたくさんある」というところまではたどり着いたものの、「本質的にアンラーンすべき、緊急度重要度の高いものはどれか」というところまでは辿り着けなかった印象です。
アンラーン系のコンテンツは「デカいものこそ捨てる」ことが肝要だと思うので、ここに繋げられるデザインができなかったのはかなり反省です。
次回は議論の方向性まである程度デザインできるよう、コンテクストなりシステムなりリデザインして行おうと思いました。
なんにせよ、メンバーレイヤーから出た意見は「ちゃんとカルチャーについて咀嚼しないと出てこないもの」が多かったので、そういう意味では成功なのかな、とは思います。みんなありがとう。
まとめ
と言うことで、ビジネスサイドだけを集めて合宿してみたよ、と言う話でした。
初の試みではあったものの1PDCA回った感はあるので、次回はもう少し美しく運営できたらな〜と思います。
合宿を行なってるスタートアップは世に無数にあると思うので、ぜひみなさま勉強させてください!!!!いつでもお話しさせて欲しいです!!!!
おまけ 合宿にまつわるtips
合宿以外のイベントを含めると、おそらく10-20回の全社イベントをやって来ているんですが、その中で得た学びの共有です。
おそらくこのnoteを見て頂いてる多くの方は人事や組織開発に興味関心がある方だと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいです。
会のテーマとゴールイメージは必ず設定せよ
ここが甘いと多くの場合コケる気がします。なんのために合宿をやるのか、何のために稼働時間を割いて参加するのか、参加するとどんなメリットがあるのか、などなど。
この辺りがメンバーに伝わっていなければ、メンバー目線「結局これなんの時間なん?」となる可能性が高いし、意義が伝わっていないのに参加者に主体性を求めるのは酷です。(サクライ調べ)
同様に、会のテーマがメンバー目線の課題感と大きく飛躍している(かつ、合理的に納得できない)場合も要注意かなと思います。
(経営はXXに課題感があるが、メンバー目線XXに課題感はそこまで感じていない、など)
カルチャー浸透の話と同じで、「せっかく時間や脳のリソースを使うなら、何かしらメリットがあるに違いない」と思うのが人間の性です。
参加する意義が醸成出来るよう、この辺りはちゃんとデザインしましょう。
会のテーマと各コンテンツは可能な限り連動させよ
上記と同じ理由で、各コンテンツの参加意義も同様に醸成出来るようにしましょう。
「カルチャーの解像度を爆上げしよう!」みたいなテーマなのに、コンテンツが「新規事業立案しよう」みたいな感じだったら点と点がつながらず、「結局何のための合宿なんや」となりがちです。
テーマに沿ったコンテンツと、「なんかやった方が良さそう」なコンテンツは明確に別です。
(上記同様、「経営目線やったほうがよさそう」だったとしても、その意義をメンバーが噛み砕き、理解してくれていなければほぼ無意味です)
会のテーマから逸れたとしても絶対にやるべき!と断言できるならWHYをインストした上でやるべきだと思いますが、そうでなければ会の一貫性を重視した方が咀嚼し易いものになると思います。
発表を要するコンテンツは必ずマイクを用意せよ
何かの質疑応答タイムで、質問者が何言ってるかわからず無になった瞬間、いままで無いですか?なんともいえない時間、流れますよね。
それです。それを防ぎましょう。
1発で「議論に参加できてない感」「学びを共有できない感」「何とも言えない感」など、不必要な感情を爆誕させるんですよね、あれ。
安いマイクとスピーカーのセットを買うか、音響設備がある場所を抑えるか、マイク等がなくても問題なく聞こえる配置にするか、などなど。対策のしようはあるし、そこまで大変な話でもないので気をつけること推奨です。
低コストで対策できるけど意外と見落としがちなので気をつけましょう...(自戒)
事前準備がマジで80%なのでめちゃめちゃ準備せよ
経験上これが本質です。結局はどれだけ準備やり切れたか、参加者を乗り気にできたかがほぼ全てな気がしています。
事前準備で解決できないことは大抵「運」の領域の話だと思います。
会の設計もそうですし、参加してくれるメンバーに対するケアやサポートもそうですし、事前に出来ることはやり切りましょう。
これ以上はもうどうしようもね〜〜、ってところまで準備しておきましょう。
志を共にする仲間を複数人作るべし
これはよくやってて「マジでみんなありがとう」案件ですね。
全社イベントの成功パターンは、ざっくり2種類あると思ってます。
一つは「圧倒的なビジョントークなどにより、誰か1人がモメンタムをつくる」パターン、もう一つは「各所でいい感じの雰囲気が醸成されて、結果的になんか全体がいい感じになる」パターンです。
前者は自分の得意分野ではないので代表などにお任せしつつ、自分が出来るのは後者なので、可能な限りメンバーを巻き込み、サポートしてもらっています。
新人メンバーや、マネージャーではないけどカルチャー体現の強いメンバーなどに、非公式でミッションを渡し、実行してもらうという感じですね。
もちろん「ただ手伝って欲しい」というより「このミッションを通じて成長して欲しい」とか「さらに一段上のカルチャー体現を期待してる」とかそっちの意図の方が大きいですが!
ただ、ともすると設計側のメンバーは自分一人ということもままあるので、同じゴールを目指して走る仲間がいると、なかなか有難いです。
最後の最後に
これ系の話題、書こうと思うと無限に続いてしまうので一旦この辺りでやめておきます。
もし聞きたいことなどあればいつでも聞いていただけますと幸いです。
長々とお読いただき、ありがとうございました!
組織周りは悩みが絶えない&他社さんの取り組みとその思考プロセスをめちゃめちゃ知りたいので、ぜひラフにお話できると嬉しいです!twitterやFBでお気軽にご連絡ください!!
(オンライン/オフラインのどちらもとっても歓迎です)
そんなソラジマでは、全力でぶつかり合い、共に組織をブチ上げてくれる仲間を超絶募集しています。
ソラジマは組織で勝負することを明言している会社です。一緒に最強の組織を作り、全員で大きな夢を叶えたいと本気で思っています。
我こそは、というそこのあなた。ぜひサクライに連絡ください。お待ちしております!
(マンガ編集職も、ビジネスサイド全般も超絶募集中です!ラフに話しましょう!!!)
▼ソラジマの会社HP
▼サクライのTwitter
新たな趣味として、podcastを始めることにしました(まさか音楽機材がここで生きるとは…)
— サクライ@ソラジマ (@canu_webtoon) January 23, 2024
コンセプトは「とにかくゆるい」なので、作業用BGMやダウナーな気分な時にでも聴いていただけるとうれしいです🐈
目標、継続…! https://t.co/c45spZLQOf
