
記憶の断片〜猫と僕の日々|#短篇小説
Chapter12.
記憶の断片
翌朝、ドアのチャイムが鳴って、インターフォンの画面を見ると由依だった。思ったより早かった。
「おはよう。―――ドア、開けるよ」
インターフォン越しに話すと、由依はにっこりと微笑んだ。
玄関で靴を脱ぎながら、
「会社に行く前に、モンの話を聞いておきたかったから、早く来たわ」と彼女は言った。
「そうか・・・有難う」
モンのところへ由依を連れて行くと、モンはいつも通り、寝室の隅で大人しく丸まっていた。
「えっ、モン―――こんなに痩せちゃったの」
数カ月ぶりにモンに会った由依は驚きの声をあげた。由依が、いつも見せない困惑した表情をしているのを見て、僕は余計気が滅入った。
「そうなんだ・・・餌もあまり食べなくて」
「薬は?」
「病院で診てもらったけど、出なかった」
由依はこぶしを口元に当てて言った。
「―――もしかしたら、高齢の猫用の餌とか、逆に赤ちゃん用の餌のほうが食べられるかもしれないわね。
・・・いいわ、何とかするから。
武井くん、もう会社に行かなきゃ。ね、駄目でしょう?」
由依に背中を押して促された。玄関先に戻ると、由依は僕に笑顔を見せた。
「モンちゃんの様子は見ておくわ。しっかりと仕事してきて」
「有難う・・・」
僕は革靴を履くために靴べらを使った。由依は手を振って、
「行ってらっしゃい」と言った。
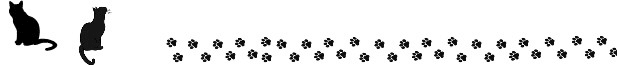
数日が過ぎた。由依が来てから、餌が良かったのと、世話の仕方が流石に細やかなこともあって、モンは少しずつ力を取り戻してきたように見えた。
丸まっている姿は変わらなかったが、顔を上げていることもあった。
(―――この調子でいけば、モンは元気になるかもしれない)
何気なく、社内でフジオナエが通路の先を歩く後ろ姿を眺めた。相変わらず、男勝りな雰囲気だ。
モンを拾った朝。ダンボール箱の中で怯えていたのを、ふたりで覗き込んだことを、僕は思い出していた。

その日、帰宅して「ただいま」と中に声を掛けた。
無音、で、静まり返っていた。
一瞬、全身に鳥肌が立って、玄関から上がる足がもつれそうになった。
「―――由依。・・・モン、何処だ?」
声が上ずっていた。鞄をその辺に置いて、慌ただしく中へ入った。
リビングを覗いても誰も居なくて、息を詰めて寝室に入ると―――
由依が、いつもモンの居る部屋の隅にしゃがんで、声を押し殺して泣いていた。・・・不吉過ぎる予感が掠めた。
「・・・由依。モンは・・・?」
由依は頬を涙で濡らしながら、真っ赤に腫らした目で僕を見た。
「武井くん、モンが・・・」その先を言うことが出来ず、顔を俯向かせて口元を覆った。
モンの姿が見えた。口を開けて、小さな舌を出して、硬直した様子で横たわっていた。
【 continue 】

