
スネ夫以上のスネ夫|完全なる証明|Review
『完全なる証明――100万ドルを拒否した天才数学者』
マーシャ・ガッセン 著、青木薫 訳、文藝春秋、2009年
レビュー2023.10.15/書籍★★★☆☆
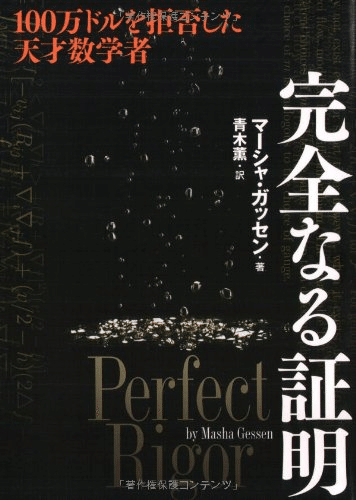
自慢じゃないが、小学2年生の頃から脇目もふらず算数が苦手な某。50代のいま、確実にできる計算は加減乗除までで、小数点や分数の計算はかなり怪しい。3.14が円周率なのはわかるが、「ひとよひとよにひとみごろ」が何の語呂なのか思い出せない。三角関数や微分積分など推して知るべし!
「試験に合格するための方法論しか教えていないからだよ」というのとも違うレベルの数学嫌い(仲間はたくさんいるはず)はなぜ生まれるのか、は専門家に考えてもらうとして、対角に位置する「数学の天才」や「偉大な数学者」の存在がとても気になる。
たぶんその一人であるグレゴーリー・ペレルマンの疑似伝記を読んでみた。
100万ドルの賞金がかけられた数学の七つの難問のひとつ「ポアンカレ予想」の証明。
今世紀中の解決は到底無理と言われたその証明が、2002年にインターネット上にアップされる。
だが、世紀の難問を解いたその男は、フィールズ賞を拒否し、研究所も辞職、数学界からも世間からもすべての連絡を絶って消えた。
そう、この紹介にあるように、ペレルマンはロシア(ソ連)出身のユダヤ系数学者で、齢36歳のときにポアンカレ予想を解いた人物である。そのことだけでも十分に耳目を集めるに値するが、その功績を称える2006年フィールズ賞、賞金100万ドルのミレニアム賞を固辞したことで、(本人の意に反してだが)話題はさらにセンセーショナルなものとなった。
ペレルマンの業績を書き出すと以下のようになる。
16歳(当時の最年少)で国際数学オリンピックに出場し、満点で個人金メダルを獲得。
米国留学中に微分幾何学の「ソウル予想」を解決。
ユーリ・ブラゴ、ミハイル・グロモフとともにアレクサンドロフ空間の幾何学を構築。
ポアンカレ予想の解決方法も、リチャード・ハミルトンのリッチフロー理論に加え統計力学を用いた独創的なもので、その検証は本書によると1年半、長く見積もると3年もの期間に及んだ。
天才ということでまず間違いないだろう。だが、著者ガッセンの見立てでは数学の知的エリートには次の3タイプがあって、ペレルマンは③のタイプに該当するらしい(p208より)。
①新しい地平を切り開き、かつて誰も問うたことのない問いを発する人
②そのような問いに答える方法を考えつく人
③ひとつのことにこだわり抜き、緻密で忍耐強く、証明への最後の一歩を踏む人
ちなみにポアンカレ予想に関しては、①はポアンカレ、②はハミルトンということになる。
本書の前半では、自然科学分野でのユダヤ人に対する締め付けがスターリン〜ブレジネフ政権下では相当厳しかったことを知ることができた。同時に、そうした社会的圧力こそがユダヤ人の抜きんでた努力を呼び起こし、彼らの成功につながったのでは、という感想を持った。
また、ペレルマンが学童期を過ごした居心地のよい数学者コミュニティの話が長々と語られる。そして、その素地をつくったアンドレイ・コルモゴロフの教育法が描かれている。同性愛者だ。その彼が何人もの男子学生と合宿をする場面など、このご時世、ジャニー喜多川的な展開になりやしないかと内心ヒヤヒヤしながら読み進めた。
本書はたくさんの関係者にインタビューした労作だ。ただその答弁からは、――遁世したペレルマンが本書を読んでさらに傷つくことをおそれているのもあるだろうが――、なんだかみんな腫れ物に触るようにペレルマンを遇していたような印象を受ける。
社交が苦手で、自分にも他人にも厳しいルール(かなりマイルール気味)の遵守を求めるという性格のペレルマンだから、なんらかの適応障害があったとしても不思議ではない。話題性でいえばサヴァン症候群との関連を疑ってしまう。下衆の勘ぐりというやつだ。実際に後天性サヴァンの数学者として、ジェイソン・パジェットがいる。
しかし、ペレルマンの天賦の数学センスが彼の社交スキルとは対照的なのは確かだとはいえ、一般的な知能が低いわけでも数学以外の領域で凡庸であるわけでもなく、よってサヴァンの可能性は低い。数学界に絶望する前後に彼が医者を訪ねたとしたら、社交回避性や自己愛性といったパーソナリティ障害、抑うつ症状などの臨床診断が下されたかもしれない。だが、これらは単なる仮説であり、その稀有な才能が閉じられてしまった悲劇になんとか折り合いをつけようとする悪あがきでしかないと心得ている。
