
明治期に創唱された日本国天皇教は近代化には貢献しえたが現代化には完敗
※-1 明治期に創唱された日本国天皇教はひとまず成功したが,ただし20世紀における棚卸しに関した評価であり,21世紀は依然,暗中模索状態のまま新策を模索中
なぜ,明治維新にともない日本においては「古代史的な天皇教」が,復活疑似的にだったが,新しく創唱されねばならなかったのか?
近代的な国家体制を発足させるにさいしては,「信じない」自由が許されない「惟神(かんながら)の道」が「非宗教(道徳・倫理)」だとして宣教・流布されてきた「神業(?)」的な摩訶不思議について,われわれはあらためて深耕しておく余地があった。
ところで,2021年を迎えるころ,宮内庁は事前につぎのような発表をしていた。2024年も9月中旬になって時点で,この宮内庁発表の意味は,説明不要である。
◆ 新年一般参賀の取りやめについて ◆
令和3年1月2日の新年一般参賀については,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,行わないこととしました。
なお,本記述のだいたいの「要点」は,こう表現できる。
阿満利麿(あま・としまろ)のこの本『宗教は国家を超えられるか』は,当初,『国家主義を超える』という書名で,講談社から1994年に発売にされたのち,2005年にちくま学芸文庫として改版,発売されていた。本書は「天皇教の批判」に学ぶ「明治謹製の天皇教」のカラクリを明かしてくれている。

【付記】 なお「本稿(前編)」のリンク先住所は以下である。
※-2 阿満利麿『宗教は国家を超えられる』1994年の「宗教と国家」論
1) 阿満利麿『宗教は国家を超えられるか-近代日本の検証-』1994年
今回とりあげ,議論の題材にする阿満利麿『宗教は国家を超えられるか』(講談社,1994年初版,筑摩書房,2005年改版)の核心は,2005年版の同書末尾に解説「阿満利麿の求道」を書いた西谷 修によって,つぎのようにまとめられている。
近代以降の日本における強固な国家主義体制の秘密を解き明かし,さらに遡って民衆に心性のうちに潜むその根源を洗い出すことで,国家を超えうる精神的根拠のありかを究明しようとしているが,この試みは,近代天皇制国家に関する政治的,思想的批判が目を向けなかった問題の位相を明るみに出す毒刃のものといってよい(西谷,290頁)。
参考にまで,この本の宣伝用の解説文をみると,以下のように書かれている。目次についても,つづけて紹介する。
国民の統合を前提とする近代国家は,人びとの生活や文化のすみずみにまで関与し,そこに国家の意思を貫徹しようとする。しかし私たちは国家を相対化し,対抗する精神を必要とするのではないか-。近代天皇制において日本はどのように国民の「臣民化」をはかったのか。
「国家神道」のもとに国民を統合しようとしてきた歴史は,いまの私たちにどんな課題を突きつけているのか。近代日本が創りあげた文化的枠組みの構造と実態を,宗教という視点から再検討し,国家中心主義を超える道がどこに,どのように用意されていたかを探る。
第1章「古式とタブ」 桜のイメージ 「女人禁制」 ケガレと穢れ 「古式ゆかしく」
第2章「つくられた『ナショナル・アイデンティティー』」
「神勅」というフィクション 天皇「機軸」論 「しらす」論の本質 現人神巡幸 よみがえる「忠孝」 「国家神道」 歴史不在 「フォーク」不在
第3章「現世主義」
現世の強大化 平家の落人伝説 「ハレ」願望 存在するのは「生」のみ 日常の聖化 現世の秩序 「聖人」と「神々」
第4章「国家を超える」
「事大主義」と「信教の自由」 「信教の自由」への道 宗教の分断 破壊された救済システム 「幸徳事件」(「大逆事件」) 「幸徳事件」の磁場 仏教徒の立場 宗教と国家
あとがき 文庫版あとがき
解 説 阿満利麿の求道(西谷 修)
2) 阿満利麿の経歴紹介
著者の阿満利麿[アマ・トシマロ]は1939年生まれ,京都大学教育学部卒業後,NHK入局,社会教養部チーフ・ディレクターを経て,元明治学院大学国際学部教授,日本宗教思想史専攻。阿満が59歳になった1998年,ホームページに掲載・記述していた文章は,彼自身の経歴をこう紹介している。
1962年京都大学教育学部卒,NHKに入る。教養番組のディレクターとして。日本の言論機関というものに失望し転職。1987年より明治学院大学へ(学生に失望することも多々あるが)。
1990年代後半において,日本の大学〔具体的には明治学院の〕「学生に失望することも多々ある」と語った点は,本ブログの筆者も大い共感できる発言であった。
筆者の場合はしかも,明治学院大学の学生たちでさえ,はるか上方にあおぎみるような窪地に立ちながらでも,こちらの水準・次元でなりにしか学力をもちあわせない大学生諸君を,それなり相手にし,たいそう悪戦苦闘してきた。
それゆえ,この阿満の発言には同感(連帯?)の気持を抱くとともに,日本の大学の現状は,「そんな生やさしい失望〈感〉」で済むものではありませんぞ,とも強調しておく必要があった。
その付近に漂う「高等」教育関連の統計情報を,たとえば,つぎのものをかかげておきたい。2024年度大学入試関係の基本情報である。

約10年後の2035年以降は18歳人口が100万人を割る

この点を具体的に統計でつぎに示しておく
▼ 18歳人口の減少傾向 ▼
2024年6月5日,厚生労働省は,令和5〔2023〕年人口動態統計月報年計(概数)を公表した。 出生数は,前年〔2022年〕の77万759人より4万3,482人減少し8年連続減少で過去最少。(以下で2023年分は筆者が補足)
2023年 727,277人 (19歳で大学生1年次になるのは 2042年)
2022年 770,759 (同上は 2041年)
2021年 811,622 ( 2040年)
2020年 840,835 ( 2039年)
2019年 865,239 ( 2038年)
2018年 918,400 ( 2037年)
2017年 946,146 ( 2036年)
2016年 977,242 ( 2035年)
-この年次より100万人を切りはじめ, 以前より( ↑ )「絶対的な減少数」の歩調が早まっていく-
-上記の8年間で減少数は 249,966人。
2015年 1,005,721 ( 2034年)
2014年 1,003,609 ( 2033年)
2013年 1,029,817 ( 2032年)
2012年 1,037,232 ( 2031年)
2011年 1,050,807 ( 2030年)
2010年 1,071,305 ( 2029年)
2009年 1,070,036 ( 2028年)
2008年 1,091,156 ( 2027年)
2007年 1,089,818 ( 2026年)
2006年 1,092,674 ( 2025年)
2005年 1,062,530 (19歳で大学生1年次になったのが 2024年)
-上記の11年間で減少数は 56,809人。
進学率の上昇率があったところで
学生の学力に低下傾向が出る
事実は歴然
阿満利麿は,ゼミナールの勉強のすすめかたについて「毎週1冊の本を読み,その要約をすることが最低条件。欠席は許さない。発言がない場合もお引き取り願う」と要求した。学生に対する希望は「とにかくやる気があること。本が読めること」という条件を付けていた。
本ブログ筆者の場合だと,1990年代後半および 21世紀に入ってからの体験であったが,この阿満のいうような条件を学生に提示したら,始めからゼミナールに学生が集まらない・集められない。つまり,お話にもなりえなかった現場の惨状は,いまでも生々しく記憶に残っている(というか,それほどにひどい日本の大学の教育現場「の部分」を実際に分担してきた)。
そうした現実の大学事情は現状から未来に向けても,ますますその日本の大学的な病状は,さらに進展(悪化)させていくほかないゆえ,ともかく阿満利麿の説明を半信半疑で聞くほかなかった。とはいえ,阿満が別に,所属してきた大学に関してうそをいっているわけでもないゆえ,とりあえずこちらとしてはそのような感想を,対比的にだが率直に語ってみた。
どういうことか?
ともかく,ゼミナール履修の希望者を募って受けいれるのだが,実際に勉強を始め〔させる〕段になると,「学習そのものが成立不能(!?▼@#■$%~★*&¥◆?!)」であるほかない状態そのものを踏まえて,たいそうていねいなる指導(?!◉☁😪☀⌚📵📳🚭)をおこなうことになる。
それにしても,前段のごとき阿満の「ゼミナールにおいて学生の勉学に対して期待する欲求水準」に提示された条件は,大学生に向けられるものとしては,ひとまずあまりにも当然であった。だが,いまどきの平均的な(とくにそれ以下・未満の)日本の大学生にとっては,それでもかなりにとてもきびしい条件たらざるをえない。
「毎月1冊でも本を読むか」といたら,これがそもそもあやしい。「欠席など平気でする学生」をつかまえて,阿満のような要求を「最低限譲れないゼミナール学習の条件だ」として突きつけていたら,日本の大学生〔もちろん平均的なその種類の彼らを想定してだが〕であれば,ゼミナールは成立する余地すらない。
学級崩壊ならぬゼミナール溶融は必然でもあった。この覚悟は毎年度新学期を迎えるときには,それこそ「褌を締めなおしてすような気持ち」(男性教員ならば・・・)を余儀なくされるというか,それなりに勇気を振り絞って新たな気分を絞り出すことが,いつも強いられる。
それはともかく,本ブログの筆者がこれまで勉強してきた「日本天皇制」に関連する研究文献のなかでは出色の出来とみなせたのが,本書,阿満利麿『宗教は国家を超えられるか-近代日本の検証-』1994年(ただしこの書名は2005年改版のものだが)であった。
ほかの著作を読むうち,阿満の本書が文庫版が2005年に公刊されていたことをしり,これをとりよせ読むことになっていた。さきに,文庫版に寄せられた西谷 修の解説から参照する。
3)阿満利麿の求道-明治天皇教の批判的分析-
阿満利麿は,本居宣長や柳田國男の思考した道の深い理解を踏まえて,その日本式神道における「現世主義」の批判にいきついた。本居の神道思想は「神仏なき救済論の原型」であり,柳田の「先祖教」は「世俗化された念仏宗の近代的展開」を示した。これら「現世主義」が,地上にその生身をもつ「神の子孫」天皇への崇敬を受け容れ,安んじてみずら「臣民化」する素地を提供したという(288頁,289頁)。
近代に作られた日本社会の構造は,敗戦による「大日本帝国」の崩壊によって潰えたわけではない。戦後の〈象徴天皇制〉のもとで,文部省も靖国神社も延命し,天皇制国家の骨格は保たれた。「国体は護持された」。われわれは,現在もそこから生じる諸問題に当面させられている(287頁)。
近代の日本は,国家や宗教や教育や文化のすべてを管理する体制を作ってきた。「古来の習俗」や「美風」といわれるものも例外ではない。「桜の神話」も国家によって意識的に作られてきた。そして,それらは「宗教ではない」とされる神道の空間に包摂されてきた。
だから,「臣民」である「日本人」は「内面の信仰」を出て公共空間に入るとき,天皇を崇敬しなければならない。これを超えようとする普遍的信仰は,ときに「不敬」の危険を冒すことになる(287頁)。
すなわち,日本は近代国家はその内的な運動によってではなく,西洋との遭遇に規定されて意図的に作られてきた。そのとき国家の設計者たちは,西欧諸国家の仕組を研究しながら,実に巧妙な操作をおこなった。それは阿満の指摘する『神道非宗教論』である(286頁)。
☆-1 信教=「内面の私事」としてならば容認される。→宗教(religion)「論」。キリスト教ほか既存の宗教宗派すべてを,そのようにあつかってきた。
☆-2 神道=「日本古来の習俗」として「公務である」。→神道非宗教「論」。万世一系を謳う明治憲法下の諸体制は,日本の公共空間をあらかじめ神道化していき,その内面化のための「教育勅語」が「帝国臣民の聖典」として定められた(286頁)。
近代国家は,人びとの死を国家に回収し,人びとを国家に帰属させることで成立した,ナショナリズムを公式教義とする「世俗的教会」なのであり〔教会はもともと信仰共同体を意味していたが〕,その資格をもってこの「教会」にとって代わったのである。
つまり,それ以前=中世のように権力の正統性の根拠をもはや神には求めず,「国民」に基盤を置くことになった国家が,この国民の「内面」にすら浸透して人びとの意識の統合を図ったことを意味する。ナショナリズムがもっとも深いイデオロギーであるのは,それが「死と不死」のテーマを包摂する点で,宗教的帰依に匹敵する性質をもっているからである(285頁)。
※-3「古式ゆかしく」の異様にも過大なる欺瞞性
1) 古代の近代的な復活の罪悪性
ここから,阿満利麿『宗教は国家を超えられるか』1994年の本文の紹介に入る。全体を包括的に紹介することはできないので,なかでも「古式ゆかしく(ゆかしい)」伝統を誇るのが皇室であるとか,つねづね意図的に紹介されてきた点の「まやかし=ウソ」性に言及する阿満の記述部分にかぎって紹介する。
明治の時代,大正天皇誕生のしらせに接した京都の町衆が,明治天皇誕生(1852:寛永5年)のさいにも,恒例として御所に届けていた「安産のお守り:神功皇后の神面といい伝えられるもの」を,こんどは宮中に届けようとしたところ,宮内省の役人に拒まれた。このとき京都の町衆の反応は「天皇はんも出世しはったさかいな」という,ずいぶん印象的な話を残していた(121頁)。
われわれはこの〈印象に強く残る〉京都町衆の「天皇評価」=歴史的な位置に関する認識に注意したい。明治維新とは,当時を生きた人びとからみて,大政奉還と廃藩置県を指して「御一新」と呼ばれた事実が関心の的であった。
大政奉還は,それまでは京都に閉じこもっていたような朝廷=天皇一族を,日本帝国を率いる統帥であるかのような政治的地位を与えて,それも宗教的威厳で強力に装飾するかたちで,一躍高く引き上げていた。京都の町衆が「天皇はんも出世しはったさかいな」と,いささか皮肉っぽく形容したわけが分かる。
明治時代の元勲のなかで一番の功労者である伊藤博文は,形式面でも実質面でも背後から,明治天皇を制御していた政治家である。伊藤博文『憲法義解』1889〔明治22〕年は,「竊(ひそか)に惟ふに皇室典範は歴聖の遺訓を祖述し後昆の常軌を垂貽し」,「帝国憲法は国家の大経を綱舉し君民の分義を明劃す意義」をもたせた,明治期の政治支配思想を実現させるための解説書であった。
伊藤博文の『憲法義解』は,古代のそれもとくに神話時代とヨーロッパの2者のみを立論の根拠とした解説書であったゆえ,現代のわれわれがしる歴史意識はまったくみいだせない。古代の転籍のみを引用するのは,神話を天皇支配の根拠としたからにほかならない(103頁)。
『憲法義解』の届く目線は,今日では神話上の伝説的人物とされている神武天皇から,いわゆる歴史時代を一挙に飛び越えて,明治維新の当代に至るところまでである。こうした古代偏重の姿勢は,伊藤博文たちが明治の時代に留学していたころのドイツ帝国が,古代ギリシャに異常な関心を払っていたこととも深い関連がある(104頁)。
ナチス・ドイツのアドフル・ヒトラーは,ドイツ国民を統合するための時代的な雰囲気作りのためにギリシャ神話の再生を夢想し,ナチス・ドイツが古代ギリシャ・ローマに続く〈偉大な文明である〉と,後世の人々に思われたいという欲求を抱いていた。
その結末がどうなったか。敗戦後,半世紀近くも東西に分断されたドイツであった。ドイツは再統一されたがその後,分裂国家の時代に原因した政治社会病理の克服を,いかほどなしえているか?
振りかえってみるに,いまもなお天皇・天皇制を中途半端に残存させているのが「日本帝国⇒日本国」である。かつて,伊藤博文など「明治の偉勲たち」が構想・設計し,確立・運用してきた「古代史的な原始共同体的首長」=「とくに明治と昭和の2天皇」下における帝政国家は,歴史に記録してきた〈負の遺産〉をいまだに清算も克服もできていない。
2) 森山眞弓官房長官を「土俵に上げること」を拒否した日本相撲協会
阿満利麿は「けっして昔からの伝統でもなかった」,しかも「民衆の本来の意図とはかけはなれた,国家によるタブー」,たとえば以前起きた,日本相撲協会が「女性官房長官森山眞弓」(1989年第1次海部内閣時に在任)が「土俵にあがることを拒否」した事件を,根本から批判する見地を明示している(とくに43-47頁)。
森山眞弓が官房長官を務めていたとき発生したその事件は,こういうものであった。
大正末期から天皇杯を優勝者に授けるようになった〈相撲界の神事〉は,不文律(女人禁制)を保持していた。森山がこれを無視して土俵に上がって,内閣総理大臣杯を授与しようとしたところ,日本相撲協会に拒否された。
すると森山やその支持者らは,その事態を「日本文化の伝統だけ」ではなく「女性差別の問題でもある」と問題を提起することになった。この事件をきっかけにその後,女人禁制反対派の活動が各地でさまざまな伝統行事のありかたに議論を喚起することになった。森山はちなみに,夫婦別姓推進・婚外子差別撤廃派でもあるという。
江戸城は1868〔明治1〕年,東京城(とうけいじょう:10月13日)と名称をかえた。東京城はその後すぐ1869〔明治2〕年,東京奠都により皇城と呼ばれ,1888〔明治21〕年,明治宮殿の完成によって宮城と称された。敗戦後,1948〔昭和23年〕は皇居と改称された。
つまり,明治天皇・大正天皇・昭和天皇〔昭和23年まで〕は〈お城〉に居住する『日本帝国の王様〔皇様〕たち』であったことになる。
【参考記事】-『西日本新聞』から引用する,女性記者が執筆-
◆ 救命措置中の女性らに「土俵から下りて」と放送し ◆
=『西日本新聞』 2018年4月13日朝刊 =
救命措置中の女性らに「土俵から下りて」と放送し,不適切だったと謝罪した日本相撲協会。それでも命にかかること以外,今後も「女人禁制」を守るそうだ。実際,〔2018年4月〕6日の宝塚場所(兵庫県)でも女性市長を土俵に上げなかった。
女性初の官房長官だった森山真弓さんが土俵上で総理大臣杯を授与しようとして拒否されたのは1990年。「女性差別だ」との問題提起から28年経つが,協会側は「土俵は神聖な場所」「伝統だから」と繰り返すだけ。緊急時に非常識さをさらすことになったのは思考停止の結果だ。
宝塚市長は土俵の下からあいさつし「悔しい」と述べても,協会には響いていない。〔4月〕8日には富士山静岡場所(静岡市)で,恒例の「ちびっこ相撲」から突然,女児を排除したそうだ。「安全面を配慮した」という説明には首をかしげる。公然の差別,理不尽な対応。角界の「常識」は,子どもたちの目にどう映るだろうか。 (相本倫子)
※-4「古式ゆかしく」という「新式の皇室中心」思想確立のための政治思想
日本の皇室内における「非常・異様なまでの〈穢れ〉忌避」の宗教的な慣習については,たとえば,髙谷朝子『宮中賢所物語』ビジネス社,2006年が〈呪文のように〉して,それも性懲りもなく,しかし当人は大真面目であったが,なんといえばいいのか,壊れたレコード(ないしはテープレコーダー)のように,無限に復唱していた。
つまり「平安の昔から変わらないしきたりのなかで,今日まで途切れることなく続けられてきました御祭の数々が,いまも昔のままの姿でおこなわれてございます」(同上,2頁)という髙谷朝子の文句は,
実は,歴史的にまったく根拠のない,でっち上げの,ごく個人的な皇室信仰心の主観的な表白でしかありえなかった。けれども,当人はしごくまじめにそのつもりを独白していた。つまり,日本天皇史の概略をしる者からすれば,この髙谷の御託は妄言の類いであっても,当人は何千年もの歴史的な由緒のあるその皇室的な伝統だと本気で信じこんでいた。
キリスト教関係で話をたとえていうと,『新約聖書』のなかにある有名な個所,イエスが,トマスのように私たち1人ひとりの前に現われて「わたしをみたから信じたのか。みないのに信じる人は,幸いである」という〈聖句〉の段落にも似ていて,
この髙谷朝子『宮中賢所物語』ビジネス社,2006年における常套句,「平安の昔から変わらないしきたりのなかで,今日まで途切れることなく続けられてきまし・・・・」は,キリスト教のその〈聖句〉とはまた違った次元における「信仰告白的な確信」を,しかも自信たっぷりに述べていたことになる。
阿満利麿もまず,こう断言していた。1989年の昭和天皇から平成天皇への代替わりや,1993年の皇族の結婚のさい,さまざまな皇室行事が鳴り物入りで繰りひろげられた。そのさいマスコミが共通して強調したことは,それらの行事が「古式」に則っているという点であった。
「新宿御苑の葬列は」「古式にのっとった装束に包む」とか「祭官らが着る古式ゆかしい衣装の着付」という表現,秋篠宮の婚礼に関して「古式ゆかしく続けられた」という表現をもって,「その『古式』ぶりがいやがうえにも強調される」。
庶民が聞いたこともないむずかしい漢字・単語をふんだんに組みこんだ葬儀や婚礼では,その「古式」という表現がひんぱんに使われていた。「それぞれの行事は,個々の細部をふくめて昔からなんのかわりもなく,延々と引きつづきおこなわれてきたかのような印象を与えることになる」(47-48頁)。
そのような報道はいまに始まったものではなく,大正天皇の「大礼」のさいにも,新聞は「あたかも太古のさま」と麗々しく報じていた(1915〔大正4〕年11月6日付,東京毎日新聞)。
だが,現今のような皇室行事は,その内容・形式について,ほとんどが明治になってから大幅な改変を経たり,あるいは新設されたものである(48頁)。
前出してみた,髙谷朝子『宮中賢所物語』2006年について繰り返して批判する。
1945年以前までの皇室事実史の一断片さえ「しりうるはずもない」「彼女自身の立場」に終始しただけでなく,その事実にすら基本から無自覚であった髙谷は,その種の無知に原因する〈自分の制約〉を寸毫も悟ることもできていなかった。にもかかわらず彼女は,宮中三殿の賢所に長年勤務してきた経歴をひけらかすことだけは,得意になって説きつづけた。
髙谷朝子は,日本の皇族がいかに高貴であるか,そして〈大昔のそのまま〉に長い伝統を存続させてきたかと,確かななんの独自の根拠もなく自慢する。歴史認識とは完璧に無縁の「〈穢れ〉なき皇室奴隷的な人物」の「愚かしい物語」を,彼女は得意気に紡いでいた。
しかも,その〈無知を下敷きにした論外の誤解〉を語る彼女の口ぶりは,みずからの〈語り〉にひたすら陶酔した姿をひけらかしていた。いわば,その無識ゆえを理由・背景にしてこそ,そこまでもタップリに幸せ感に満ちた皇室史観(?)をもって,あたかもきんとん雲に搭乗できたかのように振る舞っていた。そして,なによりも同時に「〈ほら吹き〉の役目」も,彼女は遺憾なく演じていた。
ともかく,髙谷朝子が老齢になってから,自分の表情に浮かべさせえていた「そのいにしえのゆかしさ」に関した確信のほどにかぎっては,それじたいとしては実に高い水準のものになりえていた。
※-5 古式ゆかしくない皇室行事の数々
a)「宮中三殿」 皇居には宮中三殿があり,この賢所・皇霊殿・神殿の始原は明治にある。この三殿には毎日供えものが捧げられるが,その対象である供えものじたいが,近代の変遷を経てきた。
また,天皇が親祭する13の祭典のうち11は,明治になってから新設されていたものである。『古事記』『日本書紀』を根拠にもつという「紀元節」(第1代神武の即位の日とされる:現在は「建国記念の日」)は,伝説上の人物であるのに,明治政府は「あたかも実在の天皇」であるかのようにあつかった(阿満利麿,前掲書,50-51頁)。


b)「衣 装」 天皇家の冠婚葬祭時に使用される衣装も,前段に登場させた髙谷朝子も自分勝手に恣意で誤解しながら得意げにいってもいたが,「平安時代以来の伝統的な衣装だと紹介されることが多いが,幕末までの衣装は,宮中の制度が中国の唐制にならっていたところから中国風であった。
維新以後,それらを一変して衣冠束帯と決めたのであるから,みた目には,『古式』であっても,使用は明治になってからのことといわねばならない」(51頁)。

2006年12月女優・藤原紀香とお笑い芸人・陣内智則が電撃婚約を発表
この2人は2007年2月神戸・生田神社で挙式をおこない
5月30日ホテルオークラ神戸で披露宴をもっていた
2007年4月婚姻届を提出して正式に夫婦となっていたが
2009年3 月離婚
阿満は「皇室の衣装といえば,皇族たちの喪服が洋装であるのも気にかかる」(51頁)と指摘していた。だがさらにいえば,触れえていないこともある。それは,喪服に「黒色の衣装を着る」西欧の習慣であるが,明治以降に国家の方針として生活のなかにとりいれられ,今日においては完全に浸透している習慣である。阿満はこう推測する。
喪服=洋装は「イギリス王室にならった新しい習慣である。皇室でいわゆる和服が礼服とならなかったのは,宮中からみると和服は,江戸時代の庶民の服装に過ぎず,皇族たちの着るべき服装ではないとされたらしい(51-52頁)。
c)「伊勢神宮」 伊勢神宮に明治天皇が参拝に出かけたのも,明治天皇からであった。伊勢神宮と天皇家の関係は,7世紀後半から緊密となる。しかし,歴代天皇が直接伊勢神宮に出かけることはなかった。
伊勢神宮はそもそも,天皇家の祖先を祭るのではなく,霊験あらたかなる農業神を祭る神社であって,内宮と外宮の関係も外宮のほうが大きな力をもっていた。
庶民信仰の対象であった神宮を,明治政府は一変させ,全国の神社を統べる頂点として,またなによりも近代天皇制国家のもっとも神聖な祭場として再編してきた。
伊勢神宮のたたずまいや建築は,日本古来の伝統的な美の極致を宣伝・紹介されている。しかしながら,そのすべてが日本固有で,しかも古来の形式を伝えているというわけではない。
神宮の建築美を支えている要素のひとつに檜の無地があるが,建築史の専門家によると,檜の無地の強調,とりわけ四方柾目の木取りは,明治になってからのことである(52-53頁。大田博太郎『日本建築史論集〈3〉社寺建築の研究』岩波書店,1986年)。
d)「神宮の儀式」 神宮の儀式も,中国文明の研究家によると日本固有のものもあるが,明らかに中国の儀式を受けついているものが少なくない。かつて中国でおこなわれていた習わしが,本家では早くにとだえてしまったけれども,日本で残ったのである。
遷宮のさいの行列は,中国唐代の女性の貴人の行列をモデルにしている。日本の神社・神宮のほとんどが鏡を御神体としていることじたい,中国の道教が鏡を神器とする哲学をもっていた影響といわれる(53頁)。
伊勢神宮に伝承されていることがらに,中国ではない固有の営みがあることは否定できない。ただ,伊勢神宮というだけで,その建築・行事のすべてが「古式」で「固有」であると主張することは疑われてよい。
ましてや「古い」というだけで,恐れいってしまう精神が問題である。そうした精神を利用して,やみくもに「古式」だとして常識的な歴史意識すらも曇らせてしまうやりかたに不安を覚えて当然である(54頁)。
e)「明治以来の神道式伝統」 とりわけ,そうした考えかたが日常の生活に生きている風俗習慣にまで立ち入ってきて,日本人の生活のあたかも時代の切れ目を経験することもなく,一枚の布のように昔から引きつづいていると思わせられるのは,好ましいことではない。日本人の生活には,明治生まれの伝統がまるで,それ以前から存在していたかのように生きている。実例を挙げてみたい。
◎「神前結婚式」--1900〔明治33〕年におこなわれた皇太子〔のちの大正天皇嘉仁〕の結婚式に発する。これは明らかにキリスト教に刺激されて生まれた新しい習俗である。
◎「七五三」--これも明治以降の流行である。3月や5月の節句が民間にゆきわたったのも,デパートのおかげであった。
◎「葬 儀」--告別式が登場したのは,明治末年の東京からであって,それまでは一般会葬者の焼香を受けることはなかった(54-55頁)。
見当違いの観念論
f)「古式・古来・本来・本然ということがらの強調はいつからか?」 1930年代後半くらいからか,日本人の生活にしかたについて一段と「古式・古来・本来・本然」が強調されてくる。これには,文部省など政府機関から出版され国民に広く読まれた〔そう強制された?〕『国体の本義』昭和12年や『臣民の道』昭和16年の影響もある。
『臣民の道』は,国家奉仕を第一とする「皇国臣民の道」を明確化し,その実践を国民に要求していたが,歴史の実情を無視する記述が少なくない。家々において先祖祭りをおこなうことは,宮中の祭祀に共通する「我が国古来の国ぶり」だと述べているが,
民衆の歴史にあっては先祖祭祀は村落共同体全体でおこなうのがより古風であって,個別の家々での先祖祭りは,それに比べると二義的で,古くても江戸時代後半くらいにしかさかのぼれない(55頁)。
家風・家訓の重視もまた「我が国古来の淳風」だとしているが,それは,江戸時代の豪商や武士階級の話であって,民衆にとっては,先祖といっても3代まえの名前がかろうじて判るくらいで,家代々という意識も薄いのがふつうである。まして,家風や家訓が伝承される家は,きわめて少数であった。
とくに,日本にあっては,「古来質素を重んずる風が強く」といわれているもの,天皇や貴族,大名や豪商たちの生活が質素であったとはお世辞にもいえなかった。
あるいは,隣近所が苦楽を分かちあうことが「古来の尊い伝統」だというけれども,江戸時代末になっても,飢餓のときは,老人や病人,子どもなど,弱者から見捨てられていったのである。
村落共同体は,けっして福祉の共同体ではなかった。こうした状況は昭和の時代に入ってからも,しばしば生じていた(55-56頁参照)。
※-6 小 結
以上のように,いまとなっては的確に指摘・批判されているように,「皇室神道」や「臣民の道」というものは「明治以降登場してきたもの」である。つまり「当時に生まれていた新しい習わし」であった。
しかし,臣民側は,戦時体制期において『国体の本義』昭和12年や『臣民の道』昭和16年を強制的に読まされ,それらがあたかも,「古来」の「伝統」であったかのように間違えて教えられてきた(56-57頁参照)。
思えば,明治以降に形成されてきた「国家神道の〈伝統的な立場〉の由来」も,実のところは,昭和の時代に入ってから徐々により強く,国家体制側から人びとに対して求められるものとなってきた。
戦時体制が進行・深化してく状況のもと,その時代のなかでこそ,「国家神道」の宗教精神が新しく形成されつつ定着させられもしたのだから,皇室の行事・国家神道のありかたはいずれも,
昭和における「戦争の時代」の推移とともに急速により肥大化していった事実をみないまま,古式ゆかしき「皇室文化の伝統・格式」をウンヌンするのは,作意が過ぎた「歴史捏造〈史観〉」に陥没しかねない。
そうした種類の〈歴史の真実:帝国の戦争と神道宗教との連関性〉をみうしなってはならない。日本においては本当の保守政党といえる資格をもった政党はみあたらない。
よりよってだが,保守も伝統も格式もなにもワカッテイナイ連中が,ただ右翼=極右的な磁石に吸い着けられたごとき硬直し,かつ偏倚した,それもまとな思想(哲学:フィロソフィー)や主義(信条:イデオロギー)を備えていないまま,
ただ,体制派の政治集団として政権党を構成していたゆえか,この国が21世紀に入ってからというもの,「それダメ,これダメ」だらけの為政しか実行できない顛末を招来させてきた。
ここで最新の話題となる。
オマケにパープリンの「世襲4代目の政治屋」が,自民党政権を引きつぐべく2024年9月27日に投開票予定である自民党総裁選に立候補したが,一時期は1番人気で当選するのではないかという前評判が高く出ていた。
まさにその当該人物の小泉進次郎が,その投票日まであと10日ほどしかなかった時点になってだが,日本政治の現状にかかわる基礎的な情報・識見をほとんどもちあわせない事実を,早くも露呈させた。
この程度の日本政治の伝統・格式しか具有しない世襲政治屋たちばかりであるこの日本,また,彼のオヤジである小泉純一郎の不勉強ぶりならば,息子の代にまで連綿と持続可能になっていた。ところが,肝心の政治運営に対する進次郎なりの基本方向は,いったいどこを向こうとしているのか,いまだにさっぱり判読できかねる。
ということで,「皇室由来」になる「古式ゆかしき」があれこれ奥ゆかしく実在しうるらしいと明治以来力説されてきたが,その点が天下り的に主張されてきたからには,どうしてもその「古さそのもの」に関して,あれこれ疑念が湧いてきてやまなかった。そういう歴史本質的な特性を有したのが「日本の皇室の伝統・格式」そのものであった。
それでも,前出,髙谷朝子『宮中賢所物語』2006年が一生懸命に強調していたごときに,その「古式ゆかしき」皇室の伝統が〈呪文のように〉唱えられうるのは,つまり「平安の昔から変わらないしきたりのなかで,今日まで途切れることなく続けられてきました御祭の数々が,いまも昔のままの姿でおこなわれてございます」(同上,2頁)といってのけた
髙谷朝子『宮中賢所物語』ビジネス社,2006年流の単細胞になる歴史解釈が,終始〈呪文のように〉唱えられるなかで,しかも性懲りもなく当人は大真面目になって,なんというか壊れたレコード(ないしはテープレコーダー)のように無限に復唱しつづけていた。
つまり「平安の昔から変わらないしきたりのなかで,今日まで途切れることなく続けられてきました御祭の数々が,いまも昔のままの姿でおこなわれてございます」(同上,2頁)という髙谷朝子の文句は歴史学的に観るとき,完全に〈呪文の範囲〉から脱出できる中身を,全然もっていなかった。
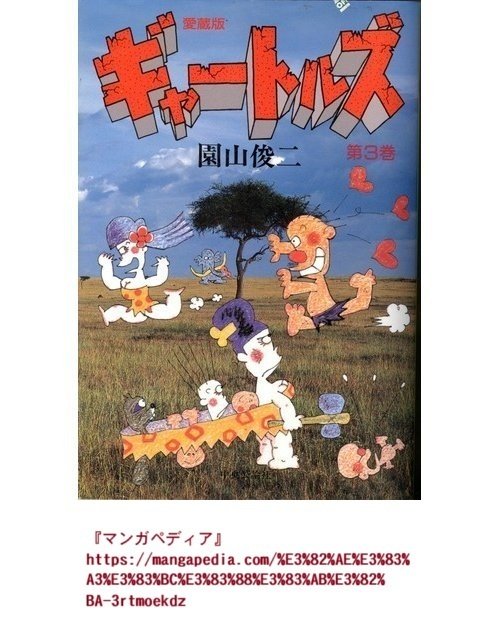
髙谷朝子が口にした文句は,自分がまだそうだと信ずる点を,他者に向けて発信しつづけるためだとすれば,まさにこの人自身が,あの「ギャートルズ風の古代原人的な日本人像」との絶対的な相違に関してなのだが,さきに説明してほしかった。
---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------
