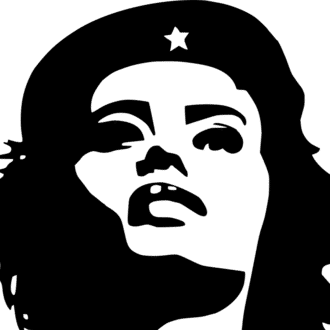H. L. A. ハート『法の概念』読んだ
めちゃ時間かかったけど無理やり読み終えたことにした。
邦訳書は2冊あって、ちくま学芸文庫のほうが電子書籍あり、かつお手頃価格である。みすず書房のほうが訳は読みにくいが、正確とのことである。さすがみすず書房だ。
そもそも法律の文章は日本語であっても読みくい。というかたぶん日本語は法律に向いていないかもしれない。そういうことをラテン語を学んでいると考えてしまう。
法律の文章は、英語の意味は取れるけど、日本語にするとめちゃ読みにくくなる。『自由の国と感染症』でも判決文の訳にはとても苦労したことを思い出した。
ちくま学芸文庫のほうは訳に問題があるのは、ニー仏さんが何度も指摘されているのである。
というかニー仏さんの読書会放送がなければ『法の概念』を読もうとは思わなかっただろうし、また最後まで読むこともできなかった。
以下、理解できた範囲で感想を。
まず法とは威嚇に支えられた命令ではない。
銀行で強盗が銀行員のこめかみに銃を突きつけ金を出せといえば、それは威嚇に支えられた命令である。
だが法律はこのようにして守られているわけではない。いつも1対1で脅すわけにはいかない。いつも脅しているわけではないのに、大多数が持続的に命令に従っているのが法である。
大多数が一致して行動するときルールが存在するといえる。必ずしも威嚇や要求は必要ではない。
制裁の必要性と可能性に関する議論の際に強調したように、ルールの秩序を力ずくで誰かに押しつけるには、十分な数のメンバーが自主的にその秩序を受容している必要がある。彼らの自主的協力によって形成される権威( authority)なしには、法と政府の強制力は確立し得ない。
大多数が一致して遵守するという意味では、道徳と似ている。しかし道徳には守らないとき罰則があるとは限らない。罰則が公的に執行され、確定されるのが法である。つまり予測可能である。
法は予測可能という点で、道徳のような法外ルールとは異なっている。
また刑法のような罰則が定められている法もあれば、義務や手続きを定めている法もある。つまり威嚇を伴わない法もある。
だから法とは威嚇に支えられた命令とはいえない。
規範は人々に受け入れられているから成立する。規範は遵守しなければ制裁が課される。
だから遵守しない人が十分に少数になるように調整されていると思われる。
だから人々は受け入れ、社会は安定する。
遵守しない人が十分に少なくなければ、彼らは制裁を課されるのだから怒って革命を起こす。
昨今、酷い男性差別がまかり通っているが、なにか暴力沙汰がおこっているわけでもないので、これくらいの男性差別なら受忍不能というわけではないらしい。
他方で、従属者集団──支配者集団と比べたその規模は、支配者集団の強制手段、連帯と規律によっても、また従属者集団の弱さや組織力のなさに応じても変化するが──を服属させ、永続的劣位に押しとどめるために、強制力が行使されることもある。こうして抑圧された人々にとって、ルールの秩序に忠誠を尽くすべき理由はなく、それは単なる恐怖の対象である。彼らはその犠牲者であり、受益者ではない。
現役世代の男性が徹底的に搾取されても、その多くは現状の秩序に服従するから、搾取は問題にならないし、これからも続いていくだろう。
いいなと思ったら応援しよう!