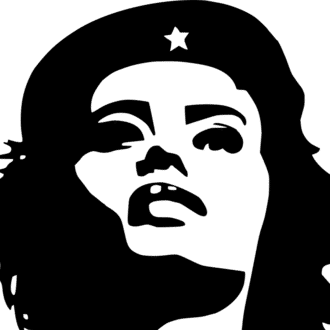音声に親しむ
昨日は休日だったので朝からお勉強に励んだのであった。昼過ぎまでに2コマのオンラインのレッスンを受けた。文字や録音された音声ばかりで勉強しているのでインタラクティブなレッスンはとても良い。
1日の課題がおおかた片付いたところで、リアルタイムで見れなかった一昨日の仏教のアレさんの読書会の録画を拝聴することから始めた。
エヴァン・トンプソン'Why I am not a BUddhist'読書会も第3章に突入した。ここは自分で読んでいてもいまいち理解できないところが多かったのでじっくり聞いた。とても勉強になった。
とくにミリンダ王の問いのくだりはよかった。ギリシャ人国家バクトリアのミリンダ王が説一切有部のナーガセーナにお前は何者だと問う有名なアレである。ナーガセーナなどというものは存在しないとかなんとか答えるのだが、初めてこのエピソードを聞いたときなんてめんどくさい人なんだと思ったものだ。そして仏教の編集部のお二人のような仏教を実践されている方でも同じように感じるのだとわかったのがよかった。
このナーガセーナのように自己は存在しないとか無我とかいうものが初期仏教の大きな柱の一つであるのだが、これは非常にややこしい問題でブッダ自身は自己があるともないとも明言していない。自己はないと思いなしている主体は自己ではないのか?というあまりお近づきになりたくない話題に発展しかねないのである。
こうしたことは仏教を含むインド哲学では千年単位で議論され続けており、別に仏教だけが哲学的に深いというわけじゃないと著者のトンプソンは仏教特別主義を批判するわけである。そしてトンプソンという人もわりとめんどくさい人らしいということがわかった、これは独学ではわからなかった。
言えることは、ゴータマ・ブッダがニカーヤで示したように、自己というのは身体性の中にはなさそうだということだ。トンプソンは鳥は飛ぶけど、飛ぶという行為は鳥の身体の中に存在するわけじゃないよね、と例をだしている。それと同様に意識とか自己とかいうものも我々の能の中にあるわけではない。
とはいうものの、なにか自身の同一性を規定するようなものを仮にでも設定しておいたほうが、我々の直観とも整合的であるし、仏教の実践においてもわかりやすいという面もある。それに関する用語としてpudgalaとか犢子部とかを知ることができてよかった。知らない単語だいすき。
とまあこんな感じで来週も楽しみというわけである。
夜は友人らとオンラインで喋り散らかした。
私は主にこの記事で書いたようなことをしゃべった。けっこう酷いことを話したようなきがするが、まあそういう時もあるだろう。
私がこの記事で言いたかったことは、自粛を始めとする需要引き締めは強者の論理であるということだ。需要引き締めの影響を受けない職業であったり、少々の経済的打撃など痛くも痒くもないほどの資産があったり、そのような強者にとっては、疫病による死は、誰かが失業しようが倒産しようが、なんとしても避けたいものだろう。感染症は偉大なるレヴェラーだからだ。
したがって持たざるものはそういう強者の論理に乗っかってはいけないのだ。そういうことがわかった上でみんな自粛してんの?と言いたかったのだが伝わっただろうか。
しかしそのようなことはともかく、音声に親しんだ日曜日となったので非常に良かった。たまにはこういう日も必要である。
いいなと思ったら応援しよう!