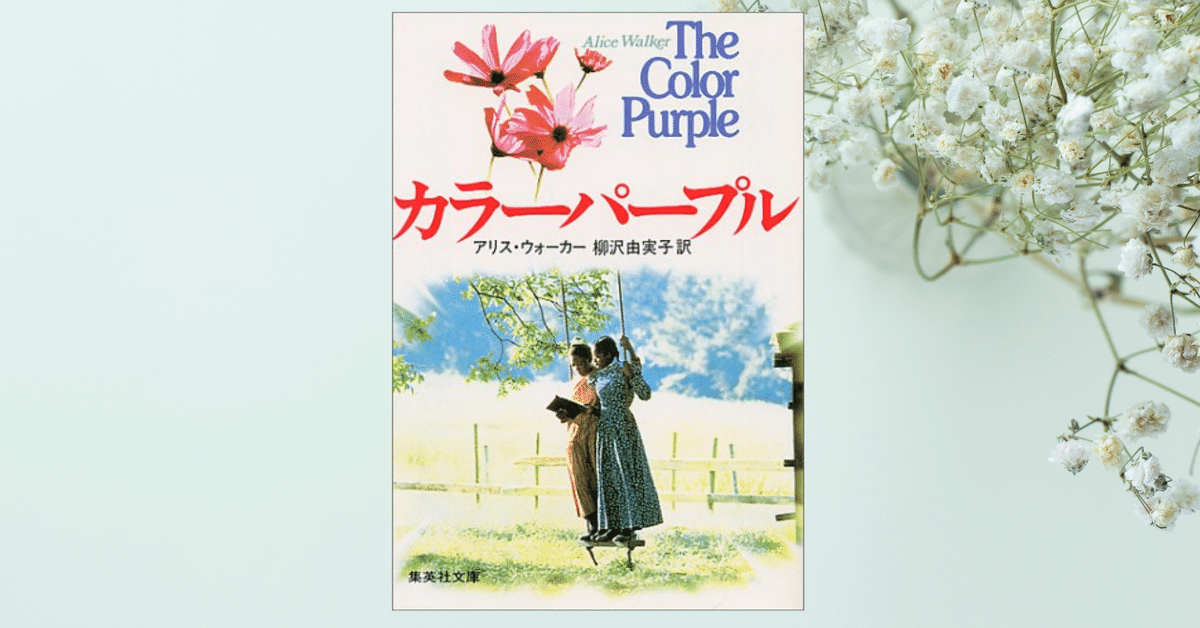
【読書】『カラー・パープル』/ピュリッツァー賞受賞作を読む
差別の色濃い時代と場所に、黒人女性として生きる。
それがどういうことなのかを、20代の頃読んだこの本で、初めて知った。
衝撃で何度も本を閉じながらも、読み止めることができなかった。
わたしの想像を超えた過酷な暴力と男性への服従が、そこにはあった。
生まれた瞬間から「白人及び男性優位」の価値観が刷り込まれることがどういうことなのか、そしてそれがどのように黒人女性から力を奪ってきたのかが、この作品ではとても立体的に描かれる。
生まれたときから絶えず「お前は無価値な人間だ」というメッセージを受け取り続けると、人は自分の足で立ちあがることを思いつかなくなる。
物として扱われることに、疑問を抱かなくなる。
これは、精神の虐殺だ。
男性優位の価値観を刷り込まれているのは、なにも女性だけではない。
男性自身もその価値観を刷り込まれているため、特段の悪意なく暴力をふるい隷属させ、ただの所有物として女性を扱う。
仕事がうまくいかずイライラしたとき、彼らは椅子を蹴るのとまったく同じ気軽さで、自分の妻を蹴る。
そこに罪の意識はない。なぜなら自分の所有物だから。彼らが後悔するとすれば、蹴った衝撃で自分の足が痛むことくらい。
悪意不在の差別。無自覚な暴力。
このことが、わたしにはとても恐ろしく思えた。
これは、そのような絶望的な環境に生まれたひとりの黒人女性セリーが、やがて立ち上がり、精神的自立を確立していくまでの物語だ。
魂が震えるような、それは読書体験だった。
セリーが自分の置かれた環境に疑問を抱き始めるきっかけを作るのは、シャグという歌手の女性だ。
彼女は同じ時代に生きる黒人女性でありながら、精神的・経済的自立を確立し、誰にも隷属せず、自分の思うまま自由奔放に生きている。
このシャグと友人になり語り合うことで、セリーに変化が起こる。
セリーとシャグが神について語り合う場面が、わたしはとても好きだ。
教育を受ける機会を持たなかったセリーの「無教養文体」で綴られるこの会話は、シャグがセリーに「あんたには神さまがどんな姿かたちに見えるのか、あたしに教えて」と訊くところから始まる。
できない、あたし、とても恥ずかしくてできない、って言った。いままで、こんなことをあたしに聞いた人いなかったから、あたしはびっくりしてしまった。それに、ちゃんと考えてみると、あたしの神さまはなんだかおかしいんだ。でもそれ以外には何も思い浮かばないから、その姿を話してみようと思った。シャグが何て言うか聞きたかったし。
いいよ、話してみる。彼は大きくて、年取っていて、背が高くて、白髪で、白人なの。白いローブをまとって、裸足で歩いてる。
青い目?と彼女。
青っぽいグレー。澄んで、大きい目してる。白いまつげでね。
シャグは、笑った。
(中略)
聖書を読んだら神は白人としか思えないもの、とシャグは言って、深い溜息をついた。あたしは神が白人で、しかも男だとわかったとき、興味をなくしたんだ。
あたしが信じるのはこういうことなの、聞いて。シャグは続ける。神はあんたの中にいる。すべての人の中にいるの。この世に生まれたとき、誰でも神をもってうまれてくるのさ。でも、それを捜す人だけが見つけることができる。
それはどんなふうにも見えないの。何か形のあるものではないから。神ってそのものなんだ。いまあるすべてのもの、いままであったすべてのもの、これからあるすべてのものなんだ。それが感じられるとき、それを感じることができてうれしいとき、あんたはそれを見つけた、ということだと思う。
シャグは続けた。あたしがその年取った白人の男から自由になったのは、木がきっかけだった。それから空気。それから鳥たち。それからあたし以外の人間たち。ある日静かに座って、母さんのいない子供のように感じていたときー実際そうだったんだけどー、突然こう思った。すべてのものの中にいるっていうあの感じ。全然離れていないっていう感じ。あたしにはわかった、もし木を切れば、あたしの腕から血が流れるだろうって。あたしは思わず声をあげて笑った、そして泣いた、そして家のまわりを駆け回ったの。
(中略)
男は何でも壊してしまう、シャグは言う。あんたのグリッツの箱の上に座るのも、あんたの頭の中に陣取っているのも、ラジオから高らかに聞こえるのも、みんな男。彼はあんたにどこもかしこも男だらけって思わせる。この世はすべて男が牛耳っているんだと思うころには、あんたは神は男だと信じるようになっている。でも男は神じゃない。いいかい?お祈りするとき、そしてあんたの祈りの向こうに男があぐらかいているとき、そこをおどきって言うんだよ、わかった?たくさんの花、風、水、大きい石の力を借りて彼を追い払うんだよ。
でも、これがむずかしいことだ。彼はほんとうに長いことそこにいたから、動こうともしない。彼はいなずま、洪水、地震となってあたしをおびやかすの。
神の姿を思い浮かべようとするとき、そこに白人男性の姿が見える。
「神が、自分に暴力をふるい隷属させる存在と同じ姿をしている」ということに、セリーは(そしてたぶん多くの読者も)、シャグに指摘されるまでなんの疑問も抱かない。
この会話のあと、「神は白人男性じゃない。このわたしの中にいるんだ」ということが心に染み入ってくるにつれ、セリーは無価値感を乗り越え、自分の足で立ち上がる精神を取り戻していく。
そしてその態度はやがて、周囲の男性たちの意識も変えていく。
ピュリツァー賞受賞の名作。
これは間違いなく、私の血肉になった本のうちの一冊。
