
#21 ミトコンドリアを知れば人生が変わる
2023年(上)
真冬
イデベノン 0.25 0.25 0.5
リバオール 0.25 0.25 0.5
コレキサミン 1 1 1
ビタミンC「2000」 0.5 0.5 0.5
身体はほとんど乾癬が出ない状態をキープできていましたが、たまに後頭部がヒリヒリすることがあったので、イデベノンとリバオールを夜だけ増やしてみました。
でも、増量してから、ニキビ跡ができるような膿ニキビが頻繁にできるようになりました。今までは、主にビタミンB2とB6で顎周りなどに1個か2個小さい赤いのができてすぐ治るようだったのが、いきなり膿を持った赤いのがこめかみやあごなど(通常できにくい箇所)に合わせて3個くらいできるようになったのです。
イデベノン 0.5 0.25 0.5
リバオール 0.5 0.25 0.5
コレキサミン 1 1 1
ビタミンC「2000」 0.5 0.5 0.5
やはり寒さが増すと小さい乾癬が身体に少し出てきたので、イデベノンとリバオールを朝も増やしました。そうすると更にニキビができるようになりました。普通は赤い小さいのができて、だんだん大きくなって場合によっては膿を持つようになると思うのですが、気づいたり、朝起きたらいきなり膿を持った大きめの赤くて痛いニキビができているのです。
90年代はニキビは思春期にできるもので大人になったら自然に治ると言われていました。(これもアトピーに似ている。子供の頃、人生の一時期に患うけれど、大人になったら自然に治ると当時は言われていたはず)これはおかしい。しかも、40代だとターンオーバーが遅くなっているので、余計に跡になってしまう。
でも、我慢して様子を見ていましたが、生理前にすごく気持ち悪くなってしまったのです。PMSでここまで強い吐き気が出るというのは覚えている限り直近ではありませんでした。ビタミンCを飲み過ぎた時の気持ち悪さのような気がしたので、とりあえずビタミンC「2000」を減薬していって残りを飲み切って終わらせることにしました。(0.25 0.25 0.25)→(0.25 0 0.25)→(0.25 0 0)→(0 0 0)
これで前橋賢先生のビオチン療法(ビオチン、ミヤリサン、ビタミンC)で飲んでいたものは完全に卒業することになりました。先生、どうもありがとうございました。
生理開始の前日くらいに肝臓全体が圧迫感を感じて発作のようになりました。15分くらい右側を下にして横になっていたら治まりました。
もう完全に
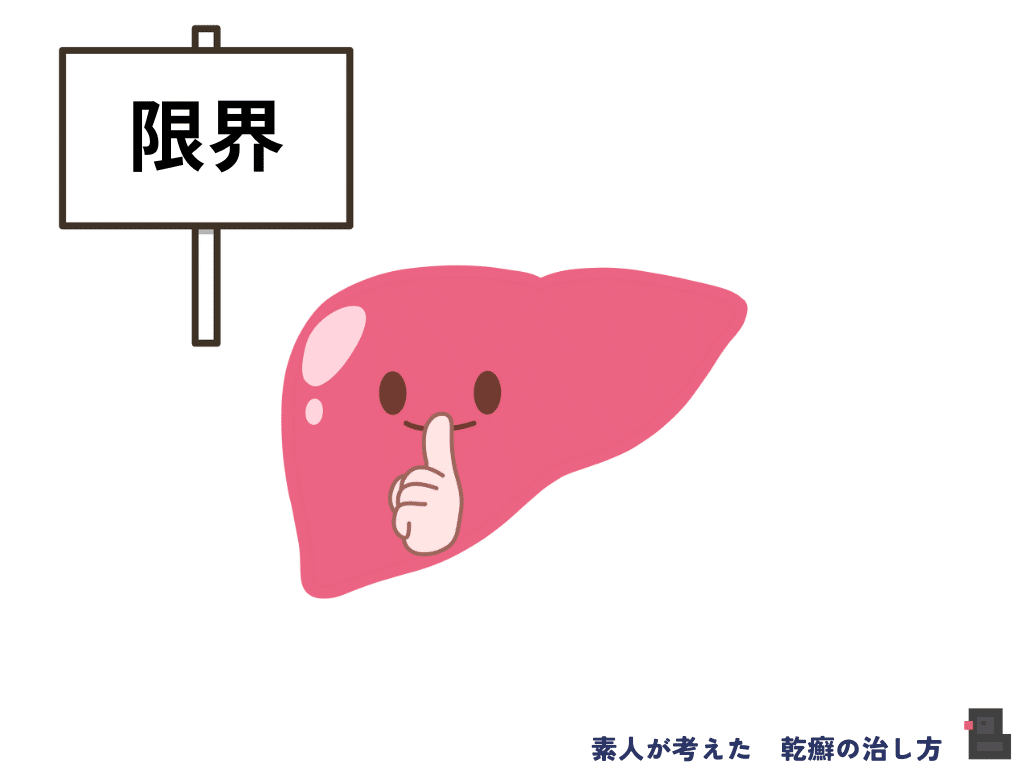
イデベノン 0.25 0.25 0.25
リバオール 0.25 0.25 0.25
コレキサミン 1 1 1
ウルソ 0.25 0.25 0.25
イデベノンとリバオールを0.25に戻して、ビタミンC「2000」の代わりにウルソを追加しました。ビタミンC「2000」は結構効いていて、一般的なビタミンCの効用ですが、肌がしっとりしたり、歯茎から出血しなくなったり、便通がよくなったりと色々体調がよくなっていました。イデベノン⬇コレキサミン⬆ビタミンC⬆のようなかんじ。ミヤフローラEX(ミヤリサンU)と一緒に飲んで乾癬が消えてきたのも医薬品のビタミンC「2000」のみだったので、やめるのが怖かったのと、肝臓が疲れていると思ってウルソに置き換えました。
イデベノン 0.25 0.25 0.25
リバオール 0.25 0.25 0.25
コレキサミン 1 1 1
ビタミンC「2000」 0.5 0.5 0.5
結果は、あまりこれと変わりませんでした。少なくとも特筆するようなものはありませんでした。
あとこの辺で生理終盤から少しだけ飲んでいたファイチも飲み切ってやめました。ネットで見る限りですが、生理後に貧血になっている人が少なかったので、やはりこれも肝臓が悪いのではないかと思っていました。そもそも、全身を巡っている血ではなくて、子宮にたまっている血だし、しかもその経血の中で血液は1割くらいなので、少しめまいがする程度ならわかりますが頭痛や強烈なだるさを伴ったり起き上がれない程の貧血になるのはおかしいと思っていました。ブレイクスルー後に肝機能があがったと考えたので、これも少しずつ減量して終了しました。経血(けいけつ)と血液(けつえき)のちがい👇
軽くだるさはありますが、普通に休息や睡眠をとれば回復するような状態になったので、貧血薬は不要になりました。
ミトコンドリア 電子伝達系 ATP🔃肝臓の再生
これらのバランス🤔
イデベノン 0.25 0.25 0.5
リバオール 0.25 0.25 0.5
コレキサミン 1 1 1
ウルソをやめて3つにしました。これ以上イデベノンを増やすと、おそらく肝臓の負担>ATPになる。細かい乾癬が完全に消えないのもそのせいだと思う。もう一段細かく割って、0.125にして、0.125~0.375で調整してもたいして変わらないだろうなと思いました。
そこでネットを徘徊して、次に試す薬を探してみましたが、これ以上はネット上の断片的な情報よりも、ある程度まとまった専門家の知識が必要なのではと考えたので、少し本を読んでみることにしました。(イデベノンは個人輸入で飲んでいる人が一定数いるようで、レビューを見ても、規定量の1日に2錠飲んでも、私のような副作用が起こっていなかったので)
医師が発見!尋常性乾癬を治したハイテクミネラル
これは、ごま書房新社の担当編集の方がX(旧ツイッター・Twitter)で宣伝していて、乾癬とミトコンドリアの関係に言及していたので、興味を持ちました。たぶん、何かの治療をしていたら、たまたま乾癬がよくなって、でも病態はわからないというよくある内容だろうし、こんな本は図書館にはないだろうと思いましたが、あったので一応読んでみました。
なんかよくわからないけれど、重要なのはここかな👇


現在の医学では、フリーラジカルは悪いとされているけれど、適度な量はミトコンドリアのターンオーバーに必要らしい。
じゃあ、具体的にどうすればいいのかと著者の名前で検索したら、癌の自由診療をされているようで、治療費を見たら高すぎて治療を受けるのは無理だなと思いました。それに、効果が高ければ、標準治療にして保険診療にしてしまった方がメリットがあるし。手に入れられそうな医薬品でどうにかできそうでもなかったので、これは終了しました。
イオン化ミネラル水か…そういえば2016年頃に、アトピーに水素水が効くと流行ったな。というか、それよりも2005年頃に私は新卒で就職できなかったので、日雇い等をしていました。ある時、春くらいだったと思いますが、手芸用品(ボタンとかパーツ)の仕分け作業の現場に行きました。その時は、腕にも小さい乾癬が出ていたので、長袖で隠していたのですが、作業をする際に見えてしまったようで、そこのたぶんパートのおばさんに「いい水があるのよ~」と売りつけられそうになりました。(同じ台で向き合って作業していたら、見つけたようで、突然言われました)あの宗教をやっているような人に特有の顔つきと雰囲気で。私はそんなに他人のことをジロジロ見たりしないし、一目でわかるアトピーのように広範囲に面で広がっているわけでもなかったので、余計にショックでした。という、とてもつらい出来事を思い出しました。
重要と思われる単語
・酸化還元反応 ・フリーラジカル(活性酸素種 過酸化水素 活性酸素) ・電子伝達系 ・抗酸化作用 ・アポトーシス
ミトコンドリアを知れば人生が変わる
ここからが本題というか、ミトコンドリアの電子伝達系にアプローチしたらブレイクスルーが起きて、その中でイデベノンがある程度までは+に働くが、強すぎる場合があるのが問題と考えていたので、ミトコンドリアについて知ろうとしました。
Amazonで「ミトコンドリア」で検索すると、いわゆる専門書があまりありませんでした。健康法のような一般書が少しあるくらい。よく聞くわりにはどうして?と思いました。でも、仕方がないので、簡単にわかりそうな本から始めることにしました。初めて見る出版社だったので、若干不安でしたが、内容はよかったです。
私たちの体を動かすには、何にしてもATPのエネルギーが必要で、本書ではそれをATP通貨と表現している。

ミトコンドリアの活性化とはATPがたくさん作られること。そういえばノーベル賞の本庶先生も言っていた。ベザフィブラートの件。(6:14~)
ミトコンドリアは、健康や老化に深く関わっている。

ミトコンドリアとアポトーシス


ミトコンドリアのマイトファジー

だから、イデベノンがアルツハイマー型認知症や他の認識障害の治療薬として開発されたのかな?でも、これも大航海時代のビタミンCのように、不足しているとされている栄養素を摂取してもその病気が治るわけではないというやつだよな🤔

低気圧だと具合が悪くなる人は結構いますよね。何気にすごいことが書いてありました。確かに体感的にそんなかんじはする。ブレイクスルー後には確実になくなった不定愁訴の原因がわからなかったし。

ここでまた私文素人の思いつきですが、シェーグレン症候群ってミトコンドリアの機能低下に伴う症状=老化現象に似ている。ドライアイ、ドライマウス、だるさ。とにかく疲れて、目や口だけではなく、私の場合はアトピーほどではないですが、皮膚も乾いてしわっぽくなってげっそりします。現代の医学では、自己免疫疾患であり、免疫の力が過剰に働いて涙腺や唾液腺を攻撃しているとされていますが、そもそものメカニズムは不明です。
シェーグレン症候群が発表されたのは1933年で、この時代はまだ、ミトコンドリアというのは、ほとんどよくわかっていなかったので、当然結びつけて考えられなかったのではないか。そして、医学=官僚制なので、そのままの定義と仕組みでずっと来ているのではないかと考えました。
そして、これもピントがずれている気がする。近すぎても遠すぎてもよく見えない。たぶんミクロで見ると、免疫の力が過剰に働いて自己を攻撃しているという現象で、マクロで見ると、「ミトコンドリアの機能低下に伴う老化現象」なのではないかと考えました。ビオチン療法(腸活・菌活)でよくなるし、その後の肝機能とミトコンドリアを狙った乾癬自己実験でも寛解したままだし。…ただの素人の思いつきです。
知りたかったのは、ミトコンドリアの基本的知識とイデベノンが強いのをどうしたらいいか?でしたが、コエンザイムQ10に関してはいいことしか書いてありませんでした。
でも、基本的には知っておいた方がいい知識だと思われますので、この本はおすすめです。
忙しい人のための代謝学〜ミトコンドリアがわかれば代謝がわかる
ミトコンドリアで検索して出てきた数少ない本だったので、一応さらっと目を通しましたが、タイトル通り、たぶん基本的なことしか書いてありませんでした。(ミトコンドリアの基本的なことはわかったので、現在の目的はイデベノンの調整)
ノーベル化学賞に輝いた研究のすごいところをわかりやすく説明してみた
これは図書館の新刊の棚にあった時に見つけて、読もうと思っていたけれど、後回しになっていた本です。何か着想を得られないかなと、軽い気持ちで手に取ってみました。本当は、ノーベル生理学・医学賞がよかったのですが、ペラペラとめくってみたところ、簡単に読めそうだったし、理系ならいいかと思いました。でも結果的にラッキーでした。
全体的におもしろかったですが、この研究に直接関係ありそうな箇所だけ簡単に書きます。
Chapter 2 アンモニアを合成し、食糧危機を救う ハーバー・ボッシュ法
これに関しては、マルサスの人口論を読んだ時に、「どうやって解決したんだろう?」と疑問を持って軽く調べたので、名前を知っているくらいでした。アンモニアを科学の力で人工的に作り出して、さらに化学反応させて肥料に変換することを可能にして食料不足の問題に対処しました。
ただ、フリッツ・ハーバーは功罪あるので、興味がある方は、以下の本の第3章 化学肥料から始まった悲劇を読んでみてください。
適切な触媒(化学反応の進行を促す物質)を見つけるために2万回もの実験を行ったと言われている。

やっぱり研究ってこういう地道な試行錯誤が必要なんだとわかりました。私の自己実験なんて、そこまで試していないし、規模も質も全然違うし、まだまだだなと。

そのような研究と同列に語るのは適切ではないかもしれませんが、答えがあるかどうかわからないところに、突っ込んで行ったところは、かなり辛かったのではないかなと思いました。(毒ガスを撒いた人なので、そういうのはなかったのかもしれませんが)
私の場合は、大きなコンクリートの壁があって絶対に前に進めない状況(新卒で正規で就職できないと、その後は正規になれない)だったので、それよりは、先に何があるかわからなくても、もし何もなくても、這ってでも少しでも進めそうな余地がありそうな方がマシだったというかんじです。正直、そちらよりは絶望的ではありませんでした。前者は完全に0で、後者も常識的に考えれば0に近いけれど完全に0というわけではない。そのくらいの違いです。前に進めているかどうかわからなくても、何もしないよりは、昨日と今日は違うという本当に微かな感覚があったというか、そのように自分に言い聞かせていただけなのかもしれませんが。
リバオールは触媒に似ている。(ネタじゃないです。私文の素人です)
他の薬剤の効果を増強(化学反応を促進)しているので、触媒に似ているなと思って調べると、生体内の触媒は酵素と言われるらしい。これも添付文書等には、効能又は効果「慢性肝疾患における肝機能の改善」に関する内容しか書いてありませんが、どういう原理で?と思いました。
そこで、(もちろんざっとは調べてありましたが、改めてちゃんと)主成分のジクロロ酢酸ジイソプロピルアミンで調べてみると
次にパンガミン酸(ビタミンB15)で調べてみると
体内の酵素系に働き、各種代謝を促進、滋養強壮にも役立つとあるので、やはりそういうかんじなのかなと思いました。(ざっと調べてはありましたが、「酵素」というのがよく聞く単語で曖昧なままだったので、なんとなくそのままでした)そういえば、ビオチン療法をしている時にエビオス錠(ビール酵母)が効くと言っていた人もいたけれど、これかなと思いました。
そうすると、乾癬が冬に悪化して、夏に軽快する理由はやはり気温なのではないかと考えました。これは小学校の理科でやったと思いますが、温度が高くなると一般的に化学反応の速度が速くなります。忘れてしまっている方も、経験的にわかると思いますが、例えば、塩でも砂糖でも、冷たい水よりは温かいお湯の方が速く溶けますよね。夏は反応速度が速くなって、冬は遅くなる。
そして肝臓は化学反応を行うところなので、やはり現代の医学では指標がない何かしらの肝機能が良くなったり悪くなったりするのが原因不明の乾癬の波🌊という仮説にも合っている。乾癬やアトピーに亜鉛が効く(亜鉛補充療法)という情報が、専門家だけでなく素人の報告にもありますが、これは、現在の医学で一般的に言われているような皮膚炎や味覚障害(コロナの後遺症でよく聞いた)、貧血、発育障害に効くなどの解釈ではなく(ネット上だともっと色々言われている)、酵素に関係しているのではないかと考えました。たぶんビオチンも。おそらく、他にも乾癬やアトピーなどに奏功すると言われているビタミン、ミネラルなどの栄養素も。

と、いうことは

イデベノン 0.25
リバオール 0.5(20倍ではなく、実際は0.25→0.5で2倍)🔥
コレキサミン 0.5(7月で暑くなって安定していたので減らしていた)

2023年(上)おわり 2023年(下)🔥につづく
