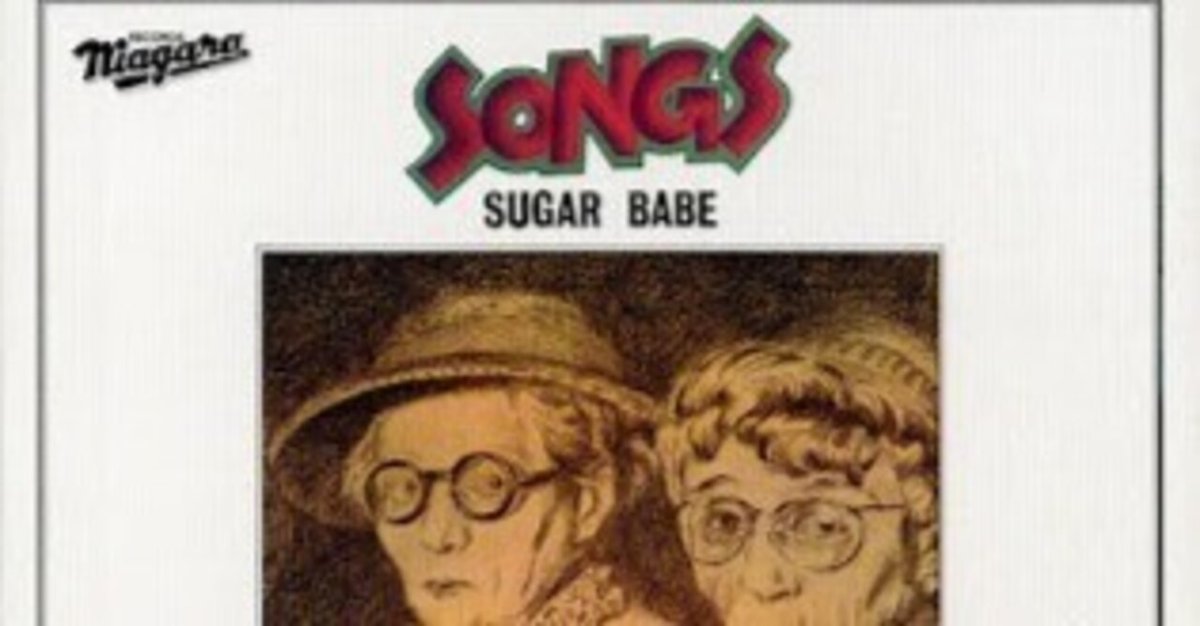
シュガー・ベイブ 『SONGS』 (1975)
━━━「誰かが話すのに疲れたとき、誰かが歌い始める」
あらゆる音楽ジャンルには、そのスタイルやトーンが音楽シーンで発展してきた中で必ず起点がある。それは、時代と場所が絶妙に重なり合い、ジャンルの形成に大きく寄与したアーティストやグループである。このような存在は、ジャンルや時代によってその影響の大きさが異なるが、音楽の歴史の中で象徴的なランドマークとなることが多い。しかしながら、彼らがその当時、メインシーン以外で注目されることが少なく、数十年後に再発見され、次世代のリスナーによってそのアルバムが再評価されるというケースも少なくない。
シティ・ポップのようなジャンルにも、そのような瞬間が存在する。この甘美で興味深い歴史が時を経て再発見され、不朽の名作と称される音楽を生み出してきた。しかし、その制作時点では、新たな音楽ジャンルを牽引する巨人たちのキャリアの起点として記録されていたに過ぎなかった。そして、日本のポップミュージックの世代を牽引する独自の音を生み出すために、様々な影響を融合させるアイデアを具現化したグループこそが、「シュガー・ベイブ」なのである。
リスナーというクランケ
シュガー・ベイブの誕生は、「Add Some Music To Your Day」というカルテットの解散を契機としていた。このバンドは末期には並木進、竹川真一、小川喜久夫、山下達郎の4人で構成され、全員が19~20歳の若さで音楽活動をしていた。彼らは唯一のアルバムをセルフレコーディング・セルフプロデュースし、ゲストボーカルやミュージシャンの助けを借りながら制作した。このセルフタイトルのアルバムは、限定的なプライベートプレスでリリースされたものの、売り上げが芳しくなく、メンバーの個人的な理由も重なって解散に至った。
このアルバムは、ポップソングやサーフロックといった様々なジャンルのカバー曲を合唱スタイルでまとめたものであった。完成度こそ高くなかったものの、音楽に対する情熱が感じられる作品であり、特に若き日の山下達郎が、後のソロ活動で展開するスタイルの片鱗を見せていた点で注目に値する。このアルバムは、当時のミュージシャンやポップ音楽のファンの間で徐々に共有されるようになり、カルテットの解散後、山下達郎はギターを担当する新たな音楽グループを構想するようになった。
山下は旧バンドメイトの小川(ベース担当)や「Add Some」のゲストミュージシャンだった村松邦男(リズムギター担当)とチームを組み、さらにロック喫茶で活動していた独立系ミュージシャンである大貫妙子(ボーカル・キーボード担当)と野口明彦(ドラム担当)を迎え入れた。こうして、シュガー・ベイブの初期で最も象徴的なラインアップが完成した。
このラインアップは1973年から楽曲制作を開始し、異なる音楽的影響を融合させた独自のサウンドを作り上げた。当時の日本のポップミュージックには珍しい、セブンスコード進行やソフトロック的なアプローチを取り入れ、西洋的な音楽に傾倒したのが特徴であった。「Add Some」のアルバムは商業的には失敗だったが、ギタリストの伊藤銀次の目に留まり、彼を通じて「はっぴいえんど」のメンバーであり後に伝説的存在となる大滝詠一へと繋がった。大滝はシュガー・ベイブのボーカル力に感銘を受け、彼らの音楽のプロデュースに興味を持つようになった。
1973年後半、シュガー・ベイブは大滝詠一とのコラボレーションを開始し、「はっぴいえんど」のラストコンサートではバックボーカルを務めた。その後、小規模なフェスティバルやコンサートホールでの演奏を通じて徐々に認知度を高めていった。メンバーは、松任谷由実(旧姓:荒井由実)など他のアーティストのバックボーカルとしても活動していた。特に山下達郎は経済的な問題からセッションミュージシャンやバックボーカリストとしての活動を増やしていた。
1974年、シュガー・ベイブは大滝詠一が設立した日本初のミュージシャン主導のレーベル「ナイアガラレーベル」の第1号バンドとして契約を結ぶ。このレーベルは後に日本で成功を収めることになる。1975年にはリハーサルと録音期間を経て、デビューアルバム『SONGS』とシングル「DOWN TOWN」が同時リリースされた。
シュガー・ベイブは、当時の日本ポップ音楽において異例のサウンドを作り出すという多くの要因のもとで誕生した。メンバー全員が絶妙なタイミングで集まり、多様な影響を反映しながらも統一感のある音楽を生み出した。作曲、歌詞、演奏は試行錯誤の連続であり、各メンバーがそれぞれの得意分野を活かしつつ、山下達郎が大滝や伊藤の影響を受けながら重要な決断を下し、完成度の高い作品を目指した。結果として生まれた『SONGS』は、予想外の展開を経たにもかかわらず、豊かで情熱に満ちた作品となり、メンバー全員の音楽への愛が詰まったアルバムであった。
美しい音楽は処方箋として
『SONGS』は11曲を収録しており、それぞれ異なる作曲や楽器演奏のアプローチを取りながらも、一貫したトーンを保っている。楽曲の構成とプロダクションが巧みにバランスを取り合い、冒頭から最後のリズムまで、質の高いトラックが次々と続く。各曲が独自の重要性を持ち、リズムの創り方において興味深いアイデアを提示している。アルバムのオープニング曲「Show」は、これらの要素を最も効果的に体現している。この曲は山下達郎がバンドに初めて持ち込んだ楽曲で、初期のライブのオープニング曲として完成させられたものだ。各楽器がシンプルなパターンを持ちながらも、それらが組み合わさることでユニークで陽気なリズムを生み出している。冒頭の力強い音は聴き手の注意を引き付け、アップテンポなメインリズムへと移行する。
大貫妙子の繊細ながらも存在感のあるキーボード、野口明彦のシンプルで的確なドラム、小川、村松、山下によるベースとギターのシンプルなコード進行の調和が魅力的だ。そして、山下の魅力的で生き生きとしたボーカルは、まるでもう一つの楽器のように楽曲に彩りを加えている。ここにはサーフロックの持続音やソフトロック的なソロ、ポップスに影響を受けたボーカル合唱など、バンドの影響が様々に現れている。バランスが絶妙で、キャッチーなポップソングでありながら、曲が機能するために様々な要素が複雑に絡み合っている。
シングル「Down Town」はアルバムと同時にリリースされ、山下と伊藤銀次の交流の中で生まれた楽曲だ。演奏はより物悲しいムードを持ちながらも、オープニング曲と同じトーンを維持している。シンプルな楽器構成でファンキーかつ情熱的なリズムを作り出し、山下の甘くキャッチーなボーカルパフォーマンスと、印象的なブリッジとコーラスが特徴的である。楽曲のアイデアと最終的な音は一見簡単そうに思えるが、どれか一つの楽器を外すだけで全く別の楽曲になってしまうほど、すべての要素が重要である。
続く楽曲では大貫妙子がボーカルと演奏の中心に立ち、特にライブでの人気曲となった。プロダクション面では微妙ながらも天才的な変化が見られ、大貫のボーカルとキーボードが他の楽器よりやや大きめにミックスされている。ギターはアルバムのメインのトーンを維持しつつ、他の楽器が大貫の甘く情熱的な演奏に寄り添う形になっている。この曲は彼女のアルバム『Romantique』でも再録音され、彼女にとって大切な感情的価値を持つ曲である。
「風の世界」は、感傷的でメランコリックなトーンがさらに際立つ楽曲だ。コード進行や楽曲全体に散りばめられた細やかなディテールが、冒頭から終わりまでのダイナミックな流れを作り出している。例えば村松が起こした小さなミスで、大貫の息遣いが遅れて録音された箇所があるが、これが楽曲に美しく魅力的なニュアンスを加えている。
アルバムのA面を締めくくる「ためいきばかり」は、前曲までの落ち着いたムードとは対照的に、明るく軽快な雰囲気を取り戻す楽曲である。シュガー・ベイブは山下や大貫という主要メンバーの存在が注目されがちだが、この曲はバンド全体としての協力と、個々のメンバーの重要性を示している。村松が作曲を手掛けたこの楽曲は、春を感じさせるような魅力的な雰囲気を持ち、異なるキーボードの使用が特徴的だ。
B面は大貫の3曲目で最後の楽曲「いつも通り」で幕を開ける。この曲では、彼女の以前の貢献で提示された主なアイデアを継承しつつ、バックのストリングスや短いサックスソロなど、新たな要素が取り入れられている。タツローのギターと対話するようなサックスソロは、特に印象的である。この楽曲は楽器の層が多彩であり、アルバム全体でも最も落ち着いた一曲と言える。楽器ごとに感情が込められ、それぞれが楽曲の中で独自の役割を果たしている点は、当時のバンドの状況や経験を考えると特筆に値する。
これらの細部へのこだわりや情熱は、アルバム全体を通して随所に現れ、シュガー・ベイブが提示した音楽がどれほど丁寧に作られたかを物語っている。
砂糖でできた巨塔
「すてきなメロディー」はアルバムの中で再びトーンを変え、より陽気でアップビートな雰囲気を提供する楽曲である。短い曲ながらも多くの魅力を詰め込み、大貫妙子と山下達郎のデュエットが特徴的だ。エコーがかったボーカルは、当時の大瀧詠一のスタジオが狭く、マイクが1本しかなかったためであるが、このスタイルは曲調と驚くほど調和している。楽器面では、アルバム内でも特にダイナミックな構成を持ち、トーンの移り変わりや細やかなディテールが楽曲を新鮮に保っている。特にブリッジ後にピアノ、ギター、ボーカル合唱のソロを経て登場するトランペットの使用が印象的で、全体として控えめでありながらも多彩な要素を駆使している。このアルバム全体を代表する曲を1曲挙げるとすれば、この短くも陽気で心地よいメロディーがその候補となるだろう。
続く「今日はなんだか」は、フィル・スペクターを彷彿とさせる柔らかく軽快な楽曲である。再び山下がボーカルの主役を務め、曲中で異なるムードを対比させる構成が特徴的だ。シンプルなリズムを重ねたフォーミュラに基づきつつ、エネルギッシュなキーボードとワーミー効果を活用したギターが楽曲に層を加えている。さらに、終盤に登場するトランペットのソロが楽曲のクライマックスを形成し、弦楽アレンジを取り入れた甘美で力強い一曲となっている。
その後、「過ぎ去りし日々」はピアノ主導の楽曲で、再び山下がボーカルの中心に立つ。アコースティックギター、明確なベースライン、そして控えめなパーカッションが雰囲気を作り出し、60年代を彷彿とさせる懐かしいトーンを持つ。伊藤銀次が作詞を手掛けたこの曲は、反省的で感傷的な楽曲であり、その甘美で落ち着いた音が耳に心地よく響く。
アルバムのクライマックスとなるのは、ほぼインストゥルメンタルの「Sugar」である。アルバム中で最も長いこの曲は、それまでの全てのメンバーと要素が集結した音楽的饗宴であり、バンドが1年以上にわたって築いてきたものの集大成とも言える。この曲はライブの大団円として構想されており、その理由がよく理解できる。バンドの影響や彼らの音楽への愛を体現する一大パーティートラックであり、簡素なリズムを基盤としながらも構造が時折変化し、新鮮さと動きを持続している。全メンバーのボーカルの掛け合い、背景で聞こえるランダムなノイズ、ナンシー・シナトラにインスパイアされた山下の陽気なヴァース、ラテン風のリフを基盤とするギターの相互作用、明確なベースライン、シンプルなドラムとパーカッション、大貫のリズム感あふれるピアノ、そして大瀧の優れたプロダクションが、この楽曲をタイムレスな魅力を持つ独自の体験へと昇華している。
シュガー・ベイブは多くのものを象徴していたが、その本質はメンバー全員の情熱が音楽として具現化された点にある。このアルバムは、二人の主要メンバーが築き上げることになる長く輝かしいキャリアの出発点であるだけでなく、当時の日本の音楽シーンにおいて「シティ・ポップ」の誕生を告げる作品でもあった。シュガー・ベイブが提示した音楽スタイル、作曲へのアプローチ、そして主要テーマは、後年にグループのメンバーや彼らから影響を受けた他のアーティストによってさらに発展し、拡大されていくことになる。大瀧詠一のプロダクションスタイルは、当時の日本の音楽とは一線を画し、洗練されつつもガレージ感のある独自の音を作り出している。それは演奏の情熱と心を失わずに、すべての要素が整然と調和したクリアなバランスを求めたものである。本作は、楽曲構成や演奏、音楽的アレンジの可能性を示すメンバーの潜在能力を存分に引き出した作品であり、そのすべての瞬間が美しく最大限に活用されている。
シュガー・シュガー・ソングス
人々はシュガー・ベイブを、山下達郎、大貫妙子、大瀧詠一の三人だけで構成されたものと捉えがちである。しかし実際には、ライブでもスタジオでも等しく音楽への愛情を注いだ才能あるアーティストたちによって成り立つ、正真正銘のバンドであった。この歴史的な存在が関わったアーティストたちにとって何を意味したのかを考えるだけで、彼らがその後どれほど大きな影響力を持つ存在となったかが明らかである。シュガー・ベイブは創作上の対立で解散したわけではない。むしろ、それは全メンバーの音楽的野心にとって自然な次のステップだったのである。
『SONGS』のリリース後、バンドは1976年までに数回メンバーを変更し、最後のコンサートでは山下の「Windy Lady」や大貫の「Wander Lust」といった、各メンバーのソロプロジェクトに含まれる楽曲のライブ演奏も行った。山下は自身で音楽を編曲することに愛着を見出し、最終的にはソロキャリアを追求しながら、大貫のアルバムを含む他のプロジェクトにもゲストアーティストとして参加した。また、大瀧詠一や伊藤銀次との「ナイアガラ・トライアングル」でのコラボレーションも果たした。大貫妙子もソロキャリアを開始し、1976年に『Grey Skies』をリリースし、同年には『Sunshower』の楽曲制作にも着手している。村松邦男はソロデビューまでに時間がかかったものの、大瀧詠一やナイアガラ・トライアングル、EPOなどのアルバムにゲストミュージシャンとして参加した。野口明彦も、竹内まりやや加藤登紀子、鈴木幸子などのプロジェクトにゲストミュージシャンとして貢献した。彼ら全員が、当時のアイコニックなポッププロジェクトに関与し、多くのアーティストが『SONGS』の存在を知り、それを自らの創作のインスピレーションとしていったのである。全ては、メンバーの音楽への愛情を伝えようとしたこのシンプルなプロジェクトから始まった。
アルバム『SONGS』が時代を超えた存在である理由は、その音楽とプレゼンテーションのスタイルにある。バンドが親しんできた要素を巧みに活用し、それらを新しい要素で拡張し、練り上げることで、新鮮で心のこもった、生命力に満ちた作品を創り上げた。アルバム全体が喜びと活力に溢れており、その細やかに作り込まれた楽曲構成は聴く者を引き込み、何度でもその楽曲に恋をさせる。シュガー・ベイブが音楽シーンにもたらした影響がなければ、シティ・ポップや日本のポップ全体が今日のような形にはなっていなかったかもしれない。それは日本から生まれた最良のポップアルバムのひとつであり(あえて言えば、ポップ音楽全般においても最良のひとつだろう)、シティ・ポップというラベルにとどまらず、もっと広い評価を受けるに値する作品である。
当時としては多くの点で先進的であり、音楽においてより広く見られるべき姿勢を体現している。それゆえ、バンドが解散して数十年経った今でも、関わったアーティストたちはこのアルバムを特別なものとして心に抱き続けている。山下達郎が「My Sugar Babe」といった楽曲を発表し、キャリアの原点であるバンドを記念するコンサートを開催し続けていることがその証拠である。この作品は、甘く、魅力的で、記憶に残る、非常に楽しい体験である。
人生に少しの「甘さ」を加える情熱的で素晴らしい楽曲のコレクション。ただただ美しいこのアルバムを是非ご賞味あれ。
