
第13回の3:1978年、海外のパンクに影響された東京シーンの「知覚変動」を地引雄一さんは撮った
高木完『ロックとロールのあいだには、、、』
Text : Kan Takagi / Illustration : UJT
ビームスが発行する文芸カルチャー誌 IN THE CITY で好評だった連載が復活。ストリートから「輸入文化としてのロックンロール」を検証するロングエッセイ
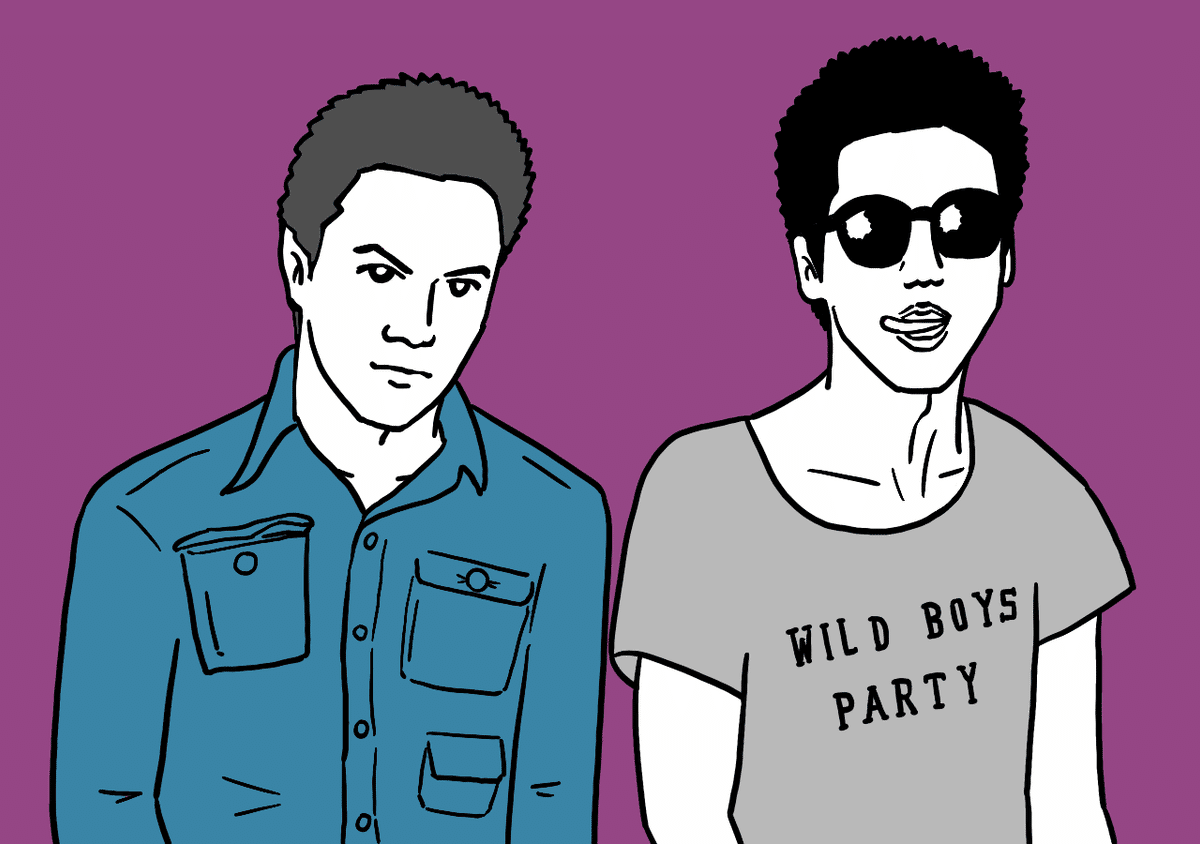
パンク・ロックの余波から日本でオリジナルなサムシング・ニューが始まるのは、1978年ということでほぼ間違いない。
と、思う。ちなみにYMOが録音を開始するのもその年の夏だ。
話をその1年前に戻す。
前回、パンク・ロックが輸入された1977年の時点では「地引さんはまだ模索していた」と書いた。
かく言う自分もそうだった。
思い起こす。
ロンドンから届いたそれは、マルコム・マクラーレンのステイトメントも理解しないまま、ビジュアルが先行した。多くの人が状況主義者と訳していたシチュエイショニストからの影響、意味深なセックス・ピストルズというネーミング&ビザールなSM成分と交配したコスチューム、EP、ポスター 、それらがセットで『anan』『花椿』『装苑』といった雑誌にも取り上げられ、ピストルズは大貫憲章さんの紹介によって、ラジオ、テレビで、目に耳に、することはできた。
一方ロンドンにも影響を与えたニューヨークに関しては、シーンの先輩格に当たるニューヨーク・ドールズが1975年に来日したこともあり、雑誌『ミュージック・ライフ』では早くからパンク・ロックという言葉自体は取り上げられていた。その後、水上はる子さんがNYの新しい動きを同誌で積極的に紹介し、後にS-KENとなる田中唯士さんも同時期に他の雑誌の派遣記者としてNYのシーンを紹介。その流れもあって? パティ・スミス、ラモーンズ、テレヴィジョンは、いずれもいちはやく日本盤がリリースされた。NYが先行していた頃は、ロンドンと違って音もスタイルもそれぞれだったこともあって、パンクという言葉はジャンルではなく、メインのロック・ビジネスとは一線を画す、秘密の暗号のように思えた。
そんな最中、3分の3のレックさんとヒゲさんは、NYに渡る。
知覚変動の始まり。
レック&ヒゲがNYでジェームス・チャンス、リディア・ランチ、アート・リンゼイと出会っていた頃、東京ではロキシー・ミュージック、デヴィッド・ボウイのカバーから始まって、ロンドン・パンクのコピーをやっていたプラスチックスは、影響は受けつつもテーマはCOPYでツイスト&シャウトしていたのだが、77年末にLAでDEVOを見てショックを受けた同バンドの立花ハジメさんの指示により、歌詞世界はそのままにバンドにリズム・ボックスを取り入れたことによって、東京オリジナルなキッチュとなる。
その変容を近くで見ていたミュージシャンの近田春夫さんは、長い髪を切り、日本で最初にピストルズを写真に収めた歌謡曲マニアの写真家・小暮徹さんからヒントを得て、歌謡曲をパンクにすることを発明する。シド・ヴィシャスが「マイ・ウェイ」を録音する前の話だ。
同時期、髪を切りストレイトなパンクに移行し始めていた紅蜥蜴は、キーボードをメンバーに加えることによって、モモヨさんが作る怒りのロックンロールに新しいスタイルを取り入れることになった。
高円寺周辺でも長髪だったバンドマンの何人かが髪を切り、ミラーズ、ミスター・カイトといったバンドが産まれた。
1978年、セックス・ピストルズ解散。トレンドとしてのパンクが終わったとされた時、ようやく日本ではそのうねりが波となる。
原宿に初めてのパンク・ブティックSMASHがオープンし、8 1/2や、ボルシーといったバンドが集まり始める。
NYに1年滞在したレック&ヒゲも帰国して新しいバンドを結成する。
1978年4月。
S-KENスタジオが始まる一ヶ月前。北区公会堂での『ロッキン・ドール』主催のライブで、地引さんはレック&ヒゲのニューバンド、フリクションを見る。
「北区公会堂で見たフリクションは衝撃だった。出てきただけで空気感が変わっちゃった。ただ、最初は理解出来なかった、音楽として。2回、3回と続けて見て、やっと理解できた。それまでの日本的な情緒とかない感じなんだけれど、決して無機的なものではなく。逆に人間が持っている未知なるエネルギーを、一番ストレイトに出しているって感じた」
僕がS-KENスタジオでその翌月5月28日に見たフリクションは、地引さん同様、その日見ていない人に「どんなバンド?」と聞かれても形容出来ないバンド・サウンドだった。
スタジオで体育座りして待っていた客側の僕らに向かってベーシストが「そろそろ立っていいんだぜ」と、マイクで呟く。みんな立つ。音が鳴る。音が飛ぶ。ドラマーのこっちを見る目つきが印象的だ。目が離せない。
時は経ち2023年6月5日。井出靖さん主催・総指揮のグループTHE MILLION IMAGE ORCHESTRAのライブが下北沢で行われた。総勢25名のミュージシャン、DJ 、ダンサーが参加するその中で僕はフリクションのベース、レックさんと久々にセッションした。
今も変わることなくクレイジー・ドリームを放ち続けるレックが作り出すリズムに乗る楽しさ。共に音を出す時、レックは波を作る。上手くメイク出来ればOK。タイムレスで古びないビートに乗って声を発し音を出すことは最高の波に乗って楽しむサーファーと同じなのだ。
そしてそれは写真を撮る側も同様。
当初、写真をどうやって撮ったら良いか、地引さんは分からなかったと言う。
「東京ロッカーズの周りにはカメラマンが多くて、そんな中でどうやったら上手く撮れるか最初わからなかった。自分では1978年の暮れの下北沢でのライブで、初めて撮れた、と、思った」
写真からは当時のエネルギーが伝わってくる。
「東京にパンク・シーンを作りたい、という思いと同時に、何か新しいエネルギーが渦巻いてるような状況を撮りたい、と思ってたんです」
地引さんが写真に残してくれたおかげで、TOKYOの一部で生まれていた現象は、今も褪せることないイメージを残している。
そしてパンク・ロックの余波が放つエネルギーは、ミュージシャンだけでなく、新しい表現を模索していた者を突き動かす何かがあった、ということも確かだとあらためて思った。

(つづく)

たかぎ・かん。ミュージシャン、DJ、プロデューサー、ライター。
70年代末よりFLESH、東京ブラボーなどで活躍。
80年代には藤原ヒロシとタイニー・パンクス結成、日本初のクラブ・ミュージック・レーベル&プロダクション「MAJOR FORCE」を設立。
90年代には5枚のソロ・アルバムをリリース。
2020年より『TOKYO M.A.A.D. SPIN』(J-WAVE)で火曜深夜のナビゲイターを担当している。
