
【宿題帳(自習用)】情報の力を獲得するために心と情報との付き合い方を再考してみる(その2)
【関連記事①】
前の記事は↓を参照。
【宿題帳(自習用)】情報の力を獲得するために心と情報との付き合い方を再考する(その1)
例えば、認知活動により、意識にのぼる情報のパターンが、言語の意味作用や、他の情報との出会いにより、ダイナミックに変化する遷移のプロセスが心の正体という定義も可能となります。
また、心は、オートポイエーシスの性質を持つとも言われています。
【参考記事①】
以上の点を踏まえた上で、私たちは、情報という概念を実生活やビジネスに拡張しなければなりません。
ところが、これが意外と非常に難しい(^^;
一般に、私たちは、日常用語として使っている言葉ほど、その定義をあいまいにしています。
前述の通り、情報もそのひとつです。
しかし、学問的には、情報の定義付けの試みは、結構、数多く行われています。
その先駆的な仕事としてよく取り上げられるのが、1948年のシャノンとウィナーの「情報理論」です。
「情報理論」(ちくま学芸文庫)甘利俊一(著)
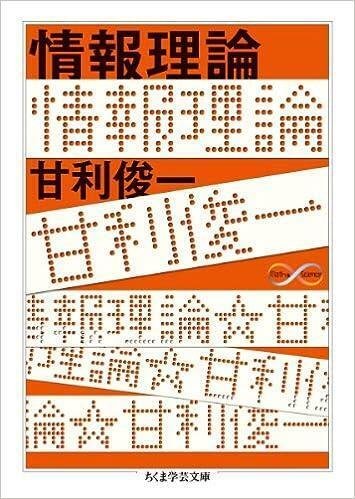
このうちウィナーは、情報について「われわれが外界に適応しようと行動し、また、その調節行動の結果を外界から感知する際に、われわれが外界と交換するものの内容である」とし、
「ウィーナー サイバネティックス――動物と機械における制御と通信」(岩波文庫)ノーバート・ウィーナー(著)池原止戈夫/彌永昌吉(訳)

また、シャノンは、「不確かなものを削減する」意味の関連で定義付けています。
「通信の数学的理論」(ちくま学芸文庫)クロード・E. シャノン/ワレン ウィーバー(著)植松友彦(訳)

また、文化人類学者ベイトソンの主著「精神の生態学」にあるコージブスキー記念講演で話した「形式、実体、そして差異(※6)」は、有名なフレーズ「情報とは、違いを作り出す違いのことである」の初出も含まれていて、この定義もよく引用されます。
「精神の生態学へ (上)」(岩波文庫)グレゴリー・ベイトソン(著)佐藤良明(訳)
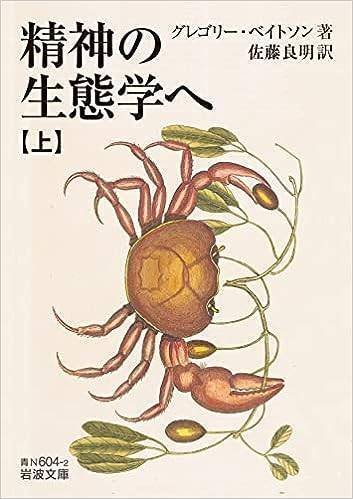
「精神の生態学へ (中)」(岩波文庫)グレゴリー・ベイトソン(著)佐藤良明(訳)
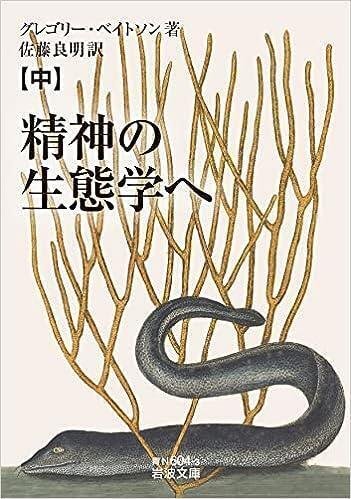
「精神の生態学へ (下)」(岩波文庫)グレゴリー・ベイトソン(著)佐藤良明(訳)
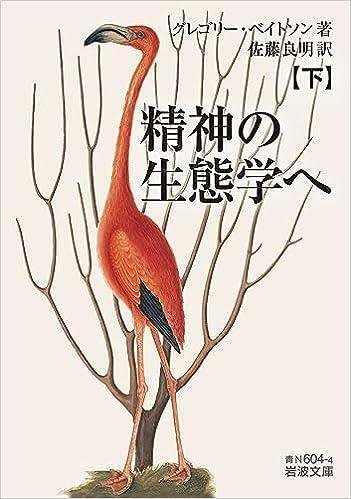
※6:
コージブスキーの「地図と領地はべつものである」というとき、地図の上に載っているのは何か?
それは領地のうち、周りと異なっている部分、そこが差異です。
例えば、高度の違い、植生の違い等の差異が地図上に線として書き込まれます。
では、差異とはなんだろう?
それは、モノではありません。
木と紙との違いは、木や紙の中にはなくて、木と紙の間に存在している空間にもありません。
差異とは、抽象的なコト(matter)です。
ハード・サイエンスの世界において、力等の具体的な原因によって結果が引き起こされます。
しかし、コミュニケーションの世界では、差異によって結果が引き起こされます。
ゆえに、知らせが無いことも原因となりえます。
カントの物自体の議論と関連付けた上で、観念とは、もっとも基本的な意味において、差異と同義ではないかと推測されます。
極端な例を上げると、コップと太陽との間、コップを構成する分子の位置、こういったところに無限の差異が存在しています。
私たちは、その差異のひとつひとつを認識することは不可能であり、これらの無限の差異の中から限られたものを選択し、それが情報として、ひとまず認識しているにすぎません。
つまり、情報(より正確には、情報の基本的な単位)とは、ある一つの差異を生み出すような一つの差異のことです。
私たちの身体は、この差異を運ぶための神経回路を、エネルギーを用いて、いつでも伝達可能な状態になっています。
このようにして身体の内部では、差異による信号の伝達があり、身体の外では、紙からの光が原因となって網膜へと入って行き(視覚)、脳に伝達され知覚されることで脳内で認知(アイデア・認識・価値判断等)されることになります。
「地図と領地はべつものである」というのは、このような神経回路での変換によって、地図が際限なくつづくものが精神の世界なのだということです。
ここで注目したいのは、情報という概念が、コンピュータサイエンスではなく、われわれ人間の認知・行為・思考とのかかわりで定義付けられているということです。
コンピュータの範囲内で情報を考えると、それは処理を司る、もしくは、処理の対象であるコードでしかないのですが、これらの定義によって、私たちは、本来の情報がわれわれの日々の営みと共にあるのだということに今更ながら気付くことができます。
確かに、人間は、秩序の中にいると、不安を覚えることはありません。
ワーマンが指摘していた不安とは、単に、情報の量の増大・爆発だけで語れるものではなくて、秩序というものが脆弱になってきて、私たちの暮らしている生活の枠の外が、何となく透けて見えるようになることが不安の源泉となっている点です。
「それは「情報」ではない。―無情報爆発時代を生き抜くためのコミュニケーション・デザイン」リチャード・S・ワーマン(著)金井哲夫(訳)

本書表紙に書かれた説明を引用すると、以下の通りです。
「(この情報時代は)まさに無情報爆発、つまりデータ爆発の時代となっている。
増え続けるデータの猛攻撃から身を守るためには、今すぐ、情報とデータは別物だということを、はっきりと認識しておくことが大切だ。
情報とは、理解に結びつく形になったものを指す言葉だ。
情報の意味を明確にするには、私たちひとりひとりが独自のものさしを持つことがぜひ必要だ。
ある人には情報であっても、別の人には単なるデータに過ぎないかもしれないからだ。
意味のわからないものは、情報とは認められない。」
確かに、「情報」か「情報でないもの」の区別が難しく直ぐに判断できない場合、自分たちに見えないものがあるという不安にかられます。
それらが、自分の思い通りにならないかもしれないという恐れ。
それに起因した苦しみ。
物事は、常に変化し、その自然な流れを思うようにコントロールしたり、逆らうことはできません。
これは、私たちにはどうすることもできず、ただ変化の中に身を任せるしかない。
しかしながら、情報は、あくまでも主観的に解釈されるもの、つまり受け手次第です。
これらの不安に依る苦しみ等は、幽霊や妖怪の話、心の病等へと、つながる話でもありますが、情報を意味する英語の「information」という語は、「in + form」の名詞形で、(人の頭の) 中に形づくられるものというニュアンスが含まれています。
【参考記事②】
従って、自ら見聞きしたり伝えられたりして知覚したときに、何らかの意味がその人の中で想起され、思考や行動に影響を与え得るものが情報であると推定できます。
この考え方について、参考になるフレームワークのひとつにDIKWというモデルがあります。
【参考記事③】
Data (データ) → Information (情報) → Knowledge (知識) → Wisdom (知恵)
データ(各種の事象)を組み合わせたり編集したりして、価値のあるものとして形作られたものが情報になります。
私たちは、情報に触れて考えたり、行動したりすることで、知識を得ることができ、ひいては、それが私たちの知恵になってゆく、というものです。
知識と知恵の段階を理解と捉えてみると。
つまりは、私たちが不安に感じる混沌とした事象と、私たちの理解を橋渡しするのが情報である、と言えるのではないでしょうか。
そのため、私たちの心を安定化させるために求められている情報設計とは、以下の様に、
①混沌として複雑な事象(データやファクト)をあるがままに受け入れる。
②それに対して私たちの目的やコンテキストに合わせて取捨選択や編集を加える。
③見つけやすく理解しやすい自身のコンテンツとして組み上げてゆくこと。
④ひいては私たちにとって価値ある情報となるよう着実にコミュニケートすること。
情報を見つけやすく、理解しやすくする設計技術である情報アーキテクチャ(Information Architecture:IA)の考え方を活用して、 個人々の心の中における情報設計を再構築していく、求められているのは、そうこうことではないだろうかと考えられます。
もちろん、量の拡大が既存の秩序を壊していく側面もあります。
洪水をイメージしてみると分かると思うのですが、大量の雨水や土石流は、建物や街の弱いところから襲ってきます。
こうした被害を未然に防ぐことが情報をデザインすることの役割でもあります。
与えられた情報を深く考えることで、物事の流れに逆らわない自然な姿勢を大切にすることは、楽に生きぬく方法の一つだと改めて学ぶことが可能です。
そのためには、全部知ろうとしないこと、及び捨てることから始めるのだ、とワーマンは述べています。
情報不安症は、自分が理解していることと、自分が理解しなければいけないと思い込んでいることとのギャップが、どんどん広がっていくことから引き起こされます。
また、私たちは、情報へのアクセスが他人にコントロールされていることを知ったときにも、情報不安症に陥ります。
そのため、逆に考えてみることが必要であり、インターネットによって、ようやく情報は、既存の価値付けから自由になったのだから、自分自身の価値付けができるように、積極的に情報を人や本やネットから取りに行こうといった行動も大切だと考えられます。
つまり、情報をデザインするとは、私たち人間の認識プロセス、会話、さまざまな行為、そして思考を描き出すことにほかならないと考えられます。
現在のデジタル社会を論じるにあたり、適切な情報の定義を様々な角度から検討する必要がありますが、情報から心を見る場合、端的に言うと、
①情報とは生命にとって意味のある恣意的な情報=<生命情報>
②<生命情報>は規範化権力により<社会情報>に
③<機械情報>は<社会情報>の安定の上に成り立つ
ということになります。
【関連記事②】
以下に↓つづく。
【参考図書】
「基礎情報学―生命から社会へ」西垣通(著)

「続 基礎情報学―「生命的組織」のために」西垣通(著)

「新 基礎情報学―機械をこえる生命」西垣通(著)

「生命と機械をつなぐ知―基礎情報学入門」西垣通(著)

「デザインマネジメント戦略―情報消費社会を勝ち抜く」佐藤典司(著)
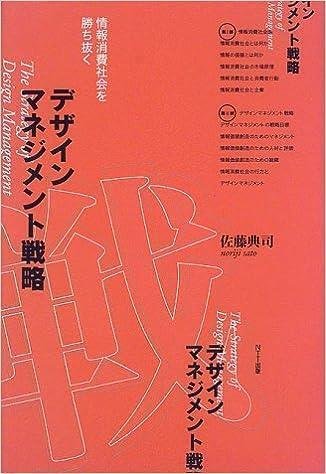
「情報デザイン入門―インターネット時代の表現術」(平凡社新書)渡辺保史(著)

「サクセス・バリュー・ワークショップ 情報構想設計 好き!から始めるコミュニケーション・デザイン」七瀬至映(著)
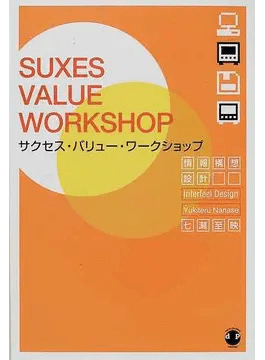
「情報編集力―ネット社会を生き抜くチカラ」藤原和博(著)

「サイバード・スペースデザイン論」渡邊朗子(著)

