
【漫筆】語幹と語感と五感
詩歩さん撮影
精選版 日本国語大辞典 「語幹」の意味・読み・例文・類語
ご‐かん【語幹】
〘名〙 語構成要素の一つ。
① 国文法では、用言の活用語尾を取り除いた変化しない部分。「読む」の「よ」、「生きる」の「い」、「長い」の「なが」など。また、「読む(yomu)」では最後の母音を除いた部分(yom)、「生きる」では「いき」をいうとする考えもある。⇔語尾。〔日本俗語文典(1901)〕
② 印欧語では、屈折系列をなす一連の語の中で、変化しない部分。
ご‐かん【語感】
〘名〙
① 語それぞれが持つ個別の感じ。
※芭蕉雑記(1923‐24)〈芥川龍之介〉六「『正す』とは〈略〉霊活に語感(ごかん)を捉へた上、俗語に魂を与へることである」
② ことばに対する微妙な感覚。
※僕の手帖(1951)〈渡辺一夫〉四「ロシヤ人と全く同じ語感を持って居られたとも思いませんから」
ご‐かん【五感】
〘名〙 目、耳、鼻、舌、皮膚の五官を通じて外界の物事を感ずる視、聴、嗅、味、触の五つの感覚。
※当世書生気質(1885‐86)〈坪内逍遙〉一九「五感(ゴカン)の鋭利に過る者を鈍くし、架空の想像をおさゆる事是なり」

「詩はすべて「さみしい」という4文字のバリエーションに過ぎない、けれど」
(木下龍也『オールアラウンドユー』より)
「オールアラウンドユー」木下龍也(著)
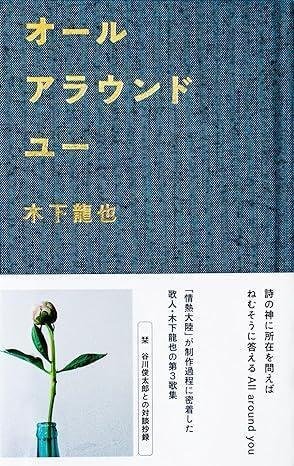
「さみしいは何とかなるがむなしいは 躑躅の低いひくい木漏れ日」
(千種創一『千夜曳獏』より)
「千夜曳獏」千種創一(著)

「淋しい人影が夢の芯になり銀河を擁いて傾いてくる」
(糸田ともよ『しろいゆりいす』より)
「しろいゆりいす」(COAL SACK 銀河短歌叢書)糸田ともよ(著)
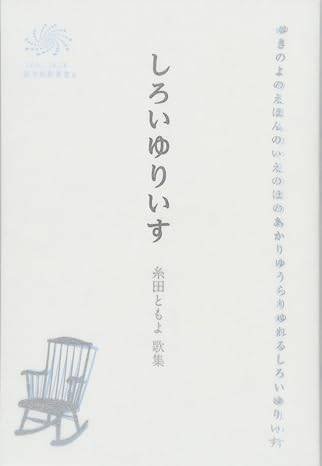
「たまり水が天へかえりてかわきたるでこぼこの野のようにさみしい」
(中野昭子『草の海』より)
「草の海 中野昭子歌集」(ポトナム叢書)中野昭子(著)
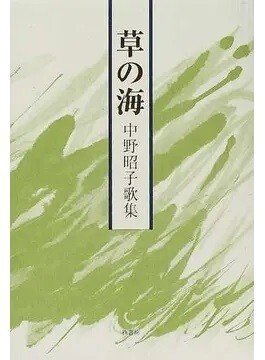
「さみしいとうつくしいって似ているね 青海と青梅を間違えず乗る」
(ショージサキ(あるきだす言葉たち)「遠くの国」朝日新聞夕刊2022年07月13日より)
韻文とは何だろうか?
遥か大昔の呪誦から始まり・・・
ギルガメッシュの英雄譚。
ホメロスの叙事詩。
古代インドの二大叙事詩「マハーバーラタ」「ラーマーヤナ」。
詩の三大部門(劇詩・叙事詩・叙情詩)。
叙景詩。
ヨーロッパ叙情詩の一形式(ソネット)。
中世のヨーロッパで作られた定型詩(バラード)。
漢詩(古詩・楽府・絶句・律・排律)。
文語定型詩(新体詩)。
口語自由詩。
和歌。
短歌。
俳句。
等々。
・
・
・
口頭伝承の領域とも密接に関わり合いながら。
それぞれの国で。
様々な言語で。
いろいろな形式で。
長い長い間。
韻文は紡がれてきた。
そこには、「さ・み・し・い」のかけら以外に、どんな「~しい」と感じた言葉が紡がれてきたのだろうか。
「~しい」と言う、言葉の持つ響き。
精選版 日本国語大辞典 「しい」の意味・読み・例文・類語
〘接尾〙 (形容詞型活用) し (形容詞シク活型活用) 名詞・動詞・畳語などに付いて、形容詞をつくる。そのような性質がある、…の様子だ、…と感じられるの意を示す。「おとなしい」「腹立たしい」「にくにくしい」など。
この「~しい」で終わる言葉は、形容詞であり、以下の様に、多様な表現が存在している。
「しい」で終わる言葉(3文字ちょうど)
あしい(悪しい)
おしい(惜しい)
ほしい(欲しい)
「しい」で終わる言葉(4文字ちょうど)
あけしい(あけしい)
あやしい(怪しい)
いとしい(愛しい)
いやしい(卑しい/賤しい)
うれしい(嬉しい)
おいしい(美味しい)
おおしい(雄雄しい/男男しい)
おぼしい(思しい/覚しい)
かなしい(悲しい/哀しい/愛しい)
きびしい(厳しい/酷しい)
くやしい(悔しい/口惜しい)
くるしい(苦しい)
くわしい(詳しい/委しい/精しい)
ぐるしい(苦しい)
けわしい(険しい/嶮しい)
こいしい(恋しい)
さかしい(賢しい)
さびしい(寂しい/淋しい)
さみしい(寂しい/淋しい)
さもしい(さもしい)
したしい(親しい)
すがしい(清しい)
すずしい(涼しい)
せわしい(忙しい)
ただしい(正しい)
たのしい(楽しい)
ちかしい(近しい/親しい)
つましい(倹しい/約しい)
とぼしい(乏しい)
ともしい(乏しい/羨しい)
はげしい(激しい/烈しい/劇しい)
ひさしい(久しい)
ひとしい(等しい/均しい/斉しい)
びびしい(美美しい)
ふかしい(深しい)
ふるしい(古しい/旧しい)
まずしい(貧しい)
まぶしい(眩しい)
まぼしい(眩しい)
まましい(継しい)
めめしい(女女しい)
やさしい(優しい)
やましい(疚しい/疾しい)
ゆかしい(床しい/懐しい)
ゆゆしい(由由しい/忌忌しい)
りりしい(凜凜しい/律律しい)
わびしい(侘しい)
「しい」で終わる言葉(5文字ちょうど)
あいらしい(愛らしい)
あさましい(浅ましい)
あたらしい(新しい)
あほらしい(阿呆らしい)
いかがしい(如何しい)
いかめしい(厳めしい)
いぐるしい(居苦しい)
いさましい(勇ましい)
いじましい(いぢましい)
いじらしい(いぢらしい)
いそがしい(忙しい)
いたましい(痛ましい/傷ましい)
いたわしい(労しい)
いとおしい(愛おしい)
いとわしい(厭わしい)
いぶかしい(訝しい)
いまわしい(忌まわしい)
いやらしい(嫌らしい/厭らしい)
うつくしい(美しい/愛しい)
うとましい(疎ましい)
うらめしい(恨めしい/怨めしい)
うるわしい(麗しい/美しい)
うれわしい(憂わしい)
おそろしい(恐ろしい)
おぞましい(鈍ましい)
おとなしい(大人しい)
おもわしい(思わしい)
おろかしい(愚かしい)
かぐわしい(芳しい/香しい/馨しい)
かしましい(囂しい/姦しい/喧しい)
かんばしい(芳しい/馨しい/香しい)
きぜわしい(気忙しい)
くちおしい(口惜しい)
くるおしい(狂おしい)
くるわしい(狂わしい)
こうばしい(香ばしい/芳ばしい)
こさびしい(小寂しい)
こざかしい(小賢しい)
こぜわしい(小忙しい)
このましい(好ましい)
このもしい(好もしい)
こまかしい(細かしい)
こわらしい(怖らしい/恐らしい)
さわがしい(騒がしい)
しおらしい(しをらしい)
したわしい(慕わしい)
すばらしい(素晴(ら)しい)
せぐるしい(せぐるしい)
そぐわしい(そぐはしい)
そそかしい(そそかしい)
たくましい(逞しい)
たのもしい(頼もしい)
つつましい(慎ましい)
てきびしい(手厳しい)
なつかしい(懐かしい)
なやましい(悩ましい)
にあわしい(似合(わ)しい)
にぎわしい(賑わしい)
にくらしい(憎らしい)
ねがわしい(願わしい)
ねぐるしい(寝苦しい)
ねたましい(妬ましい/嫉ましい)
のぞましい(望ましい)
のろわしい(呪わしい)
はずかしい(恥ずかしい/羞ずかしい)
ばからしい(馬鹿らしい)
ひとらしい(人らしい)
ふさわしい(相応しい)
ほこらしい(誇らしい)
みぐるしい(見苦しい)
めざましい(目覚ましい)
めずらしい(珍しい)
めだたしい(目立たしい)
もどかしい(もどかしい)
ものほしい(物欲しい)
やかましい(喧しい)
ややこしい(ややこしい)
よくどしい(欲どしい)
らんがしい(乱がしい)
わらべしい(童しい)
「しい」で終わる言葉(6文字ちょうど)
あいあいしい(愛愛しい)
あいくるしい(愛くるしい)
あいひとしい(相等しい)
あさあさしい(浅浅しい)
あつかましい(厚かましい)
あつくるしい(暑苦しい)
あらあらしい(荒荒しい)
あらくもしい(荒くもしい)
あわあわしい(淡淡しい)
あわただしい(慌ただしい)
いかがわしい(如何わしい)
いきぐるしい(息苦しい)
いきだわしい(息だわしい)
いしこらしい(いしこらしい)
いそいそしい(いそいそしい)
いそがわしい(忙わしい)
いたいたしい(痛痛しい)
いちじるしい(著しい)
いとしらしい(愛しらしい)
いまいましい(忌ま忌ましい)
いまめかしい(今めかしい)
いらいらしい(苛苛しい)
いらだたしい(苛立たしい)
いわきいしい(磐城石井)
ういういしい(初初しい)
うさんらしい(胡散らしい)
うすさびしい(薄寂しい)
うそさびしい(うそ寂しい)
うたがわしい(疑わしい)
うっとうしい(鬱陶しい)
うとうとしい(疎疎しい)
うやうやしい(恭しい)
うらがなしい(心悲しい)
うらさびしい(心寂しい/心淋しい)
うらやましい(羨ましい)
おいそがしい(お忙しい)
おくゆかしい(奥床しい)
おこがましい(痴がましい/烏滸がましい)
おさならしい(幼らしい)
おとこらしい(男らしい)
おなごらしい(女子らしい)
おにおにしい(鬼鬼しい)
おびただしい(夥しい)
おもおもしい(重重しい)
おもくるしい(重苦しい)
おんがましい(恩がましい)
おんならしい(女らしい)
かいがいしい(甲斐甲斐しい)
かがやかしい(輝かしい/耀かしい/赫かしい)
かしがましい(囂しい)
かたくるしい(堅苦しい)
かたくろしい(堅くろしい)
かどかどしい(角角しい)
かまびすしい(喧しい/囂しい)
かるがるしい(軽軽しい)
かろがろしい(軽軽しい)
かわいらしい(可愛らしい)
かわゆらしい(可愛らしい)
ききぐるしい(聞(き)苦しい)
きたならしい(汚らしい/穢らしい)
きづかわしい(気遣わしい)
きはずかしい(気恥ずかしい)
きもだましい(肝魂)
きらきらしい(きらきらしい)
くだくだしい(くだくだしい)
くちさびしい(口寂しい)
くちざみしい(口寂しい)
くどくどしい(くどくどしい)
けがらわしい(汚らわしい/穢らわしい)
けたたましい(けたたましい)
けばけばしい(けばけばしい)
こうごうしい(神神しい)
ことごとしい(事事しい)
こどもらしい(子供らしい)
こにくらしい(小憎らしい)
こはずかしい(小恥ずかしい)
こまごましい(細細しい)
こやかましい(小喧しい)
さえざえしい(冴え冴えしい/冱え冱えしい)
しさいらしい(子細らしい/仔細らしい)
しらじらしい(白白しい)
すいたらしい(好いたらしい)
すがすがしい(清清しい)
ずうずうしい(図図しい)
せせこましい(せせこましい)
せまくるしい(狭苦しい)
そうぞうしい(騒騒しい)
そそっかしい(そそっかしい)
そらぞらしい(空空しい)
そわそわしい(そはそは)
たけだけしい(猛猛しい)
たしからしい(確からしい)
たどたどしい(たどたどしい)
だいだいしい(大大しい)
ちくごよしい(筑後吉井)
つやつやしい(艶艶しい)
つらだましい(面魂)
とおどおしい(遠遠しい)
とげとげしい(刺刺しい)
どくどくしい(毒毒しい)
ながたらしい(長たらしい)
ながながしい(長長しい/永永しい)
なげかわしい(嘆かわしい)
なごりおしい(名残惜しい)
なさけらしい(情けらしい)
なまなましい(生生しい)
なまめかしい(艶めかしい)
なまやさしい(生優しい)
なれなれしい(馴れ馴れしい)
にがにがしい(苦苦しい)
にぎにぎしい(賑賑しい)
にくたらしい(憎たらしい)
にくてらしい(憎体らしい)
にくにくしい(憎憎しい)
につかわしい(似付かわしい)
につこらしい(似つこらしい)
のこりおしい(残り惜しい)
はかばかしい(捗捗しい/果果しい)
はじがましい(恥じがましい)
はなはだしい(甚だしい)
はなばなしい(花花しい/華華しい)
はらだたしい(腹立たしい)
はれがましい(晴れがましい)
はればれしい(晴れ晴れしい)
ばかばかしい(馬鹿馬鹿しい)
ひぜんよしい(肥前吉井)
ひとがましい(人がましい)
ひとこいしい(人恋しい)
ふくぶくしい(福福しい)
ふさぶさしい(ふさぶさしい)
ふてぶてしい(太太しい)
ふるぶるしい(古古しい/旧旧しい)
ふるめかしい(古めかしい)
ほおえましい(微笑ましい)
ほてくろしい(ほてくろしい)
ほほえましい(微笑ましい/頬笑ましい)
まあたらしい(真新しい)
まがまがしい(禍禍しい)
まぎらわしい(紛らわしい)
まざまざしい(まざまざしい)
まだるこしい(間怠こしい)
まちどおしい(待(ち)遠しい)
まどろこしい(まどろこしい)
まめまめしい(忠実忠実しい)
みすぼらしい(みすぼらしい)
みずみずしい(瑞瑞しい/水水しい)
みそぼらしい(みそぼらしい)
みみぐるしい(耳苦しい)
めあたらしい(目新しい)
めまぎらしい(目紛らしい)
めまぐるしい(目紛るしい)
ものがなしい(物悲しい)
ものこいしい(物恋しい)
ものさびしい(物寂しい/物淋しい)
ものものしい(物物しい)
ものわびしい(物侘しい)
やつやつしい(窶窶しい)
ようがましい(様がましい)
よそよそしい(余所余所しい)
よろこばしい(喜ばしい/悦ばしい)
よわよわしい(弱弱しい)
れいれいしい(麗麗しい)
わかわかしい(若若しい)
わざとらしい(態とらしい)
わずらわしい(煩わしい)
「しい」で終わる言葉(7文字ちょうど)
あぶなっかしい(危なっかしい)
いきどおろしい(憤ろしい)
いまさららしい(今更らしい)
いやみたらしい(嫌みたらしい/厭みたらしい)
うらはずかしい(心恥ずかしい)
うらみがましい(恨みがましい/怨みがましい)
うれしがなしい(嬉し悲しい)
ええかっこしい(ええかっこしい)
おりめただしい(折(り)目正しい)
かごとがましい(託言がましい)
かってがましい(勝手がましい)
きざったらしい(気障ったらしい)
きそくただしい(規則正しい)
くちやかましい(口喧しい)
けいはくらしい(軽薄らしい)
こころうれしい(心嬉しい)
こころぐるしい(心苦しい)
こころさびしい(心寂しい/心淋しい)
こころぜわしい(心忙しい)
こころやさしい(心優しい)
こころやましい(心疚しい/心疾しい)
こっぱずかしい(小っ恥ずかしい)
ことあたらしい(事新しい)
さしでがましい(差(し)出がましい)
しかつべらしい(しかつべらしい)
しかつめらしい(鹿爪らしい)
しょうらかしい(性らかしい)
じまんたらしい(自慢たらしい)
じゆうがましい(自由がましい)
すえおそろしい(末恐ろしい)
すえたのもしい(末頼もしい)
すかんたらしい(好かんたらしい)
そらおそろしい(空恐ろしい)
たいそうらしい(大層らしい)
ながったらしい(長ったらしい)
なまあたらしい(生新しい)
なみだぐましい(涙ぐましい)
にんげんらしい(人間らしい)
ねだりがましい(強請りがましい)
はなはずかしい(花恥ずかしい)
ひとなつかしい(人懐かしい)
ふんべつらしい(分別らしい)
まだるっこしい(間怠っこしい)
まどろっこしい(まどろっこしい)
みだりがましい(濫りがましい/猥りがましい)
みだりがわしい(濫りがわしい/猥りがわしい)
みみあたらしい(耳新しい)
みめうるわしい(見目麗しい/眉目麗しい)
みれんがましい(未練がましい)
みれんたらしい(未練たらしい)
もったいらしい(勿体らしい)
もっともらしい(尤もらしい)
ものあたらしい(物新しい)
ものおそろしい(物恐ろしい)
ものおもわしい(物思わしい)
ものぐるおしい(物狂おしい)
ものぐるわしい(物狂わしい)
ものさわがしい(物騒がしい)
ものめずらしい(物珍しい)
れいぎただしい(礼儀正しい)
わざとがましい(態とがましい)
以上の通り、「~しい」の言葉は、数々有れど、感覚であろう、それは、具体的には、どんなものか。
どの程度なのか、は、それを使った本人にしかわからないと思う。
確かに、表現としては明るく楽しくても、韻文や散文を書く行為というものの中に、少なからず「さ・み・し・い」があるのではないかと納得したりする。
それは、書くという行為が、私たちの現在の環境における生と密接に結びついているため、生きることからは、どうしても「哀」に近い「さ・み・し・い」といった気持ちを、拭い去れないからかもしれない。
精選版 日本国語大辞典 「哀」の意味・読み・例文・類語
あわれ あはれ【哀】
[1] 〘感動〙
① うれしいにつけ、楽しいにつけ、悲しいにつけて、心の底から自然に出てくる感動のことば。ああ。あら。やれやれ。
※古事記(712)中・歌謡「やつめさす 出雲建が 佩ける太刀 黒葛(つづら)さは巻き さ身無しに阿波礼(アハレ)」
※万葉(8C後)三・四一五「家ならば妹が手まかむ草枕旅にこやせるこの旅人怜(あはれ)」
※源氏(1001‐14頃)帚木「人知れぬ思ひ出で笑ひもせられ、あはれとも、うちひとりごたるるに」
② 下に願望、命令などの表現を伴って、願望の気持を表わす。ああなんとかして。ぜひとも。
※大観本謡曲・三井寺(1464頃)「わらはをいつも訪ひ慰むる人の候。あはれ来れ候へかし語らばやと思ひ候」
※仮名草子・都風俗鑑(1681)三「あの理発にては、あはれ至善格物の道理をしらせたや」
※読本・雨月物語(1776)吉備津の釜「あはれ良(よき)人の女子(むすめ)の㒵(かほ)よきを娶りてあはせなば、渠(かれ)が身もおのづから脩まりなんとて」
③ はやし詞として用いる。
※催馬楽(7C後‐8C)我が駒「いで我が駒 早く行きこせ 待乳山 安波礼(アハレ) 待乳山 はれ」
[2] 〘名〙 (形動) ((一)の感動詞から転じたもの) 心の底からのしみじみとした感動や感情、また、そういう感情を起こさせる状況をいう。親愛、情趣、感激、哀憐、悲哀などの詠嘆的感情を広く表わすが、近世以降は主として哀憐、悲哀の意に用いられる。
① 心に愛着を感じるさま。いとしく思うさま。また、親愛の気持。
※万葉(8C後)一八・四〇八九「めづらしく 鳴くほととぎす〈略〉聞くごとに 心つごきて うち嘆き 安波礼(アハレ)の鳥と 云はぬ時なし」
※源氏(1001‐14頃)真木柱「うちながめて、いと心細げに見送りたるさまども、いとあはれなるに、もの思ひ加はりぬる心地すれど」
② しみじみとした風情のあるさま。情趣の深いさま。嘆賞すべきさま。→もの(物)の哀(あわ)れ。
※土左(935頃)承平四年一二月二七日「かぢとりもののあはれも知らで、おのれし酒をくらひつれば」
※枕(10C終)一「からすの寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど飛び急ぐさへあはれなり」
③ しみじみと感慨深いさま。感無量のさま。
※源氏(1001‐14頃)須磨「折からの御文、いとあはれなれば、御使さへむつまじうて、二三日すゑさせ給ひて」
※徒然草(1331頃)一二五「あはれも醒めてをかしかりけり」
④ 気の毒なさま。同情すべきさま。哀憐。また、思いやりのあるさま。思いやりの心。
※源氏(1001‐14頃)桐壺「命婦は、まだ大殿籠らせ給はざりけると、あはれに見たてまつる」
※今昔(1120頃か)二「王宮を追出し事を哀れに思ひ出して」
※吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉一「憐れな声が糸の様に浮いて来る」
⑤ もの悲しいさま。さびしいさま。また、悲しい気持。悲哀。
※竹取(9C末‐10C初)「見れば、世間心細く、哀に侍る」
※新古今(1205)冬・七〇五「老いの波こえける身こそあはれなれ今年もいまは末の松山〈寂蓮〉」
⑥ はかなく無常なさま。無常のことわり。
※栄花(1028‐92頃)鳥辺野「よろづにあはれなるたびの御祈をせさせ給へば」
※謡曲・江口(1384頃)「およそ心なき草木、情ある人倫、いづれあはれを逃がるべき」
⑦ (神仏などの)貴いさま。ありがたいさま。
※枕(10C終)二〇八「霊山は釈迦仏の御住家(すみか)なるがあはれなるなり」
⑧ 殊勝なさま。感心なさま。→あっぱれ。
※源氏(1001‐14頃)橋姫「俗聖とか、この若き人々のつけたなる。あはれなることなり」
※曾我物語(南北朝頃)三「つひに敵を思ふままにうち〈略〉あはれにも、いみじきにも、申つたへたるは、此人々の事なり」
[補注]語源を「あ」と「はれ」との結合と説くものが多いが、二つの感動詞に分解しうるかどうか疑わしい。なお、「あっぱれ」は、「あはれ」が促音化して生まれた語形である。
そうであるかもしれないけれど、前述の歌の最後の「、けれど」とある様に、そうでない可能性も考えられる。
また、それは、各自が受け取るものであり、きっと、そこには、喜怒楽に関するものでもあるはず。
いや、もしかしたら、使っている本人でさえも、その時々の心境で、適切に使用しているのかは不明であり、説明できないものかもしれない。
そして、言われた側についても、自分の「~しい」の基準で聞いているのではないかと思う。
その曖昧さ故に、どんな体で使うのかで、なんとなくの空気は伝わり、想像させる。
使うときには、自分の五感を使って、届けるようなものなのだろう。
そして、受け取る側の五感も使う。
他の誰かではなく。
見たり聴いたり食べたりといった、あたりまえの事をじっくりと味わってみる。
「視覚」を満たす:
「毎日、空を眺める」
「星や月の観測を。時には天体ショーも」
「映像作品を楽しむ」
「美しい写真を眺める」

「聴覚」を満たす:
「アナログレコードをかけて暖かい音を楽しむ」
「新しい音楽に出会う旅へ」
「ラジオをつければ音楽だけでなく知識も吸収できる」

「味覚」を満たす:
「買ってきた食品を食べ比べ!」
「デリバリーのお料理を楽しむ」
「新しいお料理やおかし作りにチャレンジ」

また、自分の感覚に、正直になれる最高の機会を生かしてみる。
「触覚」を満たす:
「最高に気持ちの良い寝具に包まれてお昼寝タイムを」
「肌触りを重視したルームウエアにチェンジしてみる」

そして、意識的に、五感を満たして心に潤いを与えてみる。
「嗅覚」を満たす:
「お花をリビングに飾って良い香りに包まれる」
「ドリップしておいしいコーヒーを淹れる」
「すきな香りの入浴剤でバスタイムを満喫する」

“今、自分は生きている”という実感を大切に、自分の人生を生きることを意識してみる。
そこから、開かれ始めたものもある様に感じる。
例えば、苦みの中にも、新しい何かが存在しており、未来へと繋がっていく予感も感じられるのではないか。

「日本語はなぜ美しいのか」黒川伊保子(著)(集英社新書)
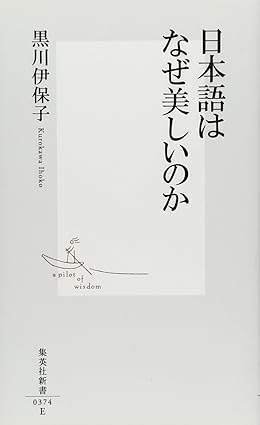
これまでにも日本語論は、広範な分野から多様な切り口で展開されてきた。
本書のユニークさは、脳機能論の立場から、語感の正体が「ことばの発音の身体感覚」であることを発見し、そこから語感と風土と意識の関連性に着目した点にある。
著者が訴えるのは、「母語」と「母国語」の重要性。
前者は、「ある個体の脳が、人生の最初に獲得する言語」で、3歳までの母語形成期が一生の脳の基盤になると説く。
それは密着時間ではなく、母親(保育者)が柔和な気持ちで、情感豊かな会話を交わす質の問題だという。
後者は「その国の風土と人々の意識とによって、長く培われたことば」。
日本語は、文字のない時代から神話の時代、言霊の時代を経て、「発音体感と意識と所作、情景がほぼ完全に一致した言語」であると説く。
この「母語」と「母国語」によって育まれた感性こそが、想像力や創造力を発揮する。
例えば、「美味しい」と聞けば、どんな形なのか、どんな味なのか、食感なのか、風味なのか、後味は?とか。
経験したものから、未体験のものまで、色々と想像する。
但し、使うときも、受け取るときも、注意が必要であり、“ちゃんと”届けたいのか、何となく口をついたのか。
届けたければ、語幹である「美味」、どんな語感「らしい」であるのか五感を使わなければ届けられないし、受け取るときも、自分の日頃の感覚と言う名の筋力がモノを言う。
この掴みどころのなさ。
使う人の裏側まで透けてしまうような言葉(ここでは形容詞)たち。
だからこそ、そこに使う人の、その人らしさを感じるときに、私の琴線に響くのだろうと思う。
それは、他人の言葉を借りた、「美しい」には、ちっとも心が囚われないから。
さて、世界的にみると、話者の音声を母音で聴く人類と、子音で聴く人類とがあり、後者は、世界経済を牽引している欧米各国やアジアなど圧倒的に多い。
日本語は、母音を主体に音声認識をする稀有な言語(ほかにはポリネシア語族のみ)で、自然音(虫の音や木々のそよぎ)もまた、言語脳(左脳)で聴き取っている。
人々が、その風土で培われなかった言語を使うようになるとどうなるか。
風土と言語の乖離は、風土と人々の意識の在りようの乖離を招く。
例えば、自然と融和して生きてきた日本人が、やがて自然と対峙するようになる。
環境が言語を作り、言語は人を作る。
言語の採択がいかに人の意識を変えていくか。
著者は、ソクラテスの言葉、「ことばの象と実体の事象とが合致する言語こそ美しい」を引用しながら、その合致の乖離に警鐘を鳴らしている。
美しい日本語を守り育てるために傾聴に値する日本語論であろう。
