
【「嗜む」のすすめ】八入の雨に焦がれ本を嗜む
【「嗜む」のすすめ】八入の雨に焦がれ本を嗜む

私達が密かに大切にしているものたち。
確かにあるのに。
指差すことができない。
それらは、目に見えるものばかりではなくて。
それらを、ひとつずつ読み解き。
それらを、丁寧に表わしていく。
そうして出来た言葉の集積を嗜む。
・
・
・
布を染めるとき、染料に、一度だけ浸すことを、一入といいます。
「ひときわ」「いっそう」といった意味の、この「一入」は、布を染めるとき、染料に一回浸すことです。
そして、幾度も浸すことを、八入というそうです。
また、八入の八は、多いを表し、入は、染料に浸すことを、意味するのだそうです。
さて、時は遡って平安時代、深みある真っ赤な紅花色は、貴族たちの憧れの色だったそうです。
【参考記事】
【参考資料】
その憧れは、万葉集の巻:第19巻、歌番号:4156番歌、作者:大伴家持に、
原文:
「荒玉能 年徃更 春去者 花耳尓保布 安之比奇能 山下響 墜多藝知 流辟田乃 河瀬尓 年魚兒狭走 嶋津鳥 鵜養等母奈倍 可我理左之 奈頭佐比由氣<婆> 吾妹子我 可多見我C良等 紅之 八塩尓染而 於己勢多流 服之襴毛 等寳利C濃礼奴」
訓読:
「あらたまの 年行きかはり 春されば 花のみにほふ あしひきの 山下響み 落ち激ち 流る辟田の 川の瀬に 鮎子さ走る 島つ鳥 鵜養伴なへ 篝さし なづさひ行けば 我妹子が 形見がてらと 紅の 八しほに染めて おこせたる 衣の裾も 通りて濡れぬ」
現代語訳:
「あらたまの年が改まって春になると、花が一面に美しいあしひきの山の、その下に音を響かせて落ち激ち流れる辟田川の瀬には、年魚の子が走りまわる。そこで島つ鳥鵜飼の者をつれ、篝火を燃やしつつ流れを歩いてゆくと、わが妻が形見にもとて、紅色に濃く染めて送ってくれた衣も、裾が濡れとおることだ。」
とあり、
「紅の八入に染めておこせたる衣の裾も通りて濡れぬ」大伴家持
と歌われるほどです。
地域などにより、先の話になりますが、霜降は、
霜降(そうこう) 二十四節気 10月24日〜11月7日頃
山々や公園などで美しい紅葉を楽しめる時季でもあります。
それまでに、何度も、八入の雨が降って染められたのでしょうねぇ。
一雨ごとに、樹々たちを色濃く染め上げる秋の雨を、古の人たちは八入の雨と呼びました。
炎天下で、生命の滾りを見せつけていた樹々たち。
風がいっそう冷たく感じられ、地域によっては霜が降りる頃である霜降で、静かに色を落としはじめるのではなくて、色雨に染め上げられているのだと思うと、また、紅葉の見方も変わってきます。
深まりゆく秋。
落ち着きのある芳醇な色香漂う大人の季節。
鮮やかで艶めく美しい秋が訪れますように・・・

の前に、風情漂う、深まりゆく春の情景を、色々と思い浮かべてみる。
「猫の恋」
「蛙(かわず)の目借り時」
「亀鳴く」
「鷹(たか)化して鳩(はと)と為(な)る」
夏は「山滴る」
秋は「山粧(よそお)ふ」
冬は「山眠る」
そして、春は「山笑ふ」
源氏物語の第五段だと、春深まりゆく寂しさになったり。
それは、本も同じだなあ~と感じられます(^^♪
「取材・執筆・推敲 書く人の教科書」古賀史健(著)

本書の著者である古賀史健さんは、
「いい文章を書く人は、たとえ多読家でなくとも日常的な読書習慣を持っています。
一冊の本を読むように、人を読み、世界を読む。
日常のすべてに対して、取材者の姿勢で対峙する。
日頃から観察眼を鍛えているわけです。」
と話しており、トップクリエイターはなぜ、同じ本を何度も読むのか?に関して、以下の様に語っておられました。
「こうした観察眼のベースをつくってくれるのは、やはり読書です。
本は、いくらでも立ち止まって考えることができるメディアであり、時間配分の主導権を持つのは、読者の方です。
どんな場所で、どのようなペースでどう読もうと、すべては、読者の自由であり、そんな自由さを持つ本というメディアを入口にして、ただ読むだけではなく、受動的な読書から能動的な読み方に変えて、著者に対して、独占インタビューするつもりで、こちらから問いかけるようにして読んでいけば、違った気づきが本から得られたりします。
読むときに、こころにとめておくことばは同じです。
「この人に会ったら、なにを聞こう?」
あなたはなぜ、この本を書こうと思ったのか。
冒頭の一文はなにを意味しているのか。
どうしてこの表現を使ったのか。
そんなふうに、読み終えたら「独占インタビュー」が待っているつもりで、たくさんの質問を考えながら読んでいきましょう。」
確かに、再読の本質は、一冊の同じ本に対して、様々な読み方をすることであり、一度目の読みは、どこに何が書いてあるか確かめる程度の下見的な読みだとも言えるかもしれません。
ここに至りて、ようやく、読むことで自分を変えていく作業が始まっていく。
八入の雨が降って、樹々たちを色濃く染め上げる様に。
作者と対話しながら、再読を繰り返す毎に。
自分が変わっていき。
同じ書物が違ったものとして現れるような。
そんな本格的な読書が始まるのでしょうね(^^)
対話だからこそ本は、100人いれば、100通りの読み方が生まれる。
質問を考えながら読む。
それは、自分だけの「読み」をおこなう手立てなのでしょう。
・
・
・
今日は、どれを読もうかなんて。
好きなことに没入し。
自分と向き合う時間に浸る「ヒタ活」(^^)
今宵、嗜む本のお品書きは・・・
【「嗜む」のすすめ】八入の雨に焦がれ本を嗜む
「E5けいはやぶさ しんかんせん」(のびのびずかん)マシマレイルウェイピクチャーズ(著)ヨシムラ ヨシユキ(イラスト)

「Elements-あちら、こちら、かけら」野又穫(著)

「N700けいのぞみ しんかんせん」(のびのびずかん)マシマレイルウェイピクチャーズ(著)ヨシムラ ヨシユキ(イラスト)

「アラビアン・ナイトと日本人」杉田英明(著)

「アルケオメトリア 考古遺物と美術工芸品を科学の眼で透かし見る」吉田邦夫(編)

「トットリッチ 詩集」(詩と思想新人賞叢書 6)岡田ユアン(著)

「ほしのはなし」北野武(著)

「みて、ほんだよ!」リビー グリーソン(著)フレヤ ブラックウッド(イラスト)谷川俊太郎(訳)

「われた魯山人」前田義子(著)

「一刀の無限 木田安彦木版画集成」木田安彦(著)

「怪談牡丹燈籠 塩原多助一代記 鏡ケ池操松影」(円朝全集 第一巻)倉田喜弘/清水康行/十川信介/延広真治(編)

「寄り添う 銀座「クラブ麻衣子」四十年の証」雨宮由未子(著)

「具体 ニッポンの前衛18年の軌跡 国立新美術館 カタログ 図録 GUTAI」

「時の冒険 デザインの想像力」松田行正(著)
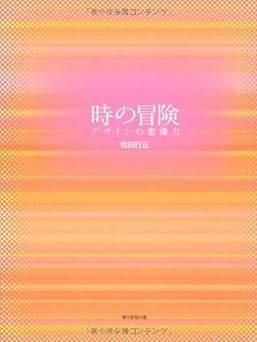
「小林且典作品集 ひそやかな眼差し」小林且典(著, 写真)

「哲学大図鑑 THE PHILOSOPHY BOOK」ウィル・バッキンガム(著)小須田健(訳)

「猫のあいさつ」(猫のパラパラブックス)浅生ハルミン(著)

「猫のおかえり」(猫のパラパラブックス)浅生ハルミン(著)

「猫のきまぐれ」(猫のパラパラブックス)浅生ハルミン(著)

「猫のたんじょうび」(猫のパラパラブックス)浅生ハルミン(著)

「猫のプロポーズ」(猫のパラパラブックス)浅生ハルミン(著)

「猫のランデブー」(猫のパラパラブックス)浅生ハルミン(著)

「秘密基地の作り方」尾方孝弘(著)のりたけ(イラスト)

「浮遊的前衛」西野嘉章(著)

「編む」(生命誌 年刊号 Vol.65-68)中村桂子(著)

「予算内でこんなにすてき! 小型グラフィック・コレクション」グラフィック社編集部(編)

【関連記事】
【「嗜む」のすすめ】畔青む季節に焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/ndbfc70606ac1
【「嗜む」のすすめ】晴耕雨読に焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/n27cc1c914476
【「嗜む」のすすめ】幻秘色に焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/n9df9c2f9b4a0
【「嗜む」のすすめ】月に叢雲華に風焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/nbc10b0331d94
【「嗜む」のすすめ】北窓開く頃に焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/nb34d01199fc6
【「嗜む」のすすめ】春疾風に焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/ned19ee61b72b
【「嗜む」のすすめ】寧日に焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/n743f524745d4
【「嗜む」のすすめ】灯ともしごろに焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/n1b252c54e1dc
【「嗜む」のすすめ】「Less is more(レス イズ モア)」に焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/nc39054c17be3
【「嗜む」のすすめ】濃淡に焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/n2f8510e45110
【「嗜む」のすすめ】未来からの学びに焦がれ本を嗜む
https://note.com/bax36410/n/nc54bcdb0442c
