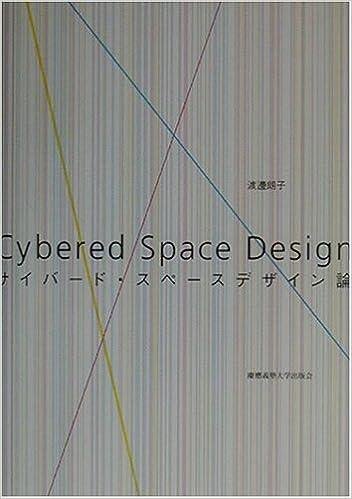【宿題帳(自習用)】情報の力を獲得するために心と情報との付き合い方を再考してみる(その5)
【関連記事①】
前の記事は↓を参照。
では、もう一つ大切なインプットである社会情報は、どのようにリアリティを獲得するのだろうか?
この2つの問いに答えることが、ヒトの心の定義に大きなヒントを与えてくれます。
そこで、言葉と音楽が密接な関係がある点について考えてみます。
たぶん、そのような考え方は、多くあるのではないかと思います。
また、言葉から発展した文化や歴史が芸術と密接に係わっていることは確かです。
言葉そのものと音楽との関係も深いものがあると感じます。
そこで、言葉と音楽の関係性を、情報(そこから送り出される内容)として考えてみた場合、音楽は、主に感情に訴えかけ、言葉は、理性に訴えかけるように発達してきたと考えられます。
そして、似ているようでいて、相反する関係ゆえに、互いに影響を与え合い、さまざまな果実を産み落としてきた結果の一部が、下記の【参考図書①】に記載した書籍たちです。
【参考図書①】
「音楽と言語」(講談社学術文庫)G・トラシュブロス・ゲオルギアーデス(著)木村敏(訳)

「武満徹著作集〈4〉」武満徹/大江健三郎/川田順造(著)
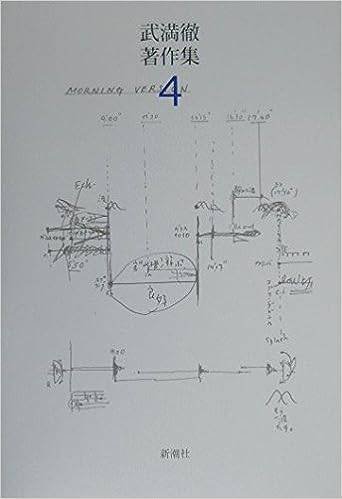
「音楽の聴き方―聴く型と趣味を語る言葉」(中公新書) 岡田暁生(著)

「言葉の誕生を科学する」(河出文庫)小川洋子/岡ノ谷一夫(著)

「ヒップホップの詩人たち」都築響一(著)

さて、フランス語は、最初の音には、アクセントが絶対に来ません。
どれも最後のシラブル(音節)が一番上がるように発音されます。
音楽も同じ感じであり、例えば、ドビュッシーのふわっとした、どこにもアクセントのないパッセージな曲である「海」。
ドビュッシー:交響詩「海」 3つの交響的スケッチ 第1楽章「海上の夜明けから真昼まで」
ドビュッシー:交響詩「海」 3つの交響的スケッチ 第2楽章「波の戯れ」
ドビュッシー:交響詩「海」 3つの交響的スケッチ 第3楽章「風と海との対話」
それに対して、ハンガリー語は、全部、最初にアクセントがきます。
だから、音楽もその通りであり、いきなり強烈なアクセントから始まる曲であるハンガリー狂詩曲第2番。
リスト:ハンガリー狂詩曲 第2番
リスト:ハンガリー狂詩曲 第2番(管弦楽編)
以上の関係性から、例えば、ヨーロッパ各国の言語を知っていると、その言語圏の作曲家の音楽の聴き方とか、表現する(フランス語とフランス音楽、スペイン語とスペイン音楽、イタリア語とイタリアの音楽等)ことに対して、有利な面があるのかもしれませんね。
また、英語は、抑揚が激しい言葉です。
そのためでしょうか。
ジャズ(例:動きの速いサックスのバップフレーズ、あるいはフリージャズ。)がアメリカで生まれた音楽なんだなって、そう感じられます。
Charlie Parker「Confirmation」
Ornette Coleman「Lonely Woman」
そして、ロシア語の響きは、ドイツ語やフランス語と比較してみると、日本語に近い様な気がします。
その事も影響しているのかもしれませんが、ジャズとクラシックを高度に結びつけたピアノ曲で知られるカプースチンの音楽は、日本人的美意識と相通じ、世界の中で、いち早く日本で人気が出ていましたね。
カプースチン:フルート・ソナタ Op. 125 第1楽章
カプースチン:ジャズ・スタイルによる24の前奏曲 Op.53‐13 変ト長調
カプースチン:「8つの演奏会用練習曲」Op.40 第4番 思い出
カプースチン:「8つの演奏会用練習曲」Op.40 第2番 夢
カプースチン:「8つの演奏会用練習曲」Op.40 第7番 間奏曲
カプースチン:ピアノ・ソナタ第15番 Op. 127 「幻想風ソナタ」第1楽章
そう言えば、映画「ショーシャンクの空に」で、主人公アンディが友人レッドに対して、そして、本当は自らに対して、「希望捨てる無かれ」という思いを込めて吐き出すセリフ「音楽は人から奪えない」。
人は、苦悩・悲哀の感情があれば、必然的にカタルシス効果を持つものに対して縋ることになります(^^;
その様な感情にある時、言葉はあてにならない。
感情を言葉で制することができるのであれば、人間は、言い尽くせない感情など持ちようもないからです。
アリストテレス的に言えば、言葉があてになれば涙など流さず、声の抑揚すら必要ないのでしょうね。
そして、大声は、注意を喚起する場合にだけあればよいことになります。
しかし、実際に人は、涙します。
声を荒立てます。
感情は、言葉によってのみでは解放されません。
そのため、感覚に直接問いかける音楽が有する情報には、大きなカタルシス効果が伴っている様に感じます。
しかし、音楽に言葉が多く含まれる程、具体的である程、その効果は弱められていきます。
つまり、抱かれる感情に、感情を抱く主体である私たちの立場や時代的・地理的な事情の差異が存在する程、メロディーやリズムが大きな効果を持つようになると思われます。
この様に、私たちは、現実世界の中で、常に、様々なメディア環境を通じて、さまざまな情報を得たり、伝達したり、処理したりしています。
それを通して、独自の情報環境(ユクスキュルの用語では環世界)を構成しているのです。
そうした行為が、コミュニケーションに他ならないと考えられます。
そうしたコミュニケーションの連鎖を通して、社会システムが自己組織的ないし、自己言及的に創発することで、存続、発展、あるいは衰退してゆきます。
現代社会においては、メディア環境なしに情報環境を作り上げることはできなくなっています。
私たちの情報環境は、いまや完全にメディア環境の一部を構成するに至っているのです。
「メディア論―人間の拡張の諸相」マーシャル マクルーハン(著)栗原裕/河本仲聖(訳)

その様なメディア(メディアは、双方向のコミュニケーションが可能であり、デジタルメディアやSNSなどが該当します。)環境下において、現実の社会情報から自分の気持ちを加工するにしても、いい方法と、あまりよくない方法がある点に注意が必要です。
人は、対処できないことがあると、それを受け入れようとするため、自分の気持ちを無意識に加工してしまう癖があります。
これを精神分析の世界では、防衛機制といいます。
防衛機制というのは、ストレスや葛藤、不安や不満といった苦痛から、自分を守ろうとする心の防衛反応です。
もともとは、精神分析学の創始者であるフロイトが考えたものですが、のちにハーバード・メディカル・スクール(ハーバード大学医学部)教授のジョージ・E・ヴァイラントという人が防衛機制を、以下の通り、心の成熟度によって4つに分けました。
①病理的防衛:5歳以下の子どもに多く見られる
例:否認=認めたくない現実から目をそらす
②未熟な防衛:3~15歳の子ども多く見られ、成人にも見られる
例:退行=発達に逆行して未熟な言動をする
③神経症的な防衛:成人にも多く見られる
例:抑圧=認めたくない気持ちを抑える
④成熟した防衛:12歳以降に意識して行われる
例:補償=劣等感をほかの優越感で補う
見せかけだけのやる気を出しても、本音ではやりたくないと思っていれば、それは長続きしません。
本音と行動が一致していれば、無理してやる気を出そうとしなくても、自然とやる気になってきます。
できない理由を上げて、なかなかその気になれない事もあったと思います。
「習慣と脳の科学―どうしても変えられないのはどうしてか」ラッセル・A・ポルドラック(著)神谷之康(監修)児島修(訳)
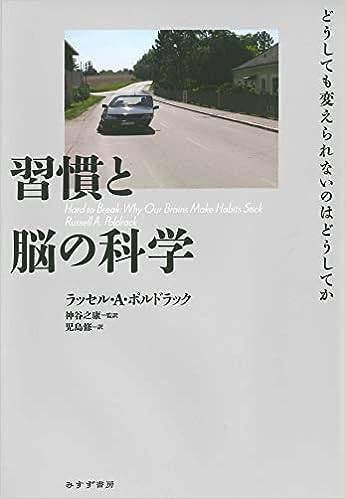
人は、どんな時でも他人にだまされるよりは、自分で自分に嘘をつく場合のほうが多くて、また、人生において何よりも難しいことは、嘘をつかずに生きるために、なんとかして、自分自身の嘘を信じないことです。
この指摘は、ドストエフスキーも看破していましたね。
何をやりたいのか。
今どうしたいのか。
何を手に入れたいのか。
大切なインプットである社会情報から、どのように実生活に有益なリアリティを獲得するためにも、見栄や見せ掛けではない、本当の気持ちを表してみる。
嫌なことを無理やり正当化して続けるより、嫌なことはやめた方が、よほど前向きで健全なはずです。
だからこそ、自分の気持ちに正直に、素直になって考えてみるべきであり、偽りのない自分の本音を語ってみることで、結果的に、自分に嘘はつけないんじゃないかと考えています。
簡単に膨大な情報が手に入るようになったからこそ、その情報を見極め取捨選択することが大切になってきている現代において、
①「知識(情報)」の危険性:「知っている」はいいことか?
⇒問①:「知っていること」に焦点を置くあまり、疑ったり、「わからない」と認めることができなくなっていないか?
「「無知」の技法NotKnowing」スティーブン デスーザ/ダイアナ レナー(著)上原裕美子(訳)

②知性は個人に属していると思われているが、じつのところ人は、知識のコミュニティのなかに生きている。
⇒問②:「無知」は歓迎すべきものではないが、かならずしも悲嘆すべきものでもない。世界はあまりにも複雑で、その全体像は個人の理解を超える。無知は人間にとって自然な状態ではないのか?
「知ってるつもり 無知の科学」(ハヤカワ文庫NF)スティーブン スローマン/フィリップ ファーンバック(著)土方奈美(訳)

気付けることがポイントではあるけど、間違っていると気が付いたら、すぐに軌道修正するようにする。
自分の態度や行動は、無意識のうちに、自分自身を変えることになってしまうから、自分のしたことは、いつか自分に跳ね返ってくると考えて、手遅れになる前に、自分の態度を客観的にチェックしてみる。
問題を先送りすると、更に、条件は悪く厳しくなり、労力も必要となるから、気になることはすぐに対処する習慣をつけて、ストレスを軽減して行くためにも、そして、氾濫する情報に惑わされないで、自分で情報を読み取れる力を付けていくために、
③媒体、情報、意味は不可分だったのに、やがて情報は媒体を離れ、意味は情報量で置き換えられる。それは、もう人間を必要としない。いまや情報は自律的に増殖し、人間はそのお守り役でしかない。
⇒問③:意味と切り離された「情報」とは何なのだろうか?また、その情報洪水の中で必死にそのおこぼれのような意味を探す人類とは、結局、何なのだろうか?
「インフォメーション 情報技術の人類史」ジェイムズ グリック(著)楡井浩一(訳)

物事の「なぜ」を探る道に正解はあるのか?
常に、考えて行く必要があると考えています。
そして、サイバーな心、これはなんだというと、情報化社会におけるヒトの心です。
ヒトの心は、動物の心の一種である。
みずからの生命情報の外部化、機械化(規範化)を激しく求める社会動物、それがヒトの心であった。
規範化権力の威力は文字、印刷技術の登場によりいや増し、書籍を媒介に流通する機械情報は、増量に増量を重ね、そして、コンピュータ、インターネットの出現により、ついに爆発的な奔流となりました。
文字・印刷技術という情報テクノロジーによるヒトの閉鎖システムの表象とも言える言語は、ヒトの心を変容させるに至った事実を理解しておく事が重要です。
権威の発する声に耳を傾けるのではなく、機械情報を自らの閉鎖システム更新の手段とし始めたんです。
例えば、前著「こころの情報学」において、ヒトの心では、山奥の農夫に3段論法をしかけると、ほとんど正解しないという事例を紹介していました。
これは、彼らの閉鎖システムが、それを必要としていないからです。
このような状態では、中心者が運ぶ父祖の声というもの、あるいは文脈を持つ神話が共同体を結束させる求心力となるのは何となく想像がつくと思います。
索引のついた印刷物の一部を、何か情報データベースのように文脈から切り離し参照するグーテンブルグ後のヒトとは対照的です。
印刷機械により、王は死んだのだと言えるかもしれません。
そして、AIを含むコンピュータやインターネットによる情報の痛烈なまでの流通は、さらにヒトの心を変容させ得ると推定できます。
生命であり、閉鎖システムで生きているにも関わらず、外部の機械情報で自らを統御しようとする特異な生物であるヒトは、すなわち鋭い矛盾を抱えている存在であると言えます。
それが究極に達するのが、現在のデジタル社会だと言えるのではないでしょうか。
「情報セキュリティの敗北史 脆弱性はどこから来たのか」アンドリュー・スチュワート(著)小林啓倫(訳)

印刷物をはるかに超える機械情報のインパクトに生きる私たち(人間)に、それは、何をもたらすだろうか?
【参考資料(間主観性/共同主観性)】
1.「フッサールにおいて、間主観性という問題系は、客観的世界の構成という文脈のなかで提示される。
フッサールによれば、意識はつねに何ものかについての意識であり、それゆえに、さまざまな対象とその全体としての世界への問いは、現象学的には、意識する〈わたし〉と意識された〈世界〉とのあいだの、意識という志向的な関係への問いにほかならず、したがってそれは「あらゆる可能的認識の主観としてのわたしの自我の自己解明」という形式をとる。
超越論的主観性による世界構成の志向的分析は基本的に超越論的自我論として展開されるのである」(鷲田清一、1998「間主観性」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:282])
2.「私にとっての世界と、あなた(あるいは「かれら」)にとっての世界は「おなじ」世界なのだろうか。
それともその二つの「世界」はまったく「ちがう」世界なのであろうか。
この問いに、だれもが納得する事得を与えることは、意外と難しい。
間主観性ということばは、「客観性」ということばにかえて、この問いに対して答えを与えるために、まずは現象学の立場から提出された、比較的あたらしい概念である。
それは、主観性がそれぞれ単独ではたらいて世界に対峙しているのではなく、たがいに絡みあい交錯しあいながらはたらいて、「共に」機能し、共通な世界を成り立たせている、ということがらをいいあらわそうとすることばなのである。
間主観性という概念は、こうして、単独の主観が信用をうしない、客観性という概念が疑われる場面で登場する」(熊野純彦、2002「間主観性」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:206])
3.「世界は、私にとってさまざまに切り分けられて存在している。
世界のうちの、あるものごと、たとえば一定の色、特定の音が切り分けられて存在しているとは、そのもの(色、音)・こと(色が見えること、音が聞こえること)が、それぞれに「意味」をもっているということだ。
世界は、こうして、さまざまに意味づけられて、私に対して存在している。
だが、私は、ただ一人で、世界に、世界のうちのもの・ごとに、意味を与えているわけではない。
私は、「私たち」が共有することばをつうじて、いわばその分類の網の目を介して、世界を切り分け、意味づけている。
私が世界に「対峙」し、世界のものごとに意味を与えながら生きているとき、私はじつは「私たち」というかたちで「共に」生きている。
「私たち」は「たがいに絡みあい交錯しあいながら」世界を意味づけている。
世界はこうして、「私たち」にとって「間主観的」に与えられているのである」(熊野純彦、2002「間主観性」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:208])
【関連記事②】
【参考図書②】
「基礎情報学―生命から社会へ」西垣通(著)

「続 基礎情報学―「生命的組織」のために」西垣通(著)
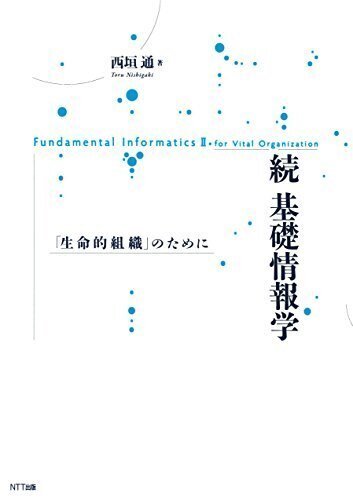
「新 基礎情報学―機械をこえる生命」西垣通(著)
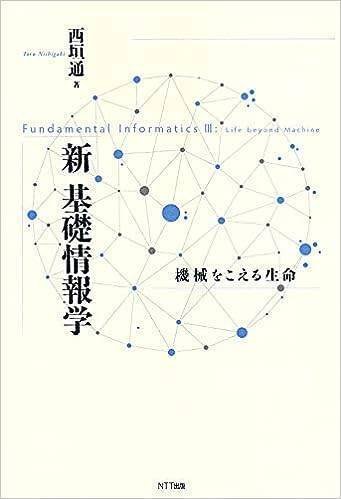
「生命と機械をつなぐ知―基礎情報学入門」西垣通(著)

「デザインマネジメント戦略―情報消費社会を勝ち抜く」佐藤典司(著)

「情報デザイン入門―インターネット時代の表現術」(平凡社新書)渡辺保史(著)

「サクセス・バリュー・ワークショップ 情報構想設計 好き!から始めるコミュニケーション・デザイン」七瀬至映(著)
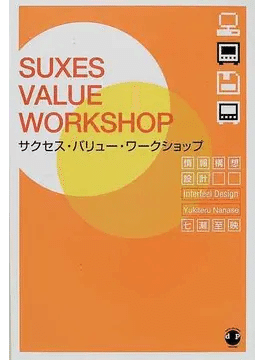
「情報編集力―ネット社会を生き抜くチカラ」藤原和博(著)

「サイバード・スペースデザイン論」渡邊朗子(著)