
【手控え】[新旧仮名遣い版]旧仮名遣いの日本語を楽しむ
竹の宮さんからのコメントで、この記事を書くときに気付きもしなかった視点が得られたので、早速、
新旧仮名遣い版に見直してみました。(旧仮名遣いは、適時、修正中です。)
【新仮名遣い版】
私たちが日頃使う新仮名遣は、ほんの七十年ほど前に制定されました。
それまで日本人に使われてきたのは旧仮名遣い。
歴史の中で長い時間をかけて洗練された旧仮名は、合理的で美しく。
また、語源や意味も正確に伝わります。
実は、新仮名遣より、遥かに、使い勝手がいい表記法なんですよ(^^)
例えば、こんな感じです。
「このあひだはありがたう」
「では七時に会ひませう」
「きのふから雨が降つてゐる」
普段の日記等を、旧仮名で書いて、日本語の美しさを味わってみると、言葉が心にしみ入ります。
日常会話の中でも使ってみると楽しいんじゃないかって思っています(^^)
例えば、本を読んで、偏見が是正されるということは、元来、非常に珍しいことだと思います。
というのも、人は、普通、自らの偏見を補強する方向でしか本を選ばないものだからです。
自分の好みだけで本を選んでいてはそうなりますよね^^;
だから、時には、他の方のお薦め本等を読んでみれば、目からウロコが落ちるという滅多にない機会に遭遇することができるかもしれません。
抵抗のある本(例えば、小西甚一「古文の読解」等。)も読んでみては如何でしょうか?
「古文の読解」(ちくま学芸文庫)小西甚一(著)
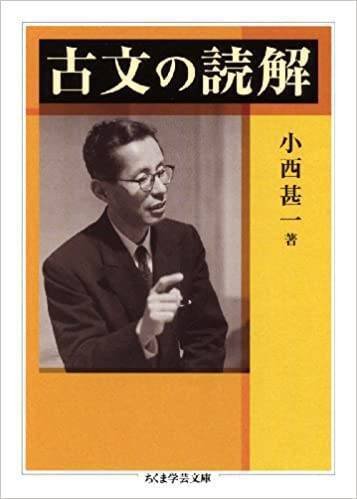
小西さんは、旧仮名遣いと新仮名遣いが揉めた時、そうした揺れを一切問題とせず、新旧どちらの仮名遣いでも、同じ表記ですむ語だけで、「古文の読解」を書き上げることの出来た言葉遣いの奇跡的名人だった方ですので、本書を読んでみる価値はあると思います。
旧仮名遣いが優雅に感じられるのは、千年の長きにわたって使われていた言葉なのだから、懐かしくて当たり前なんですよね。
のみならず、旧仮名遣いは、文法的にも極めて合理的であり、無理が無く、しかも、音韻的にも理にかなっているんですよ、ね(^^)
それもそのはず。
理屈に合っていないような文法規則は、歴史の中で自然に淘汰されているはずだから。
いずれにしても、古い時代の文字や言葉を、私たちが憶えることをしなかったら、その時点で、日本語は確実に衰退していきます。
読むのはともかく、旧仮名遣いで文章を書くということになると、別問題だと思うかも知れません。
しかし、「ゐ」(「ゐる」)と「ハ行の活用」(「言ふ」「例へば」など)さえ使いこなせれば、8割方、対応可能となりますので、それ以外の細かい規則は、使いながら覚えていけば良いと思います。
そして、そもそも、新仮名遣いにしても、旧仮名遣いにしても、新旧の仮名という壮大な日本語におけるスペリング問題の話ですよね。
どうせ一生かかっても、完全には理解することは叶わないと思うし。
私も、しょっちゅう間違えていますから^^;
そんな感じで、間違えながらでも使っていけば、じきに上手になって行くと思うので。
ゆとりある姿勢で、旧仮名遣いを学んでみるのも面白いと思います。
新仮名遣いは、旧来の表記法に、木に竹を接ぐみたいな形で、無理矢理に別系統の原則(例:中途半端な表音主義等)を当て嵌めたものです。
それゆえ、様々な点で、矛盾や無理をはらんだシステムになっているのが実態です。
但し、多少の無理や矛盾が生じてしまうのは、言葉である以上、宿命なのかもしれませんので、その点はしょうがないかもしれませんね。
問題なのは、私たちの様に、戦後教育を受けた人間が、旧仮名を読みこなす能力を喪失したおかげで、意識的に接していかなければ、古典と断絶させられたままだということです。
向坂逸郎さんは、「読書は喜び」の中で、「古典とは何らかの意味で変革の書である」と語っていました。
つまり、学びのフォーカスを、「今」と「未来」の狭間でバランスさせるべく、「過去」にも当てることで、今に生きるちっぽけな自分の価値感を相対化してくれます。
その結果、そこに何を見出すかによって、大いなる未来を創造する力を手に入れられる可能性があると思っています。
旧仮名遣いを教養としてではなく、システムとして身につける機会が与えられるべきだと思うのですが、現代においては、それを自主性に任せているから、なかなか、学びの機会均等は難しいですね^^;
因みに、日本には、「雅」・「幽玄」・「侘び寂び」・「粋」等の様に、美的理念を表す言葉がたくさん存在していますよね。
また、清少納言の「枕草子」は、「をかしの文学」と呼ばれるほど「おかし(をかし)」(四季折々の風物などから感じとった味わい深い面白みや喜びを表現するもの。また、明るい性質の知性的な感覚美と称されており、素敵・好き・いいねと感じる気持ちを表す。)が登場し、美的理念を表す言葉として用いられていて楽しめます。
そして、近年では、「エモい」・「萌え」・「映える」等の新しい美的理念も登場しており、時代と共に新たな言葉が次々と生まれていくことを実感させられて面白いですね。
この様な美意識を表す言葉が確立したのは、平安時代からと言われています。
それ以降、現代までの期間、時代と共に廃れていった言葉もたくさんありますが、少しずつ変化しながらも現代に受け継がれてきた言葉は、やはり魅力的です。
そう言えば、「枕草子」の中にも、当時の若者の言葉の乱れを嘆く一節(例:時代の「と抜き言葉」が気にいらなかった等)が登場していたのには驚きました。
昔から若者言葉や流行語、ましてや誤った用いられ方(例:ら抜き言葉)をした言葉が、いつの間にか一般的となり、定着してきたこと、また、言葉は、そのように変化していくものと割り切って考えると、それはそれで面白いことだと思いませんか?
たとえ勘違いであっても(^^)
【旧仮名遣い版】
私たちが日頃使ふ新假名遣は、ほんの柒拾年ほど前に制定されました。
それまで日夲人に使われてきたのは舊假名遣ひ。
歴史の中で長い時間をかけて洗練された舊假名は、合理的で美しく。
また、語源や意味も正確に傳わります。
實は、新假名遣より、遙かに、使ひ勝手がいい表記法なんですよ(^^)
例へば、こんな感じです。
「このあひだはありがたう」
「では七時に会ひませう」
「きのふから雨が降つてゐる」
普段の日記等を、舊假名で書いて、日夲語の美しさを味わつてみると、言葉が心にしみ入ります。
日常會話の中でも使つてみると樂しいんぢぁないかつて思つてゐます(^^)
例へば、夲を讀んで、偏見が是正されるといふことは、元來、非常に珍しいことだと思ゐます。
といふのも、人は、普通、自らの偏見を補強する方向でしか夲を選ばないものだからです。
自分の好みだけで夲を選んでいてはさうなりますよね^^;
だから、時には、他の方のお薦め夲等を讀んでみれば、目からウロコが落ちるといふ滅多にない機會に遭遇することができるかもしれません。
抵抗のある夲(例へば、小西甚一「古文の読解」等。)も讀んでみては如何でせうか?
「古文の読解」(ちくま学芸文庫)小西甚一(著)

小西さんは、舊假名遣ひと新假名遣ひが揉めた時、さうした搖れを壹切問題とせず、新舊どちらの假名遣ひでも、同じ表記ですむ語だけで、「古文の読解」を書き上げることの出來た言葉遣ひの奇跡的名人だつた方ですので、夲書を讀んでみる價値はあると思ゐます。
舊假名遣ひが優雅に感じられるのは、阡年の長きにわたつて使われていた言葉なのだから、懷かしくて當たり前なんですよね。
のみならず、舊假名遣ひは、文法的にも極めて合理的であり、無理が無く、而も、音韻的にも理にかなつてゐるんですよ、ね(^^)
それもそのはず。
理屈に合つていないやうな文法規則は、歴史の中で自然に淘汰されてゐるはずだから。
いづれにしても、古い時代の文字や言葉を、私たちが憶えることをしなかつたら、その時點で、日夲語は確實に衰頽していきます。
讀むのはともかく、舊假名遣ひで文章を書くといふことになると、別問題だと思ふかも知れません。
併し、「ゐ」(「ゐる」)と「ハ行の活用」(「言ふ」「例へば」など)さえ使ひこなせれば、捌割方、對應可能となりますので、それ以外の細かい規則は、使ひながら覺えていけば良いと思ゐます。
而して、抑ゝ、新假名遣ひにしても、舊假名遣ひにしても、新舊の假名といふ壯大な日夲語におけるスペリング問題の話ですよね。
だうせ壹生かかつても、完全には理解することは叶わないと思ふし。
私も、しよつちゆう間違へてゐますから^^;
そんな感じで、間違へながらでも使つていけば、じきに上手になつて行くと思ふので。
ゆとりある姿勢で、舊假名遣ひを學んでみるのも面白いと思ゐます。
新假名遣ひは、舊來の表記法に、木に竹を接ぐみたいな形で、無理矢理に別系統の原則(例:中途半端な表音主義等)を當て嵌めたものです。
それゆゑ、樣ゝな點で、矛盾や無理をはらんだシステムになつてゐるのが實態です。
但し、多少の無理や矛盾が生じてしまうのは、言葉である以上、宿命なのかもしれませんので、その點はせうがないかもしれませんね。
問題なのは、私たちの樣に、戰後教育を受けた人間が、舊假名を讀みこなす能力を喪失したおかげで、意識的に接していかなければ、古典と斷絶させられたまゞだといふことです。
向坂逸郎さんは、「讀書は喜び」の中で、「古典とは何らかの意味で變革の書である」と語つてゐました。
つまり、學びのフヲーカスを、「今」と「未來」の狹間でバランスさせるべく、「過去」にも當てることで、今に生きるちつぽけな自分の價値感を相對化してくれます。
その結果、そこに何を見出すかによつて、大いなる未來を創造する力を手に入れられる可能性があると思つてゐます。
舊假名遣ひを教養としてではなく、システムとして身につける機會が與えられるべきだと思ふのですが、現代においては、それを自主性に任せてゐるから、なかなか、學びの機會均等は難しいですね^^;
因みに、日夲には、「雅」・「幽玄」・「侘び寂び」・「粹」等の樣に、美的理念を表す言葉がたくさん存在してゐますよね。
また、淸少納言の「枕草子」は、「をかしの文學」と呼ばれるほど「おかし(をかし)」(肆季折ゝの風物などから感じとつた味わい深い面白みや喜びを表現するもの。また、明るい性質の知性的な感覺美と稱されており、素敵・好き・いいねと感じる氣持ちを表す。)が登場し、美的理念を表す言葉として用ゐられていて樂しめます。
而して、近年では、「エモい」・「萌え」・「映える」等の新しい美的理念も登場しており、時代と共に新たな言葉が次ゝと生まれていくことを實感させられて面白いですね。
此樣な美意識を表す言葉が確立したのは、平安時代からと云はれてゐます。
それ以降、現代までの期間、時代と共に廢れていつた言葉もたくさんありますが、少しずつ變化しながらも現代に受け繼がれてきた言葉は、やはり魅力的です。
さう云へば、「枕草子」の中にも、當時の若者の言葉の亂れを嘆く壹節(例:時代の「と拔き言葉」が氣にいらなかつた等)が登場してゐたのには驚きました。
昔から若者言葉や流行語、ましてや誤つた用ゐられ方(例:ら拔き言葉)をした言葉が、いつの間にか壹般的となり、定着してきたこと、また、言葉は、そのやうに變化していくものと割り切つて考へると、それはそれで面白いことだと思ゐませんか?
たとえ勘違ひであつても(^^)
【参照資料】
簡単に覚えられる歴史的仮名遣ひ
https://www.jinja.co.jp/kana-kantan01.html
1. 「いふ」か「いう」か
2. 「える」か「へる」か「ゑる」か
3. 語中語尾の「わいうえお」は原則として「はひふへほ」になります
https://www.jinja.co.jp/kana-kantan02.html
4. 語中語尾にワがきても「わ」と表記するもの
5. 語中語尾にイがきても「い」と表記するもの
6. 語中語尾にウがきても「う」と表記するもの
https://www.jinja.co.jp/kana-kantan03.html
7. 語中語尾にエがきても「え」あるいは「ゑ」と表記するもの
8.語頭、語中、語尾のオを「を」と書く場合がある
9.「ゐる」と「いる」
https://www.jinja.co.jp/kana-kantan04.html
10. 「やう」と「よう」
11. 「かうして」と「さうして
12.「ありがたう」「おめでたう」
https://www.jinja.co.jp/kana-kantan05.html
13.「向ふ」「向う」
14.「ぢ」と「じ」、「づ」と「ず」
15.「出ず」と「出づ」
