
編んで、私を取り戻す。3つのニット帽と、8歳の子どもを見つめて気づいたこと。
はじまりは、突然だった。
子どもが生まれて1か月くらいの頃。なんとなく、私が編んだティーコゼー(ティーポットが冷めないようにかぶせるカバー)を子どもにかぶせてみた。そのサイズ感に、激しく、胸がきゅん……!となった。

この子に帽子を編んであげたい、と思った。きっと素敵なものができるにちがいない、そういう予感がした。
いざ編まん、子どものニット帽を
さて、編んであげたいが、どうするか。子どもサイズのものなんて、それまでつくったことがなかった。とりあえず、自分のお気に入りのニット帽を小さくしてみようと思い立った。つまり、編み図を自分で考えるのだ。え…難しそう……
以前編んだことのある、三國万里子さん(大人気のニットデザイナーで私の尊敬するニッター)の「アランのニット帽」の編み図をベースに、子どもの頭のサイズで計算をして、なんとか簡単な編み図をこしらえた。(学生時代「なんの役に立つのさ…」なんて文句を言いながらやってきた数学が、この時しっかり役に立ちました)

そもそもニット帽は、初心者だってがんばれば数日で編めちゃうくらいハードルが低い。子どもサイズならもっとカンタン。つまり、失敗してもぜんぜん平気。編み物だから、何度でもほどいて編み直せる。
とりあえず編んで、完成させた。そうして、編み終えたニット帽を子どもにかぶせてみた。やっぱり、きゅん……!

なんて、なんてかわいいんだろう… しかも、この帽子をつけている我が子はあたたかそうだ。こんな幸せな趣味があるだろうか…とすっかりハマってしまった。
こうして私は、子どもが赤ちゃんのころからニット帽を編んできた。成長していく子どもにあわせて編み直し、現在、8歳になった子どもがかぶっているのは三代目ニット帽(J Soul Brothersではなく)だ。
不思議なのは、ワンオペで子どもをみながら仕事をするのに精一杯だった私の、いったいどこに編み物をするエネルギーがあったんだろう?ということ。今となってはあの頃のことがあまり思い出せない。

※左上はティーコゼー
編み物との出会い
はじめて毛糸と編み針を持ったのは、小学生のとき。一つ上のいとこの家に遊びに行くと、同居していたおばあちゃんに持たされた。(子どもの大騒ぎを鎮めようとしたのだろう)「これが表編みでこれが裏編み」と、なんとなく教えてもらったのが出会いだった。
表編みと裏編みを2つずつ繰り返して行くと、ゴム編みになる。そのまま、まっすぐに編み続ければマフラーになる。おばあちゃんに教えてもらった後、子どもなりに独自のアレンジを加えるもんだから、編み方も適当だしぜんぜんきれいに編めない。だけど、いとこと私は競うように夢中で編んだ。「一本の毛糸から何らかの形ができる」のが楽しかった。
そのうち、一人でいる時にもときどき編むようになった。いろんな遊びのなかの一つに編み物がある、という子ども時代だった。
編み物は「おおらか」である
「編み物をしている」というと、「すごいね」とか「私は不器用だから無理だ…」という言葉をもらうことがある。けれど、声を大にして言いたい。謙遜なんかではなく、ぜんぜんすごくないし、我こそ、不器用であります!
小学校、中学校の家庭科の授業ではかならず失敗し(誰も怪我しない場面で怪我する子いるでしょ、あれ私です)、特に裁縫については男子に憐れみの視線を向けられるほど、不得意だった私だ。そんな私でも編んでいる。
それに、わたしの敬愛する三國万里子大先生は仰った。「糸と糸がからんでいれば それは編み地」なのだと。
「編んでます」とは言えなくても、「糸をからませてるんです」、そのくらいの認識で始めたっていい。編み物は不器用ニッター(私)をおおらかに包み込んでくれる。だから楽しく編んでこられたのだと思う。

大人になっても、ときどき編む生活は続いた。マフラー一辺倒だった10代を経て、手袋や靴下も編めるようになった。
初心者にわかりやすい本が増えたり、おしゃれな編み物キット(編み図と詳しい解説と毛糸がセットになったもの)が販売されるようになったのも、編み物を続けられた理由の一つ。
編み物と、母になった私
編み物をすると、いつでも子どものころの感覚を思い出すことができた。おばあちゃんの家で、いとこと二人で、一人きりで。安心できる場所でなにかに夢中になれたあの時間。あそこに時々もどることが、自分には必要だったんだと思う。
母親になってからの数年間。私は「子どものため」を最優先にして、「自分のため」を削ることでなんとか生活を保っていた。そうしかできなかった。そんな生活のなかで、「子どものため」と「自分のため」が重なる心地いい時間をくれたのが、子どものニット帽を編むことだった。
母だって、楽しんでいい。自分のための時間をこじあけることが難しくても、寝室で寝ている子をベビーモニターで監視しながら、とか、保育園にお迎えに行く前の30分だけ、とか。すこしずつ、すこしずつ。
今思えば、編み物が、子どもを優先してきた私に「自分のため」を取り戻すきっかけをくれたような気がする。
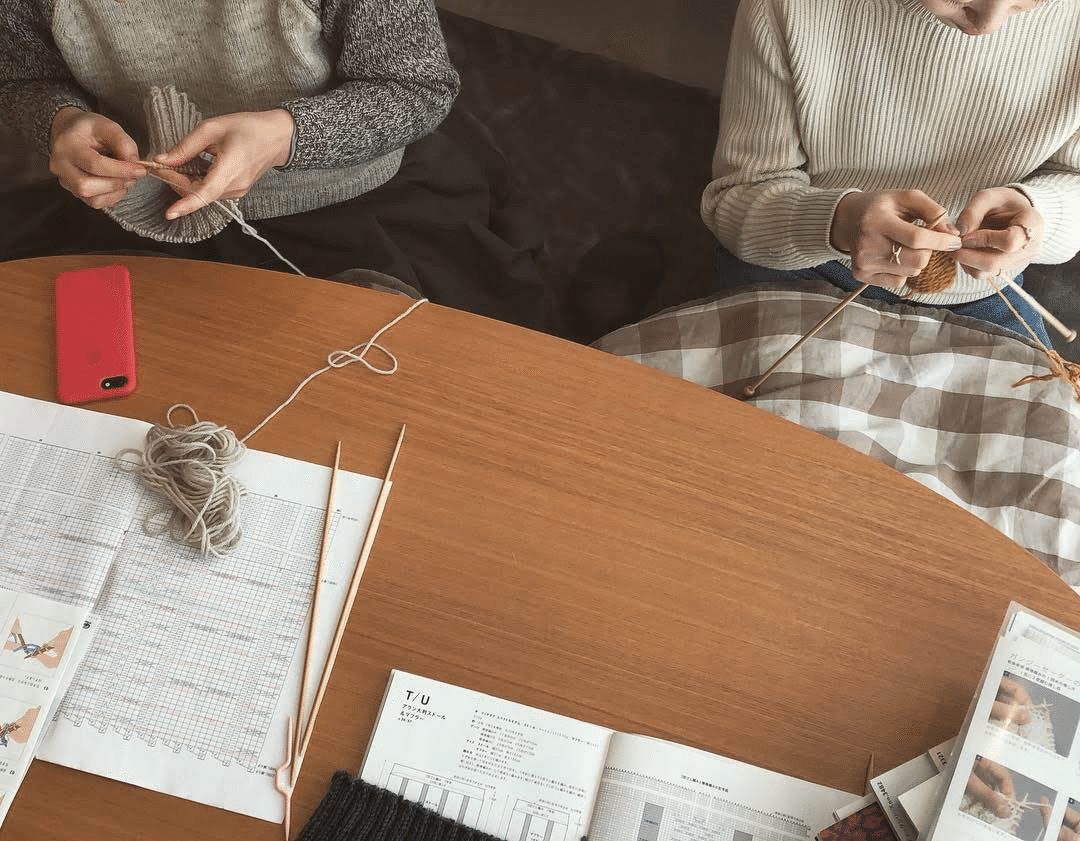
小さくなったニット帽と、大きくなった子ども
この冬ついに、三代目ニット帽がジャストサイズすぎてのびてきているのに気づいた。子どもがまた大きくなったのだ… こういう時、時間の経過を実感する。日々はいつも、いつのまにか通りすぎてゆく。
つい先日のこと。子どもが「このぼうし、ママが編んだんだよ」とクラスメイトに言ったところ、「うそつけ!」と言われた、と話してくれた。不満げなのに、どこかちょっぴり嬉しそうな子ども。それを見て、私も内心にやりとしてしまった。
子どもは新しいニット帽ができるたびに大喜びして、小学生になった今でも、冬は毎日かぶって登校している。とびはねるように学校へ行く子どもの頭に、私が編んだニット帽。毎朝、「今日もかわいい」と思いながら送り出す。いつまでかぶってくれるだろう。
来年の冬に向けて、また新しいニット帽を編もうと思っている。子どもは、「丸いポンポンがついたのがいい!」とのこと。さあ、つぎは何色の毛糸にしようかな。


