
ミノルタの遺伝子(157回目)

ギックリ腰
どうやら腰をやったようである。
動けないまではいかないが、立ったり座ったりするたびに酷い痛みが右腰にくる。
もう何回もやっているから、こうなってしまうと、やれ冷やすだの温めるだのやったところでどうにもならないのは経験則で分かる。
大人しくしているほかない。
なので今日はお座敷写真になる。

α100
ソニーα100を相変わらず使う。
SNSなんかを見ているとαでも「7」とか「1」とかがソニーのαということになっているらしく、どんなもんだろうと見てみると「α1 II ILCE-1M2」というのが5000万画素くらいの画素数にこれまた高感度もISO102400とかになるらしい。
お値段となると891,000円からとなっている。
素晴らしい。
頑張っていただきたいものである。
ウチのα100は2006年に発売されている。
「α」ブランドはミノルタのものだが、ミノルタは2003年にコニカと合併、2006年にはカメラ、フィルム事業から撤退した。
αも潰えるかと思ったらソニーがブランドごと引き継ぎ、同年にソニーブランドのαが登場する。
それがα100だ。
その後のソニーのカメラの躍進はご存知のとおりである。
このα100の頃は、たぶんミノルタの技術者が先導してカメラを作ったはずである。
軍艦にダイヤルが2つが斜めについているというのもフィルム時代のミノルタα7なんかを彷彿とさせる。
これは一眼レフ機であるからEマウントではなく、ミノルタのAマウントレンズがそのまま使える。
ミノルタのレンズは銘玉が多い。MF時代はもとより、α7000以降のAFにもある。
ところが時代はミラーレスとなり、ミノルタのAFレンズはジャンクボックスの住人となり果てている。
まあこちらからすると嬉しい限りなのだが。
ミノルタAF小三元
初期のズームである「MINOLTA AF ZOOM 35-70mm F4」、さらに広角側を広くした「MINOLTA AF ZOOM 24-50mm F4」、通称「茶筒」と呼ばれる望遠ズームレンズ「MINOLTA AF ZOOM 70-210mm F4」はF4通しということで「小三元」と呼ばれている。
これらは大変によく写る。
しかも投げ売りのような値段で手に入る。



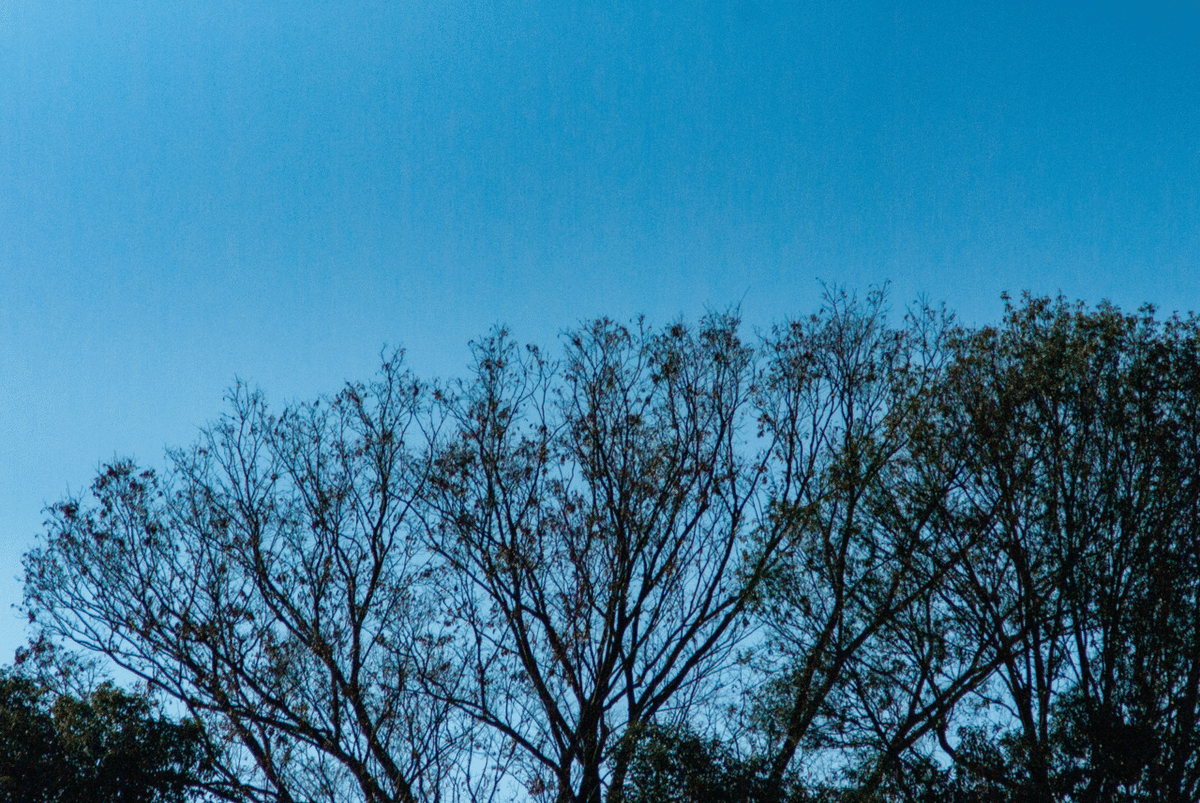
ミノルタ主導の設計のおかげなのか、このカメラには実しやかに囁かれる「ソニータイマー」は存在しないようだ。
もうすぐ20年にもなるカメラだが、いまのところ不具合らしい不具合はない。
よくソニーの商品にある「保証期間が終わったら壊れた」なんてこともなさそうだ。
そう。ミノルタのカメラは頑丈だった。



価値の相対化
急に見出しが難しくなったが、カメラに限らず世の中にあるものの価値というのは相対的なのである。
経験や視点によって同じ物事に対する価値の捉え方が異なる。
SNSなどで見かける論争というのは、まずこの視点が欠けていることが多い。
だいたい冒頭の90万円近いカメラも、昨日書いたCampSnapCameraも極最近に新発売された「カメラ」という同じカテゴリのものだ。
同じ価値観でしか語れないものであるなら、何もISOが102400も要らないとなるし、またピント合わせができないなんてカメラとして認められないという話になるだろう。
これは車だろうと洋服だろうと、または料理だろうと同じことだ。
良い悪いの話ではなく、そういうものなのだ。
だから、と書くとなにやら言い訳がましく聞こえるかも知れないが、ぼくはおそらくこの先も「最先端」のカメラを買うことはない。
そこに価値を見出せなくなっているからだ。
自分にとって使いやすいとか、使っていて楽しいとか、そういうことの方が大事に思えるのである。
まあここまで散々散財してきたのだけど。



ISOは1600までだが、そこまで使うとノイズがえらいことになる。
実用としてはISO400くらいまでかな。
これらの写真は後処理でノイズを軽減している。
