
複雑な世界について、考え続ける<小佐野彈さん×李琴峰さん特別対談>
歌人で作家の小佐野彈さんと芥川賞作家の李琴峰さんのトークイベントが、2022年1月23日にジュンク堂書店池袋本店で行われた。それぞれの新刊『僕は失くした恋しか歌えない』(新潮社)、『銀河一族』(短歌研究社)、『生を祝う』(朝日新聞出版)に関して、大いに語り合った。答えのでない問題とどう向き合うか。資本主義社会のなかでの文学の意味とは。その一部を特別に公開する。
小佐野:李さんとは、台湾という縁があって、またお互いのセクシャリティの事もあり、なんとなく同じカテゴリーの人という括られ方をしてみられるのかなと思います。
李:そうですね。小佐野さんは、大学院までは日本にいてそこから社会人生活を台湾で過ごされて、私は逆に大学までを台湾で過ごし、大学院から日本に来て、そのまま日本で就職しました。台湾では働いたことがないので、逆の体験をしているわけですが。
小佐野:さっきも言った特定の共通点みたいなものが多いから、並べて、というと語弊があるかもしれないんですけど、同じような看板をつけられるというような印象を抱くのですが、創作で目指している方向は違うとも感じていて、むしろ違うから作品を読むと刺激を受けるというところがあります。最新作の『生を祝う』も、めちゃくちゃ面白かったです。
李:ありがとうございます。
小佐野:李さんの作品で面白くないものはないんですけど、芥川賞を受賞した『彼岸花が咲く島』でも感じたのですが、世の中の人が見なかったことにしようとすることを、絶対に許さないで、これが現実だから、きちんとそこに目をむけようという訴えがあるように感じます。僕自身ゲイであることにくわえて、たとえば台湾では「外国人」というマイノリティなので、そういうマイノリティの立場のようなものが、自分は勝手にわかったつもりになっていたけれど、李さんの小説を読むとわかってなかったと思わされます。

『生を祝う』は、2075年の近未来が舞台で、その世界では生まれる前の胎児に出生の意思を確認するというのがグローバル・スタンダードになっていて、その意思を無視して出産をすると「出生強制」の罪に問われる。今、我々が住んでる社会は、胎児に意思があることを前提としない社会ですが、でもそれが間違っているとは決して言っていないですよね。単行本の帯にも書かれている通りですが、「人間が完璧でない以上、どんな制度にも必ず欠陥は存在する」と。まさに李さんの小説というのは、特にこの『生を祝う』に関しては、非常に確かな筆致で我々が向き合ってこなかった現実、出産とか、子供の意思という問題について、ものすごく切実に迫っている。一方で決して何かを強制もしない。あるべき論にならないというのは、文学的態度として当然のことなのかもしれないですけれど、でもやっぱり、その匙加減が李さんは本当に絶妙だなと思います。

李:私たちは今、基本的に自由意志が尊重される社会を生きているじゃないですか。誰かに強制されて結婚することもおそらくないし、誰かに強いられて職業を選ぶことも、多分ないと思うんですけれど、出生だけは自分の意志が全く介在しない。そういう意味では強制されているというふうに言ってもいいと思うんですね。現状とは逆に、自分が産まれて来るかどうかを、自分で決められる世界だったらどうなるのか。小説でシミュレーションしたわけですけれども、その世界には、やっぱりいろんな綻びがある。胎児の意思は尊重されているかもしれないけれど、妊娠する側の気持ちはどうなるか。ブラックボックスな部分がある制度ゆえに、不備があるのではないかという批判もある。何が正しいのかについて、この小説では、答えは出せていないんですけど、それはつまり読者の方々に一緒に考えて欲しいと思うからだし、答えはないけれども考え続けることを諦めてはいけないと思っているからなんです。何が正しいのか、なんてどうせわからないのだから、現状維持でいいじゃないみたいな感じにはならず、やっぱり何が正しいのかを常に考え続けないといけないし、なるべく多くの人の選択肢を増やせる方向になればいいなとは思っています。
小佐野:社会が豊かであるというのは、そういう状況のことをいうのではないかと思います。選択肢が保障されるべきというのは、まさしく僕もそうだと思っていて、そして答えが出ない問題があるというのも、本当にその通りですよね。李さんの場合は、そういう答えが出ない問題に対しても絶対あきらめないし、ちゃんと考えていこうっていうのが作品からも、すごく強い意志として感じられます。一方、僕の作品は、既存の社会秩序に対しての、諦めみたいなものが、あるように映るらしいですね。デビュー作である歌集『メタリック』に対しても、最新刊『僕は失くした恋しか歌えない』に対してもそういう声がありました。率直に、今回の僕の新刊を李さんはどう読まれましたか。

李:今回の作品は自伝的な小説ですよね。小佐野さんの小説はデビュー作の『車軸』、それから「文學界」に掲載された「したたる落果」を読んでいまして、今回はすごく毛色が違った。デビュー作の『車軸』は、私は正直そこまで好きではなかったんですけど(笑)。「したたる落果」は台湾に住んでいる日本人のコミュニティーを舞台に、いろいろな人間が描かれていて、とても深みがあって面白かった。今回は、改行も多くて、文体がまず全然違いますよね。

小佐野:今回の小説はエンタメをかなり意識しましたし、「自分の物語」なので、自分の心のリズムを優先して書いたところがあるかもしれません。短歌が間に入るので、散文のリズムが崩れないようにというふうにも思いながら書きました。
李:私は、短歌に関しては明るくないのですが、今回の小説は散文のなかに挟まれた形で韻文(短歌)が出てくるので、何が詠まれているのかがわかりやすい。短歌の初心者にとっても優しい本になっていると思います。同日に発売された歌集の『銀河一族』も読みましたが、こちらは日本の歴史、たとえばロッキード事件のことを、台湾生まれなので、私はそんなに知らないんですよね。でも「落花生麻袋詰三匁しめて三億適正価格」という歌があって、そういうのが、すごく面白かったです。「落花生」って何だろうと思って、調べたんですよね。それで、ロッキード事件で、ピーナッツが隠語として使われていたことを知りました。
小佐野:李さんは本当に真面目なんですよね。僕の本にもマーカーを引いてすごく読み込んでくれていて、本当にありがとうございます。『銀河一族』に関しては、端的に言うと僕の生まれた家の歴史を書いています。今回、僕は、ある意味で、ちょっとルール破りというか新しいことをやらせてもらったと思っていて、短歌というのは、そのときの感情を記録するにはとても優れていると思うんですが、一方で、散文と比べると、事実を記録するのには向きません。けれど、『銀河一族』では、僕が自分の一族のことを内部からの目で綴っていったら、違う歴史のようなものが描けるのではないかと思ったんです。
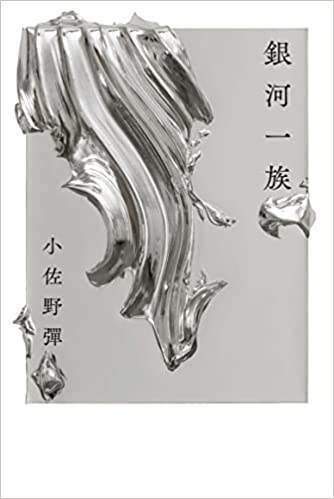
李:私は物語が好きなので、どうしても物語を求めてしまうところがあるんですよね。だから『僕は失くした恋しか歌えない』のほうが面白く読めました。
小佐野:『僕は失くした恋しか歌えない』は、散文の部分は中に出てくる短歌の長い詞書のつもりで書いている部分もありました。
李:私は短歌は書けないんですけど、小説に漢詩をちりばめてみたら、どうなるかなと思いました。実際、中国の古典小説では、そういうことを普通にやっていたんですよね。
小佐野:日本の古典の「伊勢物語」とかも歌物語ですし、「源氏物語」でも歌は主役級です。詩歌と散文というのは、今は綺麗に分かれていますけど、昔はグラデーションがあったんですよね。綺麗にしっかり分けられていなかった時代というのが多分、中華圏も日本も長かった。その時代の文学は麗しいものが多いですよね。
李:中国には四六駢儷体というものがあってですね、整ったリズムで書かれているけれども、言葉も凄く麗しいという、南北朝あたりの時代に流行っていたという文体です。
小佐野さんの今回の作品は、「アイコちゃん」という登場人物もすごく魅力的でした。青春小説っていいなーって素直に思いました。自分も書いてみたいなとも。

小佐野:ありがとうございます。「したたる落果」も、ある意味では青春小説だったと思うんですけど、ガチな青春小説に今回初めてチャレンジしたので。
李:アイコちゃんとハヤト、そして主人公のダン。主人公のダンはゲイであることを認識しはじめているけれども、それを認めたくないし、周囲にも気づかれないようにと、アイコちゃんとの関係をカモフラージュに使おうとする。一方で後輩のハヤトに心惹かれていく。不思議な均衡を保っていた三人の関係性が、徐々に崩れはじめる、そこが凄く良かった。でもおそらくこの部分は実話だと思ったので、良かったという言い方は失礼ではないかと、ためらうところもあるんですけれど。
「青春のあるべき姿」を手放したくないと固執する僕がいて、そのくだりのあとに短歌が入っていますよね。「まぼろしの春に溺れる少年が拾い集めてゆく嘘の種」と、この感じがね、すごくいいですよね。ある欠落感が散文と短歌とで、見事に描かれている。
小佐野:僕は、やはり恵まれた環境にいると思うんです。けれど、そういう環境にいることで逆に生きづらいとか、あるいは苦しいということが言いづらいというところもあって、もちろん食べるものがないとか、誰に助けを求めていいのかもわからないというような状況にいて、いままさに生命の危機に瀕しているような人と比べると僕なんかの感じていた苦しみは大したことがないように、どうしても思うんですけど。でも、「伊勢物語」の在原業平が子どもを失くしたりだとか、愛する人と結ばれなかったりして悲しんだように、どんな立場の人であっても感じる悲しみとか苦しみっていうのはあるのではないか、そういうものを感じてもらえたらというつもりで、この作品は書いたところがあります。
李:私は今回の作品を読んで、小佐野彈という作家に関しての理解が増したような気がしました。主人公のダンとアイコちゃん、そしてハヤトくんという三人の関係は、ひょっとしたら『車軸』のインスピレーションのもとになったのかなと思いました。『車軸』も、ゲイの潤、大学生の真奈美、ホストの聖也という三人の関係が軸になる話でした。
小佐野:たしかに変な三角関係というのは、僕の根底にあるものなのかもしれません。人間関係に関して、恋人やセフレとか、その関係性にみな名前をつけたがるじゃないですか。でも実際は、名前がつけられない人間関係ってすごく多いと思っていて。僕の彼氏というか、彼氏と呼んでいる人物は、バリバリのノンケで、僕の中では、そういう相手、パートナーを、どう呼べばいいのか、その関係には名前がつけられない。どういう関係までいけば恋人で、どこまでが友達なのか、関係性を形容する名称がわからないものがあって、僕と李さんの共通点としては、その何が正しいかわからない、あるいは名前をまだ持ってないものの名前を探しているという意味では近いものがあるのかなと、勝手に今、思いました。

李:そうですね。そのグラデーションとか揺らぎの部分を描くのが文学なんじゃないかと思います。そういう意味で、私達は近いのだと思います。
この世界は人間が考えている以上に複雑ですよね。そういう事を忘れないということは、すごく大事なのではないか。SNS上の意見の応酬をみていると、「彼ら」と「うちら」みたいな、敵か味方かという感じの見方をしがちです。でも本当はひとりひとり違う考え方を持っている。人には、いろんな側面があって、いろいろな考え方があって、複雑なんだということを忘れてはいけないと思います。
小佐野:最近、政治とかに「わかりやすさ」を求めますよね。でも「わかりやすさ」は危険でもあるわけですよね。実際は政治とか権力とか、社会もシステムも、あるいは、ひとりの人間もですけど、とても複雑でわかりにくいものです。すごく難しくて、わかりにくい。この難しさ、わかりにくさを受け入れていくために、文学というものがあるのではないかと思います。僕は大学院で経済思想史を学んでいました。近代経済学の父と言われるアダム・スミスの主著のひとつに『道徳感情論』という本がありますが、その中でアダム・スミスは、我々の暮らす近代の市民社会の根幹にあるのは、シンパシー=同感なのだと言っているんですね。我々は他者の気持ちを同感によって、つまり言い換えれば想像力ですよね、「こいつは痛いだろうな」あるいは「ここまでやったら傷つくだろうな」というようなことが想像できる力を本性として持っている、と。資本主義というと、弱肉強食というようなイメージがありますが、資本主義の思想的父であるアダム・スミスが描いている資本主義、市場経済の社会というのは、シンパシー=同感によって、自分の行動を適宜性、つまりちょうど良さですよね、そのちょうど良い範囲の中に収めるという社会なんです。やや性善説的ですけど、そういうふうに『道徳感情論』で言ってるんですよね。僕は、やっぱり、そこに真実があると思っている。我々がこの民主主義、そして資本主義市場経済の中で暮らしていく上においては、同感すること、つまり想像力は必要不可欠なのだと思う。それを養うために、僕たち、きっとこれからも物を書いていくんじゃないか。短歌は行間だらけで、空白だらけですけど、まさにその空白をうめていく想像力が必要になる。そういう想像力を養う一助に、自分の作品がなればいいなと思うことがあります。なんだか、ちょっと偉そうなことを言って、恐縮なんですけれど。
