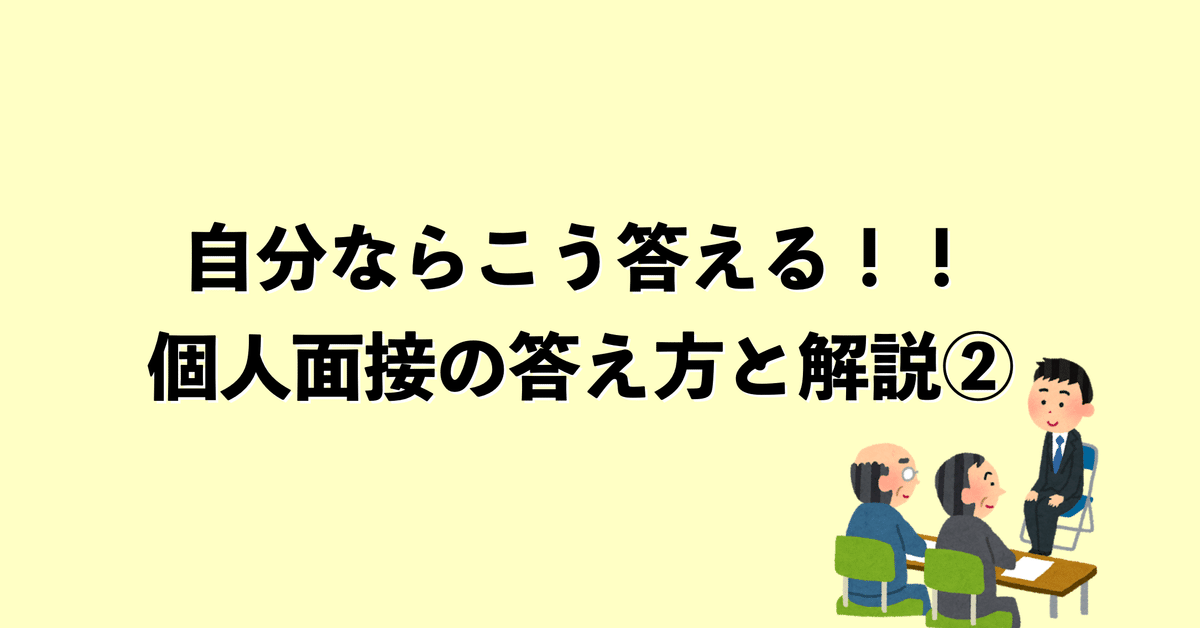
【教採対策】 個人面接答え方と解説 第2弾
2つの県の教採を一発合格した現職の教員が教採の個人面接に答えるならこう答える!というものを載せていこうと思います。
集団面接の対策もマガジンに載せてありますのでこちらも参考にしていただければ、より深い学びになると思います。集団面接の練習は個人面接でもすごく役に立ちました。質問に対して多角的な視点で物事見ることができるようになったからです。ぜひ、集団面接がないよという人も、集団面接対策にまとめた記事をご覧いただけると参考になるのではないかと思います。
第1弾はこちらから見れます。
質問が被っている場合がありますのでご了承ください。
⑴ 教育実習で楽しかったこと、辛かったこと、学んだことは何か?
楽しかったことは授業です。子どもたちの反応が新鮮で、思考の多様性があって楽しかったです。辛かったことは、手を出し合ったけんかをした生徒同士に対してどのように対応していくと良かったのか焦ってしまい、生徒の想いなどをきちんと聞くことができなかったことです。学んだことは、教材研究の大切さです。生徒が解決していきたいことが解決できるようにどんな教材を用いると良いか、どんな発問をすると意欲を掻き立てられるのかしっかりと考えて、これから授業をしていきたいです。
[解説]
自分はポジティブな質問に関してなるべく授業関係で、ネガティブな質問に関してはなるべく生徒指導関係の返しをすると決めていました。ポジティブな質問と言うのは、⑴でいうと”楽しかったこと””学んだこと”です。ネガティブな質問は”辛かったこと”です。なぜポジティブな方は、授業関係で進めて行くと決めたかというと、自分の教員として一番重要な資質能力として「授業力」を挙げているからです。授業が一番大切だからこそ、こんなことを学んだ、こんな授業をしていきたいなどの一番大切だと感じたその理由や将来の展望を語りやすくなります。だから、一貫してポジティブな質問に関しては授業の内容でできるだけ話すことを意識しています。ネガティブな質問に関しては、現状なかなか知らない現場のことを持っていくことで今後学んでいきたいという意欲を出すためにも生徒指導関係を挙げています・
⑵ 教員になって苦労することは何か?
教員の周りには教員・保護者・地域の人・子どもなど幅広くたくさんの人がいて、関わり合っています。その中で、皆が子どものためを思っているとは思いますが、価値観のズレや見方の違いが出てきてしまい、自分はどう行動するといいのか考えることに苦労するのではないかなと思っています。
[解説]
生徒指導にあたっては、教員同士でも少し考え方が異なる場合もあります。まして保護者の方とは大きく異なっていくることは当たり前です。しかし、児童生徒がより良く育ってほしいという思いは皆同じはずなので、その対応の仕方をみんなと共通理解を図っていく必要があります。実際、生徒指導をしていてもそこに苦労することはあります。
今回はざっくりした答え方にしておいて、この後に「生徒指導などで対応に困った時どうしますか?」などの質問を誘導させようという狙いがありました。しかし、実際はうまくいきませんでしたが、この作戦は使えるかもしれません(笑)
⑶ そのようなこと(⑵のこと)を実習中に体験したのですか?
実習中には体験はしていませんが、寮に住んでいて同じような経験は何度もありました。寮にも幅広い年齢層、考え方、価値観を持った人がいて、快適に生活しようとする中で意見の違いが生じてしまうことがあり、苦労したことがあります。しかし、きちんとみんなで話し合いをして共通理解を図っていけば解決できたこともあるので、教員になってからも全員できちんと話し合って困ったことを解決していきたいと思います。
[解説]
⑵の続きの質問ですが、こんなことを体験した。だけで終わってしまっては今後の展望が面接官に伝わりません。だからこそ、こういう体験のときにはこんな解決をしました。などの事実から、教員になったときにも同じようにこういう風に解決していきたいです。などの展望が言えると面接官へのアピールになると思います。
⑷ 教員の不祥事は聞いたことあるか?
滋賀でのわいせつ行為のニュースなどを見て、わいせつ行為が多く取り上げられている印象があります。その中で私は教師としての自覚のなさが不祥事に結びついていると考えました。少しの気の緩みが引き起こしてしまっていると思うので、子どもたちへの影響力を考え行動しなければならないと考えます。
[解説]
不祥事はよく聞かれる質問の一つです。採用者からすれば、完全にゼロにしていくことが求められるからです。教育に関するニュースもこのことを言っておけば間違い無いでしょう。この質問もそうですが、聞いたことあります。で終わっていては意味がないので、なぜ、不祥事が起きてしまうのか自分なりの考えを言えるといいと思います。
今回も誘導するための答え方になっています。教師としての自覚ってなんですか?と思わず聞きたくなる答え方です(笑)
⑸ 教師としての自覚とは何だと思いますか?
私は、「教師が与える影響力を常に考えること」が自覚だと思います。子どもにはもちろん、保護者や地域の方などにも大きな影響力を持っています。教師の一つ一つの言動が与える影響力は大きいので、責任があることを常に考えながら自分の言動が適切なのか考えていきたいと思います。
[解説]
この回はうまく誘導ができました。とにかく、不祥事は、自分の立場の自覚と、ストレス発散方法のどれかで解決策を言うことが一番簡単だと思います。「こんな対応をしていくので自分は不祥事を絶対におこしませんよ!」とアピールできればバッチリです。
⑹ 学校ボランティアを行ったきっかけと、参加してみてどうだったか?
きっかけは、教育実習が附属だけだったので、公立の中学校での学びがある方がより教員になったときの状況に似ているのかなと思い、ボランティアに参加しました。参加してみて、学級の中で静かに授業を聞いている生徒の中には学習について行けていない生徒が数人いることが分かり、学力の差が同じクラスの中でも大きく開いていることを知りました。自分はTTという形で入っていたのでそういった生徒に寄り添って学習を進めることができました。教師になり、自分が授業するときにも、授業について行けていない生徒をより早く察知し、1人1人の学力に応じた机間指導を心がけていきたいと思います。
[解説]
学校支援ボランティアというものがあったので、申し込みをして、活動をしました。実際自分が働くときには公立中学校を想定していたので、公立中学校の状況を知るということは非常に大切だと思い参加しました。参加したといっても5ヶ月くらいでした(笑)他の人は1年間ということなので少しズルでしたが参加したことには変わりないので(笑)
とにかく学習の差は大きいです。これが現状です。同じ授業をしてもクラスの1/3くらいはわかっていないと思った方がいいです。だからこそ、机間指導やできた子がスモールティーチャーとして教えてあげる活動が重要になってきます。ぜひ、そういった体験をしておくと面接のネタに使うことができますよ。
また、これも必ず最後に展望を言えるように心がけるといいと思います。
