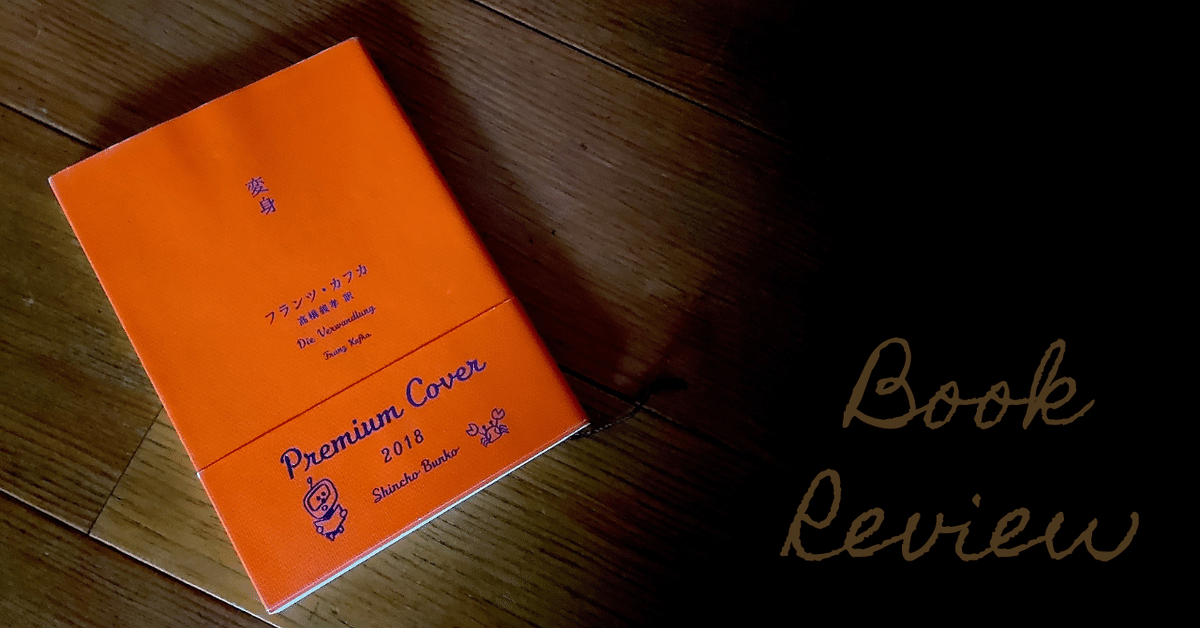
8books|フランツ・カフカ『変身』(1915年/高橋義孝訳)
知っているようで知らない名作を読む
「朝起きたら虫になっていた」ことでお馴染みのフランツ・カフカ『変身』。「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という川端康成『雪国』にしても「祇園精舎の鐘の声」の『平家物語』にしても、冒頭だけ知っていて読んだことのない物語は、たくさんありますよね。実際に読んでみると、こんなにも想像と違うものだと驚きました。
読む前は、虫に変身したグレーゴル・ザムザ氏が街に繰り出し、「なぜ嫌だと思いながら仕事に行くのか」「人間というものは理解し難い」などと虫の視点から人間の不条理を嘆く話だと思っていました。
しかし、ザムザ氏は家どころか自分の部屋からも満足に出ることができず、虫になったことで家族の理解を得られずに死んでしまいます。
難儀な仕事に精を出して両親を養い、妹を音楽学校に入れようと計画していたザムザ氏。大黒柱として一家を支える彼の行為は、実は家族の自主性を抑圧して、家に閉じ込めることになってしまったのではないか。
「モラハラ」という言葉の存在する現代的な解釈だろうとは思いつつ、そういった感想をもちました。
いまだ解明されない謎
解説を読むと、『変身』には父親との対立、役人と小説家の二重生活といった作家の私生活の反映を指摘できるものの、カフカ自身は『変身』について明言することは避けているとありました。
例えば、カフカは扉絵に虫の姿を登場させることに猛反対しました。私が読んだ1952年初版の高橋義孝訳では、ザムザ氏は「一匹の巨大な虫」になったと訳していますが、2015年の多和田葉子訳では「ばけもののようなウンゲツィーファー(生け贄にできないほど汚れた動物あるいは虫)」と、ドイツ語のUngezieferをそのままの意味で訳しています。
原典を読んでいないのでわかりかねますが、ムカデやネズミといった具体的な生物名では表現できない、得体の知れないものだと書かれているのです。
放送大学のラジオ(「世界文学への招待」という科目だったと思います)で知ったのですが、カフカは出版前に(友人に?)本作を読んで聴かせました。その時は時折プッと吹き出しながら読んでいたそうですが、書籍として印刷された作品を読んだところ、カフカの意図したものとは異なる印象になっていたというのです。
カフカとしては、ブラック・コメディーのつもりだったのでしょうか。
新潮文庫 「プレミアムカバー」
本書を手に取った理由は、もちろんストーリーが気になったからでもありますが、この素敵な装丁にもあります。毎年夏に出版される新潮文庫の「プレミアムカバー」は、単色に箔押しの施された特別装丁シリーズです。
むささび|本と美術と旅 さんの紹介記事↓
私の読む本は大きく重いことが多いので、電車で読もうとすると、鞄の中でも場所を取るし荷物も重くなってしまうのです。それと、あんまり変な本だと内容を他の乗客に知られるのが恥ずかしくて。
(言うて、その日のモチベーションに合わせて本を選ぶので、いつも重くて変な本を持って行くんですけど)
文庫本ならコンパクトで比較的薄いですし、プレミアムカバーならぱっと見で内容まではわかりません。それに小説なら繰り返し読めるので、荷物が多いとき用の本として購入しました。
表紙のザラザラとした質感やオレンジ色の美しい装丁は「本を読んでいる」感じがして、気分が高揚しますね。
ざっくり感想

この記事が参加している募集
よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートでミュージアムに行きまくります!
