
シン・短歌レッス123
王朝百首
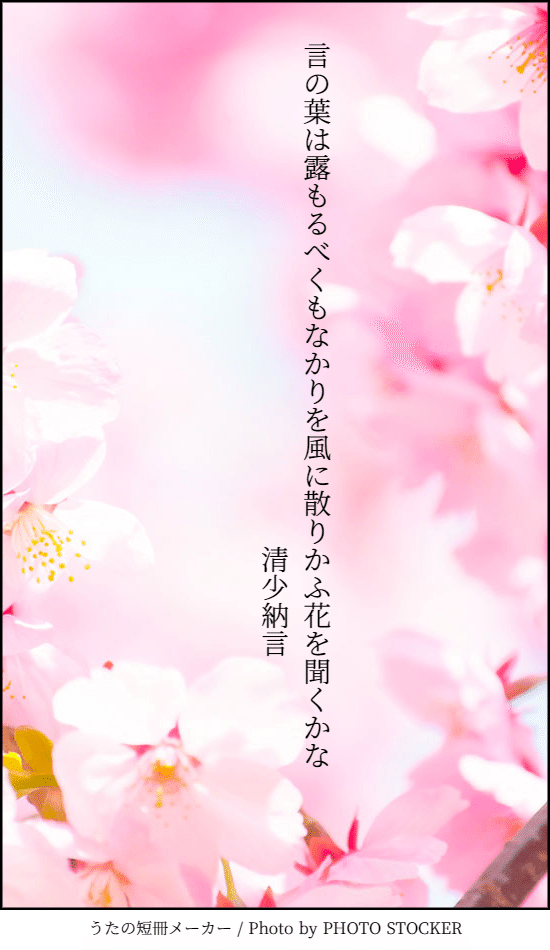
紀貫之の歌は情緒よりも理知的な部分があるという。それがあえて「水無き空に」とことわる部分であろうか?「なごり」は「名残」より「余波(なごり)」であるという。「天のさざ波」が「あった花」ではなく「失われた花」の幻想という部分は塚本邦雄らしい解釈か?つまり華やか日々を回想しているという情況なのだ。それが理知なる言葉で歌を構築していく紀貫之の言葉。
NHK短歌
吉川宏志さんと「実感的 表現力アップ」をめざす第3週、最終回のテーマは「批判するまなざし」。ゲストはノンフィクション作家の梯久美子さん。司会は尾崎世界観さん。
吉川宏志も今月で終わりだった。このぐらいの講義してくれると短歌も上達するような気がする。吉川さんは技術論だったよな。
今月はゲストが梯久美子だった。硫黄島の栗林中将の最期の軍人短歌。
国のため 重きつとめを 果たし得で 矢弾尽き果て 散るぞ悲しき
仇討たで 野辺には朽ちじ 吾は又 七度生まれて 矛を執らむぞ
醜草(しこくさ)の 島に蔓延るその時の 皇国の行手 一途に思う
「散るぞ悲しき」を政府が新聞発表で「散るぞ口惜しき」に改ざんして、その一言で意味が変わってしまったという。軍人の指揮官なるものはあくまでも軍隊を鼓舞しなければならないとされたが、国からは弾丸も供給されないで部下を無駄死にさせるしかない指揮官がいたという歴史的証言の歌。
<題・テーマ>川野里子さん「オノマトペを入れる」(テーマ)、俵万智さん「家族」(テーマ)
~3月18日(月) 午後1時 締め切り~
齋藤史
『記憶の茂み: 齋藤史歌集 和英対訳』から。「魚歌」。
白い手紙がとどいて明日は春となるうすいがらすも磨いて待たう 齋藤史
モダニズム短歌。「うすいがらす」から春の景色が透けて見えるよな。「白い手紙」の「白」はモダニズムの色か?
アクロバティックの踊り子たちは水の中で白い蛭になる夢ばかり見き 齋藤史
「白い蛭」という表現。蛭の悪のイメージから天使のようなイメージへ。「アクロバティック」が効いている。
飾られるショウ・ウインドウの花花はどうせきえちやうパステルで描く 齋藤史
「どうせきえちやう」という短歌では拙い口語体が「パステル」の華やかさを演出しているのか?窓辺の歌が多いのは外との境界なのか?
はとばまであんずの花が散つて来て船といふ船は白く塗られぬ 齋藤史
「白」はなんでも描ける希望の色なのかもしれない。舶来の外国船を見る波止場は行き止まり感ではなく、新たな出発の予感。
春はまことにはればれしくて四つ辻のお巡査(まはり)さんも笛をひびかす 齋藤史
「春」は青春短歌で、巡査もおまはりさんと成る。そこに危険は感じられない。むしろすべてが晴れ渡っていて見通しのいい世界を迎えるかのようだ。
指先にセント・エルモの火をともし霧ふかき日を人に交じれり 齋藤史
「セント・エルモの火」は海外文学の航海小説からか(『白鯨』とか)。そういう話題をするモダニストたちと交流か?
せめて苦悩の美しくあれ爪に染む煙草の脂を幾度ぬぐふ 齋藤史
煙草の脂まみれの指も苦悩として美しいのか?
山の手町がさくらの花に霞む日にわが旅行切符切られたるなれ 齋藤史
卒業旅行とか春の観光旅行なんだろうな。山の手のお嬢さんか?
定住の家をもたねば朝に夜にシシリイの薔薇やマジョルカの花 齋藤史
この青春讃歌だけじゃないんだよな。それ以後の暗黒の歴史があるから余計に儚く明るさに満ちているのか?
西行
辻邦生『西行花伝』
「七の帖」西行が自身を語る出家の理由。
捨てしをりの 心をさらに 改めて 見る世の人に 別れ果てなん 西行
出家の辛さを歌っているのだが、泣いてすがる娘を足で蹴り上げたという伝承の元になった歌だろうか?『西行花伝』にはそのシーンは出てこない。この歌から導かれてくる話は女院(藤原璋子)との愛欲と彼女の立場の問題で鳥羽帝に新后に藤原泰子が来て、女院の立場が危うくなるのだ。このへんの天皇家のドロドロした関係性はわかりにくい。鳥羽帝と後鳥羽院は同一人物なのか?違うんだ。
惜しむとて 惜しまれぬべき この世かは 身を捨ててこそ 身を助けめ 西行
鳥羽院に仕えていた西行は歌の力で鳥羽院を支えたいということなのだが、それは現実世界は幻影みたいなものだから、確かな言葉の力(真言?)で歌として土台を作るのだと言っているのだが、出家したあとも性欲は断ち切れないでいるただの歌僧としての西行だと思ってしまう。
散るを見で 帰る心や 桜花 昔にかはる しるしなるらん 西行
皇族の歌会の上座に招かれてありがたやみたいな。そこで藤原俊成と知り合うのだった。
花に染む 心のいかで 残りけん 捨て果ててきと 思ふわが身に 西行
「八の帖」女院(待賢門院璋子)の凋落。
知らざりき 雲居のよそに 見し月の かげを袂に 宿すべしとは 西行
藤原清隆が女院御所別当になると、女院が帝の妃を呪いをかけていると噂がひろがり、女院の立場が悪くなる。女院は引きこもって読経などの日々を過ごす。西行はかつての花の宴での一夜を思い出すのだった。
(女院)
今日ぞ知る 思い出でよと ちぎりしは 忘れんとての 情なりけり
(西行)
おもかげの 忘れるまじき 別れかな 名残を人の 月にとどめて
西行は女院が忘れがたく、出家したのも女院との関係を断ち切る為だったが思うように行かなかった。
恋しさや 思い弱ると ながむれば いとど心を くだく月影 西行
拘束・リズム・散文
『現代にとって短歌とはなにか』から批評、平出隆「拘束・リズム・散文」。
平出隆が現代詩人側から定形詩(俳句・短歌)を論じる。
その昔、定形の短歌や俳句に対して自由詩と言っていたのは定形にこだわらなかったからだ。ただその枷をはずして本当に自由に表現できるのかというそうでもないと言う。自由詩には自由詩なりの枷があるのだ。それは現代性ということなのか?今では現代詩と呼ばれていたりする。短歌でも俳句でも現代のものであるのに、なにゆえ詩だけがそうなのか?やっぱそこにモダニズムの問題があるのではないか?
芥川龍之介は、古典の韻文はその詩形が存在していて、古典の詩を読むことはその韻文の詩形を呼び覚ますことであるから興味深く、さらにそれを新たに目覚めさせることはなおさらである、というようなことを言っている。芥川の文学が古典から近代文学を照らしたものだからだろうか?また芥川は俳句にも興味を示した。
その一方、詩人の側から萩原朔太郎は『詩の原理』でポー『詩論』に影響を受けて西欧の象徴詩であるボードレールやヴァレリーから多く得ようとしていた。
「三種の詩器」という言葉があるという。「詩」「俳句」「短歌」の敷居が語られて、それらの断絶が言われる。吉本隆明はその断絶を、単なる差異ではなく近代の断層(モダニズム問題か?)と見た。このへんは「言語にとって美とはなにか」とか詩論に詳しいと思うのだが忘れてしまった。日本人論でもあるのかな?これは課題ということで先に進む。
現代短歌史
篠弘『現代短歌史Ⅱ前衛短歌の時代』から「岡井隆の挑戦」。
「アララギ」から短歌を始めた岡井隆は、「アララギ」の主張するリアリズムということにこだわり続ける。それは初期の短歌から岡井隆はモノローグ的な世界観をしめしており、岡井隆は学生短歌運動に関わっていく。そして、そのことが短歌を作ることだけではなく、批評家として先人たちの短歌を考えていくのだ。
「『写生』をめぐる断片」では、リアリズムが写生として生きるのは写実という社会的立場によって写生するという。そこに当時の社会状況の中で変化していく運動を「アララギ」のなかでも見出そうとするのだ。
しかし、そのリアリズムも「アララギ」の狭い意味での写生とは相容れなくなってくる。そのときに当時新しい短歌として登場した塚本邦雄と出会うのだった。それは短歌のモダニズム(現代性)の問題として塚本邦夫を無視出来ないと知るのであった。
『短歌研究 2024年3月号』作品
竹中優子「青い箱」
きなこもち八百屋の隅に売られおり正月の餅焼かれて並ぶ
生活詠か。八百屋で餅を焼くというのは珍しい光景だ。それ以外に読みどころはないよな。正月の風習か?
たかちゃん、とお店の人はよばれつつたかちゃんの子がティッシュをくれる
内輪短歌だよな。模範的定形か?
脇山口、3番のバスに乗るように友達のメール音なく届く
固有名は内輪でしか通用しない。脇山口ってどこだよ!福岡だった。ネットで検索すればバス停まで出てくる不思議。
仕事辞めればもう誰からも聞かれない お正月どうして過ごすのって
ちょっと社会詠っぽい歌が出てきた。
団地とは死のカタログと友は言う 人間は割と焼死をすると
その前に母が死んだという短歌があり、それと焼死は繋がるのか?意味深だが、深いところはよくわからない。
小説を書くのは口だけになる どちらかが黙ればどちらかが話す
これはよくわからんな。彼女の小説がということなのだろう。それに比べて短歌は沈黙が多いのか?彼女の小説を読みたいと思うが、彼女詩も書いているのだった。そっちの方が気になるかもしれない。
廊下から花火を眺める隣人を見かけた夏の 椅子出して何かを噛んで
もう花火の季節かよと思ったら回想シーンだった。
歯磨きを外でするのにはまっていて冬の団地のドアひょいっと越える
「ひょいっと越える」がいいかな。口語短歌なのか。
会った日の最後の弁当箱を見た セールで1.000円の青い箱
「青い箱」の意味が最後までわからなかった。母親が買った弁当箱というのかな?今日は一人だけだな。
映画短歌
今日は、『ボブ・マーリー ラスト・ライブ・イン・ジャ マイカ レゲエ・サンスプラッシュ』力を抜いてただレゲエのリズムに身を任す。
本歌
アクロバティックの踊り子たちは水の中で白い蛭になる夢ばかり見き 齋藤史
映画短歌
ボブはレゲエ妻子もレゲエレレのレゲエジャマイカの木々と揺れてレゲエ やどかり
