
シン・短歌レッス125
王朝百首
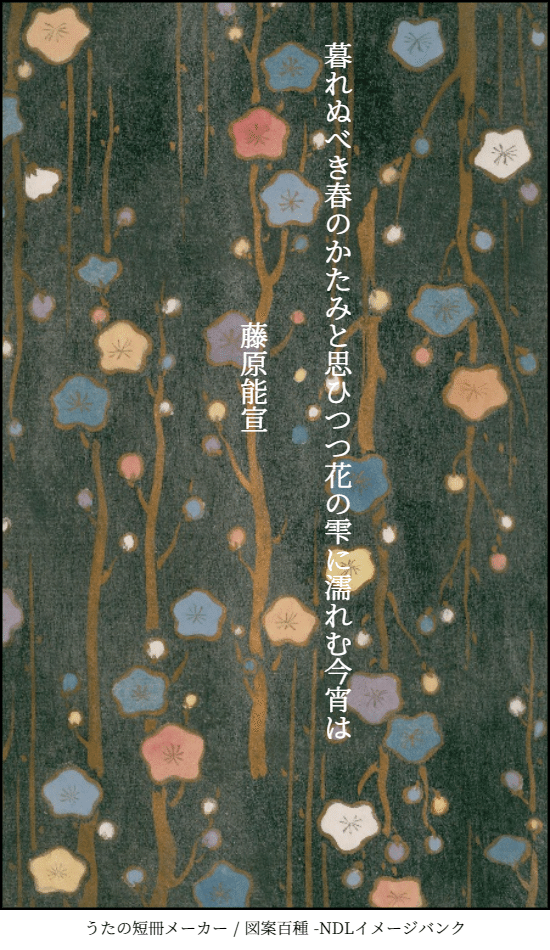
暮れぬべき春のかたみと思ひつつ花の雫に濡れむ今宵は 藤原能宣
「やなぎさくら」は柳とさくらなのか?枝垂れ桜を「やなぎさくら」と称しているのか、よくわからないが、塚本邦雄は詩でやなぎとさくらをそれぞれ別の色に喩えているから柳と桜なのだろう。素性法師という風狂な人だから桜より柳が最初なのかとも思う。どちらも街路樹としてよりもやはり庭木なんだろうな。広大な宮廷の庭がにしきなりけるというような。
齋藤史
梯久美子『この父ありて』から。
人の運命(さだめ)過ぎし思へばいしぶみをめぐるわが身の何か雫す
史が1980年に父の斎藤瀏と暗殺された渡辺錠太郎の一緒に建てられた石碑を見て石碑とは違う感情の歌を詠んでいた。石碑の歌は、
ゆくすゑを知らねば渡邉・齋藤の名もつらねたり一つの碑の面に
とある。実際に史は暗殺された渡辺和子に一度も会ってはいなかった。史の本音と建前が伺われる歌だ。
暴力のかくうつしき世に住みてひねもすうたふわが子守うた
この短歌を作ったときに史は妊娠していた。後に史は「暴力が美しいはずはありません」と明言しているのである。作者と作中人物(主体)とが虚構の中で違っているのは小説世界では当たり前のことなのだが、短歌では作中主体と作者が同一されがちなのだ。少なくとも齋藤史はモダニズムを生きた歌人なのである。そして以下の歌も残していた。
正史見事につくられてゐて物陰に生きたる人のいのち伝へず
史の二面性を見ていくと面白い歌があるのだ。幼馴染の栗原中尉を歌ったうたも、
額の真中に弾丸をうけたるおもかげの立居に憑きて夏のおどろや
北蝦夷の古きアイヌのたたかひの矢の根など愛する少年なりき
先の歌は公の歌のような感じだが私的な歌は後者だろう。史と栗原は北海道の広大な大地にアイヌが残した矢じりなどを探したという。史が栗原の思い出は後者なのだ。
ひそかに訣別(わかれ)の言の伝はりし頃はうつつの人ならざりし
安藤と最後にあった時に史は弾丸を貰ったという。矢じりが弾丸になったのだ。
白きうさぎ雪の山より出でて来て殺されたれば眼を開き居り
その安藤中尉を詠んだ歌だと思われるが、史の代表作になっている。
みずからの神を捨てたる君主にて少し猫背の老人なりき
猫背の老人は父を詠んだものである。父の最後を看取り、そのときのもう一つの歌。
ある日より現神(あらひとがみ)は人間(ひと)になりたまひ年号長く長く昭和
史はその後、歌会始の招人になり天皇と談笑する。
「おかしな男です」といふほかはなし天皇が和(にこ)やかに父の名を言ひませり
史は生前に出した歌集は十一冊にもなるのだ。「子守うた」と言いながら止めることはなかったのだ。
心つくしてうたを憎めよその傷の痛みすなわち花となるまで
西行
辻邦生『西行花伝』
「十一の帖」
女院が亡くなって陸奥一人旅にでる西行なのだが、無目的なわけではなかった。奥州藤原氏の藤原秀衡に会いにいくのだった。
都出でて 逢坂超えし をりまでは 心かすめし 白川の関
そこで一人の自害しよとする女を助けるのだが、また西行の助平心が起きたというわけでもなかった。
白川の 関屋を月の もる影は 人の心を 留むるなりけり
その女の夫は清原通季(みちすえ)という武官(国衙使)であり藤原氏の領地を攻めてきたのであった。その時に西行が幼少の頃に出会った氷見三郎と諍いになり討たれたという。西行の従兄弟である佐藤憲康が加勢に行く前に病死した因縁があったのだ。そんな武力の時代よりも藤原秀衡は西行のように出家して歌僧にでもなりたいと西行に告げるのであった。
年月を いかでわが身に おくりけん 昨日の人も 今日はなき世に
西行の旅の動画を見つけた。すでに後半に入っているが。面白いです。
〈座談会〉「日本人・こころ・恋歌」
『短歌と日本人Ⅱ 日本的感性と短歌』から「座談会「日本人・こころ・恋歌」…阿久悠・夏石番矢・俵万智・佐佐木幸綱」。歌人二人に俳人と作詞家の対談。阿久悠が入っているから面白いのだが、最近の若い奴らはという話になりがちだった。
阿久悠が言うには最近の歌にはロックのようなフォルテでがなり立てる歌が多いがピアニシモの歌がないという。なるほどそれは言えているかも。ピアニシモで歌う歌手って誰かいるだろうかと思うと八代亜紀とか演歌系になるのかな。中森明菜はそうかもしれないな。
中森明菜のイメージが少女Aの不良ぶっている女子からマッチとすったもんだで捨てられたからそのへんの女心がでるのかな。この当時に出てきたのはそれとは逆の元気のいい女の子の歌だったような。
その反動として俵万智の『サラダ記念日』が中年男に人気だったというのもわかるような気がする。一巻で富岡多恵子が『サラダ記念日』に文句を言っていたのは女歌の部分であったようだ。俵万智はあまり自覚してないが、佐佐木幸綱との関係は教授と女子学生という師弟関係なのだ。そう言えば男歌とか女歌をいい出したのこの頃かもしれない。
俳句には男歌とか女歌という明確な区別がないのは、私を滅私するからか。でも台所俳句というのがあるな。そうか虚子が育てようとしたのは女俳句の世界だったのかもしれない。
以外にも中世の和歌にはあまり男歌女歌を区別することはなかったという。男も女に成り代わったり、悲しみの感情を発露したからか?そうだ、天皇は恋の歌を歌うときは女になると言っていたのはそういうことかもしれない。男がつくる女歌は男のイメージだからな。今の学生に男の俳句を作れというと女子高生ばかりになるというのが興味深い。おたくアニメでもほとんどそういう世界だった。
ただテレサ・テンとか都はるみは女歌を歌っていたのかもしれない。男歌とか女歌とか短歌で出てきたときは驚いたのだが、それは演歌には確かにあったな。坂本冬美は男歌が特異だとか。そのイメージを変えたのが「夜桜お七」なのだが、女歌でも力強い歌なんだと思う。女歌の演歌はやはり八代亜紀なのかな。だからトラックドライバーに好かれる?
都はるみは気に入らない歌だと普段着の衣装で出てくるというのが面白い。高い着物を着て決めているときは、歌も気に入ってやる気があるのだとか。演歌歌手ってそうかもしれないな。ステージ衣装に金かけるのは紅白とかあるからな。
現代短歌史
篠弘『現代短歌史Ⅱ前衛短歌の時代』から「現代詩との架橋」。大岡信や吉本隆明などが現代詩の立場から現代短歌への方法論への疑問を投げかけたことにより現代短歌は揺さぶられていく。大岡信は俳句へも投げかけたのだが、当事者以外は我関せずという態度で(大岡信・金子兜太の「季語」に対しての議論)、伝統俳句(現代俳句はとしたほうがいいのか)は素通りしていく。その態度の違いが塚本邦雄や岡井隆の前衛短歌運動が継続していく現代短歌と現代俳句の違いだろうか?
塚本邦雄は現代詩人との討論によって、「遁走曲」50首を発表する。それは短歌が円環的伝統性からの脱出を大岡信との討論によって、自身の短歌で答えた形であった。
突風に生卵割れ かつてのかく撃ちぬかれたる兵士の眼 塚本邦雄
少女死するまで炎天の縄跳びのみづからの円駆けぬけられぬ
遁走曲(フーガ)われのうちにひびかふ 初夏の涸れしプールの底あゆみ来て
塚本の転身を受けて岡井隆も同じ「短歌研究」にハンガリー動乱をモチーフとした連歌を詠んでいる。
うつうつと地平をうつる雲ありてその紅はいずくへ搬(はこ)ぶ
どの論理も〈戦後〉を生きて肉厚き故しずかなる党をあなどる
市民兵に肩を並べてためらわずよびかくる言葉もてりや 妻よ
また同時期の「ナショナリストの生誕」三十二首を「短歌」に発表したことも見逃すことできない問題作だという。
列島のすべての井戸は凍らんとして歌いおりふかき地下から
帝国の黄昏(こうこん) 無辜の白鳥を追いて北方の沼鎖(とざ)さしむ
つぎつぎに大陸に立ちあがりゆく諸声とおきわが揺籃歌
当時の批評でそれは短歌よりも現代詩のようだ(短歌のシンフォニー)と捉えられていた。また連歌という形式は、新興俳句が見出していた連句とも共通しているのかもしれないのは、塚本邦雄は昭和初期の新興俳句運動へ言及している。そのことを通過してない新興短歌の問題点(敗北史)を炙り出すのだった。
寺山修司も「開かれた本」三十首、「ぼくらの理由」五十首という問題作を発表している。
失ないし言葉がみんな生きるときゆうやけており種子も破片も
猟銃を撃ちたるあとの青空にさむざむとわが影うかびおり
外套のままかがまりて浜の焚火見ており彼も遁れてきしか
『短歌研究 2024年3月号』作品
石井辰彦「トミスへの旅 カナンからの旅」作品五十首
この短歌連作は現代詩アプローチ的なものかもしれない。かなり難解短歌である。まず題名の固有名詞がどこなのか、よくわからない。
トミスへの旅
大望(タイマウ)の缺片(かけら)を胸に鐘の鳴る(暮れ泥む)キーウを出で立ちぬ
北風はバビン・ヤルから。精神を病んで、肉體(からだ)は衰へ果てて
潮風は此處(ここ)に吹かねど思ひ遣る永劫の失意オウィディウス
繰り返し観た。港へと傾(なだ)れ込むオデーサの(階段の)惨事は
国境を超えれば師の坐(いま)すトミス。詩書四巻を手挟み、征(ゆ)かな
トミスがどこなのか場所がわからないが?ウクライナなのかな。歌われていることはウクライナだとは思うのだが、難解歌。旧字や旧仮名遣い派なのでアップするのも苦労する(旧字にしてないところあり)。
下士官と看護師のバラッド
前線を放れた兵に血の薫蕕(におひ)──。塹壕は硝煙に咽(む)せてゐて
死は休息(いこひ)、生は戦闘(たたかひ)。戒兵(ジュウヘイ)は危疑(キギ)無く擇ぶ、苦難の生を
迷彩の※を掻き分け看護師が押す、血まみれの※※車(ストレッチャー)を
看護師の手が下士官の手に触れる。夜の外気を雷が打つ
パソコンでは出しにくい(漢字が読めない)は※にした。なんでこういう漢字を使うのか?特殊漢字と言っていいかも。伝えられないもどかしさを感じてしまう。内容はガザとかの戦争地域を歌った社会詠だと思うのだが。
発熱の夏
悪疫の先陣として来たと云ふ。全ての河の涸れる季節が
この夏の徒(た々)ならざるに潟湖(ラグーン)に巨船(忍びやかに)投錨(トウベウ)す
高熱に焼かれて死なむ!後陣の世誉(ほまれ)に遺して
生者(シャウジャ)なほしとゞに汗す。忘却(レーテー)の流れも煮え朝まだき
難解漢字や旧字が難しいのでここまで。ガザとかウクライナの戦争詠なんだと思うが読むのに苦労する。伝えるのはなお苦痛。まさに塚本邦雄タイプの現代詩的短歌の力作なんだろうと思うが、こういうのは読み手を選ぶよな。
映画短歌
『ゴールデン・ボーイ』
本歌。今日も齋藤史の短歌。
人の運命(さだめ)過ぎし思へばいしぶみをめぐるわが身の何か雫す
サイコパス戦い過ぎて思へば殺人(コロシ)は無益 罪だけ残る やどかり
今日はあまり出来が良くないのは難解短歌に疲れてしまった。そうだ。歌会の作品が出来てなかった。今回は無理かもしれない。あと三日だもんな。
