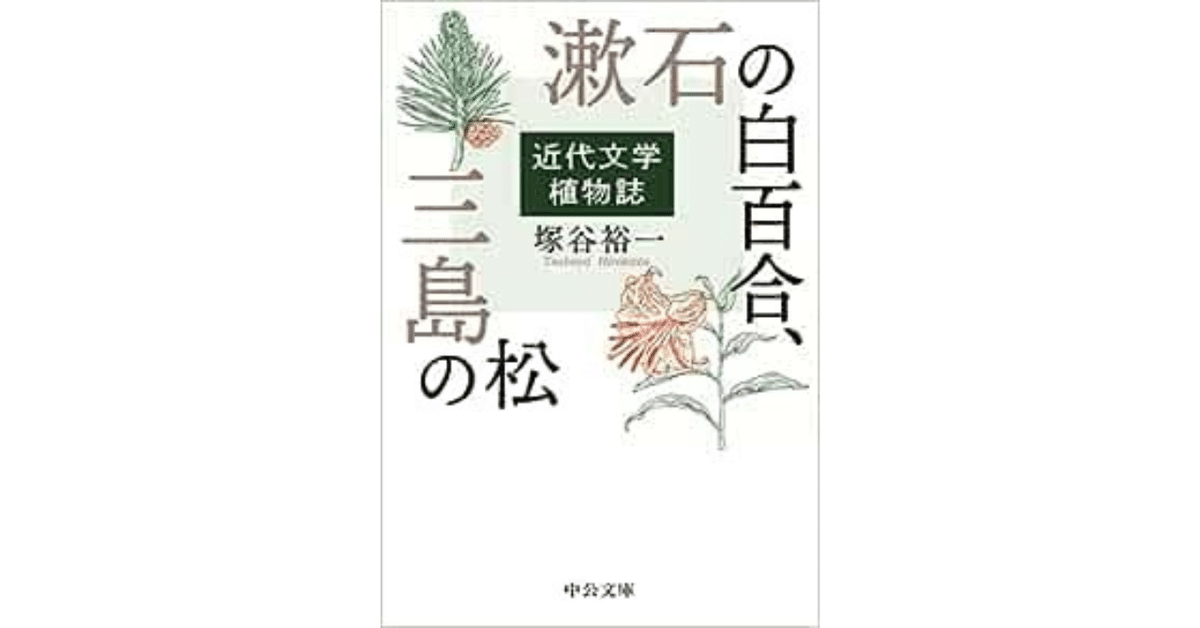
植物学者から見た文学の話
『漱石の白百合、三島の松-近代文学植物誌』塚谷 裕一(中公文庫)
漱石の『それから』に登場する白百合はテッポウユリかヤマユリか。植物オンチと言われた三島由紀夫の卓越した草木の描写を挙げてその汚名をそそぐ。鏡花、芥川、安部公房ら、広大な文学作品の森に息づく草花を植物学者が観察。新たな視点で近代文学を読み解く。
『漱石の白くない白百合』を改題
〈解説〉大岡玲
(目次)
Ⅰ
漱石の白くない白百合/描かれた山百合の謎/『金色夜叉』の山百合/白百合再考
Ⅱ
『虞美人草』の花々/朝顔と漱石/毒草を活けた水を飲む事/泉鏡花描く紅茸/「ごんごんごま」とは?/ごんごんごまの本名/クロユリ登場/芥川の心象に生えた植物
Ⅲ
三島由紀夫と松の木の逸話/再説三島と松の木の逸話/洋蘭今昔/志賀直哉と藤の巻き方/スイートピーは悲しみをのせて/『デンドロカカリヤ』異聞
Ⅳ
関東大震災でカビた街/小説とチフスの役割/小石川植物園を読む/三四郎池の植物散歩
あとがき/文庫版あとがき/〈解説〉大岡玲
Ⅰ白百合
夏目漱石の小説では『それから』が一番好きだと思ったのは、三千代の白百合の花のイメージにあったのかもしれない。
まず著者は『それから』白百合は鉄砲百合ではなく、匂いが強いことから山百合とする。それは尾崎紅葉、泉鏡花から受け継いだ山百合を白百合とする日本文学の花を女に見立てる伝承だと明らかにしていく。尾崎紅葉の『金色夜叉』の貫一を虜にする魔性の女お宮が、山百合でそれを白百合と描いているという。またその百合の花の芳香な匂いは精神を乱さずにはいられない匂いとして描写される。それは漱石ならば代助の好きな野草である鈴蘭の香りを駆逐する匂いなのだ。
ただ二回目の考察では、この山百合のイメージを西欧のマドンナ・リリーとして、それは聖女のイメージなのだけど、西欧文化の象徴である花は、日本の野草のイメージを駆逐するものと描かれていたとする。しかし、それは最初は三千代が持ってきたのは鉄砲百合で純潔の花のイメージとしてであった。二回目に持ってきたのが山百合であり、その変化に漱石の描写の的確さを称賛するのである。
そこまでは詠んでいなかったのだが、百合の花のシーンはなんとなくイメージしていたような。山百合の三千代の姿に納得するのであった。
Ⅱ虞美人草
漱石『虞美人草』は美人だけど愚かな女に喩えられるが、その題名になっているのは日本画、酒井抱一の屏風の『虞美人草』である。それはそれまで否定してきた藤尾の花の喩え(赤い薔薇とか)から遠く、それほど嫌っていないのではないかということだ。「虞美人」は「四面楚歌」でも有名な中国の古典『項羽垓下の歌』(『覇王別姫』でも有名)から来ている。藤尾のクレオパトラのイメージだというが、中国の古典の意味だと少し違ってくるような。
他に昔の作家は植物について詳しい描写が多いがその中ですぐれているのが泉鏡花だという。花だけではなく茸も描写する(それも食べ物ではなく)「紅茸」(毒はなく食べても美味しいという)は美しい茸として描写される。それを毒のあると描写するので「ベニテングダケ」なのではないかと考えるが「紅茸」の描写は正確だという。赤い茸に毒があるという迷信を信じたのではないかという。
その他にも芥川の植物描写についてなど。植物描写が詳しいという。
Ⅲ松
三島由紀夫の松の逸話でドナルド・キーンが同行取材していたときに、植木屋に松の名前を尋ね、それは雌松だと答えので、雄松はないのと聞いたという。それで三島由紀夫は松も知らなかったという逸話が出来たが、三島由紀夫の作品を調べるとそんなことはなく描写に詳しい。ただ花鳥諷詠というような文学的描写(『古今集』のような決まりきった描写)はせずに、三島独自の観察眼で描写していたという。例えば桜は雲のように全体像で描かれるが、三島は桜の花弁の中心まで精密に描いていたという。三島は日本的決まりきった描写はせずに観察眼に徹していたという。
その三島が描写で手本にしたのが志賀直哉で彼も動植物の描写が素晴らしい小説を残している。植物の描写が出来るかどうかで作家の力量がわかるという。変わり種としては安部公房の「デンドロカカリヤ」。それは小石川植物園の木を描写したようで、自然界にあるもの(日本では小笠原諸島にある「ワダンノキ」として知られている)とは違っているという。
Ⅳ黴
関東大震災の後に以上に繁殖した黴について、それは大火災のあと発生する(実際には60℃ぐらいで)黴を調べて、東京大空襲でも発生していたのではないか(これは目撃談があった)とか江戸の大火事でも発生した(そういう根源が生き続けている)メカニズムを推測する。赤カビの一種だそうだが特殊な黴で60℃ぐらいならないと発生しないという。
海外旅行から帰って友人がチフスに感染したことから日本の小説を調べるとチフスが登場してくる小説が実に多いという(そういえば感染症の文学の本を読んだ時にスペイン風邪はないのかと読んでみたらチフスばかりだった記憶がある)。
チフスに作家が惹かれれるのは、その突然死の悲劇であり例えば結核も文学的テーマとして良く出てくる病気である。現在はチフスは根絶されて、それに変わった高度成長期らしく交通事故に取って代わられたとか。いや、癌があったと思うのはスーザン・ソンタグ『意味としての病』を読めばわかる。
泉鏡花『外科室』から小石川植物園が舞台となったという後半部を紹介しながら、小石川植物園は他にも出てくる文学を紹介する。先程あげた安部公房『デンドロカカリヤ』も。その他にも漱石『三四郎』では三四郎池の植物散歩など文学には植物は良く描写されているが、最近の小説では少ないという。植物園に行って植物の出てくる作品を読みたくなってくる好エッセイだ。
