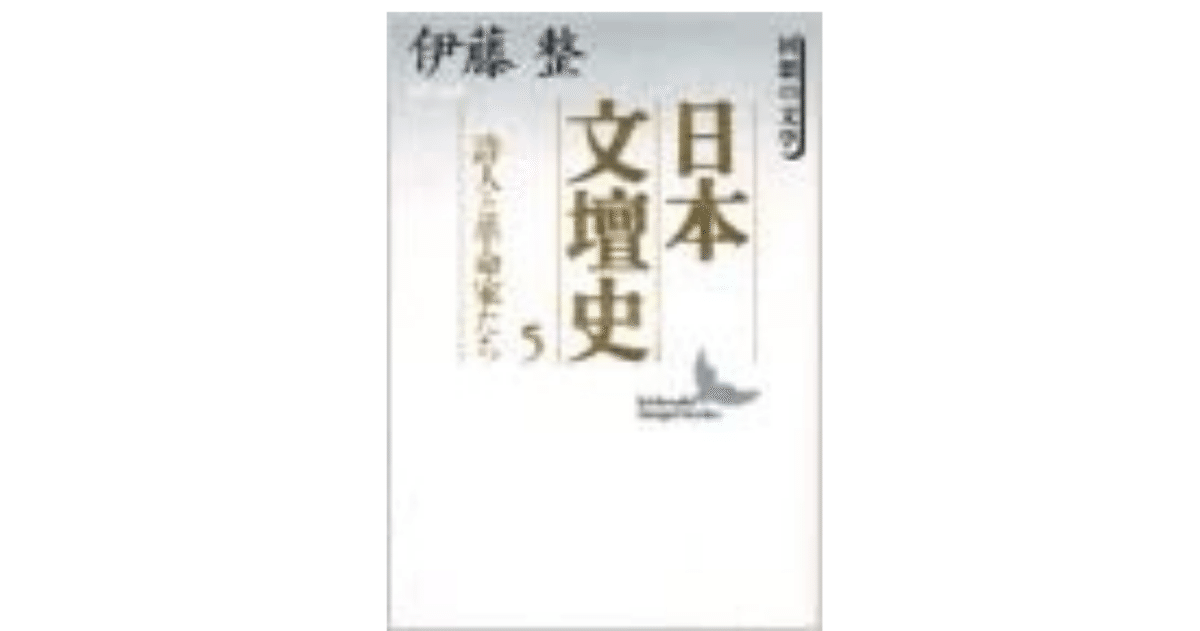
詩人と革命家と女たちと補足するべきだな。
『日本文壇史5 詩人と革命家たち』伊藤整 (講談社文芸文庫)
既成の文壇に独歩、子規らの鮮烈な文学革新足尾鉱毒事件が社会問題となる中、中心的文壇の外で明治31年の子規の短歌革新等、日本文学の根本的改革始まる。明治33年蘆花『不如帰』刊行、寛「明星」発刊
たまたま古本屋で伊藤整『日本文壇史』を見つけたので読んでみた。『日本文壇史』は、高橋源一郎『日本文学盛衰史』の旧約版みたいな位置だろうか。全24巻。今では忘れさられた日本文学の『失われた時を求めて』だろうか?伊藤整はジョイスやロレンス『チャタレイ夫人の恋人』を翻訳した人なのだ。チャタレイ裁判や「純文学論争」が有名で本人が書いたものはあまり読まれなかったのかもしれない。
しかしこの『日本文壇史』元ネタの宝庫というか、様々な文学者の顔が時代と共に現れてくる。この巻は、「詩人と革命家たち」とされているので小説家だけではなく、詩人や俳人も登場してくる巻である。がその中で誰が主役ということでもない。あえて言えば明治三十年(1897年)から明治三十三年(1900年)の時代が主役とも言える。その中で後の「大逆事件」の首謀者とされる幸徳秋水が最初に描かれている。「足尾鉱山事件」の社会的変質。その中で中江兆民らの政治運動の流れ、その弟子が幸徳秋水であった。
幸徳秋水も一つの時代の顔であり、すべてではない。「大逆事件」そのものも様々な思惑を持った文学者の顔があるのであり、それを「大逆事件」と一つの事件でくくってしまったための悲劇なのだ。まして幸徳秋水は主犯でも実行犯でもなく冤罪だった。
明治30年は政治と文学が革命ということで接近していく。黒岩涙香の『萬朝報(よろずちょうほう)』に幸徳秋水や堺利彦の記者がいた。彼らはのちに『平民社』を立ち上げる。
詩人では、島崎藤村が『若菜集』を出すが詩だけでは食べて行けず小説を発表するが酷評されて、音楽学校に入学する。そこで滝廉太郎と知り合い、唱歌を相談されて土井晩翠を紹介して『荒城の月』が生まれた。柳田国男(詩人のペンネームは松岡国男なんで松岡と出てくる。最初誰?と思ってしまった)との「椰子の実」エピソード。
明治31年、二葉亭四迷がロシアに渡る前にツルゲーネフの短編を翻訳した『あいびき』が発表され、それに刺激を受けた国木田独歩が『武蔵野』を発表。
自然な微細な変化やその美しい現れを、人間の動きとの対比において描き、人間が自然の中で自己の存在を意識する瞬間を鋭くとらえていた。その明快さ、簡素さにおいて、それは日本語の文章表現の改革であった。(伊藤整『日本文壇史5 詩人と革命家たち』)
この時代全盛期は、尾崎紅葉の硯友社だった。まだ文語体の美文調。ただ紅葉『金色夜叉』は会話は言文一致で、そのセリフが大受けだったと。
「来年の今月今夜は、貫一は何処(どこ)でこの月をみるのだか!再来年の今月今夜…十年後の今月今夜…一生を通して僕は今月今夜を忘れん、忘れるものか、死んでも僕は忘れんよ!可以下、宮さん、一月の十七日だ。来年の今月今夜になったならば、ぼくの涙で必ず月は雲らして見せるから、月が…月が…月が…曇ったらば、宮さん、貫一は何処かでお前を恨んで、今夜のやうに泣いていると思ってくくれ」(同書、尾崎紅葉『金色夜叉』より)
そして、貫一がお宮を足蹴にしていう。
「宮、おのれ、おのれ姦婦、やい! 貴様のな、心変をしたばかりに間貫一の男一匹はな、……」(同書)
裏を返せば、この時代は物言う女性が出てきたということなのです。尾崎紅葉の硯友社は旧世代ということで、それを変えて行ったのが国木田独歩の自然主義文学だった。
そして、この頃は新聞小説全盛時代。尾崎紅葉は「読売新聞」。後に出てくる夏目漱石は「朝日新聞」。そうした中央の新聞に載るのは、大作家だけのようで、多くの作家は都落ちして地方紙で記者などをしていた。夢野久作も地方紙でスキャンダル記事を書く記者だった。また新聞社が作家を囲いこむことで給料を払っていた。
尾崎紅葉と「読売新聞」には面白いエピソードがあって、歌舞伎の創作を人気投票で決めるというのを読売新聞がやっていたけど、それはすでに歌舞伎界との了解でやる作品も作家も決まっていた。それでも尾崎紅葉は『金色夜叉』の続編を連載していたこともあり、自分の作品が一席になるだろうと自信を持っていて、各界にアピールなどをしていたという。それで結局次席だったという。
新聞その他の出版が力を持っていたのは、正岡子規の写生俳句が短期間に広まったことで、芭蕉が各地に旅をしながら俳諧を広めていくのに、一生かかるわけだったが、正岡子規は病気持ちで、家で動けない状態でも正岡子規の「写生」俳句が松山から全国まで広がって行った。それで『歌よみに与ふる書』で短歌改革にも乗り出す。
正岡子規の俳句雑誌『ほととぎす』は、松山の記者が立ち上げ、病気持ちの正岡子規に代わって編集・経営面は高浜虚子が担った。虚子はその過労から病気になってしまう。その時に編集をやったのが河東碧梧桐で、俳句仲間は貧乏なのに虚子は家も建て温泉で療養していると文句を言ったという。それが分裂の原因でもあったようです。でもその後に闇鍋大会とあって(『巨人の星』で知ったけどそのルーツはここにあったのか?)大盛りあがりだったと書いてある。
尾崎紅葉は弟子を多く抱えて、その一人に泉鏡花がいた。当時は、まだそんな時代だったのかもしれない。その中で孤高の存在が森鴎外で、彼は軍医として、紅葉や漱石よりも給料も良く新聞社に頼らくて生活が出来た。当時の鴎外の給料は250円で、漱石や紅葉が100円。他の作家は島崎藤村は15円で生活していたということなので、詩人と小説家では歴然とした差があったわけだ。その貧しさが売りだったのが歌人の石川啄木なのか。
それで、文学の第一世代の鴎外が次の世代の文学者を名指しで批判文を書く。それがまた騒動になったとか。当時は誰でも作家を目指していたので人気作家を真似たものが多く質も落ちていた。また国木田独歩の自然主義文学は、誰でもエッセイ的に身の回りのことを書けた。有島武郎は、同性愛者で心中事件を起こして、それから内村鑑三から影響を受けてキリスト教へとのめり込んでいく。
永井荷風は、尾崎紅葉の硯友社に憧れていたのだが、国木田独歩たちと付き合うようになって、独自の文体を求めていく。落語家に入門したというのもこの頃だ。ただ永井荷風は文学者としては一段下に見られていた。その当時はまだ硯友社の時代で次第に影響力も失っていくのだが、その最後のスター文士が泉鏡花だった。
詩でも島崎藤村が音楽学校に入って、韻律を学んだり、正岡子規から俳句の手ほどきを受けた漱石やその弟子の寺田寅彦などが俳句にのめり込んでいく。そして、漱石は虚子の『ホトトギス』で作家としてデビューする。
もう一つ短歌の流れでは与謝野鉄幹が子規よりもさらに短歌を改革しなければとなって、国家主義的な短歌を世にだす。虎の短歌というような勇ましい歌いぶりのもの。そして、与謝野晶子も出てくる。最初は叙情的な女性の歌を詠んでいた与謝野晶子が後に国家主義的な短歌を作るようになるのは夫である与謝野鉄幹の影響だと思われる。
ただこの時代は治安維持法なども出来て次第に言論統制され、出版不況になっていく。日清戦争もあり、世の中が文学よりも暴力の方向へなだれ込んで行く。そこから一部の作家たちが政治的になっていくのだった。
解説によると後の文壇的な流れを伊藤整は見ていたようだ。あと女性のスキャンダルのエピソードも意外に多く明らかにしているのがこの『日本文壇史』の特徴で、泉鏡花は当時人気だった桃太郎に熱を上げ、尾崎紅葉にバレないようにしていたとか、森鴎外はそういうことは生真面目にやり過ごしたとか(それでも母親が愛人を作らせたというのもすごい時代だ)、幸徳秋水は女性にだらしがなかったとか。
伊藤整がフロイトの精神分析の限界をジョイスに感じて、そこからまた逃れるため、ジョイスよりも通俗的なロレンスや知覚小説のオルダス・ハクスリーとかに向かったとするのもこの『日本文壇史』に影響を与えたのかもしれない。
