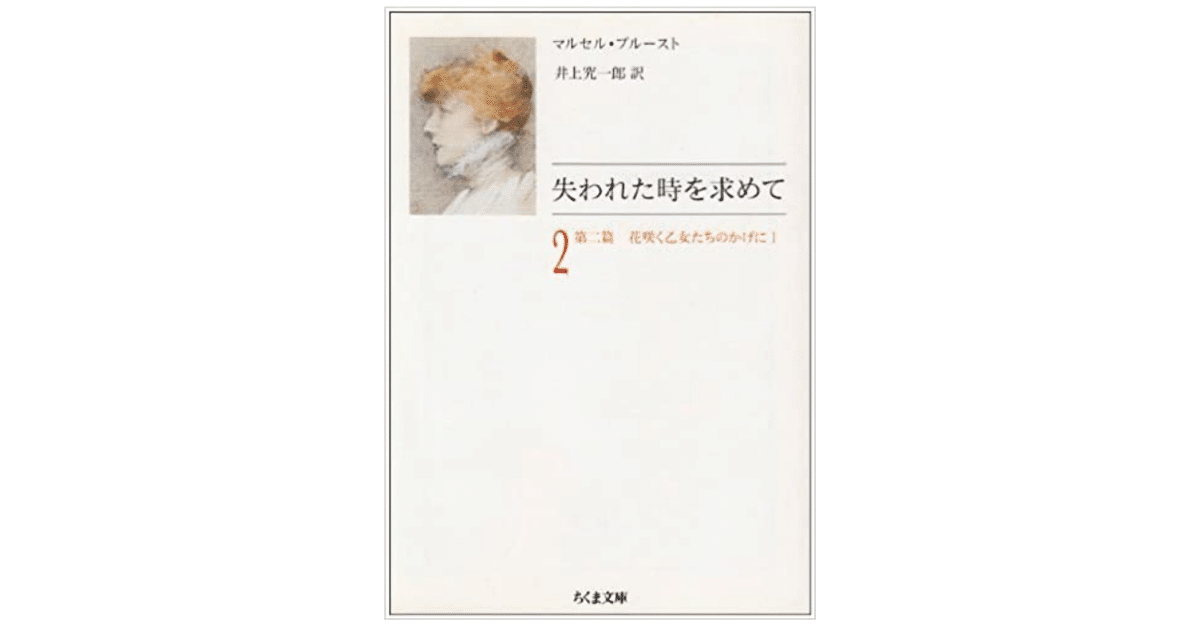
「欲望する機械」で読むプルースト
『失われた時を求めて2 <第2篇>花咲く乙女たちのかげに 1』マルセル プルースト , 井上 究一郎 (翻訳) (ちくま文庫)
一八九〇年代のパリにおける話者はスワン夫妻とその娘ジルベルト、文豪ベルゴットに会う。第一部「スワン夫人をめぐって」から第二部冒頭まで。
第一部 スワン夫人をめぐって
ちょっと頓挫してドゥルーズ『プルーストとシーニュ』を燃料投下。昔読んでいたのだがすっかり忘れていた。欲望機械ということです。過去の回想ではなく、未来を欲望していく文学機械というのが、無意識的過去の回想物語というのとは違った視点。開かられた文学。創造的進化。読書機械という状態でどんどん読む本を広げてしまう。不燃物ばかり。
ジルベルトの思い出を語っていたと思ったらスワン夫人の方へ興味が移って行った。スワンから観たスワン夫人は、以前のオデットではない。スワンの愛の嫉妬の感情で増幅されたオデットがいたということだ。今は倦怠期なのか?それは語り手がジルベルトを視る視線にも感じる。反復される時。
語り手がジルベルトのまなざしに父(スワン)の善良なものを見出していたが、それがかつてオデットがスワンに向けた偽りのまなざしと知る。嘘をいった時に見出すその仕草がオデットのものであるのだと。これは語り手がスワンを偽ったオデットをジルベルトの偽りの眼差しで強化する。どうしてオデットの偽りの眼差しを知っているのか?スワンの立ち位置で想像するのだ。裏切られた愛の者として。しかし、またスワンの眼差しをも見出す。二人のジルベルトがあったと。
他者の評価で変化していく人間。そのもっとも興味深いのがスワン夫人のオデットなのかな?オデットに対する語り手のママの評価で、イギリス帝国の植民地主義に例える描写があって、オデットのサロンが欲望する機械だった。それはヴェルデュラン夫人のサロンで学んだことだがヴェルデュラン夫人のサロンの客人を奪い尽くす(銀座のクラブみたいな話しだと思ったのだ。そうだった成瀬巳喜男『銀座化粧』『女が階段を上るとき』のイデアを見出していた)。その最大の功績がスワンだったのか?
語り手は女優のラ・ベルマ(サラ・ベルナールがモデルとされる)幻想が一旦は実際の舞台を観て幻滅する。演劇の鑑識眼がなかったのだ。外交官のノルポワ侯爵の鑑賞眼で評価を変える。語り手が大女優のポスターや前評判から受けたイメージは、役を超越して圧倒する舞台女優の声だと思っていたのだ。しかし、そこに見出したのはラシーヌ「フェードル」を忠実に演じる控えめなラ・ベルマだった。その役柄に忠実な姿を示されるとラ・ベルマの偉大さを知ることになる。さらにベルゴットによる鑑識眼は、まだ舞台を観ていないジルベルトにラ・ベルマの偉大さを知らしめる。それは絵画によって。その絵画の仕草、手の位置が寸分も狂わずに同一性を見出していた。それは何を意味するのだろうか?
それは芸術のイデアということなのか。プラトンのイデア説。イデアはものの本質という魂のこと。絵画のイデアは、その絵の中にあるのではなく魂として放たれるのだ。だから絵画のイデアを通じて、ラ・ベルマの中にそれを見出す。それは「フェードル」役そのものの神話時代の姿なのだ。
芸術のイデアを見出す作家ベルゴットの語りは、サロンでおしゃべりをするベルゴットではない。それは書かれたものへの痕跡によってだ。ベルゴットの人と成りは、外交官であるノルポワ氏や医者のコタールから否定される。サロンでのおしゃべりの中のスノビズム。それは人の噂話や自身を過大に見せかける見栄の中に存在する欲望によってである。ベルゴットが芸術を語るときには仮称の世界よりは本質的なもの、それは芸術の中に見え隠れするイデアに他ならない。
もう一つ重要なのが「ヴァントイユのソナタ」が啓示するもの。絵画は、理知的に解釈されるが、音楽が持つ感情性は絵画には精通しているスワンを狂わすものだった。その效果を知っていたのがオデットなのだ。愛という感情。理知的には判断できない。
「ヴァントイユのソナタ」がヴァイオリンとピアノのためのソナタである。ドゥルーズは欠如したヴァイオリンを孤独なピアノが弾くということで、その差異について語っている。「ヴァントイユのソナタ」という全体的な音楽のイデア像があるが、語り手は最初聴いたときは全体像がつかめなかった。オデットの弾くのは一部分だけで、「完全な愛」の欠如として演奏された。スワンがその曲が「愛の国歌」となったのは、オデットと一緒に聴くことによってその場が特別だった。愛の感情が生まれたので、二小節でも音楽を再現出来る。
芸術性は愛の欠如として、愛を求める欲望だというのが欲望する機械なのか。愛は、プラトンの言うイデアです。スワンの鑑賞眼は理知的な絵画では役立ったが、感情的な音楽ではオデットの策略にはまった。それは、オデットが持っていた才能ではあるのだが、サロン的なスノビズムのおしゃべりに費やされる。それを過剰に求めていたのはスワンの欲望であり、語り手の欲望となって反復する。愛の欠如としての差異が芸術の創造性を生み出す。ラストのスワン夫人との春の散歩のシーン。ジルベルトがいない中でも満たされている。
第二部 土地の名、ーー土地
避暑地のバルベック。語り手の年齢がいつもわからない。ジルベルトとの失恋の後だけど、一人で列車に乗れるぐらいの年には達している。途中でミルクスタンドの女の子に思いを寄せる。旅の期待と不安。
豪華なホテルの最上階に泊まっている。天井が高くて眠れないという贅沢な悩み。死の観念。ちょっとエヴァンゲリオンでシンジ君が病院のベッドで寝ているシーンを思い出しました。「見知らぬ天井」と言ったと思う。そういう見知らぬ土地で眠れないことはあったと思いながら、やっぱ入院していた病院の天井とか思い出します。
語り手はお祖母ちゃんっ子で、病弱な語り手を看病してくれています。療養の意味の避暑地だったのかも。壁越しにノックの音で状態を知らす。気分が悪くなったらノックして、お祖母ちゃんが来てくれる。
ゲルマント家の血を引くヴィルパジリ公爵夫人登場。ヴェルデュラン夫人と名前が似ているので混乱する。サン・ルーはまだ出てこないです。アルベルチーヌももう少し先か。期待が持てるところです。
