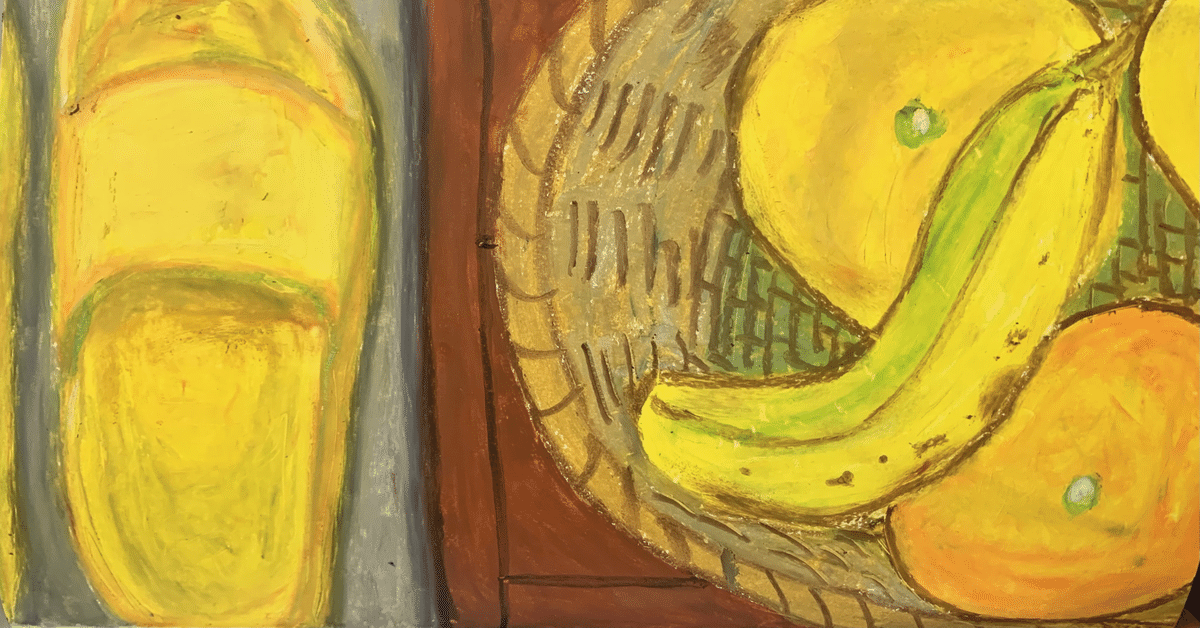
たらない雑煮
盛りだくさんの朝ご飯じゃなくなった。
つくり続けていたヨーグルトが、市販のものになった。
冷蔵庫の中に賞味期限切れのものが沢山あった。
…雑煮にかしわが入ってなかった。
慌ただしい朝の台所に母と並んで立ちながら、この二年という歳月がもたらした明らかな変化に、私はいちいち反応している。
***
うちの雑煮は昔からずっとすまし汁で、具は餅と紅白の蒲鉾とかしわと決まっていた。お椀の上に三つ葉を結わえて浮かせ、仕上げにゆずの皮をほんのひとかけら散らす。私が物心ついたころから母が作り続けてきた味は、確かに二年前に訪れたときまで、ちゃんとここに存在していた。
「お節は出来合いでも、お雑煮ぐらいわねぇ。」
母はそう言って、昆布と鰹節でとった澄んだお出汁に薄口しょうゆをたらし、かしわを放り込む。
「これからいい味がでるから、かしわは忘れんと入れんなね。」
婿である私の夫を気にして、具の少なさの言い訳を私に小さい声でつぶやいた。それでも、味見をする横顔に長年作り続けた自信が見て取れた。
それは確かに二年前まであった光景だ。
*
新年を迎えて急遽、帰省を決めた。混み合う時期をずらしたつもりが、オミクロン株によるコロナ感染者は日を越すごとに桁を変えて増え続けている。迷ったけれど今を逃すと次はいつ両親の顔を見れるか分からない。
直前に検査を受けて陰性であることを確認のうえ、2泊だけすることにして昨日の夜遅くに両親の家に到着したのだった。
母は玄関先に私達を出迎えるとすぐ、両手で顔をおおった。息子が私の後ろから「ババ!!」と母に飛びついた。画面越しではない、またひと回りちっちゃくなった母と息子をひっくるめて私も抱き着いた。
「ただいま。泣かんでも、ええんよ。」

翌朝、私は少し甘えたつもりになって少し寝坊をした。
平屋の狭い家で、私が寝ているこの襖の向こうは台所と扉を挟んで食卓である。夫や息子はすでに起きて犬の散歩に出ているようだった。
母の仕事の気配がしている。父が新聞をめくる気配がしている。
布団の中までふんわりと出汁の匂いが漂ってきた。
〈ーああこの匂い。雑煮?〉
私はやっとのそのそと起き出して、母の立つ台所へ向かった。ここは小窓が開いているので、ひときわ空気がひんやりしている。
「おはよう」と声をかけ母の丸い背中越しに鍋をのぞきこんだ。アルミの両手鍋にいっぱいに澄んだお出汁が、おつゆだけ揺れている。
湯がいたほうれん草がまな板の上にあるのは、三つ葉の代わり?
「味、見て?」と差し出されたお玉の汁を口に含むと、なんだか塩がすこしきついようだ。
母が自信のなさそうな顔をしたので「大丈夫」とやかんのお湯を少し足した。
「かしわはこれから?」
そう聞くと、きょとんとしている。
「かしわ?買ってないんちゃう?」と母が言った。
はっとした。
母と何気ない会話を続けながら、私は冷蔵庫の扉を開けた。
定期的に拭かれ清潔にするのが当たりまえだった母の冷蔵庫の庫内が、少し様子が違ってみえる。なんか…黄色い。
漬物が入ったタッパが斜めなっていくつか奥に押しやられている。
お味噌とヨーグルトの蓋が外れたままで入っている。
正月用に買ったであろうハムが、ラップからはみ出たまま入っている。
何かの汁がこぼれて固まったままの跡。
野菜室の引き出しを開けると、ぎゅうぎゅうにつまった葉野菜が飛び出す。
冷凍庫の引き出しに、いつ買ったのか分からない合いびきやらなんやらが、ビニールがかかったままでつっこんであった。
自分のみぞおち辺りに、ゆるく、どすんとした鈍い圧力を感じた気がした。
母は高齢ながら数年前まで、病院の食堂の調理場でパートとして働いていた。その経験もあって料理の手際もよく、私達が遊びに来ると豪勢でなくてもいつも食べきれないほどの手料理でもてなしてくれた。私達や孫が勝手に冷蔵庫を開けるのを見越して、普段自分達は食べたりしないゼリーや飲み物やおやつなどが沢山入っていたりもした。
それなのに。
この冷蔵庫は、孫や娘(私)が来ることを、準備していたものではなかった。母の中でそれができていた数年前までの冷蔵庫と、そうじゃない今の冷蔵庫に、私は気が付いてしまった。
「ええと、何人かな?。いち、にぃ…」
母は人数分のお椀を棚から取り出そうとしている。私は冷蔵庫の扉をしめた。
いや。それでも…。
今回こういう事と向き合う覚悟を。私はどっかでしてきた、はず。
今の私には急な変化に映るこのことは、母にとっては違う。
ゆるやかに、少しずつ変化してきた事を私が知らなかっただけなのだ。
お母さんは、いまも台所仕事を元気にしている。父と二人で文句を言いあいながらまだ。毎日、自分の料理をしている。
「かしわ。なくても全然いいよ。あるもんでええんやから。」
私は明るく声をはって、かしわが無い事が気になりだした母に伝えた。
調理場の作業台の上に母が用意したお椀は、ひとつ数が足らない。
オーブンで焼きあがったお餅は、数が一つ多かった。
「寒いけど。雑煮、嬉しいなぁ。」
「ほんま?正月らしいこと何もしてないけど。なら、よかったわ。」
私は足らないお椀をひとつ取り出し、一つ多いお餅を父のお椀によそった。
ほうれん草を取り分けて、少し濃いめの出汁を回しかける。餅が”じゅっ”と小さく鳴いて、澄んだお汁から香りが立った。
お椀の中身は色々足らなくても、これで満たされているのだった。
母の作る雑煮は、私がしっかり覚えていれば十分だから。
お母さんのこだわりを私が覚えていればいい。
そしてそれを手放している今の事も、知れたのがいい。
出汁の香りは、私が知ってる懐かしい香りのまんまだった。
***
玄関が開いて、夫と息子が犬の散歩から帰ってきた。
寒かった!寒かった!と大騒ぎしながら、ヤギがいただの、近所で飼われているすっぽんがまだ元気だっただの、明るい声で家が一瞬で賑やかになった。
「ちょうどお雑煮出来たから、食べよ。」
母は嬉しそうな笑顔を向けて、孫を部屋へ呼び込んだ。
ああ、今。
この光景が見られてよかった。
少し泣きそうにながら、私は心から嬉しいと感じた。
***
短い滞在を終えて両親の家を出るとき、玄関の外で写真を取り合っている皆から離れ、忘れ物のチェックをしに家の中に戻った。
台所を通りがかって、そうだ、と足を止めた。
今まで私たちが飲んでいたマグカップが流しにつかっている。
コンロ、電子レンジ、トースター。食器棚、ゴミ箱、調理台。
重なったボールにアルミ鍋。
蛍光灯、空いた小窓。
冷蔵庫。
見まわしたそれらに向けてゆっくり頭を垂れ、祈った。
「どうか。これからも守ってください。
二人の日常が穏やかに続きますように。
またすぐ、会いに来ますから。」

私達はまたしばらくの間、緊張の日々を送らなければいけない。それでも変わらず時間は進んで、1日はどんどん更新されていく。
あらゆるものがゆっくりと時に急に変化する事を、私はもう一度覚悟しようと思う。
それから。
思う事、考える事。言葉にして伝える事も、諦めずにいようと思う。
いいなと思ったら応援しよう!

