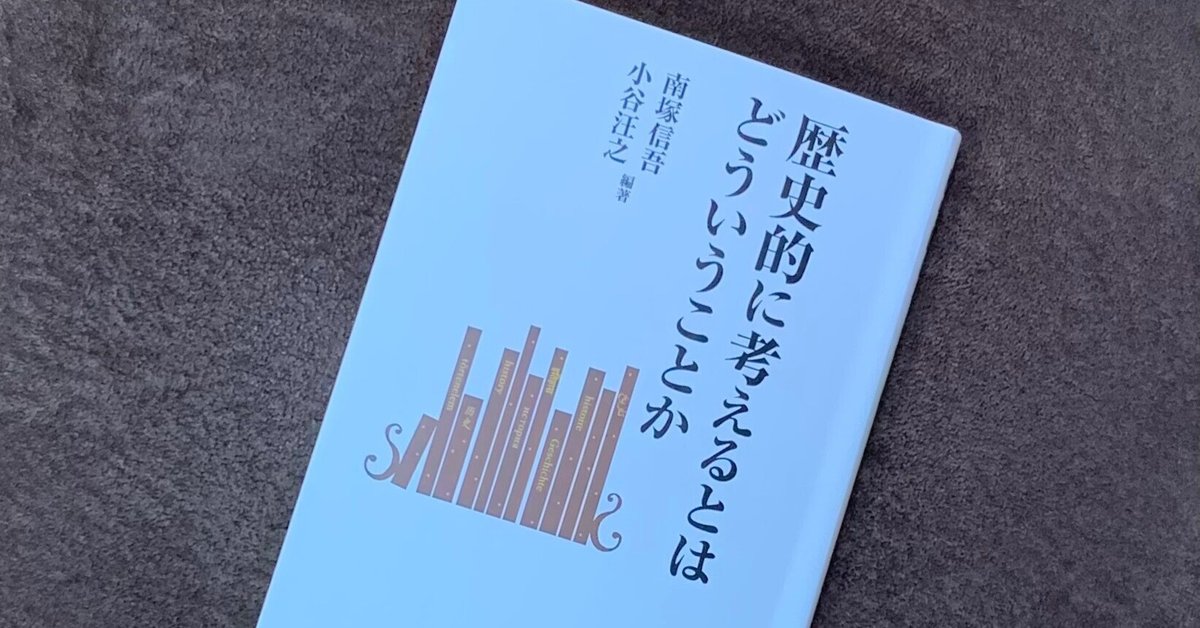
今日ときめいた言葉162ー「私たちが認識する『歴史』は何らかのバイアスとは無縁ではいられない」
「このことに気づく経験が現在の教育では必ずしも重視されていない。『歴史』を『歴史的に考えること』が必要だ。
2024年5月30日付 朝日新聞に掲載された東京学芸大学准教授 日高智彦氏の「『歴史的に考える』ことの学び方・教え方」という記事を読んで興味が湧き、日高氏の論考が所収されている「歴史的に考えるとはどういうことか」(南塚慎吾・小谷汪之編著 ミネルヴァ書房)を読んだ。そのまとめである。
「『歴史的に考える』とはどういうことか」
ーー直接経験していない歴史に出合うには、歴史家の記述やドラマや小説などのメディアを介する。この時これらの歴史記述にはたらく何らかのバイアスに自覚的になり、相対化する必要がある。何故ならそこには記述した人の心が入り込んでいるからだ。
「私たちが接する「歴史」は、純然たる過去そのものではなく、史料を残した者の意図や、史料を読み解いた歴史家の解釈など、なんらかのバイアスがかかっているということだ。また、私たちも歴史的な存在であり、生きている時代や地域の価値観から自由ではないのだから、ものごとをありのままに見られるわけではない。ただでさえバイアスのかかっている『歴史』の中の過去に、さらに自分のバイアスをかけ、デフォルメしながら見ている、というのが実態なのだ」(第6章)
たとえ教科書であっても執筆者の教育的配慮などが働いていることを自覚すべきである。教科書から歴史的な考え方を学ぶということは、「教科書自身を聖書のように崇拝してそれを暗記したりすることではない。むしろ、その教科書を疑うことから「歴史的な思考」は始まる(本文第8章)。
だが、他者のバイアスを指摘することのみでは、自分の考えを正当化する口実になりかねない。だから自分にもバイアスがあることをも自覚することが大切だ。「過去の残され方に伴うバイアスに自覚的に歴史にアクセスし、自分の歴史の見方のバイアスを相対化すること」が「歴史的に考えること」である。
人は過ぎ去った事象そのものに出合うことはできない。自分の生活経験や想像力を通じて、経験していない過去を現在とつながりのあるものとして把握する。自分につなげないと歴史を認識することはできない。
しかし、このように考えること=「歴史的に考えること」は、教育の中で重視されてきていないし、歴史教育に携わる人間にも共有されていない。
多様性が尊重される社会実現に向かって、現在起きている事象を考えるには、他者と対話を重ね、集団的、社会的に歴史が認識されていく必要があるのに、日本の受験体制はこれを妨げている。一人黙々と勉強することを求められる状況では、「歴史的に考える」ことの意味を教える機会も訓練の場もない。
「本来そういったことをすることが歴史教育の役割のはずなのに」
この著書「歴史的に考えるとはどういうことか」を読んで、自分の歴史に対する認識を検証してみた。
「人はいつ、どういうときに、『歴史的に考える』のか?」
多くの学生は、大学生になって歴史学概論の授業を受けたときと答えているようだ。それは小中高時代に「歴史」は学んでも「歴史的に考える」ことは学ばなかったということを意味する(日高氏の言葉) 私の場合も多くの学生たちと同様、大学の一般教養で歴史を学んだ時だろう。それまではただただ教科書を暗記するのみだったから。
大学の授業で私が衝撃を受けたのは、「人間の歴史は労働者と資本家の階級闘争の歴史だった」とか「下部構造(経済的土台)は上部構造(イデオロギー)を規定する」という歴史観を初めて知った時だ。そんな歴史観があるんだと驚いた。でも、そんな歴史観のことを今まで学校では教えてくれなかった。
私が入学した大学は、当時マルクス主義思想が主流だった(今は違うらしい)。経済学部に所属していた友人は「マル経7割(マルクス経済学)、近経3割(近代経済学)といったとこかな」と言っていた。
社会学部の一般教養科目も専門科目もマルクス主義理論に基づく講義が主だった。そんな中で原書講読(と言っても日本語で読むのだが)で読んだのは、マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」だった。なぜかとても新鮮に感じられた。こちらは精神が経済構造を規定すると言っているようなもの(かな?) 歴史へのアクセスの仕方にはいろいろあることを知った。
3年後大学を変わった。次の大学で受けた講義は前の大学とは全く違う社会学や歴史だった。こうまで違うとものごとを見るときに懐疑的にならざるを得ない。
マルクス史観を学校教育でやらないのも理解できる。戦前戦中の社会主義活動家は国家転覆を目論む危険人物扱いで、思想警察の取り調べを受け獄中死したり、拷問を受けたりしたということを本や新聞で読んでいたし、世間の人々も「アカ」などと言って恐れたり忌避したりしていた。
学生時代に読んだ小林多喜二の小説「蟹工船」は壮絶だったし、彼の拷問死の記述も凄惨だった。戦後になってそれまで拘束されていた活動家たちが解放されはしたが、冷戦の煽りでレッドパージで公職を追放されることが起きた。こんな背景があって国家の意図が働き「マルクス主義思想や歴史観は学校教育ではタブー視されたのだろう」(アメリカでは共産主義が一時期非合法化されたことがあった)
最後に、日常の中で歴史的に考える「七ヶ条」が掲げられているのでご参考までに。
第1条 「面白い」「ためになる」は卒業しよう。
ーーそれは娯楽としての歴史に終わる。「面白いこと」の原因や背景や詳細を調べようということになれば、そこから「歴史的に考える」ということが始まる。
第二条 自分の「偏見」を自覚しよう。
ーー「歴史的に考える」さいの「落とし穴」を意識するところから始める必要がある。我々は、歴史を書く人、歴史を読む人の「レンズ」「偏見」を通して、過去を見ているということを自覚する。
第三条 この歴史を書いているのは「誰か」と問おう。
ーー「まず歴史家を研究せよ」(とはE・H・カーの言葉)歴史上の事実はけっして「純粋」に現れてくるものではなく、いつも記録する者の心を通して屈折してくる。
第四条 「史実」を重んずる本かどうかをまず見よう。
ーー過去の事実をどのように確定しているか。参考文献、先行研究、注は事実をどの程度重視して書かれた本かを示している。
第五条 史実の作られ方を警戒しよう。
ーー特に新聞。史実が書いてあるとたやすく信じてはいけない。少なくてもいくつかを読み比べて確認することが必要。ドキュメンタリーは要注意。
第六条 歴史についての「判断」は慎重にしよう。
ーー丁寧な事実の確認が必要。
第七条 未来への「展望」を持って過去を見よう。
ーー「歴史は過去との対話」であるが、歴史家は現在を生きながら未来に向かっている人間である。人は未来に対してどのような展望を持っているかによって、過去への見方も変わってくる。
