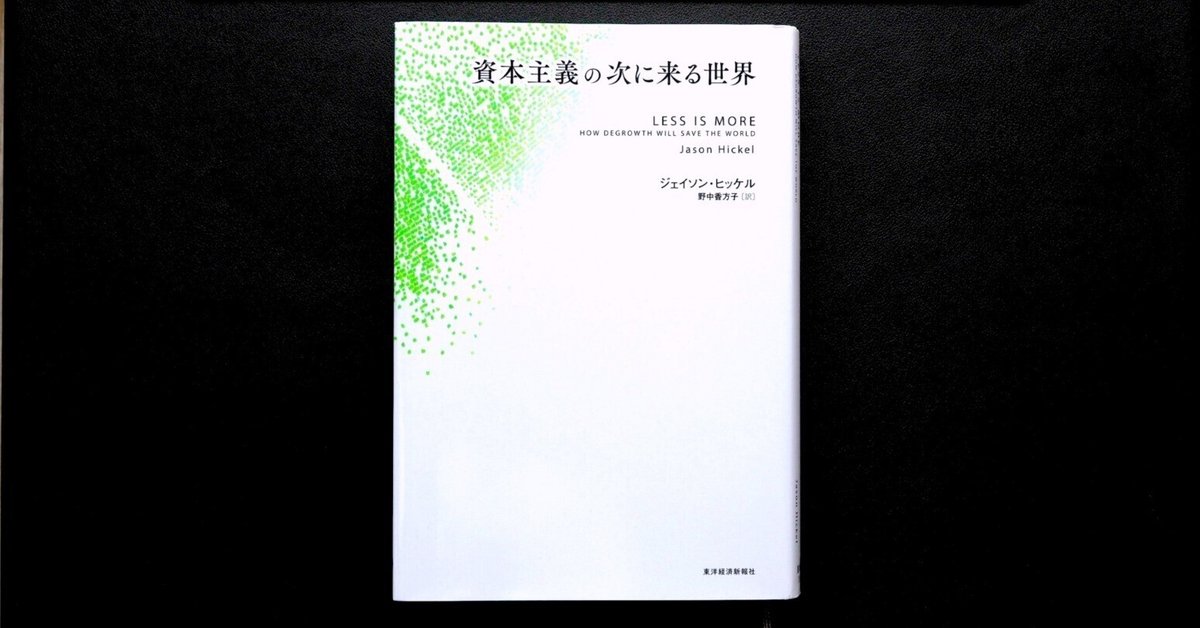
『資本主義の次に来る世界』(読書メモ)
中学生の頃だっただろうか、古代ローマ貴族の食事について学んだとき、なんてもったいない話だろうと思った。豪華な食事を味わい続けるために、貴族たちは食べたものを無理やり吐き出していたという話だった。それならば、お腹を空かせた庶民や奴隷に分けてあげればいいのにと当時は思ったものだった。
王侯貴族が民を支配し富を独占した封建社会のあと、農奴制が解かれ、世界は資本主義へと移行した。これにより、領主や貴族による強制的な取り立てではない新しい政治経済のあり方、つまりは市場を信じるという、より自由で平等で民主的な、すなわち市民一人ひとりのニーズに基づいてモノやサービスがやり取りされる健全な社会へと移行した。と思われているが、果たしてそうだろうか? という辺りから本書は始まっている。
資本主義の特徴は、市場の存在ではなく、永続的な成長を軸にしていることだ。事実、資本主義は史上初の、拡張主義的な経済システムであり、常にますます多くの資源と労働を商品生産の回路に取り込む。資本主義の目的は、余剰価値の抽出と蓄積であるため、資源と労働をできるだけ安く手に入れなくてはならない。言い換えれば、資本主義は、「自然と労働から多く取り、少なく返せ」という単純な法則に従って機能しているのだ。
「成長がすべて」という資本主義経済の下で、私たちは今、ローマの貴族の食事に代わって「大食い選手権」や「大食いチャレンジ」を目にするようになった。制限時間内に胃袋に押し込まれた8キロのステーキや10キロの寿司は、チャレンジ収録後には大半が便器の中へと吐き出されるそうだ(あるいは大量の便となって、いずれにせよ便器の中へと消えていく)。正直、もったいないと思うが、なぜそんなことまでして食べるかと言えば、それが高い視聴率や再生回数を叩き出し、テレビ局やユーチューバー、その背後にいる企業や株主を儲けさせ、経済を成長させるからである。
ローマ時代の貴族の食事と、現代の大食いチャレンジは、どちらも「必要量を超えて食べ続ける」という点で共通している。貴族たちは栄華の象徴として食事を詰め込み、大食いエンターテイナーたちはお金のために食べ続けている。その量は、人が生きるために摂る食事、必要カロリーの摂取という目的からはかけ離れてしまっているのだ。
本書『資本主義の次に来る世界』の前半部分は、主に資本主義が生まれた経緯と、その本質としての「成長そのものの追求」が世界にもたらしてきた弊害にページが割かれている。経済成長は、生産のための安価な資源や労働力など、搾取可能な「外部」を必要とし、また生産品に富を差し出す消費者なしでは成り立たない。
ではどうすれば安くて大量の資源、労働者、消費者を作り出すことができるのか? 資本主義の導入が始まって以来の500年間で、世界では植民地政策が推し進められ、奴隷貿易が強化され、コモンズ(森や水源などの共有地、共有資源)の囲い込みが起きた。それまでは無料でアクセスできていた必要物資が手に入らなくなった人々は、”食うに困って”都市へと流れ込み、低賃金労働者として、また消費者として経済成長を下支えすることなった。
著者のジェイソン・ヒッケルは、資本主義経済の仕組みを次のような分かりやすい価値の違いで表している。
ここから先は
らくがき(定期購読マガジン)
身の回りの出来事や思いついたこと、読み終えた本の感想などを書いていきます。毎月最低1回、できれば数回更新します。購読期間中はマガジン内のす…
らくがき帳(定期購読マガジン)
身の回りの出来事や思いついたこと、読み終えた本の感想などを書いていきます。毎月最低1回、できれば数回更新します。購読期間中はマガジン内のす…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
