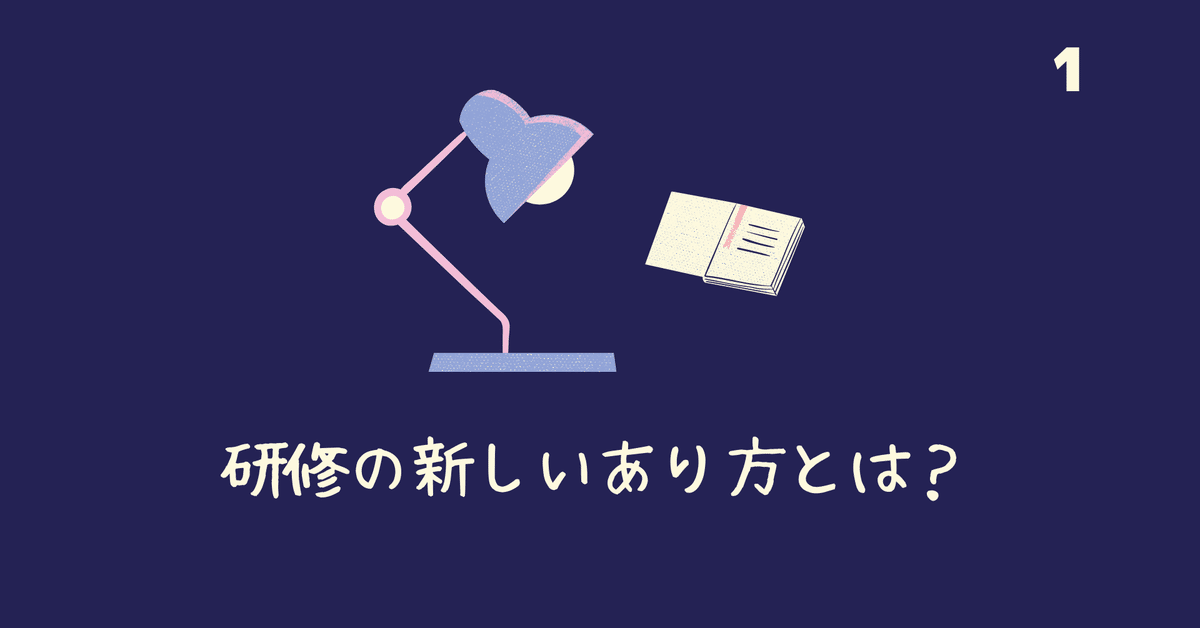
伝統的企業の新しい研修(1)
本日はこの内容を考えます。
オンライン研修は既存の研修カリキュラムの継続では成立しない。
そういう気づきがないと研修体系が破綻してしまう可能性が出てきました。オンライン化というもの自体はすっかりとお馴染みのものになり、チャットとビデオ会議が当たり前の時代となりました。
もちろん、その前からもウェビナーという形でオンライでの講座みたいなものは存在していましが、こうもチャットとビデオ会議が普及すると現場で行われていた「イベント」もまたオンライン化の波が押し寄せてきます。
典型的なのが製品勉強会や工場見学、あるいは工場見学とセットで行われる技術研修といったものです。
これらをここではまとめて研修と呼びますが、こう言った研修は実施するメーカーからすると、ある種の販促物であり、関係を深めるためのイベントでもありました。
それがオンライン化するとなると、オンラインに最適化した形は何か?という再構築の話題が出てきます。もう少し具体的に言えば、研修カリキュラムをどう見直すか?という問題になってきます。

そもそも、既存の現場での研修も、本当にこのカリキュラムでいいのか?という疑問を持ちつつも、忙しさにかまけて大きく手を加えることが中々できていなかった会社は相当数あるのではないでしょうか?
失われた何十年は、真っ先に「教育」へのコストをカットしてきました。それは自社の社員への教育費だけでなく、社外向けの教育人員(講師とか)やイベントの縮小もまたそうです。
しかし、オンライン化はそういった観点の見直しを否が応でも進めます。巣篭もりする以上、その時間を勉強に当てるという比率は高まるからです。
現在のカリキュラムについて
というわけで、それではオンライン化に適した研修のあり方を考えていきたいのですが、そもそも現在のメーカーの研修体系とはどのようなものなのでしょうか?現状を把握してみたいと思います。一口にメーカーと言っても、製品や分野や慣習が違えば異なる部分があるかもしれません。
しかし、そこはかなりざっくりと以下のような分類とカリキュラムで一まとめにしてしまいたいと思います。
基本分類
まず対象は以下の3つかと思います。

1)初心者や営業向けの商品や業界の基本を教える基礎研修
新入社員が顧客のところに配属されてくると、メーカーはこぞってその社員向けに基礎研修の実施を申し出ます。そう言った初心者向けの基本を教える研修のことを指します。
2)実際に使用する顧客に製品の使用方法を教える技術研修
これはある程度実力のある方向けのものです。自社の製品が使いやすいな、と思ってもらうために技術研修を行います。自社の製品の使い方を詳しく知ってもらい、使いやすいから購入してもらおうという戦法です。
3)顧客の中でも特に導入を担当する人向けの設計研修
実際に使用するというよりも、その製品の社内導入や内部での企画やコンセプトといった、間接的に顧客社内での自社製品のプレゼンスを高めてくれる人向けに行われる研修というものもあります。こちらは使いやすさだけでなく、顧客の製品やサービス全体の中で、どのように自社製品が貢献するか?という観点で説明がなされます。
***
毎度毎度、中途半端なところで終わって恐縮ですが、今日はここまでです。
次回は、この3つの研修についての、既存カリキュラムを分析し、その後に今後のオンライン研修のあり方、について考えていきたい思っています。
ということで、また。
いいなと思ったら応援しよう!

