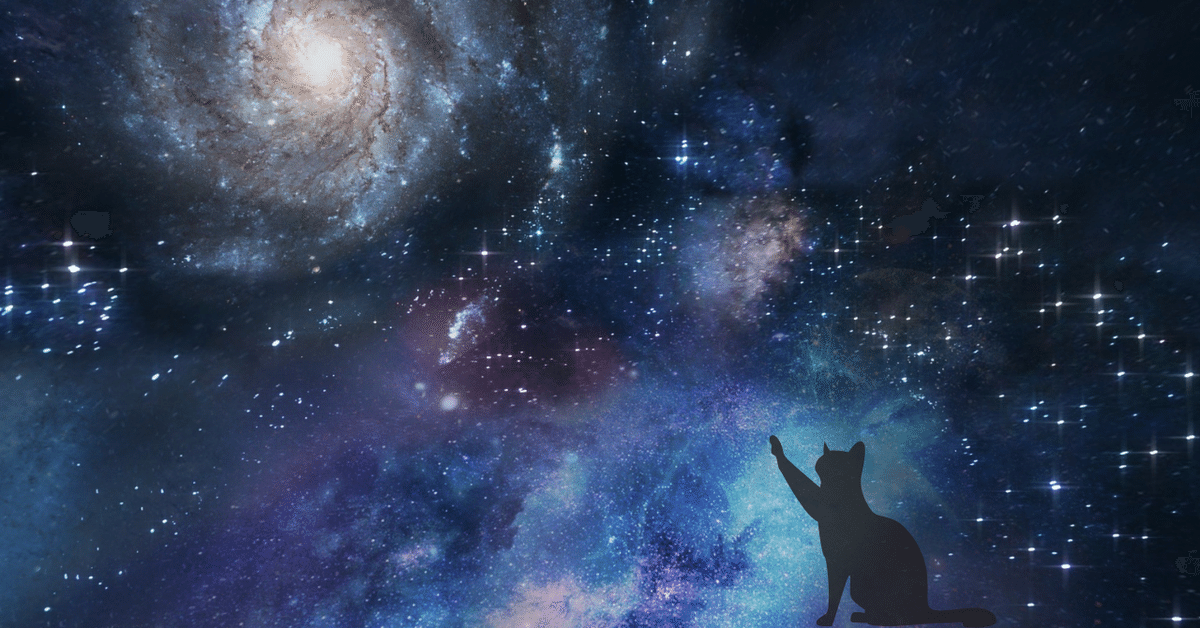
宇宙猫は輪廻の夢を見る🪐🐈⬛
宇宙猫。それは、銀河の背景をバックにして、ぽかん…( ゚д゚)とした顔の猫が載せられた写真である。

そのフリー素材で作成された画像がまたたく間に広がり、今もなおTwitterなどでスタンプ代わりに利用されている。
そんな中、宇宙の画像と撮影した猫の画像を合わせて、せっせと宇宙猫にした写真をインスタグラムに投稿しているアカウントがあった。
密かに、人気を博していたのも無理もないだろう。
私と友人のミオは、そのアカウントの話題でもちきりだった。
「ねお、昨日の宇宙猫の写真見た〜〜〜??」
「見た見た!ブリティッシュもポカン顔でかわいいよね〜〜〜!!」
仕事の休み時間、すかさずやってきたミオは、スマートフォンを片手に意気揚々と話しはじめる。
良くもまぁ、こんなにも猫のポカン顔( ゚д゚)を撮影できるものだなぁ、と関心していると、アカウントの投稿が更新された。
今日の猫は……。
「今日の猫もめっちゃかわいい〜〜〜!!マジうける!!!笑いすぎて涙出そ〜〜〜!!!……ってねお??」
その猫の画像を見るなり、身体が硬直してしまう。私の名前を呼ぶ声が、どこか遠くでこだましていた。
写真に写る猫の柄は、先日虹の橋を渡った、私の家の猫と同じものだった。

忘れもしない、何度も撫でたあの頭。まんまるな目。そして、三毛猫のオスだったということ。
けれど、三毛猫のオスは先天的に弱い個体である。だから、幼くして命を落としてしまった。
わたしの胸の中で、冷たく固くなっていくソラの身体を、今でもずっと覚えている。身体中の水分が全部なくなるんじゃないかってぐらい、泣いた。
そのソラが、画面の向こうにいるのだ。投稿のキャプションを確認すると、
迷い猫です。都内で発見、保護しています。どなたか心当たりのある方はDMください。
というように記載があった。もう、行くしかないだろう。
休み時間の終わりを告げるチャイムで我に返った。ミオは心配そうに私を見つめていたので、なんでもないよ、と笑ってごまかした。
終業のチャイムが鳴るのをこんなに心待ちにしたことがあるだろうか、というほど、秒針が遅く感じた一日だった。
ミオの誘いを断り、私はインスタグラムでDMを送った。
すると、すぐに返信が来る。今から行っても大丈夫、とのことだったので、指定された公園に向かった。
公園は、職場から二駅のところだった。家を指定してこないあたり、相手は慎重な人だろう。そう思うと、初対面でも不思議と安心していた。
しかし、なんて言おう。ソラではないわけだし、ほんとうに誰かの飼い猫かもしれない。それでも、一度この目で見ておきたかった。
電車を降りて、小走りで公園に向かう。弾む息を抑えながら公園の中を見渡すが、それらしい人は見当たらなかった。
仕方がないので、公園の隅にあるベンチに腰掛ける。18時を回っているので、公園の中は閑散としていた。
今か今かとスマホを何度も確認していると、キャリーバッグを持った一人の男性が公園の入り口に立ち、周りを見渡しながらスマホに目を落としたのが見えた。きっとあの人に違いない。
勢いよくベンチから立ち上がり、男性の元に向かう。男性も私の姿に反応し、近づいてきた。
「あの、猫ちゃんの画像を見て、それで…」というと、男性はにっこりと笑ってキャリーバッグの中を見るように促した。
格子の内側には、こちらを伺うような猫の目が光っている。しかし、わたしの高揚感はすぐに消えてしまった。
鳴き声が、違ったのだ。ソラは、男の子にしては高く甘い声で鳴く。しかし、格子の向こうからは、少し低い鳴き声が聞こえてきたのだった。
がっかりした様子をさとられないように、なんとか言葉を発しようとするが、うまく言葉は紡げず、頭の中はぐるぐると思考が支配する。
思考がショートして硬直するわたしの耳元で、男性が囁いた。
「また、会いに来たよ」
それは、甘く、男性にしては高い声だった。
びっくりして男性の顔を見ると、まんまるな目がこちらを見ている。
ソラだ。間違いなくソラだ。そう確信した。
あの頃の毛並みを彷彿とさせる柔らかな茶色の髪が、そよそよと春風に揺られているのを見ていると、涙が溢れてきてしまった。
「ほら、ねおがいつまでも悲しそうだったからさ。僕もまだ小さかったのに死んじゃったから、心残りで。もう一度ねおに会いたいって、神様に必死にお願いしたんだ。この子には、お手伝いしてもらったけど」
そう言うと、キャリーバッグの中の猫は、不満げににゃーと鳴いている。その様子を見ていると、少し笑えてきてしまった。
「ねお。突然のことでびっくりしてると思うけどさ。もう一度、ねおの側にいてもいい……?」
肯定の代わりに、ソラを強く抱きしめた。ソラはそっと抱きしめ返し、優しく、優しく私の頭を撫でる。
さぁ…と風が吹き、桜の花びらが待っていく中、暖かいおひさまみたいな、懐かしいソラの匂いを鼻にすると、涙がとめどなく溢れてきた。
いつしか、空には無数の星たちが輝きはじめている。桃色のベールが、いつまでも優しく二人を包んでいた。
春芽吹く宇宙の摂理でまた出会う
会いたいよその一言で輪廻する
九つの命か宇宙の摂理か
