
碧空を征く 最後の海軍航空艦隊 彗星艦爆隊員の手記より 第二章
この記事は、下記の記事の続きです。
昭和100年・戦後80年の節目のこの年。
「碧空を征く」は、特攻隊員としての父の実体験をもとに、戦争の悲劇と平和の尊さを伝える手記です。父が残した言葉を通じて、当時の歴史や心情を振り返り、未来へのメッセージを紡いでいきます。今回は、「第37期飛行術練習生」です。

第37期飛行術練習生
第37期飛行術練習生として谷田部海軍航空隊に入隊を命じられた。昭和19年3月25日、「鬼の谷田部に、蛇の筑波」と言われた谷田部海軍航空隊第37期飛行術練習生教程に進んだ。
谷田部海軍航空隊の隊門をくぐるや否や、待ち受けていた篠崎先任教員(乙飛8期)の一喝が響き渡り、早速飛行場一周の駆け足で気合を入れられる。ノンビリムードの予科練課程とは異なり、さすがに飛練航空隊だと自覚を新たにしたのは、鹿児島海軍航空隊出身の我々甲飛12期生操縦分隊の50名であった。
飛練教程は、いわゆる赤トンボと呼ばれる93式陸上練習機、複翼のエンジン300馬力の飛行機での操縦術取得の訓練である。
訓練は教員1名、練習生5人のペア(組)でマンツーマン方式だ。操縦操作が悪ければ、「コラー!俺を殺す気か!」と、後席から伝声管の金具部で殴られ、飛行帽の下の頭から血が流れることもあった。
飛行作業が終わり、教員の注意講評を受けるその間、太陽で焼けた誘導路のコンクリート舗装に手をつき、「前に支え」と命じられることもしばしばあった。
また、全員罰直で重い落下傘を尻に飛行服、飛行靴で飛行場を駆け足一周することも度々あったが、とにかく最前の目標は単独飛行に到達することだと張り切った。
「第4旋回・見張りヨーシ・変更輪ヨーシ・パス角度ヨーシ・機速ヨーシ」「高度7メーター」スロットル閉、機体の沈みに応じて操縦桿を引き上げる着陸時の操作手順のイメージトレーニングが、夢の中で出てくるようになった。
総飛行時間8時間を過ぎて、待望の離着陸単独飛行の許可が下された。

「松下練習生。離着陸単独飛行出発します!」力のこもった大声で地上指揮官に報告する。誰にも頼ることもできない中、「第2旋回高度200メーター水平飛行、」「見張りヨーシ」となったとき、無我夢中から覚め、我に返ったときの感激は言葉では言い表せないものであった。
後席は教官の体重に合わせた土嚢を積んでいるのみだ。この碧空にただ1人で飛んでいるのだ。
思わず「ヤッター!」と歓喜の声をあげた。次はドンピシャリの着陸だ、細心の注意と見張りを自分自身に言い聞かせ、教官同乗と同じ動作呼称で無事着陸を果たした。
訓練課程の次は、①離着陸互乗、練習生同士で、②編隊飛行同乗、教員と、③編隊飛行単独、④夜間飛行同乗教員と、⑤計器飛行同乗教員と、⑥特殊飛行同乗教員と、⑦定着訓練同乗教員と、⑧特殊飛行単独、⑨特殊飛行互乗、練習生同士で、次々と教程は進んでいく。
まさに月月火水木金金の訓練飛行生活にも大分慣れたある日の飛行作業で、甲飛10期生の先輩教員と同乗し、5月晴れの空で特殊飛行科目を終了し、飛行場に機首を向けたとき、突然、「操縦桿から手を離せ!」と伝声管から教員の声と共に急降下に入る。
目標は苗代から苗を運び終えて、畦道に休憩し草を食む馬である。爆音を轟かせ、一直線に計器高度0メーター、馬はあわてて突っ走り、反復してまた馬に突っ込む。
暴走する馬を捉えようと百姓さんは慌てて、あれよ、あれよと後を追って走る光景であった。
次の目標は、田植えをしている横一列の早乙女たちのお尻である。変更輪を一杯アップにして電線が来たら、すぐ機首が上がるように調整して突っ込む。
爆音に驚き、振り向き慌てて蜘蛛の子を散らすように田の中を這い、逃げまどう早乙女を横目に見ながら飛行場に、何食わぬ顔をして着陸した。悪ふざけをした訓練のひと時もあった。
飛行作業が本格化するにつれて、必然的に事故が発生する。飛行練習生卒業までに10余名の者が志半ばにして航空機事故による犠牲となった。
予科練とは比較にならない猛烈な訓練の連続であり、またそれに対応して飛行場一周の駆け足や、前に支えの罰直は毎日のように行われた。
これは誰がヘマをしたから全体責任という理由によるものではなく、根性を鍛えるのが目的で実施されるため、理由など何とでも付けられたのである。
偵察員の同期生は9月末には飛行練習生課程を卒業した。そして八重桜の特技章を付与されて実施部隊に配属された(推定人員366名)。
予科練入隊以来わずか1年2ヶ月で、北は北海道、南は仏印、シンガポールと各地の実施部隊に赴任して実戦配置についた。
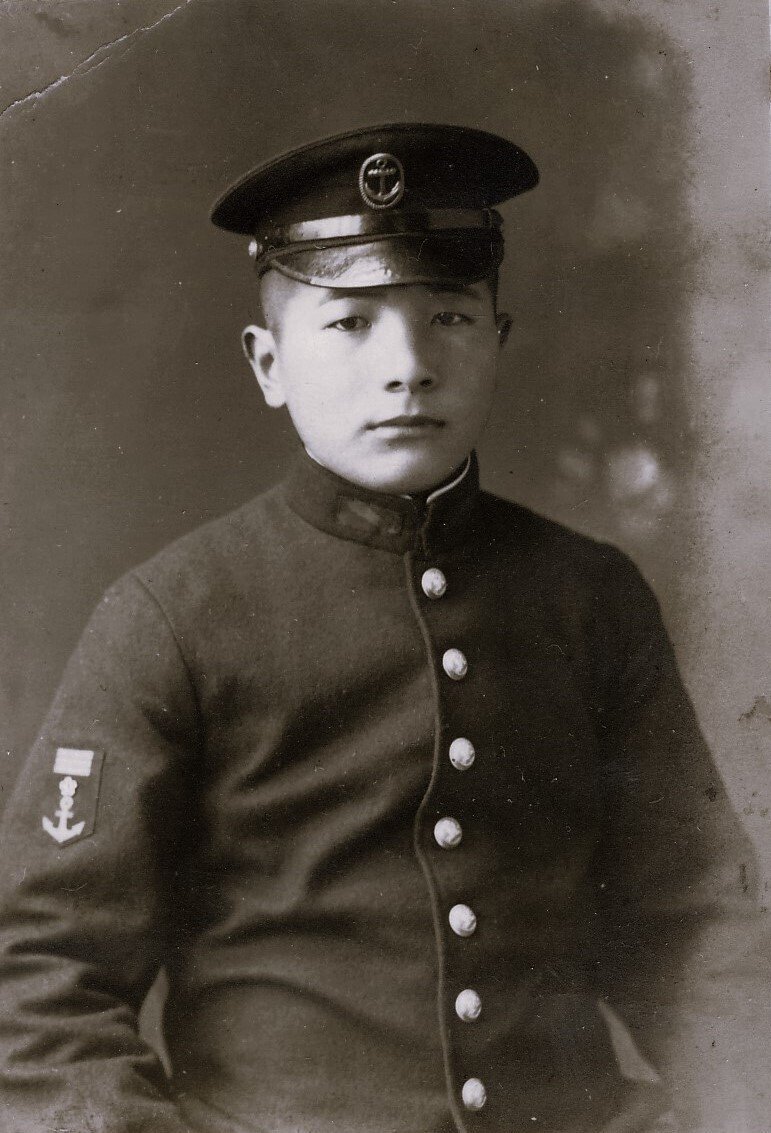
我々操縦練習生は7月29日、中間練習機課程の卒業となった。卒業飛行で、谷田部飛行場から霞ヶ浦航空隊飛行場まで、54機の大編隊飛行が実施された。
行きは小生操縦で霞空まで、帰りは後席同乗者と交代で谷田部空へと素晴らしい編隊飛行で卒業式を飾った。飛行後、司令より「貴様等は何時でも戦闘に連れていかれる技を習得した」とお褒めの訓示があった。


卒業直前に決められた機種別に分かれ、専修を受ける各航空隊に直行入隊した。専修の機種別は、艦上戦闘機(艦戦)96名、艦上攻撃機(艦攻)79名、艦上爆撃機(艦爆)32名、陸上攻撃機(陸攻)102名の4種類である。
水上機組は同じ飛練空で延長教育を受けた63名。艦戦は筑波空へ、艦攻は百里原空、姫路空へ、陸攻は豊橋空へ、小生は艦爆で宇佐空での実用機課程に即日赴任の令が下された。
投稿者のコメント:当時の訓練の様子を時にはユーモアを交えて表現しているのが、父らしいと感じました。しかし、見方を変えると、父は入隊後10ヶ月のこの時点で、爆撃機で高速低空飛行をしながら、地上にいる人間を民間人か兵員かを識別しつつ、機銃掃射ができる飛行技術を身につけていたということになります。これではユーモアではなく、ブラックユーモアになってしまいます。
このように、父が学んだ知識をすぐに試してみる姿勢や、体験から学ぶ意欲は、この時期から培われたのでしょう。ただし、現代(2025年)からの視点で見ると、これが軍事教育・軍事訓練の内容であるということが問題なのです。「科学技術の発展」=「軍事技術の発展」ではいけません。ここに人間の知恵と倫理観が必要になってくると思います。
今の時代は、さらに複雑な課題を抱えています。特攻ではなく、ドローンのような無人機での攻撃なら許されるのでしょうか?その延長線上には、「核ミサイル発射」コマンドを送信する「Enter」キーが見えます。そして、その飛翔体の目標はいつの時代も人間なのです。
あなたはどのようにお考えになりましたか?
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
次回へと続きます。
もくじ
終 章 「事後情報分析からの考察」
おわりに 「二つの命日」
資 料 「あの日の電信の意味するもの」
※ note掲載にあたって
この父の手記は、1990年(平成2年)頃から1995年(平成7年)頃に、父がワープロで当時の記憶をたどりながら、各種文献を基に記したものです。現在では、不適切な表現や誤った表記があるかもしれません。
また、歴史的検証や裏付け調査研究等は不十分です。その点をご理解の上、お読みいただければ幸いです。
