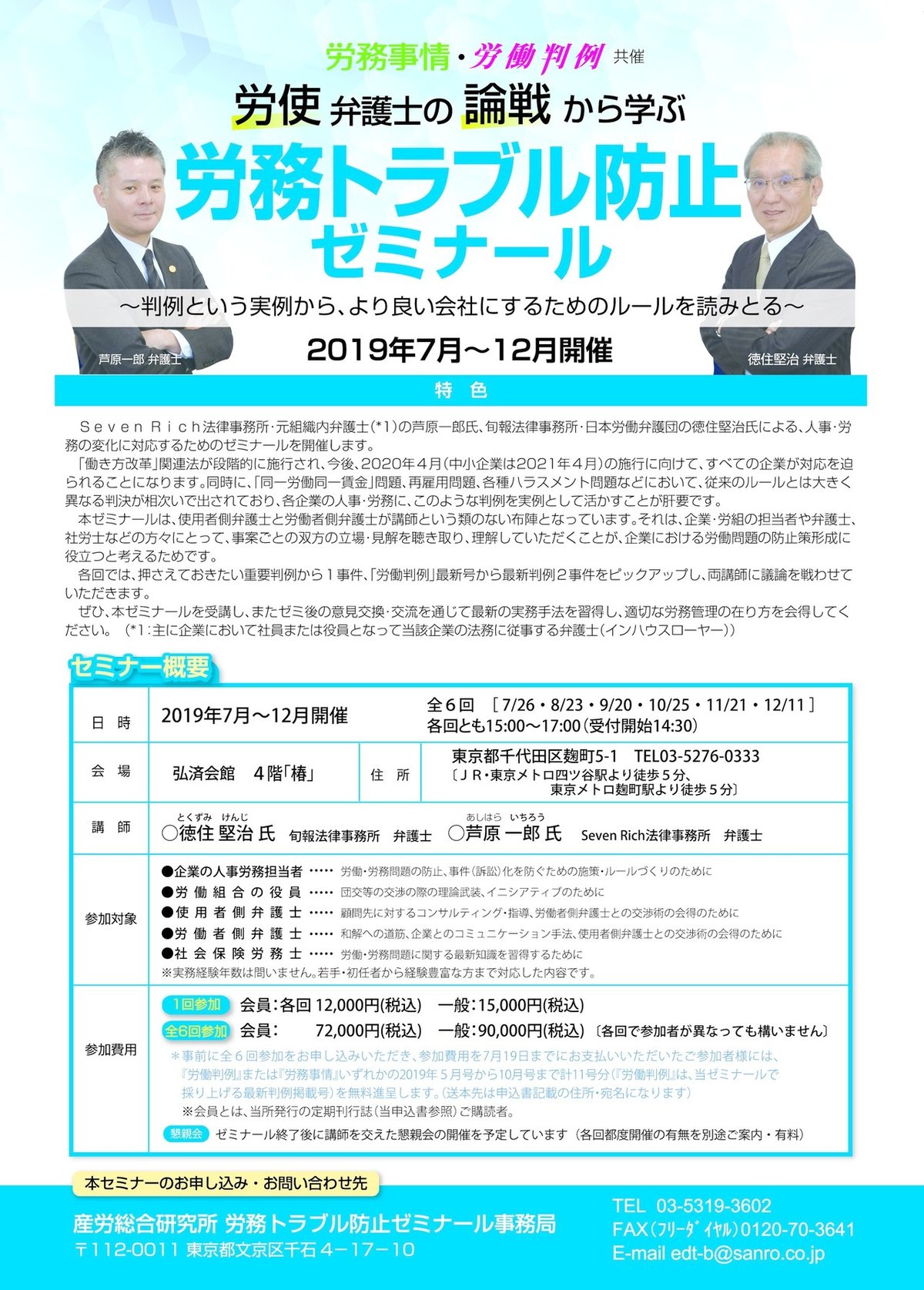松下幸之助と『経営の技法』#258
10/30 資本の暴力
~資本は現代において1つの強い力。正しく行使してこそ、社会に有益に働く。~
この会社では部品1個20円で売っていたのだが、最近ある大資本の会社が、この部品の製造にも乗り出して、これを10円で売り出した。どう会社を合理化しても、相手がこちらの半額ではとても競争できない。これでは会社がつぶれることは火を見るよりも明らかだから、ぜひ私の方で引き受けてくれ、と言われる。
「ではその相手のメーカーさんは、製造過程を改良してそんなに安くいってもいいほどコストが安くつくようになっているんですか」「いや、絶対にそんなことはおまへん。私も長年この仕事をやっているんでようわかってますが、とてもそんな値では売れるはずがない。これは結局、自分とこが大資本だというので損を覚悟で売りまくって、市場の占有率をうんと高めようとしてるのです」
一方だけの話で即断するのは危険だが、もしこれが事実なら、それは資本の暴力というものである。資本は現代においては1つの強い力なのである。これを正しく行使すれば、社会に有益な働きをするが、誤って使えばとんでもないことになる。私的な横暴となってその業界を乱し、ひいては社会全体に大きなマイナスを生み出してしまう。
(出典:『運命を生かす』~[改訂新版]松下幸之助 成功の金言365~/松下幸之助[著]/PHP研究所[編刊]/2018年9月)

1.ガバナンス(上の逆三角形)の問題
まず、ガバナンス上の問題を検討しましょう。
ここでは、特に経済市場での競争環境の話です。現在では、独占禁止法などで明確に禁止されているダンピング(不当廉売)に対し、松下幸之助氏が怒りを覚えている、という内容です。
このうち、トップが抱くべき「公のための怒り」は、昨日(10/29の#257)で検討しました。
すなわち、経営者は、合理的な競争環境の確立など、社会的に重要な問題については、ときに「怒り」を隠さず、しっかりと意見を言い、行動することが必要です。つまり、ここでは合理的な競争環境の確立のために、ダンピング(不当廉売)に対する「怒り」が表明されているのです。
ここで、ダンピング(不当廉売)の問題点についての説明は省略します。ビジネスに関わる場合、現在ではあまりにも常識的な問題だからです。
他方、特に注目したいのは、「資本」に対する松下幸之助氏のコメントです。すなわち、「(資本)は、これを正しく行使すれば、社会に有益な働きをする」という部分です。
この点は、松下幸之助氏がくり返し指摘する点ですが、資本主義経済の、市場での競争が、社会や国家にとっても有益である、という問題意識に通じるところです。日本でも、「三方良し」のように、ビジネスで利益を上げることは、自分だけのためではなく、取引相手や社会全体にとっても重要である、と言われてきたところですが、市場での競争もこれと同じだ、という思想を松下幸之助氏は、事業を開始したかなり早い段階から主張しています。
つまり、「資本」は、市場でのプレーヤーを意味します。しかも、特に大きな資本の場合には、体力も影響力も大きい巨大なプレーヤーになります。
そして、松下幸之助氏は、巨大なプレーヤーが存在すること自体は、否定していません。むしろ、「社会に有益な動き」をする可能性を認め、肯定的に評価しています。この意味で、「公正な競争」や合理的な競争環境と言っても、形式的な平等を強調し、巨大資本を否定する見解と明らかに異なります。プレーヤー自体の大小は、競争環境の問題ではないのです。
けれども、巨大資本がその影響力を不公正に用い、競争環境自体を破壊する行動を取ることは、許されないと評価しています。社会や国家のためにならないからです。
このように、松下幸之助氏が市場競争を理想とすること、形式ばった平等主義ではなく、現実的な公正さを重視すること、けれども、市場での競争環境を破壊したり歪めたりすることには、「公のための怒り」を表明し、絶対に許さないこと、が読み取れるのです。
2.内部統制(下の正三角形)の問題
次に、社長が率いる会社内部の問題を考えましょう。
会社としては、特に大きな会社になるほど、独占禁止法の定めるルール等、社会的なルールに違反したり、さらに社会に対して迷惑をかけるような行為をしたりする誘惑や危険が大きくなります。他方、これに反比例して、大きな会社になるほど現場の統制が利きにくくなっていきます。
一般的には「コンプライアンス」と言われる問題が中心となりますが、それに限らず、企業の社会的な責任やCSRなど、会社が社会に受け入れてもらえるための様々な問題にまで広がるべき問題です。会社の、外部的な環境に関わるリスクの問題であり、このようなリスクを無為無策のまま取ってしまわないように、会社体制やプロセスを作り上げることが、内部統制の問題です。
松下幸之助氏の言葉は、巨大資本に対する「公のための怒り」ですが、それは翻って、巨大資本であれば注意しなければならない問題でもあります。経営者個人の思いや願いで済む問題ではなく、組織全体に意識として浸透し、組織として対応できるようにすることが、経営者に求められるお仕事なのです。
3.おわりに
さらに、松下幸之助氏個人として注目されるのが、他の経営者から頼られ、氏も相談に応じている点、その内容に「公のための怒り」を覚え、問題提起をするほど、熱い気持ちを持っている点、けれども、「一方だけの話で即断するのは危険」と言い、冷静で客観的な視点を失っていない点です。
「心は熱く、頭は冷静に」「Warm at heart, cool at head」と言われる、ビジネスマンとしての在り方が明確に表れているように思われるのです。
どう思いますか?
※ 『経営の技法』の観点から、一日一言、日めくりカレンダーのように松下幸之助氏の言葉を読み解きながら、『法と経営学』を学びます。
冒頭の松下幸之助氏の言葉の引用は、①『運命を生かす』から忠実に引用して出典を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に了解いただきました。