
山腰亮介 主要著作目録
ヘッダー写真:中島七海
山腰亮介と申します。
瀧口修造を中心とした詩と芸術の研究とアーカイヴ構築、言語表現をおこなっています。
アーキヴィストとしては、慶應義塾大学アート・センターの所管する瀧口修造コレクションのアーカイヴ構築、その資料体を用いた展覧会の企画協力等の活動をしてきました。
ここでは、2015年以降に発表した主要著作の目録を公開します。
WEB上で発表したものはリンクからご覧いただけます。(2019年8月16日作成、2022年12月9日更新)
■目次
・詩集
・編著
・論文
・解説
・解説(共著)
・批評
・詩(WEBマガジン、同人誌)
・エッセー
・座談会
・展覧会・イヴェント
・研究発表
・その他
・二次文献
■詩集
以下の詩集はこちらからご購入いただけます
『ひかりのそう』
テキスト・デザイン・発行:山腰亮介
印刷:グラフィック
発行日:2019年7月7日
詩を束ねることが詩集の定義であるならば、形体を本に限る必要はないのではないか。一枚の紙でのみ可能になる表現があるのではないか。そのような問いとここに束ねられたテキストが、私にこの形体を選ばせました。

『ときのきと』
テキスト・デザイン・発行:山腰亮介
発行日:2022年7月7日
「ゆきのきと」「ときのきゆ」の二篇を収録した、一枚の「詩集」。
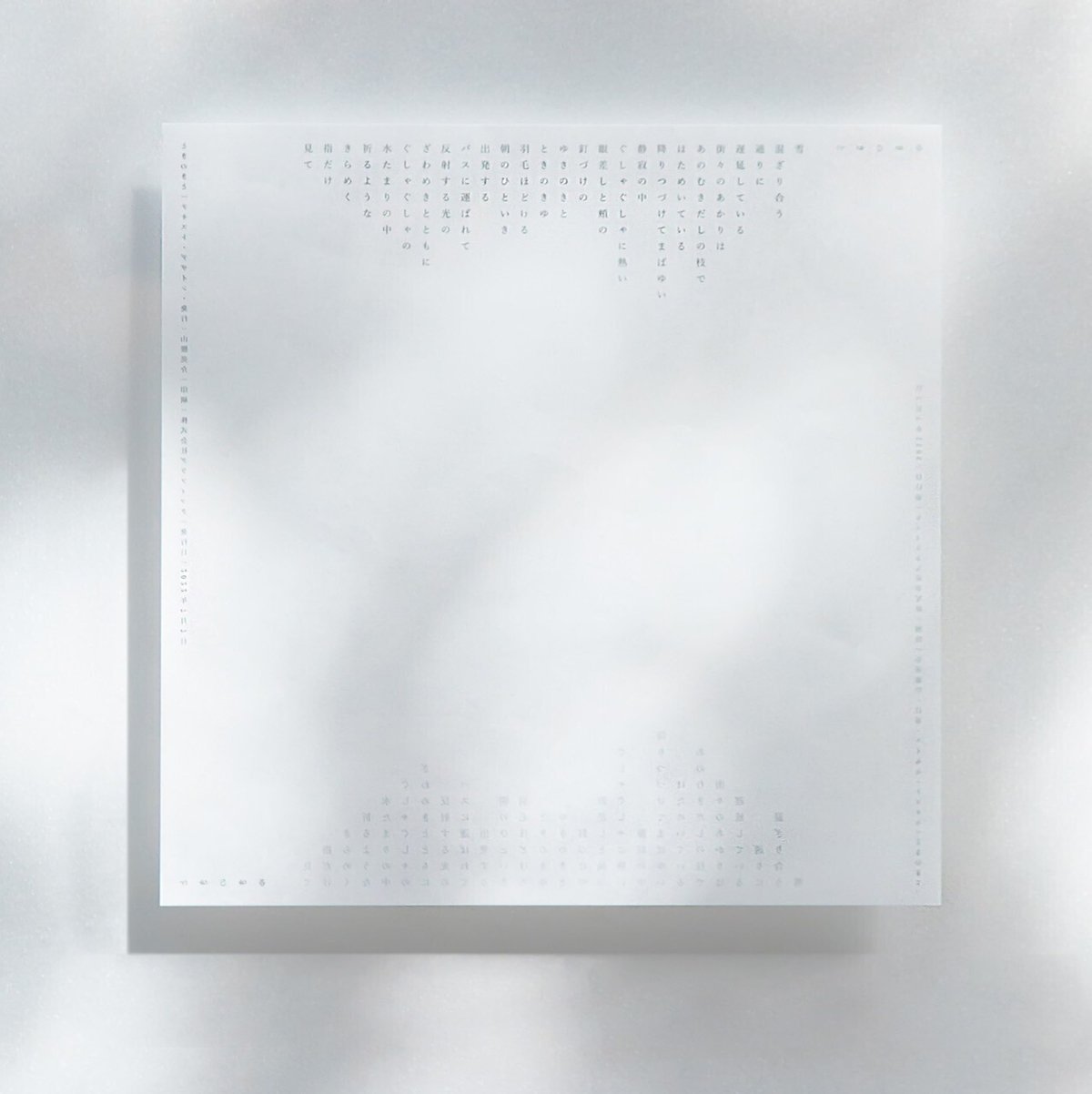
・『なつのあと』
テキスト・デザイン・発行:山腰亮介 2022年12月7日発行予定近刊(発行時期未定)
この詩集にはオンデマンド版があります。「詩客」(2022年11月19日号)にて公開中。[最終閲覧日:2022年12月2日]
■編著
久保仁志、山腰亮介、常深新平編『中嶋興年表』慶應義塾大学アート・センター、2019年、[ポスター]
山腰亮介+中村陽道編『——の〈余白に〉』1号、——の〈余白に〉、2022年
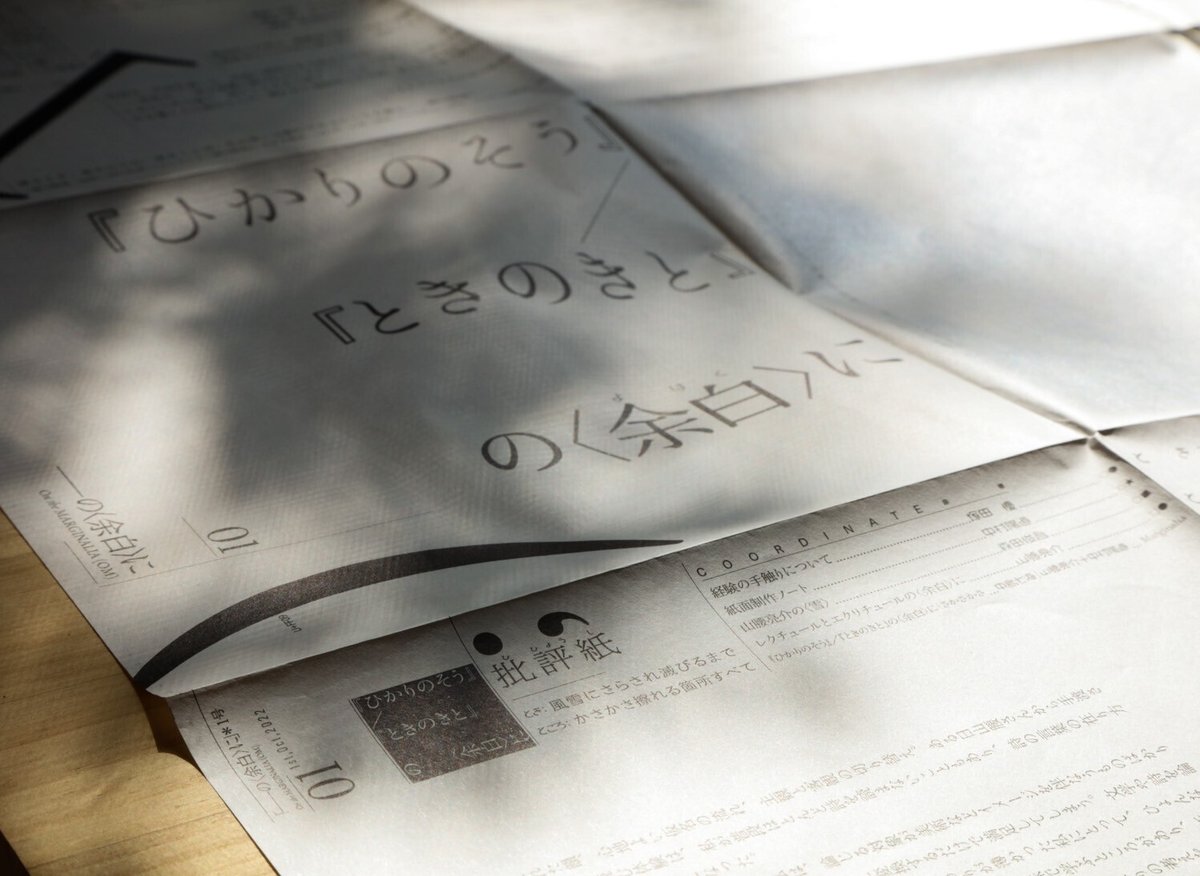
■論文
山腰亮介「『余白に書く』、あるいは一冊の書斎」『余白の部屋(アート・アーカイヴ資料展 XVI「影どもの住む部屋——瀧口修造の書斎」カタログ|KUAS-36)』慶應義塾大学アート・センター、2018年、3-37頁
山腰亮介「纜を切ること——「瀧口修造の詩的実験 1927—1937 添え書き」という記録を切り離す行為について」『瀧口修造研究会会報 橄欖』第4号、瀧口修造研究会、2018年、35-42頁
山腰亮介「瀧口修造の〈余白〉: 層|透明|痕跡|註記|影|編集(順不同)」『現代詩手帖』11月号、思潮社、2019年、34-41頁
■解説
山腰亮介「本とは発生のちからが、そのなかに、動き、流れ、循環し、衝突し、あるいは和解し、さらに流動しつつある生存である——Klee」『本影の本(アート・アーカイヴ資料展XX「影どもの住む部屋II —瀧口修造の〈本〉—「秘メラレタ音ノアル」ひとつのオブジェ」カタログ KUAS-43)』、慶應義塾大学アート・センター、2020年、7頁
山腰亮介「本とは透明の腕による貼りまぜである——MAX WALTER SVANBERG☆obsédé par femme.☆Six poémes」同上、12頁
山腰亮介「本とは頁と頁、行と行のあいだで紡がれる星座である——星は人の指ほどの」同上、14頁
山腰亮介「本とは記録であり、記憶を編集するための装置であり、補遺である——執筆記録」同上、23頁
山腰亮介「本とは、言葉/オブジェを捕獲する装置である。——手づくり本と命名」『本影の本 補遺(アート・アーカイヴ資料展XX「影どもの住む部屋II —瀧口修造の〈本〉—「秘メラレタ音ノアル」ひとつのオブジェ」カタログ KUAS-43)』、慶應義塾大学アート・センター、2020年[リーフレット]
■解説(共著)
山本浩貴、h、久保仁志、山腰亮介「本とは世界と私が「建築=詩」を始める最初の場である——『見える本』|A VISIBLE BOOK/The Visible Book」『本影の本(アート・アーカイヴ資料展XX「影どもの住む部屋II —瀧口修造の〈本〉—「秘メラレタ音ノアル」ひとつのオブジェ」カタログ KUAS-43)』、慶應義塾大学アート・センター、2020年
久保仁志、山腰亮介「本とは狂騒的物体に向かいながら行われた記録における抵抗のプロセス自体の記録である——CINÉMA 'film d'AVANT GARD」同上
山腰亮介、久保仁志「本とは封印された鏡像の鏡像である。——1939 Rrose Sélavy 1966」同上
久保仁志、山腰亮介「本とは余白の蛇である。——余白の蛇:7つの詩と絵|LE SERPENT MARGINAL: 7poémes&images」同上、20頁
久保仁志、山腰亮介「本とは不可視の透明カヴァーに包まれた、無数の線である——Rrose Sélavy」同上
山腰亮介、久保仁志「本とは、部屋の模型であり、「影どもの住む部屋」とは「手づくり本」の模型である——1960」同上
■批評
山腰亮介「「『新しい世界』(ソウル・スタインバーグ):魔術的なものと脱魔術的なもの」の余白に」[「影どもの住む部屋──瀧口修造の書斎」展関連イヴェント|石岡良治×久保仁志によるトークのレヴュー](慶應義塾大学アート・センターHP)、2018年[最終閲覧日:2022年12月2日]
山腰亮介「「書斎、境界線の移動、または唯物論と信仰について」の余白に」」[「影どもの住む部屋──瀧口修造の書斎」展関連イヴェント|土屋誠一×久保仁志によるトークのレヴュー](慶應義塾大学アート・センターHP)、2018年[最終閲覧日:2022年12月2日]
山腰亮介「「個別性と一般性の対が科学的実験を規定し、単独性と普遍性の対が詩的実験を規定しているのならば、その四項を柱とした部屋をうろうろ歩く「私(たち)」とその部屋に映し出される物たちの群れを「レイアウト」すること、「影どもの住む部屋」とはその過程で生まれるいくつもの書物のことではないだろうか。」の余白に」[「影どもの住む部屋──瀧口修造の書斎」展関連イヴェント|山本浩貴(いぬのせなか座)×山腰亮介×久保仁志によるトークのレヴュー](慶應義塾大学アート・センターHP)、2018年[最終閲覧日:2022年12月2日]
山腰亮介「からつき七緒「ところについて」の〈余白〉に」(WEBマガジン「詩客」今月の自由詩第24回)、2019年[最終閲覧日:2022年12月2日]
■詩(WEBマガジン、同人誌)
山腰亮介「(夜の肌に呼吸が触れている)」(WEBマガジン「詩客」)、2015年[最終閲覧日:2022年12月2日]
山腰亮介「(秋の眼の内側にうち寄せてくる)」(WEBマガジン「詩客」)、2015年[最終閲覧日:2022年12月2日]
「(かつて おおきな生き物の背中に)」『白仲本』第二冊、白仲会[私家版]、2015年
「(丘陵の肋骨があたりを張りめぐる)」『白仲本』第三冊、白仲会[私家版]、2016年
山腰亮介「(動植物の休息を攪拌する)」(WEBマガジン「詩客」)、2016年[最終閲覧日:2022年12月2日]
山腰亮介「(豹の瞳光が月の匂いを注視している)」(WEBマガジン「詩客」)2016年[最終閲覧日:2022年12月2日]
山腰亮介「(冬の夜の気配が窓ガラスに頬をよせる)」『白仲本』第四冊、白仲会[私家版]、2016年
山腰亮介「(さくらんぼの応答がながれてゆく)」『白仲抄1』白仲会[私家版]、2018年(デザイン:山腰亮介)

■エッセー
「アーカイヴ——驚異の部屋、あるいは編集の驚異」『慶應義塾大学アート・センター ARTLET』第51号、2019年
■座談会
久保仁志、山腰亮介、山本浩貴、h「座談会 「影どもの住む部屋」の余白に : 閉じよ、手を引け、纜を解け」『現代詩手帖』11月号、思潮社、2019年、10-27頁
■展覧会・イヴェント
「影どもの住む部屋──瀧口修造の書斎」(主催:慶應義塾大学アート・センター|場所:慶應義塾大学アート・スペース|会期:2018年1月22日-3月16日)〈特別協力〉
「ポエジー・クリティック1:「身体/言語的身体」と「言語/身体的言語」」(トーク&ポエトリー・リーディング|出演:長谷川六、野村喜和夫、岩切正一郎、渡辺めぐみ、森川雅美、芦田みのり、川津望、山腰亮介|場所:エルスール財団記念館~詩とダンスのミュージアム~ブックカフェ「エル・スール」|日程:2018年11月3日|企画:喜和堂(山腰亮介、川津望、山口勲))〈企画・司会・フライヤーデザイン〉
■研究発表
「〈視覚詩〉をどう読むか?:フランス近現代詩から瀧口修造へ 『黄よ。 おまえはなぜ』と『《稲妻捕り》Elements :《稲妻捕り》とともに』の「余白」に流れる時間性」(「フランス現代詩研究会」|日程:2018年9月25日|場所:東京/パリ(オンライン))[最終閲覧日2019年8月15日]
■その他
『日曜日の散歩者 わすれられた台湾詩人たち』[映画パンフレット]太秦、2017年(編集協力)
巖谷國士監修『絵本とメルヘン 明治学院大学図書館貴重書コレクション』明治学院大学図書館、2018年(執筆・編集協力)
■二次文献
佐峰存「自由詩時評第177回」(WEBマガジン「詩客」)、2015年[最終閲覧日:2022年12月2日]
佐峰存「自由詩時評第219回」(WEBマガジン「詩客」)、2018年[最終閲覧日:2022年12月2日]
伊藤琢麻「報告」(Atelier/Poétique)、2018年[最終閲覧日:2022年12月2日]
望月遊馬「ほんとうに正直なものを記述する」『びーぐる 詩の海へ』第57号、澪標、2022年、106–109頁
一方井亜希「不確かなものを見つめる目 新鋭展望」『現代詩手帖』12月号、思潮社、2022年、64–73頁
