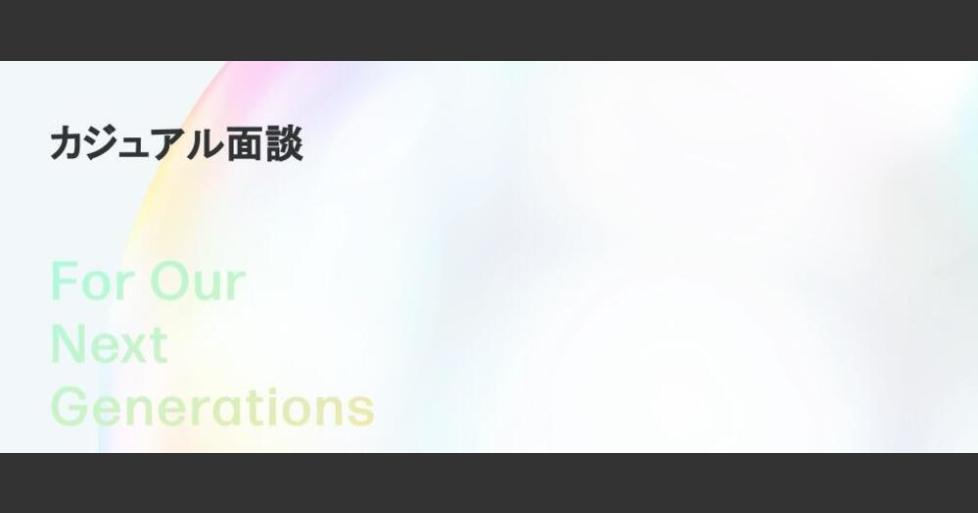スタートアップで広がる、高専出身エンジニアのキャリアの可能性
今回の記事では、一貫教育を通じて専門的な知識や技術を習得できる高等専門学校(以下、高専)に着目し、当社でエンジニアとして活躍する高専出身の藤井さんと、高専採用を含むエンジニア採用に取り組む人事の清水さんのインタビューをお届けします!
採用の具体的な取り組みや高専生に期待すること、高専での学びが仕事にどのように活かされているのかなどについてお伺いしました。ぜひ最後までご覧ください!
ZENKIGEN
人事・広報部 採用広報チーム 兼 harutaka事業部 マネージャー
清水邑(しみず ゆう)
2013年 株式会社イノベーションに新卒入社。BtoB営業/マーケティングのコンサルタント営業として、同社が上場までの4年間、数百社以上の顧客支援に携わり同社の成長を牽引。2018年、第一号社員として創業直後の株式会社ZENKIGENへ入社。新規営業、CSなど立ち上げ期のBusiness Divisionを牽引。2023年より現在の役職に就任。
ZENKIGEN
新規事業部 兼 harutaka事業部 開発チーム エンジニア
藤井駿吉(ふじい しゅんきち)
1998年三重県生まれ。鈴鹿工業高等専門学校電子情報工学科を卒業後、2019年に新卒でSI企業に入社。その後、フロントエンドエンジニアに興味を持ち転職。2022年4月よりZENKIGENに入社し、既存プロダクトの開発や保守運用を経験。現在は新規プロダクトの開発を担当。
市場価値を高め、新しい時代をつくるエンジニアへ
ーZENKIGENは現在エンジニア採用を強化していますが、その中でなぜ高専に注目しているのでしょうか?
清水:高専に注目した理由として、大きく分けて「決断力」と「技術力」という2つの視点があります。
まず決断力の観点では、高専生は、15歳という若さで自分の進路を決断している点が素晴らしいと感じています。社会全体を見ても、これほど早い段階で将来の道を選ぶ人は少ないのではないでしょうか。私自身の経験を振り返ってみても、中学3年生の頃は部活に夢中で、進路について深く考えられていなかったと思います。それを考えると、エンジニアリングやものづくりという専門的な道を選ぶ意志の強さや、将来へのビジョンの明確さには大きな魅力を感じます。純粋に応援したい気持ちもありますね。
また、技術力の観点では、高専ならではの特異なカリキュラムや、5年間の一貫教育が育む技術的な洗練度にも注目しています。基礎的な知識を身につけたうえで、専門的なカリキュラムを通じて実践力を養える点は、高専教育の大きな強みです。このようなバックグランドを持つ方々とぜひ一緒に働きたいと思っております。
ーエンジニア職にも様々な種類がありますが、ZENKIGENではどのような役割を高専生に期待していますか?
清水:主に「ソフトウェアエンジニア」と「データアナリスト」の2つの職種を中心に考えています。ですが、入社後にはその方の適性や志向をしっかり見極めながら、一緒にキャリアを形成していきたいと考えています。
また、高専生に限らず、新卒で入社してくれたエンジニアやデータアナリストの皆さんには、ZENKIGENの環境を最大限活用していただき、ともに成長したいと願っています。生成AIの登場によって、これからの時代では高度な知識や技術を駆使できる人材がより一層重要になり、求められるスキルがさらに進化していくことが予想されます。
ZENKIGENは膨大なデータを保有しており、新しいサービスやプロダクトの開発、PoC(概念実証)を実践できる環境が整っています。こうした環境を活用することで、経験を積みながらスキルを磨き、市場価値をも高めていただきたいと考えています。

学生の視野を広げる—ZENKIGENが描く採用の意義
ー職種として市場価値を高められる環境があるのは理想的ですね!
では、そんなZENKIGENで現在取り組んでいる高専採用について、具体的に教えてください。
清水:実際には顧問を通じてご紹介いただいた高専を訪問させていただき、会社説明を通じて先生方との関係を築いたり、学生さんには最新のトレンドをセミナー形式でお伝えする活動を行っています。
こうした活動を行う中で、先生方から「生徒が最新のAI技術の社会実装についてや業界動向に触れる機会が少ない」というお悩みをよく伺います。ZENKIGENはまさにその最前線で事業を展開していることもあり、AIの歴史や概要に関するセミナーを実施させていただくと、とても喜んでいただけるんです。
もちろん、最終的にZENKIGENに興味を持っていただけたら嬉しいですが、それ以上に高専の生徒、先生方が抱える課題に寄り添い、皆さんとの関係性を深めることを大切にしています。
ーそのような取り組みが、どのような効果や可能性につながっていると感じていますか?
清水:セミナーを企画する中で、会社をご紹介させていただく時間も自然と生まれ、それが結果的に働く仲間とのご縁にもつながると良いなと考えています。
また、学生生活を送る中で、社会に出ている大人の話を聞く機会は意外と少ないのではないかと思います。実際に、「特定の分野の企業しか知らなかった」「こういうキャリアの考え方もあるんですね」といった声を学生さんからいただくことが多いです。
自社の採用に直接結びつかなくても、未来を担う若者の視野を広げ、選択肢を増やすきっかけを提供できることには大きな意義があると思っています。これこそが、ZENKIGENの採用活動が持つ重要な役割だと考えています。
高専での学びが「挑戦」を支える
ーここからは藤井さんに、ご自身のキャリアについてお伺いしたいと思います!これまでの経歴と、ZENKIGENでの現在の業務内容について教えてください。
藤井:私は鈴鹿高専の電子情報工学科に5年間在学し、主に「電気」と「情報」の2つの分野について学びました。卒業後はSIer企業にSEとして就職し、その後フロントエンジニアという職種に興味を持ち、SES企業へ転職しました。さらに、より高度なことに挑戦したいと思い、ご縁があってZENKIGENに入社しました。
現在は新規事業部で、目標設定をサポートする「コレドウ」というAIプロダクトの開発、運用を行っています。主にフロントエンド全般を担当しており、新規機能の開発に日々取り組んでいます。
ー高専で学んだことが、これまでのキャリアや実際の業務においてどのように活かされていると感じますか?
藤井:そうですね。やはり、高専で培ったプログラミングやIT関連の基礎知識があったおかげで、新卒の頃のスタートダッシュは比較的早かったのではないかと思います。この基礎があったからこそ、これまでの仕事において、自分の専門外の業務を任された際にも、新しい挑戦として自然と受け入れられ、前向きに取り組める土台ができたと感じています。
また、高専での学びと業務で必要とされる知識は重なる部分も多いため、それを実践でどのように活かすかを、経験を通じて磨いていくことが大切だと考えています。

ー藤井さんが仕事をする上で、大切にしていることは何でしょうか?
藤井:いろいろありますが、仕事の中で「楽しさ」を見つけることを一番大切にしています。日々の業務を通じて、新しい学びや挑戦の機会があると、より主体的に業務に取り組むことができると感じています。
現在はフロントエンドを主に担当していますが、新しいプロダクトゆえに、バックエンドやインフラなどにも関わる機会があり、その都度キャッチアップしながら学習できることがとても新鮮で刺激的です。ZENKIGENの新規事業部ではこうした挑戦の場があり、スキルを広げながら仕事を楽しむことができていて、とても充実しています!
若さを生かした挑戦で、自分の人生を生きよう
ー最後に、高専出身の先輩として、そして採用担当者として、高専生へのメッセージをお願いします!
藤井:私からのメッセージは、「何にでも挑戦してほしい」ということです。高専生の最大のアドバンテージは「若さ」だと思います。挑戦してみて「合わない」と感じても、若さがあれば次の一歩を踏み出すことができます。だからこそ、若いうちに「これだ!」と思えるものを探し、どんどん挑戦してほしいです。ZENKIGENは、そんな皆さんの挑戦を全力で応援します!
清水:自分の人生を、自分の意思で切り拓いてほしいと思います。ご自身で決断し、情報を集め、周りの意見に流されるのではなく、自分の意思で社会人としての第一歩を踏み出していただきたいです。その選択肢の一つとして、ZENKIGENとのご縁があれば嬉しいですし、私たちは皆さんのキャリアや将来に真剣に向き合い、全力でサポートする覚悟があります。
ぜひご自身の決断を大切にして、納得のいく道を歩んでください!

(撮影場所:WeWork 城山トラストタワー 会議室内)
最後までお読みいただきありがとうございました!
\ZENKIGENは採用を強化しております/
ZENIKIGENのエンジニア・データアナリストについては、ぜひこちらの記事も合わせてご覧ください。
カジュアル面談も大歓迎ですので、当社にご興味をお持ちいただけた方は、お気軽にエントリー・お問い合わせをお待ちしております!