
あり得ない日常#85
子供たちの前では滅多に苦しさを見せない咲那さんだが、彼らが教務センターの学習室へ勉強をしに行っている間だけは解放される。
とはいえ、他人の前でみっともない姿をさらしたくないという芯の強さもあって、わたしの前ではおろか旦那さまである社長の前でも、そう簡単に弱音を吐くような人ではない。
社長のほかに取締役が二名いるから、最悪社長は彼らの方針に判断をするだけで問題はないが、例の事件の反省もあって、把握していない事があってはまずいと出来るだけ直接現場に関わる姿勢を見せている。
そのため、気が休まることが無いのは容易に想像ができる。
しかも、健康保険制度の廃止も相まって実現した最低給付保障制度によって、ある程度の所得がある世帯はその医療費のほとんどを自費で賄う必要があるから稼ぎを減らすわけにもいかない。
財団に申請すれば、小さな子供を育てていることもあって3割くらいの負担にしてもらえるかもしれないが、いかんせん本人の咲那さんが延命治療を望んでいないので、社長としては個人的にも辛い日々が続いている。
咲那さんの入院に同行した際にその気持ちを吐露されたことがあった。
「僕は、妻に生きて欲しいとこんなにも願っているのにさ、どうしても叶えてくれるわけにはいかないんだろうな。」
タクシーの窓から今にも雨が降りそうな曇り空を見上げつつ、そう小声で問われたか独り言なのかわからない叫びに対して、答えられる言葉をわたしは持ち合わせていなかった。
由美さんとキッチンに並んでいたこともあって、ある程度の料理はできるようにはなっていたが、それがこんな風に活かすことになるとは思っていなかったな。
新しい事務所が入るビルの上に自宅を移してから、あの事件の事もあって咲那さんはわたしの顔を見るたびによく自然に招いてくれた。
うちの子たちがあなたによく懐いているからと言っていたが、今からよく思い返せばこうなることを考えていたのかもしれない。
その代わりと言えるのかわからないが、社長がよく自宅を留守にしつつ、各拠点の効率化に力を注ぐようになったからだ。
設備のモニタリングなどは人員を割かなくても実現できる。
本当は奥さんと一緒にいる時間を多く作りたいだろうに。
日本でも人が多く集まり住む地域では、それだけ人気が高いために賃貸でも住居を構えて維持するのはそう簡単ではない。
最近ではついに最低給付保障制度でもらえる金額では賄いきれなくなってきたため、ここで生活を続けようと思うと一般人は会社にどうにかしがみつくほかなく、それができなければ地方に脱出するしかなくなる。
社長の努力で、ある程度自動化が実現しつつあるこの会社にわたしは社員としていつまで居続けることができるだろうか。
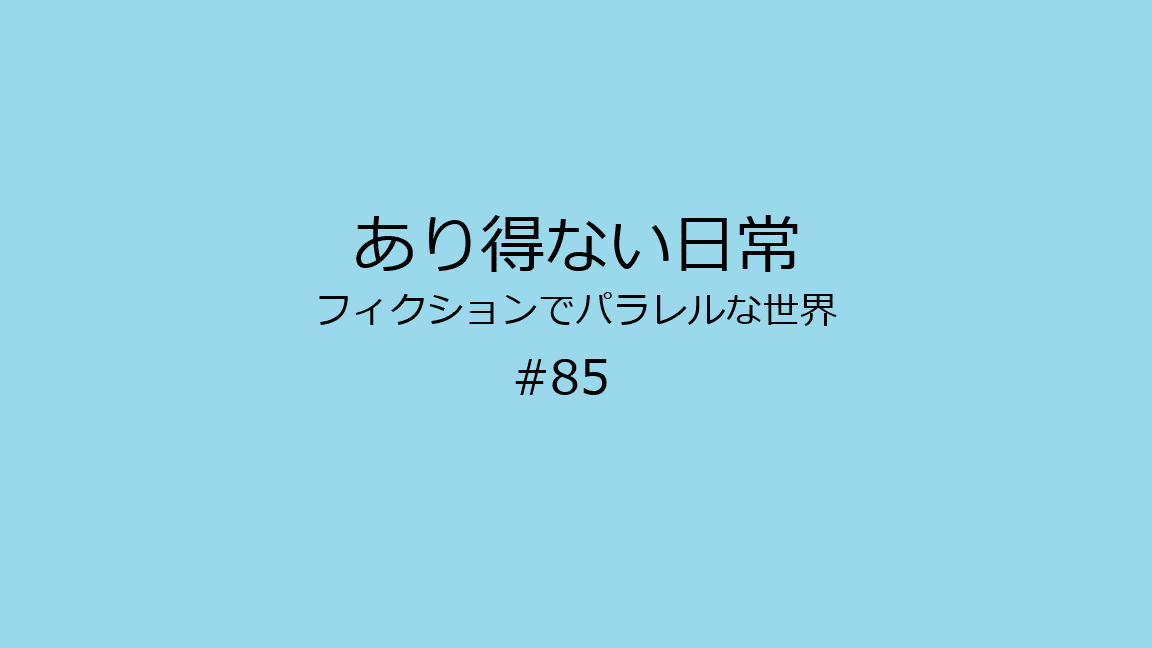
※この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在する人物や団体とは一切関係がありません。
