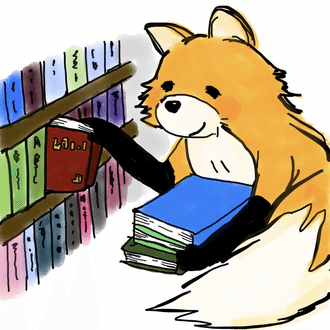“打たれ強くなりたい(切実)”《マガジン“新書沼にようこそ” vol.9》
『打たれ強くなるための読書術』/東郷雄二
読書における「打たれ強さ」とはなにか。それは解答がひとつではないということに耐え、複眼的な見方で本を読むことができるということである。「どのように世界を理解するか」に重点を置くあり方とも言い換えられよう。本書は、そのための本の探し方から、段階を踏んだ読書、読んだ本の活用法など、しっかり使える技術を伝授するものだ。この技術を磨いてゆくことで、これまでとはひと味違う成熟した、「大人」の読書が成立するのである。
落ち込んだ時に読む本とか読書術という意味ではなく、「知的に打たれ強くなる」ための読書術とのこと。
著者は京都大学工学部から文学部に「文転」し、言語学の教授となったちょっと変わった経歴の持ち主。
すでにあちこちで指摘されていることではあるが、最近の大学生の変化のなかでいちばん気になるのは、以前に較べて「知的に打たれ弱くなっている」のではないかという点だ。
これを仮に「知的に打たれ弱い症候群」と名づけておこう。この症候群は次のような具体的症例を示す。
・すぐに解答を欲しがる
・どこかに正解がひとつあると信じている
・解答に至る道をひとつ見つけたらそれで満足してしまう
・問題を解くのは得意でも、問題を発見するのが不得手である
・自分の考えを人に論理的に述べる言語能力が不足している
では「知的に打たれ強い」とは?
「知的に打たれ強い」というのはどういうことだろうか。それはいろいろなことについて知識を豊富に持っていて、議論で常に相手を言い負かすということだろうか。いや、そうではない。それはひと言で言うと、「正解のない世界に耐える」ということであり、ビター・チョコレートのように苦み走った大人の態度なのだ。
2008年出版ですでにこう言われているわけで。
いわんや現在をや…ですね。
読書術そのものは是非読んでいただくとして、著者の読書に対する姿勢の、面白かった(共感した)ところを引用紹介します。
書店で本を買うのがふつうだった時代の話だが、私には本を買う時に実行していたいささか乱暴な三原則というのがある。(一)本は見つけた時に買え(二)買うか買わないか迷ったら買え(三)値段を見ないで買え、というものである。
これをね、ネット書店でやるとえらいことになります(電子書籍ではなく、ECサイトで紙の本を買った場合の話)。
なんといってもレジまで持って行く物理的重さがないんですから。
めっちゃ買っちゃったなーなんて、のんきなこと言ってると、後日とんでもない量が届くなんてことも。
こわいこわい。
私はかねてより積ん読にはそれなりの効用があるのであり、決して日陰者として扱ってはならないと言じて止まない者である。
(中略)
読書人で積ん読をしていない人はいない。もっともあまり机の上に積み上げると、そのうち崩落して人体に危害が及ぶこともあるので、積み方には各自工夫を凝らされたい。
こういうダメな読書人の言葉、大好物です。我が意を得たり!というか、援軍来たり!というか。
こちらの本、著者の別著『独学の技術』の中の「独学のための読書術」という章を発展させたものとのこと。『独学の技術』は先日買ってみたあとに、亡き父の本棚からも同じものを見つけたという、なかなかに感慨深い一冊。
父はちゃんと書き込みなどもしながら読んでいた様子。せっかくなのでそれを手元に置き、自分が買った本は手放しました。
ちなみに本書での読書術の参考にしたと紹介されていたのが『本を読む本』。
これ、1940年にアメリカで刊行された本なのに、今言われている読書術ほとんど網羅されているんです。
さすがに電子書籍やSNS、AIの活用についてはないけれど。
でも読書というものの普遍性をひしひしと感じることが出来ます。
私自身も珍しく、書き込みなどもしながら読みました。
おすすめです。
最後までご覧下さり、ありがとうございました。 どうぞ素敵な読書生活を👋📚
いいなと思ったら応援しよう!