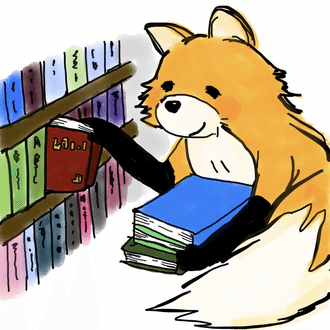“新書沼の入り口”《マガジン“新書沼にようこそ” vol.24》
『毒草を食べてみた』/植松黎
たった0.06ミリグラムで巨象を打ち倒すバッカク。天武天皇系の皇位が天智天皇系に移る一年前、正倉院から密かに持ち出された毒草冶葛。絶望的な激痛から人類を救い出したケシ。高速道路のかたわらで、青酸カリより激しい毒草としての甦りを待つキョウチクトウなどなど、人間の生と死をあやつる毒草は私たちのすぐそばにいる。これは、そうした毒草を食べてしまった人たちの世にも怖ろしい44の物語である。
記憶が確かなら、この本が私の新書沼の入り口の一冊。
初版が平成12年。
西暦2000年。
若かりし頃の樹田が、手に取ったのが、書店での新刊だったか、当時住んでいた大学近くの図書館の棚だったか、定かではないのですが、こんな面白い本があるんだ!としばらく何度も読んでいたことは今でも覚えています。
引越しやら 何やらでとりまぎれ、今、手元にあるのは再購入したもの。
この本のおかげで、毒とか、薬とか、興味持つようになったようにも思います。
まずタイトルがいいですよね。
身も蓋もないw
そして、内容は植物ごとに章がわかれ、大体4ページ程度にまとめられ、エッセイ的で読みやすい。
決してふざけたものではなく、それぞれの歴史や作用、現代の事件等まで幅広く取り上げられ、興味がそそられます。
(注:食べてみたくなるという意味ではない)
再販されるとしたら、図版がカラーだと嬉しい。
美しい花とか言われると、カラーで見てみたくなるので(本書は白黒なので、気になった時はスマホで調べてます。至極便利)。
ぱらっと開いて、気になるところから読めばいいので、ここでは私が何度読んでも驚いてしまう箇所をひとつ紹介。
イギリスの植物でもっとも猛毒といわれるセイヨウイチイも、そのなかで大枝をのばし、針のような葉の茂みのあいだから真っ赤な実をのぞかせている。イギリス人が昔からもっとも親しんできたこの木は、キリスト教が伝わるはるか昔に仰されていたドルイド教のシンボルであり、イングランドの歴史や文化に深く根ざしてきた。
この記事だけでは、何が驚愕?と思われる方。
次の写真をご覧ください。

これ、食べたことある!!
って人いませんか?
令和の時代にはいないかもしれませんが……平成でもいないか……
樹田、昭和の時代生まれなので、まぁ、その辺の実を食べるとかデフォルトだったので←昭和生まれ関係ある?←いやしいだけw
私も毒、食べてた!
イチイの毒成分は、葉(落葉)にも、枝にも、タネにもすべてにふくまれている。しかし、赤く熟した生の実の部分だけは毒をもたない。だから、昔の人は「子供の頃はよく、この甘い実を食べたものですよ」という。
はい、昔の人です。
甘くて美味しかったですよ←
タネとかかじったり、飲み込まなくてよかったー命拾ったー
と、何度読んでも思ってしまう次第。
同じこと繰り返してしまう…
これも老化でしょうか、汗
と、まぁ、身近な植物の毒を知るのに役立ち、読み物としても面白い一冊。
ぜひ一度読んでみてください。
こちらはもはや文学的な一冊。
今読むと、ところどころ「ふてほど」(←すみません、みてないけど使ってみました…)なところもあるけれど、それもまた一つの歴史ということで。
最後までご覧下さり、ありがとうございました。 どうぞ素敵な読書生活を👋📚
いいなと思ったら応援しよう!