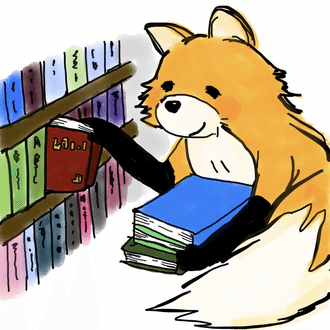“稼ぐ予定、残念ながらないけれど”《マガジン“新書沼にようこそ” vol.16》
『書いて稼ぐ技術』/永江朗
フリーライターは名乗れば誰でもなれるが、それで食べていけるかどうかが肝心。
何をどう書き、得意ジャンルをいかに確立するか。
自らのキャリアをどのようにデザインするか。
そして、世間をどう渡っていくかー。
文筆稼業25年の著者が自らの体験を披瀝し、「書いて生きる方法」を説く。
永江朗さんは読書のことなどを中心に、様々に活躍されるライターさん。
好きな著述家さんのお一人です。
今回、本棚から引っ張り出し、手に取ったのは永江氏の『書いて稼ぐ技術』。
と言っても、別に稼ぐ予定があるわけではなく。
最近、こうやってnote再開したので、「書く」ことをもう少し上手く形にできたらなと思ったので。
長年の経験を活かしたライターの技術の中で、ここでは取材としての「読書術」から一部紹介。
資料の基本は本です。どんな本をどう読むかによって、フリーライターの仕事の質は決まります。趣味で読むのではありませんから、好きな本だけ読んでいればいいというものでもない。ときには苦手なジャンルや嫌いな人の本も読まなければなりません。苦痛でも退屈でも、我慢して読むしかありません。
ここ↑、自分が著述を生業には出来そうにないところです。
苦手なジャンルはともかくとして、嫌いな人の本を読むことは精神的に耐え切れないだろうなと。
その苦行を乗り越える著者さん達に改めて敬服するばかりです。
資料を読むときは付箋を活用します。気になったところ、これは原稿に使えると思ったところには、どんどん付箋を貼っていきます。付箋なんて貼らなくても、ページをめくればすぐ見つけられるさ、と思ったりもするのですが、やはり付箋を貼るのと貼らないのとでは、後での作業効率がぜんぜん違います。
私も付箋派なので、こういう意見を聞くと嬉しくなります。
本は増え続けます。本棚を眺めて、十年以上開いたことのない本は、もう処分してしまってもいいでしょう。これまで十年読まなかった本は、今後の十年も読まないでしょう。読まない本に埋もれて、読むべき本が見つからないのはばかげています。
本増えて困っているのは確かなのですが、なかなかここまで思い切れない。
こんな本あったっけ?となる本なら、手放せるのですが、この本は持っているという記憶の方がまだ強いみたいです。
(ふだん物覚え悪いのに、本に関してだけは結構な記憶力を発揮するという、無駄な特殊能力があるので、余計にタチが悪い)
私は書評を書くとき、三回読むようにしています。まずは通読します。私は『不良のための読書術』で、本は三十ページだけ読めばいい、なんていっていますが、それは仕事以外の読書のときのことで、書評する本は最初から最後まで読みます。お金をもらって、読者の代行業として読むのですから当然です。このときに気になるところ、重要なところ、書評を書くときに引用したいところなどに付箋を貼ります。二回目は付箋を貼ったところを中心に読み返します。そして原稿を書きながらもう一度ぱらぱらと読み返します。ほかの参考文献は、重要なところだけを拾い読みすればいいでしょう。そうじゃないと体と時間がいくらあっても足りません。
「書評は読者の代行業」
書評とはなんぞやと思った時に、この言葉は一つの指標になりますね。
この「新書沼」でも、書評と言えるほど大したものではないですが、読んでくださる方たちを新書の沼に引き摺り込む、いえ、新書の素晴らしさをお伝えするために、参考にしていきたいです。
永江朗さんの著作ではこちらも面白かったです。
よし、51歳まではもう少しある!
まだまだいける!
楽しみしかない!
(と、先日また一つ歳をとったので自分を鼓舞してみる次第)
最後までご覧下さり、ありがとうございました。 どうぞ素敵な読書生活を👋📚
いいなと思ったら応援しよう!