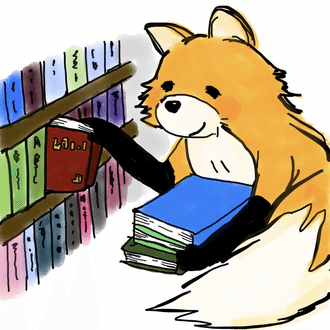“是非末永いお付き合いを”《マガジン“新書沼にようこそ” vol.28》
『新・本とつきあう法』/津野海太郎
印刷・製本された形ではなくて文章を読む手段が広まり、「本」のイメージは大きく変わりつつある。何が本で、何なら本でないのか。境界は曖昧になり、従来の本にしても、新形態の本にしても、支持者は互いに対立して、こちらこそ本だと譲らない。本書は、長年、本づくりに携わってきた編集者が、自ら読む本にどう対しているかを、
①活字本②電子本③インターネット上の読書④図書館、というテーマごとに示す自在な読書のすすめである。
発行が1998年!
青空文庫ってこの頃に出来たそうです。(あとがきより)
30年前ってこんなんだったかと驚くことしきり。
そして同時にそうだったそうだったと思い返すのです。
あの頃、「私の若い頃は論文を全部手書きで写したものです」と語る教授がいました。
(さすがに自分はコピー機使ってましたが)
レポートもパソコンでもいいけれど、手書きも許容されていました。
主な記録媒体はフロッピーディスク。ちょっと容量大きいということで、画像入れる場合はMO。
授業のスライドはもちろん元祖スライドかOHP。
何を言っているかわからないかもしれないが、本当のことなんです。
すみません、昔話ばかりで。
わかる方がいらしたら、ありがたい。
そんな時代から、ほんの四半世紀経った今、もはやスマホひとつでプレゼンの資料探しからスライド作成までできてしまう。
わからないことはすぐに調べられるし、欲しいものはクリックひとつで手に入る。漢字がわからなくても文章は書けるし、うまく文章を構成できなくてもAIが組み立ててくれる。
とにかく便利。
ITからの受けて余りある恩恵がなければ、私自身今、こうしてnoteを綴ることもままならない。
そういう意味では、この本の内容は確かに古い。過去の遺物という部分、私でも感じるところはある。
でもこの本は、そういう時代を知らない若い方にこそ読んで欲しい。
いつの時代でも、方法は変われど、読書を、本とのお付き合いを、こんなに楽しんでいる人がいる。
内容を古臭いと切り捨てるのではなく、30年前でもこんなに本を愛している人がいることに、読書に内在する普遍的な魅力を感じ取ってもらえたらと思うのです。
私のように、あの頃はこうだったなぁと懐かしみながら読むのもありですが、笑。
著者、まだまだ本を読むこと楽しんでおられるようです
↓
私もこちらの本はまだ未読なので、読みたいと思っています。
電子書籍楽しんでらっしゃるかな?
最後までご覧下さり、ありがとうございました。 どうぞ素敵な読書生活を👋📚
いいなと思ったら応援しよう!